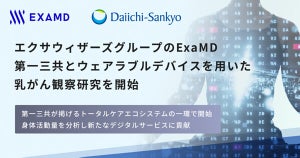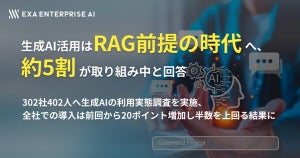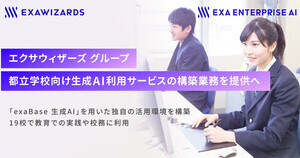編集者の朝は早い。1歳を迎える早起きの息子に文字通り"叩き"起こされると、朝ごはんの用意。前日に用意した離乳食を温める。その間、自身の着替えや洗顔などを済ます。毎日同じ時刻に改札を通るべく、ここは時間との勝負だ。自分の朝食もそこそこに保育園へと送り届けると、電車に揺られ取材へと赴く。
日中は取材や記事の執筆。ビジネスタイム中の読者へ最新のニュースを届けるため、各社が発表するリリースの収集や記者説明会、個別の事例取材に奔走する。こうしている間、保育園で子どもたちは何をして過ごしているのだろうか。たまに思い浮かべてみる。夕方に迎えに行くと保育士は日々の生活の様子を教えてくれる。お昼寝の時間や食べたおやつの量など、一人一人の成長を記録し保育してくれる先生には頭が上がらない。
日々多忙を極める保育士や幼稚園教諭を支援するサービスとして、AIソリューションに強みを持つエクサウィザーズグループが手掛けるのが「とりんく」だ。同サービスは、園のスマートフォンで撮影した多数の写真の中から、子どもたちの笑顔や何かに夢中になっている瞬間が公平に写り込むようにAIが自動選定し配信してくれるというもの。
また、保護者との情報共有だけでなく、多量の写真の中から整理が必要な卒園アルバムの制作業務なども支援する。先生がこれまで手作業で実施していた活動記録をAIによって自動化し、作業の効率化を促す。本稿では、とりんくのプロダクトマネージャーと事業責任者に取材した、プロダクト開発組織の特長と今後の方向性についてお届けする。
園児の写真撮影を支援するとりんくのサービス概要
とりんくは画像認識AIを搭載し、保育者の写真撮影に伴う業務を支援する。シャッターを押さずに自動で写真を撮影する「とりんくカメラ」、園児の着替えや鼻水など外部に公開できないNG写真を自動判別し加工や整理も可能な「とりんくマネージャ」、保護者に写真を自動配信する「とりんくフォト」などの機能で構成される。
園児らの写真を撮影するといっても、その裏には予想以上に多くの工程が発生する。園児の安全を確認しながら画面を見てシャッターボタンを押すだけでも大変だが、撮影後には写真をPCへ転送して残す写真を選別。子どもごとに不公平が無いよう枚数を確認し、トリミングなどの加工を施す。それからクラスや日付を管理してフォルダに保存する、といった工程が必要だ。同サービスはこれらの工程をAIによって効率化している。
サービス拡大のきっかけは先生からの一言
とりんくの開発の経緯について聞くと、最初から保育園向けに立ち上がったサービスではないそうだ。もともとは、汎用的な用途に対応するエッジAIカメラ「ミルキューブ」に端を発するという。AIカメラのユースケースとして、展示会やイベントの混雑回避、小売店の来店客の動向把握、工場作業の効率化などを検討する中の一つとして、保育園での活用が検討された。
プロダクトマネージャーとしてサービス開発を手掛ける若狭達也氏は「保育園は他のユースケースと比較して、撮影環境の明るさが確保でき、比較的狭い範囲の中で撮影が可能。そのため実証を進めやすかった」と振り返る。
ミルキューブの開発を進める中で、いくつかの課題も見えてきた。まず、10センチメートル四方ほどのカメラ機材を園内に設置するためには、専用のポールなどを用いる必要があり、設置の手間や圧迫感などの理由から、なかなか導入が進まなかったという。そこで、スマートフォンを壁に固定する方式へと転換した。
しかし、これ以降も導入はうまく進まなかったそうだ。当時はスマートフォンを壁に固定するための治具(ジグ)も合わせて設計し、展開の拡大を図った。だが、上手に取れる角度に設定することが難しかったり、壁に設置したい部分と治具が合わなかったりと、運用が困難だったという。スマートフォンの設置を支援するためのスタッフが施設へ行くオペレーションや、スマートフォンを固定することによる画角のマンネリ化が新たな課題となった。
そこで考案されたのが、スマートフォンを固定するのではなく保育士が手で持ちながら自動撮影する機能。先生からの「写真の撮影自体は苦ではない。むしろ楽しい。でもその後の写真の処理や整理に時間がかかっている」とのフィードバックが大きなきっかけとなった。この新機能によって外出時の写真も撮影できるようになったほか、手持ちでなければ撮れない子ども目線のダイナミックな写真が撮れるようになり、とりんくの導入施設数も増加し始めた。
ユーザー目線で自律的な開発を進めるエンジニア組織
とりんくを裏側で支える開発組織は、数名程度と少人数な点が特徴だ。若狭氏とエンジニアが面談をしながら、アジャイル開発の手法である「スプリント」を2週間程度の間隔で回しているという。面談の中で課題を明らかにしつつ、次の2週間へと生かす。
とりんくのサービス全体を統括する山中氏は開発組織について「企業文化として、自律的な開発メンバーが多いと思う。現在は、プロダクトマネージャーや私が細かく指示をしすぎないように気を付けている。仕様を最初から作りこむのではなく、現場のエンジニアが最適な方法を考えながら実装することで、結果的に少ない人数でも開発できている」と、語っていた。
若狭氏は、「プロダクトマネージャーがヘビーな仕様書を作成し、チームがそれを忠実に実行するような組織になるのは避けたい。せっかく自律的なプロフェッショナル人材が集まっているので、この強みを生かしたいと思っている。意思決定がプロダクトマネージャーに集中すれば遅延を招き、プロダクトの分割を余儀なくされ、一貫性維持も困難になる。このような非効率な組織であれば現在の5倍の人員が必要になるだろう」と話していた。筆者は数十人~100人ほどのエンジニア・デザイナーが開発に関わっていると予想していたので、非常に驚いた。
山中氏は「とりんくのサービスが拡大する中で、メンバーの選考が難しくなっている。サービスの成長に合わせていたずらに大きな組織を作るのではなく、人材の採用にはこだわっている」とも話す。現在は自律的に動けるエンジニアを集めながら、組織を徐々に拡大している途中とのことだ。
ちなみに、開発組織には30代後半~40代前半のメンバーが多いという。まさに子育て中で、保護者として保育園と関わっている(または関わっていた)世代だ。だからこそ、とりんくの魅力やポテンシャルに共感し、自律的により良いサービスを開発するべく稼働できるのだろう。
「私はサービスを統括する立場ではあるが、開発については『餅は餅屋』のように各メンバーに任せられる環境である。幸運なことに、それだけスキルのあるメンバーが今は集まっている。これからもそうしたポテンシャルのあるメンバーに集まってもらうために、いかに再現性のある採用を仕組み化できるかをこれから考えなければ」(山中氏)
【導入事例】湘南台よつば保育園plusは保育を妨げない写真撮影・管理を実現
ストーブカンパニーの湘南台よつば保育園plusは、とりんくを導入し活用を進めている。そこで同園に、導入のきっかけや導入の効果について取材した。
とりんく導入以前の課題と、導入のきっかけについて教えてください
新里先生:撮影する際は子どもの表情を確認することと、カメラを子どもたちに向けることなどが必要で、短い時間ではありますが一時的に子どもから目が離れてしまいます。以前は、このちょっとした時間に事故が起こってしまわないか不安でした。また、早く撮影を終わらせなくてはという焦りで、手元が狂ってしまうこともありました。
当時の撮影は、私用のスマホと園のiPadを使っていました。基本的には、前日に私用スマホで撮影した写真は翌朝に園のiPadに転送してスマホから消去するという運用を徹底していたのですが、その分手間もかかりますし、何よりも写真が流出してしまうことが不安でした。このことには、園長だけでなく現場の保育士も不安を抱えていました。
そんな中、当社の代表がとりんくを知り「保育士の負担を軽減できるサービスだから使ってみないか?」と紹介してくれたことがきっかけです。サービス内容を拝見して、これは良さそうだと思い、試してみることにしました。
とりんくを使ってみていかがですか
新里先生:保育に集中しながら、子どもたちの自然な表情の写真も撮れて一石二鳥です。保護者からも「普段の表情や仲の良いお友達が分かる」「先生とのふれあいが見れてよかった」と好評です。枚数は、1人当たり月間200枚を超える写真を提供できています。
島田先生:現場の保育士の視点では、数値で出る効果以上に楽になったという感覚があります。隅っこでお着替え中の子が映り込んでしまっていないか、鼻水が出てしまっていないか......など、保護者への写真共有には細心の注意を払っていたので、時間以上に体力や精神力を使っていました。この日々の10分程度の作業がなくなっただけで「めちゃくちゃ楽になった」という感覚です。
どの程度の導入効果がありましたか
新里先生:園長としては、保育士の負荷が軽減されたことに最も価値を感じています。保護者に共有する写真の選別と仕分けに加えて、撮影の負荷まで考慮すると、クラス当たり1日20~30分、園全体では1カ月に換算すると60時間分の業務削減になったと考えています。カメラを向ける時間が減った分、保育士は子どもと向き合えるようになりましたし、写真の選別と仕分けに費やしていた時間は、他のデスクワークのために使えるようになりました。
とりんくの将来像と今後の挑戦
とりんくは将来的に、単にAIで写真の撮影と選別を効率化するというサービスにとどまらない領域に挑戦するとのことだ。これから、写真からどのように保育・教育的に意義のある情報を得られるのかにチャレンジするという。
多くのデータを蓄積することで、撮影した子どもの写真から「この子はこんなことに興味がありそう」「この子は先月と比べてこんなことを新しく学んだ」といったことを先生の代わりに言語化し、レポートするような機能の開発も視野に入れているそうだ。こうした機能は、保護者にとってはもちろんのこと、保育者・教育者にとっても非常に有意義な情報となるだろう。
そろそろプール開きの保育園も増える時期。今日は子どもたちは何をして遊んでいたのだろうか。どんな絵本を読んだのだろうか。寄り道せずに、いつもより少しだけ早足で園まで迎えに行こう。