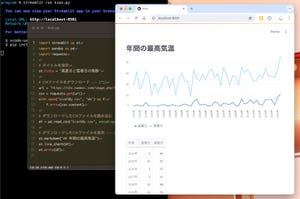「銀行がお役に立つ時代が来た」─みずほ銀行頭取の加藤勝彦氏はこう力を込める。2024年3月に「マイナス金利」が解除され、日本でも徐々に「金利が付く世界」が戻りつつある。その中で、銀行としてどう役割を果たすかが問われるが、1つ注目されるのが「店舗」。今は様々な顧客ニーズに合わせた専門店を設置するとともに、デジタル、非対面のサービスと融合させて顧客対応を推進中。金融領域での時代変化への対応とは─。
金利が付き、経済が回り始めた
「金利が付く世界」への回帰でメガバンクの戦略はどう変わるのか─。
2024年3月に日本銀行がマイナス金利を解除、YCC(長短金利操作)を撤廃するという決定を行って以降、日本にも金利が付く世界が戻ってきている。
銀行業界は16年に日銀がマイナス金利を導入して以降、預金が力を失い、貸出の利ざやが取りづらくなるという形で苦しんできた。それがわずかではあるが金利が付くことは、銀行業務にとって大きなプラス。
メガバンクの一角・みずほ銀行頭取の加藤勝彦氏は、この金利が付く世界における銀行の役割を考える上で「3つのポイントがある」と話す。
第1に戦略。預金に金利が付くことで、収益力が高まるため「戦略的に預金を取っていく」(加藤氏)ことに大きな意味が出てくる。一方で、その預金の獲得のために「昔のように金利競争をやるかというとそうではない」と加藤氏。
マイナス金利の導入以前、それこそ「失われた30年」の間は低金利環境が常態化したこともあり、銀行はコンサルティングなどの「非金利ビジネス」や、銀行・信託・証券が連携した、グループ総合力を生かしたビジネスに活路を見出して、ノウハウを積み重ねてきている。
そのため、預金金利が付くことで、大きな戦略の変更はないものの、グループの中でマスリテール(一般の個人顧客)の重要性が増してきたと言える。
第2に顧客の認識。例えば、24年から始まった「新NISA(少額投資非課税制度)」によって、証券会社のみならず銀行に対する注目度も高まった。「『みずほってNISAやっているの?』と聞かれるなど、銀行が話題に上る機会が増えた。これは我々にとって働きがいのある話だし、銀行がお役に立つ時代が来た」(加藤氏)
資産運用への注目度が、かつてないくらい高まる中、この受け皿の一角を担うことも銀行の役割。その動きに対しては対面、非対面、リモートという3つの接点で対応し、顧客ニーズに応えていく考え。
第3にインフレ。金利が上がるという環境の中、インフレや賃金上昇が定着しつつある。それ以前のデフレ環境下では「企業のお客様は物価も賃金も上がらない中で『ステイ』のまま動かなくてもマイナスにはならなかった」と加藤氏。
それがインフレ環境下では、自ら動いて新商品、新市場の開拓を進めなければならない。「ステイ」のままではコストだけが上昇してしまう。
「経済を回していかなくてはいけないという推進力が出てくる。預金金利が上がるという背景にある、経済が動き始めることにつながる」
そのため、銀行としては顧客企業のビジネス拡大や、成長に向けたM&A(企業の合併・買収)の支援の他、逆に業況が悪化する企業に対して事業再生支援をするという形で、役割を果たしていく。
デジタル化の今、顧客接点はどう変わる?
気になるのは、我々個人顧客との接点がどう変化していくのか。前述の対面、非対面、リモートの3つをどうバランスさせながら、顧客との関係を深めていくかは大きな課題となる。
今の時代に重要な非対面の接点は「デジタル」。銀行取引や手続きがパソコンやスマートフォンで利用できるインターネットバンキングサービス「みずほダイレクト」の機能や使い勝手を向上させている他、今年度はスマホ決済アプリの「みずほウォレット」をバージョンアップ。みずほが提供しているQRコード決済アプリ「J―コインペイ」を標準装備させた。「お客様の手の中でできる銀行取引の利便性を、より高くしていく」
デジタル関連では現在の中期経営計画の中で「オープン&コネクト」という考え方に基づき他社との連携を進めているが、現在までに楽天グループ傘下の楽天証券、ソフトバンク傘下のPayPay証券に出資している。みずほ単体ではなく、こうした出資先などのパートナーの力も活用して、顧客ニーズに応えていくというのが戦略。
例えば楽天証券とはNISAに関して、契約のある法人顧客の職場で、その従業員に対して金融商品を提案する「職域営業」でも連携している。業法上、みずほ銀行と楽天証券はお互いの商品を販売することはできない。そこで提案時間を分けて、それぞれの商品を顧客企業に紹介する機会をつくっている。
「デジタルのビジネスパートナーとリアルの場でも連携できるという相乗効果が生まれている。彼らとは発想が違い、学ぶべきことが多く、刺激的」
もう1つ、非対面の顧客接点で重要なのが顧客からの問い合わせに対応する「コンタクトセンター」。みずほ銀行で22年に発生したシステム障害では「電話がつながらない」という事態になったのは記憶に新しいが、みずほでは、この改善に注力してきた。
顧客が電話をして、回線に空きがなく接続できなかった確率を「呼損率」という。高ければ高いほどつながりにくいという指標だが、みずほ銀行は現在約8%。他社は10%台だという。その結果、ITサポートサービス業界における世界最大のメンバーシップ団体・HDIの評価で3年連続の「3つ星」を獲得。
「今も優位性があるが、今後は次世代のコンタクトセンターをつくっていきたい」と加藤氏。
24年8月から、最先端の生成AIを活用して顧客との会話を分析、迅速な回答と顧客にあった提案を実現する他、学習によって生成AIの高度化を進めていく。さらに、電話やチャット、LINEなど様々なチャネルからの相談内容をコンタクトセンターで引き継ぎ、問題解決をサポート。そしてコンタクトセンターでの応対内容は営業店、ネットバンキングとも共有し、次の顧客対応に生かしていく。
「これまでリモートの接点は、支店との関係を主従で言えば従だった。このコンセプトを変えて、リモートを主にしていく」
こうしたデジタルの接点が拡充されていく中、では対面の場である店舗はどういう存在になっていくのか。これに対し加藤氏は店舗を「みずほの〝顔〟」と強調する。
みずほ銀行の店舗は、法人の事務手続きなどにも対応する「中核店」と、個人顧客への対応に特化した「専用店舗」とがある。この専用店舗は129店舗あるが、これを「よりコンサル的な、相談専門の支店に変えていく。今年度から試行店を始めるが、将来的には129店舗全てを変える方針」と加藤氏。
他のメガバンクでも相談専門の店舗などを設置する動きはあるが、みずほ銀行は「相談だけだとお客様の利便性が高まらない」として、顧客の相談に関連した事務は行えるようにする。その分、顧客にタブレット端末を操作して必要事項を入力する「セルフ事務」を担ってもらうことで効率化を図る考え。
「これまでの銀行店舗はどうしても敷居が高い面があった。それを入りやすく、相談しやすい雰囲気の店舗に変えていく」
なるべく、通常の取引はデジタルのみずほダイレクトで行ってもらい、複雑な取引など人対人の対話はコンタクトセンターが担う。そして顧客ごとのニーズに応える機能を持った個特店などでコンサルティングを提供するという「三位一体」で顧客に対応するのがみずほの戦略。
【関連記事】みずほFG・木原正裕の「投資戦略」、積み重ねた資本をどう活用していくか?
企業の成長を支援し、日本経済を底上げ
前述のように、金利が動き出したことで法人部門の顧客にはプラス・マイナスそれぞれの影響が出る。これにどう対応するかも、みずほ銀行にとって重要な仕事。
みずほフィナンシャルグループは昨年、新たなパーパスを制定した。それが「ともに挑む。ともに実る。」。このパーパスには、地政学リスクや金融環境の先行きが読み切れないなど、外部環境が不透明、不明瞭な中で「ようやく回り始めた日本経済を好循環に持っていく。我々はそこに使命感を持っている」
例えば大企業であれば、人口減少の日本での事業にとどまらず、海外に成長機会を求めるケースがある。その時に、みずほの海外ネットワークを活用してもらう。M&Aを行うのであれば、グループのみずほ証券に加えて、23年に買収した米投資銀行のグリーンヒルの知見も活用でき、かつみずほ銀行のファイナンスの力も生かすという形で総合力が発揮できる。
一方、中堅・中小企業の成長は、日本経済の底上げという意味で欠かせない。みずほ銀行では23年に、中堅企業の企業価値向上を支援する専門部署「事業成長支援室」を立ち上げた。例えば、PBR(株価純資産倍率)が1倍を割れている中堅上場企業などにアプローチして成長戦略や、「物言う株主」対策などを支援してきた。
1年間の活動を通じては「非常に手応えがあった」と加藤氏。そこで今年度は「事業成長支援部」に格上げし、70名の人員を擁する部隊となった。
さらに、経済の活力という観点ではスタートアップ企業の支援も重要。みずほ銀行では、この10年以上、スタートアップ支援に注力してきた。同行を中心に運営するスタートアップ企業向け会員サービス「Msʼ Salon」は会員数約4100社を数える。
みずほ銀行ではスタートアップ支援の担当者を昨年の160名から倍増して約300名規模にした。支援の際に大事にしているのが「審査」。そのスタートアップの潜在力を見るにあたり社内に評価軸を設けて審査し、担当者が変わったとしても、その評価軸をベースに議論ができる体制にしている。「リスクテイク、クイックな判断をするために、審査のレベルアップを進めている」
23年8月には、グループのみずほキャピタルが「みずほベンチャーデットファンド」を設立。これはメガバンクの中で初めての取り組みで、スタートアップが発行する新株予約権付社債を引き受けて資金調達を支援する。みずほもリスクを取って、スタートアップに資金を供給する。
「近代日本経済の父」渋沢栄一の精神を生かして
折しも、7月から新紙幣が発行されるが1万円札には、みずほ銀行の源流の1つである第一国立銀行を立ち上げた渋沢栄一が採用された。
「渋沢栄一が銀行を始め、多くの企業を立ち上げたことは、まさにスタートアップ。新興企業を立ち上げて、日本の近代産業を作り上げてきた。私は、スタートアップとはそういう存在だと思っている」と加藤氏。みずほ銀行が、早いタイミングでスタートアップ支援を手掛け始めたのも、「渋沢イズム」があったからではないかと振り返る。
そして渋沢栄一が唱えてきたのが「公益と私益」の両立。「今は社会課題を解決することが、イコール経営課題になっている。今まさに渋沢栄一の考え方が、ピタリと当てはまる時代になっているのではないか」
その観点で言えば、今のサステナビリティやカーボンニュートラルを始めとする環境問題への対応も、渋沢の精神につながるものだと加藤氏は言う。
「カーボンニュートラルは外部不経済を内製化していくもの。しかし、これは1社では実現できるものではない」
水素1つを取ってみても、製造、輸送、貯蔵、利用など様々な工程があるが、そこに参画する事業者を「つなぐ」のがみずほ銀行の役割になる。
企業のカーボンニュートラルの取り組みを支援するための「トランジションファイナンス」で、みずほ銀行は世界トップレベルの実績となっている他、2030年までに、企業の水素製造を後押しする融資を2兆円実行すると発表している。
「渋沢栄一のアイデンティティを持つ企業の1社として縁や巡り合わせを感じる」と加藤氏。
その意味で、渋沢栄一の精神が改めて見直されている今、みずほ銀行にとっても原点に立ち返って、取り組みを強化する機会とする必要がある。