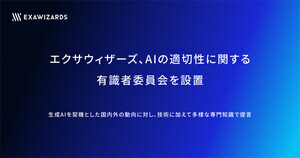デロイトトーマツはこのほど、オンラインで生成AIのルール形成の潮流および官公庁における活用事例に関するセミナーを報道関係者向けに開催した。
日本を含めた各国における生成AI活用の動向は?
はじめに、デロイトトーマツグループ マネジャーの嶋威一郎氏が生成AIの各国の動向について説明した。
海外の動向として、米国では生成AIを含むAI規制に関する法制化について、超党派での動きが活発化しているものの、時間を要するため大統領令による連邦政府機関への対応指示に加え、AI事業者との自主的な取り組みの合意などで暫定的に対応しているという。
嶋氏は「昨年10月に米バイデン大統領がAIに関する安全・安心・信頼性を高める大統領令を発令したほか、超党派の議員でAIに関する新たな規制法案の検討に向けて、専門家や企業、民間団体などを含め、意見交換を行う『AI Insight Forum』を提供している。また、AIで生成されたコンテンツを含む著作物の著作権登録ガイダンスを公表した」と説明。
EUでは、従来から審議していたAI規制法案について生成AIの普及をふまえた見直しが行われ、昨年12月に暫定合意に達した。英国は「AI Safety Summit 2023」を開催し、AIの安全性を評価する研究所「AI Safety Institute」が政府内に設立した。
また、中国は生成AIの規制に特化した世界初の法律を施行したほか、ASEAN、シンガポール、UAEでは法規制ではなく、ガイドラインによる対策を進めている。
国際機関としては、国連がAIの非軍事利用、偽情報での利用を懸念しており、欧州評議会はAI条約案の草案をもとに、加盟国との交渉が開始し、オブザーバーで参加する日本の対応を注視。G7では広島AIプロセスでも国際機関、各国政府、AI企業、専門家、市民団体と意見交換しており、検討を進めた。
そして、日本のAI政策はAI戦略会議やAI戦略チームを中心に議論が交わされており、AIセーフティー・インスティテュートの設立を昨年12月に発表。さらに、総務省と経産省では「AI事業者ガイドライン案」の策定に取り組んでいる。
現状で新たな法律の制定などの動きはないものの現行法にもとづいた解釈の見直し、現行法を考慮したうえで考え方の整理、ガイドラインの策定、利用の通知などの対応を各府省庁が取り組んでいるという。
日本のAI事業者ガイドラインの策定はソフトローを中心に
次に、デロイトトーマツグループ シニアスペシャリストリードの松本敬史氏が広島AIプロセスを受けた日本政府の取り組みとAI事業者ガイドラインの策定に関して解説した。
松本氏は「日本はソフトロー(権力による強制力は持たないが、違反すると経済的、道義的な不利を国家・自治体・企業・個人にもたらす規範)を中心に進めていくだろう。AIガバナンスの実践については、さまざまな企業でホットトピックになっており、今後は法改正なども検討されている」と話す。
日本におけるAI事業者ガイドラインは、国際的な最新の検討を反映して作成。内閣府が公表している「人間中心のAI社会原則」を土台に、内閣府の「AI開発利用原則」に該当するAI開発ガイドライン、AI利活用ガイドライン、AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインを統合・見直しつつ、諸外国の動向や新技術を考慮し、広島AIプロセスの検討も反映させて新規策定を進める必要があるという。
ガイドラインは基本的には企業に向けたものとなり、消費者は対象に含まれず、関わるプレイヤーはAI開発者、AI提供者、AI利用者(ビジネス利用者)の3社での原則を検討している。
ガイドラインをもとに、企業のAI CoE(Center of Excellence)がどのようなガバナンスを実践しているのか、またAIサービスであれば事業者ガイドラインに従い実践しているプラクティスを蓄積し、企業の検討事例をもとにガイドラインをリビングドキュメントとして、磨き上げていくことが期待されている。
松本氏は「こうしたサイクルを多様な企業で回していければ、日本のガイドラインはよりプラティカルなもの充実していくだろう。また、さまざまな実例をベースに諸外国に対してガバナンスの実践に関するプラクティスを具体的に発信していける」との見立てだ。
生成AIを官公庁ではどのように活用していくのか
続いて、デロイト トーマツ グループ マネージングディレクターの根本直樹氏が官公庁における生成AI活用の支援実績について説明した。
同氏は官公庁におけるAI活用の目的について「社会課題解決や国民向け行政サービスの価値向上、効率化、高度化をはじめとした政策目的のあり方を考えときの補助的な使い方が検討されている。そうした領域に対して、当社は従来からEBPM(Evidence Based Policy Making)を提供している」と説く。
EBPMは1990年代から英国や米国で発展し、政策を限定的なエピソードではなく、目的を明確したうえでエビデンスにもとづく政策立案のこと。
日本では2013年から議論されており、さまざまな政策の分析・立案する際に活用されているが、行政は膨大なテキストデータを、どのように処理すべきか、そして人員不足などもあり、社会変化が激しい中で迅速に政策を分析・立案する必要があるという。
根本氏は「政策の策定だけではなく、過去の動向をふまえた将来の見通しを定め、データドリブンな政策評価の補助としてAIを使うべきだ。これは最終的な評価は人が行うことを前提としており、デジタル時代にふさわしい政策形成・評価のあり方への転換、国民・地方公共団体の声を適切に反映し、スピード感を持った高度な政策立案、AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)などを前提に最新のデジタル技術を活用した評価方法の導入などが挙げられる」と説明した。
同社のEBPMは、ロジックモデル作成・リサーチデザインの「立案」からデータ取得・整備・モニタリングの「実行」、「効果検証」、政策的インプリケーション(含意)の「対策・見直し」のサイクルで支援。
根本氏は「正確なものをAIがアウトプットするためには、データの品質が重要になる。政府では行政文書の扱いを紙からデジタルに切り替えており、データの正確性の確保については、砂上の楼閣にならないためにも品質がクローズアップされており、これがないとAIの活用が進まないという現場の議論がある」と述べた。
データの品質を保つためには公正性・透明性、国民の権利、利益の保護を前提にデータガバナス、つまり責任あるAIとAIガバナンスが必要となり、データポイズニング(学習モデルに対して、悪意を持って不正な情報をインプットして、事実とは異なるアウトプットを出させるように仕向けること)やハルシネーション(幻覚)などの排除が望まれるという。
このようなことをふまえたAIの活用として「収集した多様な情報・データの要約・構造化」「政策課題の原因推定、政策評価の高度化」の2つを仮説として挙げている。
多様な情報・データの要約・構造化に関しては、行政文書や行政記録情報など行政機関で保有されているデータだけでなく、社会経済活動、消費生活活動をはじめとした周辺データから課題・制作に関係しそうな社会環境情報、政策に対する意見・考えといったものを自動的に要約・構造化したうえで抽出可能になり、多様な視点で政策立案や業務改善が効果的にできるのではないか、としている。
政策課題の原因推定、政策評価の高度化については、分野特化や政策分野(または所管法令)ごとの推論・生成に最適化されたLLM(大規模言語モデル)が開発されることで政策課題の原因推定に加え、仮に政策を実施した場合の効果予測が可能になるのではないかという。
生成AIに関する2024年の見通し
最後に、デロイト トーマツ グループ パートナーの森正弥氏が2024年の生成AIの動向を紹介した。
森氏はトレンドの方向性として「現在のAIはディープラーニングベースが多く、特に生成AIとLLMはディープラーニングに大量のデータを掛け合わせて、飛躍させていくというトレンドの頂点だ。また、世界モデルと呼ばれる生成AIに枠組みを与えて学習させていく高度化のほか、従来のシステムやオペレーションなどと統合していく動きも想定され、生成AIと企業内、外部のデータを連携させることでAIを学習させることなく広範な知識による回答を可能にしていくことが今年は進化していく。そして、信頼できるAIとしてのガバナンスとなる」との認識を示した。
このような動きは、同社が提唱しているAFO(AI Fueled Organization:AI駆動型組織)の実現に向けたものであり、大半の企業はAIをテーマごとに導入しているが、現在は企業自体がAI駆動型組織に進化する段階を迎えているとのことだ。実際、AIを全社適用し、ビジネスプロセスや組織そのものをAIで駆動していく組織に進化させていく企業は増加しているという。
現在、日本企業における生成AIに関連する活用・新規事業創出は以下の4種類のパターンを挙げている。
1. 全社導入
ChatGPTなどをユーザーとして活用する。
2. 業務システム連携
APIを使い自社システムに組み込み、新規サービスを生み出す。
3. 顧客対応進化
音声対話版の生成AIを導入して顧客価値を創出する。
4. 独自LLM開発
特定ドメインにおけるLLMを開発し、R&D(研究開発)や新規事業に活用する。
この中でも、特に今年は(2)と(3)の領域での事例が出てくると、同社では推測している。
とはいえ、生成AIによるパフォーマンス向上を全事業に広げようとしても複雑さに阻まれ、これを克服していくには「CoEによる組織的取り組み」「生成AIを含むデータマネジメントの実施」の2点が重要になるとのこと。
そのような取り組みを進めていくことで、組織内の効率化・自動化だけでなく、顧客への価値創出、ひいてはビジネスパートナーを巻き込んだ高度な経営基盤の確立に向けたAIの戦略的活用が見えてくるという。