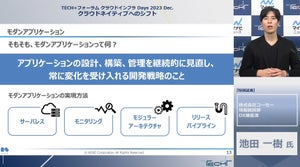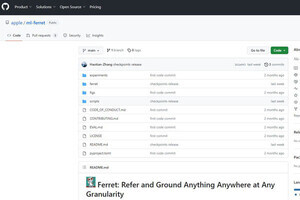良品計画は「無印良品」ブランドを展開することで知られる企業だ。同社はその他にもさまざまな事業を展開しており、国内外に多数の店舗を持つグローバルカンパニーである。
そんな良品計画では現在、データの利活用の促進によるDXを急速に進めているという。では、どのような仕組みでデータを収集し、どう活用しているのか。11月6日~17日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」に、同社 ITサービス部 データサービス課 課長 データアーキテクトの王毅超氏が登壇。良品計画におけるデータ活用について語った。
「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」その他の講演レポートはこちら
「第二創業期」に入り、DXを推進する良品計画
一般的には「無印良品」ブランドで知られる良品計画だが、その事業範囲はおそらく一般に想像する以上に広い。
例えば、生活の分野では「MUJI HOTEL」や「MUJI HOUSE」の事業、コワーキングスペースなどのサービスを展開しているほか、地域・文化分野では店舗の土着化活動や里山の保全なども行っている。
特に注力しているのは環境分野で、サステナビリティなどを掲げ、衣服のリユース・リサイクルを行う「ReMUJI」を展開している。
こうした各事業を、32の国・地域にグローバル展開。海外店舗数は604店舗と国内の532店舗を上回り、公式アプリも11カ国で6,978万ダウンロードを達成するなど、同社は今や日本を代表するグローバルカンパニーと言っても過言ではない。
そんな良品計画は、2021年9月から「第二創業期」に入ったことを宣言しており、ここへきてさらなる変化と成長を見せている。中でも注目したいのが、IT部門とECデジタル部門だ。中期経営計画では、基幹系システムの刷新や店舗レジ基盤の刷新、店舗業務のデジタル化による効率化などを目標に掲げている。
同部門の変革を主導するのが、王氏が所属するデータサービス課だ。その使命は、データの利活用を通してデータドリブン組織変革を推進し、ビジネス効率を向上させることに他ならない。
「弊社の金井政明会長も『ITとは空気のようなもの。皆は気付かないけど、業務の中に溶け込む存在』だと話しています。その世界観を叶えられるように、社員一同で頑張っています」(王氏)
マーケティング、需要予測、発注最適化に注力
では具体的に、良品計画ではどのようなデータ活用が実践されているのか。
まず王氏は、データの収集と管理の方法について解説した。
「ECサイトや店舗といった現場のデータ、物流や取引先といった外部のデータ、さらに予算データや人事データなど、あらゆるデータを収集し、これらをデータレイクで一元管理しています」(王氏)
その後、利活用のためにデータの変換と加工を行う。なぜなら、データを単に収集しただけでは形式などがばらばらの状態になっており、データ同士を組み合わせて活用することが難しいからだ。
そして、これらのデータをさまざまなかたちで利活用する。例えば、顧客や商品に関するマーケティングやレポーティング、AIと組み合わせた需要やトレンドの予測、発注の最適化などである。
同社のマーケティング担当者による利活用を例に挙げて、より詳しく紹介しよう。顧客に関するセグメントデータを活用することで「30代の直近1カ月再来店していないヘビーユーザへ新商品の紹介通知を配信する」ことや、「先月発売した新商品のチャネル別購入データを分析して、今月の広告チャネル配分を見直す」ことが行われている。
また、データサイエンティストやデータエンジニアであれば、AIを活用することで直近5年分の店舗来店ユーザー数と、来月の天気予報データから、来月の時間帯別来店客数を予測してワークスケジュールを自動で組み立てるといった対応も行える。
現場での活用だけではない。同社は毎週、事業の振り返りを行っているそうだが、毎日の数値をただ見ているだけでは、結果に一喜一憂するだけになってしまう。そこで現在はデータを活用し、従来の帳票形式にとらわれずに全体的な傾向を把握することで総合的な意思決定を実現しているという。
商品企画についても同様だ。これまではセンスや経験といった属人的な要素を基に商品企画を行ってきたが、現在はデータを基にした定量的なアプローチが可能になり、より質の高い商品開発が可能になったと王氏は言う。
店舗におけるデータ活用を“日常”にする
同社のデータ活用で重要な位置付けにあるのが、店舗におけるID-POSデータの活用だ。その目的は3つある。
まず、店舗運営自体の効率化である。データを活用することで、売上や在庫などの情報をリアルタイムで把握し、業務プロセスを最適化できる。在庫不足や在庫過剰といった問題もすばやく検知し、補充や調整を行えるというわけだ。
データ活用は顧客購入体験の向上にもつながる。例えば顧客の購買傾向や需要予測を厳密に分析することで、顧客が必要としたときに必要とするものを購入できるよう、品揃えなどを最適化できる。
さらに、商品戦略の最適化もデータ活用の目的だ。どんな商品が売れているのかを多軸的なアプローチで分析することにより、より効果的な商品戦略の立案が可能になる。
では、ID-POSデータの要件とは何か。王氏が挙げるのは次の4項目である。
まずは「リアルタイム性と信頼性」だ。適切な頻度でデータを収集することにより、データの正確性や完全性、一貫性を確保することが求められる。
「大量データの保管と管理」も重要な要件だ。データレイクやデータウエアハウスを構築し、適切にデータを保管する必要していく。これにより、データへのアクセスやクエリの効率化、セキュリティなどを向上させられる。
ビジネス関係者がデータをわかりやすく理解するために、「データの可視化とレポート」も欠かせない。そのためには可視化ツールやダッシュボードの構築が必要だ。
店舗増加などに伴う将来的なデータの増加に対応するため、ID-POSデータ活用には「スケーラビリティとパフォーマンス」も求められる。高いパフォーマンスと処理能力が確保されれば、リアルタイムでのデータ分析にも役立つ。
こうしたID-POSデータ分析は、3つのレイヤーで構成されるデータレイクにより管理されている。
1つ目のレイヤーは「Staging層」だ。ここでは、さまざまなデータソースから収集したデータを加工せず、そのままの状態で取り込んでいく。次に、これらのデータを基にフォーマットを変更し、2つ目のレイヤーである「Raw層」に格納する。最後に、ビジネス要件による加工を施し、汎用的なデータとして3つ目のレイヤー「Insight層」に保存するという流れだ。
「POSデータはストリーミング処理とバッチ処理の2つの処理を行うことで、鮮度と精度を両立させています」(王氏)
この流れを使うと、次のような仕組みが構築できる。
まず、店舗レジからはリアルタイム販売データをストリーミング処理で収集。リアルタイム分析により、陳列不足品を分析して店長にアラートを出す。これにより、店長は陳列品不足を事前に把握し、補充を行える。
一方、物流センターからも同様に、リアルタイム在庫データをストリーミング処理で収集。前述した店舗の販売データと組み合わせることで在庫不足を検知し、物流センターに自動発注指示が出せる。これにより、欠品リスクも最小限に抑えられるわけだ。
このように、データは可視化だけでなく利活用しなければ意味がないと王氏は言う。
「どんな人気商品でも、お客さまにとって都合の良いタイミングで購入できるように、充実した品揃えと程よい買い物体験を実現していきます」(王氏)
王氏はまた、「データ活用が店舗運営の“日常”になることを推進したい」と話し、講演を締めくくった。
「店舗におけるデータ活用はまだ始まったばかりです。現在はようやくデータの利活用が業務に組み込まれ始めた段階なので、今後は、全ての業務にデータの活用を組み込みたいですね。良品計画のイノベーションと、非連続的な成長を促進していきます」(王氏)