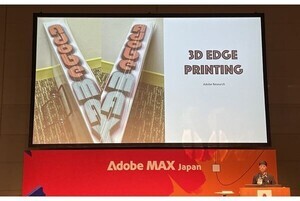11月21日 、NVIDIA主催の「NVIDIA 生成AI Day 2023 Fall」がオンライン上で開かれた。基調講演ではデロイト トーマツ コンサルティングの研究組織、Deloitte AI Institute (DAII)所長の森正弥氏が、「生成AIの衝撃、ChatGPT/LLMの戦略的活用」と題し講演を行った。
現在、生成AIの活用について国内100社以上から相談をうけるという森氏は、企業における代表的な活用方法を次の4つのパターンに分けて紹介した。
生成AIアバターが注文をとる? 米レストランの事例
最も初歩的な活用方法は、(1)ChatGPTを導入して社員の生産性を高めるパターンだ。次に、(2)さまざまな業務システムと連携させて自動化を発展させるパターン。いまは(2)の段階にある企業が最も多い。そして、(3)生成したAIアバターを接客に活用するパターン。最後は、(4)独自LLMの開発だ。とくに今、期待すべきパターンとして森氏が強調したのは、(3)生成AIアバターによる顧客対応だ。
「アメリカのとあるレストランチェーンでは、生成AIによるアバターがメタバース上で顧客のオーダーにこたえるという面白いサービスを始めています。この生成AIアバターは注文をとるだけでなく、オプションの提示や、サイドディッシュの紹介、現金払いやクレジット払いなどチェックアウトの方法までインタラクティブに提案ができます」(森氏)
もちろんアバターには、あらかじめ回答用のシナリオが用意されているわけではない。高度な言語認識、合成音声など技術を組み合わせることで、まったく遅延や違和感を感じさせない対話が可能となった。
「もしも顧客がレストランとまったく関係ない話をしたとしても、アバターはきちんとした回答を返せるように出来ています。こんな高度なコンシェルジェアバターを作り出せるのも、大規模言語モデルならではでしょう」(森氏)
この生成AIアバターによるコンシェルジェサービスは、デロイトが開発したFrontline AIによって生み出された。いまは英語版だけでなく、日本語版も提供しているという。
「攻め」の生成AI活用をしたい6つの社内業務とは
生成AIを活用する企業はレストランだけでない。いま攻めの生成AI活用に乗り出す発表が、大手企業を中心に相次いでいるのをご存知だろうか。
森氏は、米OpenAIの生成AI「ChatGPT」を導入して社員の生産性を高めるケースや、さまざまな業務システムと連携させた自動化まで取り組む企業が、いま大企業を中心に「続々と現れている」と明かした。
「たとえば、今年4月、三井住友ファイナンシャルグループは、グループ専用のチャットツール『SMBC-GPT』を開発しました。同月、三井化学はChatGPTに500万件以上の特許・ニュース・SNSといった外部のビッグデータを分析させ、新規事業の探索や、開発のスピードアップに乗り出すと発表しています」 (森氏)
では、実際に「攻めの生成AI活用」を企業が考えようとする場合、どんな業務が候補となるだろうか。森氏は次の6種類を提案した。
1つ目は、「調査分析の効率化」。生成AIに自分のアイデアを投げかけて、壁打ち相手になってもらう。技術的な質問をして、テクニカルトレーニングの先生になってもらうなどだ。
2つ目は、「社内知見の共有促進」。生成AIは雑多な会話も、まとまりのある文章に整理整頓ができる。メモのように思いついたまま話しかければ、知識やノウハウとして蓄積され、業務の属人化を防ぐことにつながると同氏は説明。
3つ目は、「問合せ対応の削減」。社内の問合せ窓口やデータと生成AIを連携させることで、業務の効率化を図ることができる。
4つ目は、「業務自動化の推進」。RPAなど社内システムと生成AIを連携させて、自動化を進化させる。さらに業務システムの活用にもつながる。
5つ目は、「エンジニアの強化」。コードが書けない一般社員でもプログラミングできるよう生成AIが支援する。エンジニアはプロトタイピングを生成AIに任せて開発に専念できることが期待される。
6つ目は、「ノウハウの共有」。社内の生成AI活用ノウハウを蓄積し、さらにAIの生産性を高められるとのこと。
時間短縮・業務効率化につながる3つのユースケース
基調講演では有効なユースケースとして、以下の3つがデモ動画とともに紹介された。
【事例1】多言語翻訳と議事録作成ができるケース
たとえば、海外メンバーと多言語会議をする場合、生成AIを使って同時翻訳すれば、議事録も同時に作成することが可能だ。
デモでは日本、インド、中国という多様な国籍をもつメンバーが発言。PC画面上に発言内容が文字起こしされ、同時に英語、もしくは母国語へ次々と翻訳されていく様子が示された。
「言語の違いを乗り越えやすくする同時翻訳は、メンバーが合意形成にかかる時間を短縮できます。
しかも、生成AIが自動的に要点をまとめてくれるので、議事録がわりにもなるでしょう。業務の効率化につながります」(森氏)
【事例2】財務分析を簡素化するケース
財務分析のROEやROA、利益率などといった計算式は覚えづらく、算出に時間がかかるという問題があった。だが、生成AIに企業の財務データと分析用プロンプトを入力すれば、あっという間に作業を肩代わりしてくれる。
「将来、株価情報に時事ニュースなどマーケット情報も反映できれば、『株価予測も可能になる』とする研究さえあります」(森氏)
【事例3】稟議の時間短縮につながるケース
社員にとって、「稟議書の作成」は時間や手間のかかる作業だ。作成にあたって、社員は参考となる過去の事例や規定集を探しまわらねばならない。決裁が下りやすいストーリーも考えながら、文章やビジュアルを作成する必要もある。すべてを人手で行っていると、トータル時間は平均16時間、2営業日はかかる計算だ。
「一方、ChatGPTなど生成AIを使えば参考資料の調査やストーリー検討、稟議書作成、自己レビューという、面倒な作業の大部分を自動化できます。トータルでかかる時間は6時間20分。手作業でやる時間を、半分に短縮できるでしょう」(森氏)
そして今後、生成AIは「既存の業務システムをつなぐ“ハブ"になるだろう」と森氏は予見した。
「バラバラな業務システムをAPIで疎結合化し、生成AIをハブとして機能させれば、単一のインターフェースから命令を出したり、データ取り出したりが可能になるでしょう。生成AIは既存システムの複雑性解消につながります」(森氏)
ブルームバーグ社が進める独自開発LLM
最後に、森氏は生成AI活用のさらなる発展形として「独自LLMの開発」を挙げた。
「自分達の事業に最適化した大規模言語を作り出せば、製造業ではマテリアルズインフォマティクス、製薬業界で新薬開発、金融業界ではデータアナリティクスがいっそう進むことでしょう」(森氏)
先進的な事例として、森氏はアメリカのブルームバーク社が2023年3月に開発した、金融特化型LLMを紹介した。
「金融データ提供企業として40年以上の歴史を築いてきたブルームバーグ社は、膨大な金融データのアーカイブを利用し、3630億トークンのデータセットを作成しています。このデータに3450億トークンの公開データセットを加え、7000億トークンを超える大規模なトレーニングコーパスを構築しました」(森氏)
ブルームバーグ社は、同社のLMMモデルが「金融タスクにおいて、同規模の既存オープンモデルを大きく上回る性能を発揮した」とプレスリリースで明らかにしている。 日本ではNECやNTTなど大企業、そしてサイバーエージェント、LINEなどのスタートアップなど、独自LLM開発を目指す動きが相次いでいる。
「政府もこの動きを積極的に支援しており、今後、世界の生成AI開発競争における日本のポテンシャルは高まっていくでしょう」(森氏)
3ステップで成長させる生成AI活用
企業は「攻めの生成AI活用」をどう進めるべきか。森氏は3つのステップに分けて考えるようアドバイスした。
「まずは生成AIを使って業務効率化に努めるファーストステップを目指してください。その上で、顧客や市場のニーズを捉える価値創出のステップを目指し、最後のステップである新ビジネスの創出へと発展させていくといいでしょう」(森氏)
現在、日本ディープラーニング協会顧問で、東北大学特任教授も務める森氏は、グローバル6000名(国内は500名)を擁するDAIIをリードする存在だ。AIの戦略的活用とガバナンスの研究を専門としているDAIIに、生成AIを活用した「攻めの事業」をどう進めるべきか相談してみるのもいいだろう。