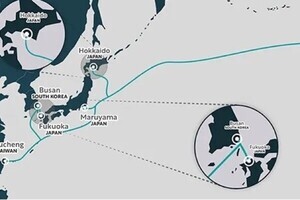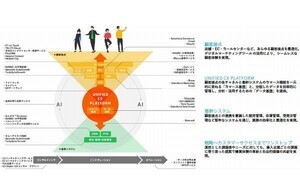日本音楽事業者協会、日本芸能実演家団体協議会、音楽制作者連盟の芸能3団体は4月30日、インターネットなどでテレビ番組を配信する際の許諾申請の窓口となる「映像コンテンツ権利処理機構(仮称)」を設立することで合意したと発表した。
テレビ番組の権利処理は、歌手や俳優など多くの実演家が出演するため、これら実演家の「著作隣接権」の権利処理が複雑なものとなっている。今回の新機構は、こうした権利処理を一括して受け付けることで権利処理を容易にし、テレビ番組の二次利用を促進することを目的に設立されることとなった。具体的には、放送事業者や番組制作会社を対象に、テレビ番組をインターネットで配信するための許諾申請を統一窓口として受け付ける。
機構を設立した3団体は趣意書で、「実演家の許諾権を制限し、事後的な報酬請求権とする制度を創設することが、流通促進及びコンテンツ市場拡大につながるとの主張が散見される」といわゆる「ネット法(※)」などの構想に言及。「流通促進のために創作活動のインセンティブを奪う制度を作ることがコンテンツ大国に資するとの主張が、本末転倒であることは明白である」と批判している。
※ 「ネット法」=2008年3月、政策研究大学院大学学長の八田達夫氏が代表を務める民間研究団体「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が開催したフォーラムで発表された、ネット上の著作権を制度的に制限しようとする案。同案では、ネット上の流通に限定した、デジタルコンテンツの使用権(ネット権)を創設。このネット権を、映画製作者や放送事業者、レコード会社などに付与し、著作権者は、コンテンツのネット上での使用に対する「許諾権」を制限されるとしている。
その上で、「コンテンツ大国の実現を願う我々実演家、事業者としては、自らの演技・パフォーマンスの露出を許諾し、制御していく権利こそ、コンテンツ大国を支える最も重要な基盤」と主張。権利者主導でネット配信を促進していくことを目的に、映像コンテンツ権利処理機構を設立した趣旨が述べられている。
同機構は2009年5月中に一般社団法人として法人登記した後、2010年4月から業務を開始する予定となっている。
番組IDなどのデータベースが整備されれば、「将来的には、通信事業者など放送・制作事業者以外からの申請も受け付けることになる可能性がある」(日本音楽事業者協会)としている。