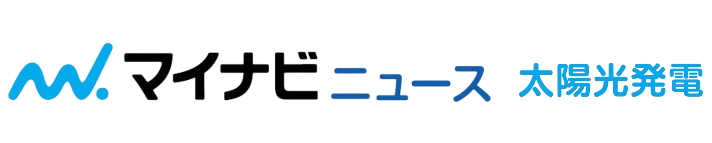太陽光発電に興味はあっても、そもそもどのようなものなのかよくわからずに、導入を迷っていませんか。太陽光発電は、光電効果という現象を利用した発電方法です。
屋根の上などに太陽光発電パネルを設置し、太陽光エネルギーを活用して電流を起こします。家庭の電気代を直接減らせるほか、売電という仕組みを利用することで利益を得ることも可能です。
ここでは基本的な太陽光発電の仕組みのほか、太陽光発電の仕組みを活かす具体的な方法を紹介します。太陽光発電を検討している方はぜひ参考にしてください。
マイナビニュース太陽光発電ガイド運営おすすめ!




太陽光発電の仕組みとは

なぜ屋根の上に乗せたパネルに太陽光が当たると発電が行えて、家庭で使えるようになるのでしょうか。まずはその仕組みを解説します。
発電の肝は光電効果
太陽光発電パネルに太陽の光が当たると、光電効果という現象が起こります。この現象に深く関わるのが、私たちの体にも備わっている電子という小さな粒です。電子は物質の最小単位でそれぞれが電気を帯びており、どんな物体にも存在しています。
しかし電子は通常、原子核という物質の周りを回転しており、そこから動くことはありません。ただし物質に光が当たった際には、原子核の周りにある電子の束縛が切れて、物質の外へ飛び出してしまう光電現象が起こります。太陽光発電パネルはこの飛び出した電子を捕まえ、活用することで電気を起こす仕組みです。
2種類の半導体を組み合わせて電流が発生
太陽光発電パネルは、n型とp型の2つのシリコン半導体を重ねることで、飛び出してきた電子を逃さない仕組みを持っており、この仕組みが電流を起こします。
半導体とは、たとえば鉄など金属ほど電気を通すことはないものの、ゴムのように電気を全く通さないわけでもないという、両者の中間の特徴を持つ物質です。この性質を活用することで、光電効果で外に飛び出してきた電子を逃さずに電流へ変えます。
乾電池をイメージしてみましょう。n型半導体はマイナスを帯びやすい性質で、p型半導体はプラスを帯びやすい性質に調整されています。
光電効果が起きた瞬間に、マイナスの性質(電荷)を持つ電子はn型半導体へ移動し、プラスの性質を持つ電子はp型半導体へ向かいます。
そのため、乾電池のようにプラスとマイナスの極が出来上がり、太陽光発電パネルの中で電流を集められる状態となるのです。
パワーコンディショナで交流に変換
太陽光発電パネルで発電された電流は、パワーコンディショナと呼ばれる機械で交流(AC)という電流に変換されます。なぜ変換が必要になるかというと、私たちが家や会社で通常利用する家電製品が対応している電流の流れ方が交流だからです。
太陽光発電パネルは、巨大な電池に似た仕組みを持っています。乾電池を正しく使うためには、機器が指定するプラスとマイナスの向きに合わせて電池をはめる必要があり、逆向きにはめてしまうと、そもそも乾電池として利用できません。そこで交流の状態へ変換できるパワーコンディショナを通すことで、発電した電気を利用できる形にします。
太陽光発電で押さえておくべき用語・単位

太陽光発電を効率の面から理解する際に、知っておきたい用語がいくつかあります。
- 太陽光発電パネルの単位
- 太陽光で生まれる電気の量
- 太陽光発電の変換効率
それぞれについて詳しくみていきましょう。
太陽光発電パネルの単位
太陽電池をたくさんつなげたものが太陽光発電パネルで、つなぎ合わせた規模により3つに分かれます。
- セル
- モジュール
- アレイ
セル
セルは太陽光発電パネルを構成する太陽電池の中でも、もっとも小さな単位です。大きさは25mmの四角形で、セルがいくつもまとまることで、モジュールやアレイといった構成単位で呼ばれるようになります。
モジュール
セルをいくつか並べてパネル状にし、屋外で使える状態に加工したものをモジュールと呼びます。モジュール変換効率をもとに計算された発電量の数値が、実際の発電量により近いとされ、一般的な太陽光発電の単位として利用される点が特徴です。
アレイ
複数枚のモジュールを直列に並べ、さらに並列で組み合わせたものをアレイと呼びます。モジュールを直列でつないだ単位はストリングとも呼ばれ、つなぎ方次第で発電量を安定させてより多く引き出すことも可能です。
太陽光で生まれる電気の量
電気の量、すなわち電力そのものを示す単位をワット(W)といいます。太陽光発電では、主に太陽光パネルの性能の違いを示すためにWを利用するため、覚えておくと太陽光パネル同士の比較に役立つでしょう。
kW
Wは1,000から上の数値になると、1kWと表示されます。つまり1,000Wは1kWで、主に住宅用ではkWという単位が使われることが多いです。瞬間的な電力の強さを知りたい場合はkWを確認しましょう。
また、産業用の太陽光パネルの場合は発電量が家庭用より多いため、MW(メガワット)やGW(ギガワット)という単位で示します。この場合は1MWが1,000kWで、1GWは1,000MWです。
kWh
kWh(キロワットアワー)は、簡単に言うと一定時間内で発電できる電力の総量を示すための単位です。表にまとめると、kW(キロワット)とは次のような違いがあります。
| 単位(読み方) | 示している単位 | 使用される場面 |
| kW(キロワット) | 瞬間的な電力の発電量 | 設備の能力を示す際 |
| kWh(キロワットアワー) | 1時間で発電できる電気の総量 | 稼働により得られる電力の総量を表す際 |
たとえば6kWの太陽光パネルが、1時間ずっと発電できた場合の電力の総量は6kWhと表示されます。
太陽光発電の変換効率
変換効率とは、太陽光発電パネルへ太陽光が当たった際に、その太陽光発電パネルが何%くらいの電気を生み出せるのかを示す数値のことです。数値が高いほど、効率よく太陽光を電力へ変換していると判断できます。
太陽光発電パネルの単位に応じて、次の2つのどちらかで表示されます。
- モジュール1平方メートルあたりの変換効率
- セルあたりの変換効率
モジュール変換効率
一般的に太陽光発電パネルの性能を示す際は、モジュール変換効率が用いられます。計算の際に使用される式は以下の通りです。
(モジュール公称最大出力(W)×100)÷(モジュール面積(m2)×1000(W/m2))
製品のカタログに掲載される数値は、一般的にはモジュール変換効率を利用していることが多いです。もし業者などの説明で変換効率という言葉が出てきた場合は、モジュール変換効率のことを示していると考えるとよいでしょう。
セル変換効率
セル変換効率とは、太陽光発電パネルのもっとも小さな単位である、セル1枚あたりの変換効率を示すための値です。計算式は次の式が使用されます。
出力電気エネルギー÷太陽光エネルギー×100
もっとも小さな単位であるセル変換効率が使われず、なぜモジュール変換効率のほうがよく使われるのかというと、セル変換効率のほうが実際の効率よりも高く出やすいためです。
モジュール内ではセルとセルが並んで配置されますが、その間を回路がつなぐため、どうしても発電量が落ちてしまいます。したがってセル変換効率で示してしまうと、実際の変換効率を正しく把握しにくくなるのです。
太陽光発電パネルの種類と特徴
現在、一般に普及している太陽光発電パネルの種類は2つあります。
- 一般的に広く普及しているシリコン系
- 低コストで量産しやすい化合物系
導入時の建設費や発電効率の予測にも関わるため、特徴を把握しておきましょう。
太陽光発電パネルで普及しているシリコン系
最も多く普及しているのがシリコン系と呼ばれる素材で、国内市場の80%はシリコン系とされるほど普及しています。シリコンとは、ケイ素と呼ばれる物質の原資を規則正しく並べたもので、半導体として初期から太陽光発電に活用されてきました。次の表のようにシリコン系には3種類あります。
| 種類 | 特徴 | 初期費用 |
| 薄膜シリコン |
| 安価でコストを抑えやすい |
| 単結晶シリコン |
| 比較的高額でコストが高い |
| 多結晶シリコン |
| 単結晶シリコンよりは安価 |
低コストで量産可能な化合物系
シリコン以外の素材で作られた化合物を利用して作られるのが、化合物系と呼ばれる太陽光パネルです。シリコン系と比較すると、全体的に素材が少なくて済むためコストがかからず、設置先の候補も柔軟に選べます。主に利用されるのは次の2つです。
| 材料 | 特徴 | 初期費用 |
| CIS |
| シリコン系と比べると比較的コストは安価 |
| CIGS |
| シリコン系と比べると比較的コストは安価 |
また海外では、CdTeと呼ばれるカドミウムやテルルといった素材を利用したものも導入されています。ただしカドミウムは毒性を有するため、国内では利用されていません。
開発が進められている2種の新素材
まだ一般には普及していない、次世代型の太陽光発電パネルも開発が進められています。現在注目されているのは次の2つですが、それぞれ特徴が異なります。
- 実現すると薄くて軽い有機系
- エネルギーの変換に無駄が少ない量子ドット
実現すると薄くて軽い有機系
無機物ではなく、有機物を素材とした太陽光発電パネルです。実用化はまだ難しいものの、製造コストが非常に安いほかに自由自在に曲げられるほど薄く、着色も可能な素材として注目を集めています。研究されている方向性として、有機薄膜太陽電池と色素増感型太陽電池の2つに分かれます。
有機薄膜型太陽光電池は、p型半導体とn型半導体を持つ非常に薄い膜の接合を活用した発電方法です。有機系の素材は、パネル状にする必要がある化合物系やシリコン系と異なり、インク状になった半導体を塗り付けることで使えるため、太陽光による発電が行えるのはパネルだけとは限りません。
また色素増感型太陽電池は、植物の光合成のように色素自体が光を吸収することで、太陽光を電気へ変える仕組みを持ちます。光の量が少なくても発電効率を維持しやすいほか、寿命の長期化も期待されています。
エネルギーの変換に無駄が少ない量子ドット
量子ドットとは、直径10ナノミクロンの非常に小さな結晶を活用した太陽光発電の素材です。これまでは太陽光発電パネルに当たっていても、利用できなかった光まで活用することで、理論上は75%という高い変換効率が見込めるとされます。
ただし、まだ基礎研究と呼ばれる技術の根幹部分の段階です。そのため、将来的には成功する可能性もあるというこ認識でとらえておきましょう。
太陽光発電の発電量を左右する3つの要素

効率よく太陽光発電が行われ、実際に活用できる電気を得られるかどうかは、次の3つの要素が重要です。
- 太陽光発電設備の性能
- 太陽光発電中の天候
- 太陽光発電パネルの状態
それぞれ重視したいポイントが異なるため、別々に解説します。
太陽光発電設備の性能
発電性能は次のような条件で異なります。
- 使用している太陽光発電パネルの種類
- 設置数
- パワーコンディショナの変換効率
- パワーコンディショナの最大定格出力
太陽光発電パネルの種類や設置数は、設置を予定する場所で異なります。たとえば自宅の屋根の上と利用していない水田では、置ける面積も場所も違うため設置数は異なるでしょう。ただし設置数が少ないほど発電できる電気量も減るため、希望する発電量と比較することも大切です。適切な設置数や種類を選ぶことで、発電量を高められます。
そしてパワーコンディショナは、接続される太陽光発電モジュールの出力可能な電力よりも、出力可能な数値が大きい必要があります。太陽光発電モジュールのほうの出力が大きいと、変換しきれずに不要な電気として捨てられてしまうためです。変換効率を確認するとともに、チェックしておくとよいでしょう。
太陽光発電中の天候
太陽光が太陽光発電パネルに当たらない地域では、どうしても発電量が減ってしまいます。そのため次の表のように、地域の天候を考えて適切な太陽光発電パネルを選ぶことが重要です。
| 地域 | 気温 | 日照時間 | 積雪 | 災害 |
| 発電量が多い地域 | 25℃前後 | 年間を通じて長い | ないか、あっても手入れできる | 比較的少ない |
| 発電量が少ない地域 | 30℃以上 | 年間を通じて短い | あり | 台風や水害の可能性がある |
たとえば高温になりやすい地域なら、温度が上がると変換効率にどのような影響が出るのかをチェックして、比較的影響が少ない太陽光発電パネルを設置するという手があります。
太陽光発電パネルの状態
太陽光発電パネルそのものに起きる変化でも、発電量は変わってきます。具体的には次のような状況です。
- 太陽光発電パネルを設置してから20~30年
- 台風によるパネルの損傷
- 落雷によるシステムトラブル
- 太陽光発電パネル表面についた汚れ
- 草木の影
- 積雪
太陽光発電パネルの寿命は20~30年と比較的長いものの、その性能自体は毎年劣化してしまいます。定期的なメンテナンスが必要なほか、太陽光発電パネルごとに設定された出力保証を参考に、交換していくのも手です。
また、台風など自然災害によるトラブルやパネル表面に積雪や汚れなどで影ができると、太陽光を受けて電力へ変換できる面積が減ってしまいます。よって定期的にチェックし、周辺環境も含めてメンテナンスを行うとよいでしょう。
太陽光発電の仕組みを活かす方法

せっかく発電した電力を、無駄にせずに活用するための方法として次の3つが挙げられます。
- 環境に合った太陽光発電設備を導入
- 電気を無駄にしないために蓄電池を設置
- 太陽光発電の余剰分は売電
太陽光発電の仕組みを活用するためには、方法ごとに必要な要素があるためそれぞれ解説します。
環境に合った太陽光発電設備を導入
太陽光発電パネルを設置する場所やその環境を考えて、導入する太陽光発電パネルを選ぶことで、発電量を落としにくくなります。場所ごとに考えられる対策を表にまとめました。
| 設置場所の環境 | 対策 |
| 狭い場所や屋根の上の複雑な位置に設置したい |
|
| パネルの一部に影がかかる可能性がある |
|
| 地域として曇りや雨が多い | 日照が少なくても発電効率が高いパネルを選ぶ |
| 晴天が多いが気温が高くなりやすい | 高音でも変換効率が落ちにくいパネルを選ぶ |
| 晴天は多いが積雪の可能性がある | 積雪が多い地域のメーカーを選ぶ |
【専門家の回答!】発電量が確保できるかは事前に確認

 高島さん
高島さん太陽光発電の設置が向いている家、そうでない家の特徴はありますか?



北向き・積雪・塩害地域など発電量があまり確保できないお家はやめた方がいいです。
新築時であれば屋根の種類や向きの調整である程度太陽光に向いた家が作れますが、積雪、塩害地域など発電量があまり確保できない地域の場合はおすすめできません。必ず導入を検討する前に確認しましょう。
電気を無駄にしないために蓄電池を設置
せっかく発電した電気でも、その日の使い方次第では余ってしまう場合があります。そこで、太陽光発電と組み合わせて利用されるのが蓄電池です。導入することにより太陽光発電で作られた電気を貯めておき、夜間や停電時などの非常時に利用できます。夜間のほうが電力を使うことが多い家庭にとっては、電気を無駄にせず利用できるでしょう。
ただし、メリットが多い一方で、次のようなデメリットもあります。
- 家庭用でも90万~150万円以上と価格が高い
- 充電を繰り返すと寿命が来て利用できなくなる
- 設置場所を追加で確保する必要がある
価格面については、自治体や国の補助金を活用することでカバーできる場合もあります。また蓄電池によっては、機能を維持しやすいシステムが搭載されているものや、パワーコンディショナとセットになっているものもあるため、安さだけでなく性能面も確認することが大切です。
太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!


太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
太陽光発電の余剰分は売電
売電とは、太陽光発電で作られた電力を電力会社へ送り、買い取ってもらうことです。1kWhあたり何円で買い取るのかは、固定価格買取制度(FiT)という制度によって定められています。売れる期間や価格は発電量によって異なるほか、売却を始める年によっても異なるのが特徴です。
例として、2024年に売電を始めると次の価格で売却できます。
| 電源 | 規模 | 2024年の価格 |
| 住宅用太陽光発電 | 10kW未満 | 16円 |
| 事業用太陽光発電 | 10kW以上50kW未満 | 10円+税 |
| 事業用太陽光発電 | 50kW以上250kW未満 | 9.2円+税 |
“参考:資源エネルギー庁 固定買取価格制度 を元に作成”
この内容から見ると住宅用と仮定した場合は、1kWhあたり16円で買い取ってもらえると分かります。
太陽光発電設備にかかるコスト


太陽光発電を設置する場合は、初期費用とランニングコストの2つの視点から費用を考える必要があります。
太陽光発電設備の初期費用
家庭用の太陽光発電設備を購入すると仮定したときに、初期費用は1kWに対し20万~30万円程度が目安です。ただしメーカーによって、1kWを発電できるパネルの枚数や1枚当たりの価格は異なるため、実際にはメーカーごとに比較する必要があります。
また、工事費用やパワーコンディショナの費用も別途かかるため、余裕をもって初期費用は30万円前後を目安にしておくとよいでしょう。
ポイントとして、太陽光発電の導入には補助金の利用も可能です。自治体が提供している補助金を利用することで、費用を抑えられる可能性もあります。
初期費用をより詳しく把握したい方は、以下の記事で太陽光発電の初期費用について詳細に解説しているのでぜひご覧ください。


「複数の業者を比較して、質の高い業者に依頼したい」「評判が悪い業者に騙されたくない」という方に向けて、実際にサービスを利用したことのある方に行ったアンケート結果をもとに、太陽光発電一括見積もりサイトをランキング形式で紹介!
さらに、専門家に聞いた太陽光発電一括見積もりサイトを利用する際の注意点や、質の高い業者を見極めるポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。


太陽光発電設備のランニングコスト
太陽光発電パネルに汚れや故障があると発電効率が落ちる原因になるため、定期的なメンテナンスや掃除をすることが重要です。かかる可能性があるランニングコストとしては、以下の表の内容が挙げられます。
| ランニングコストの内訳 | 費用の目安 |
| パワーコンディショナの夜間の待機電気代 | パワーコンディショナの台数に応じた定額料金 |
| 設備点検費用 | 1回10,000円前後 |
| 清掃費用 | 汚れに応じて高額になる |
| 故障時の修理費用 | メーターは10,000~50,000円 |
| パワーコンディショナの交換費用 | 10万~40万円 |
| 所得税 | 売電で利益が生じていた場合 |
メーカーによって期間は異なりますが、10年以上の保証期間があることが多く、保証期間内であれば点検や修理がお得に行えます。また導入後のことも考えて、定期点検を受けやすい太陽光発電の専門業者を選ぶのもひとつでしょう。


太陽光発電の設置費用は徐々に下がっている





太陽光発電の設置費用は今後も下がり続けていくのでしょうか?



太陽光発電の導入費用は徐々に下がる予測です。
世界的な需要が高まって、1枚当たりのコストを下げることができています。設置費用が下がっている理由は、世界的に需要が増して大量生産されることにより、コストが下がっていることが挙げられ、今後も下がり続けていきます。
日本は円安の影響もあるが、今後も世界的には下がっていくと予測しています。


まとめ
太陽光発電は光電効果を利用し、太陽光発電パネル内で電流を起こすことで発電します。そのままでは家庭用としては使えないため、パワーコンディショナを利用して交流という電流に変換することも必要です。
また発電量はパネルの機能や設置環境にも左右されます。適切な発電量を得るためには、設置を予定する場所ではどのような機能が必要なのか、事前に繰り返し検討したうえで導入を進めていきましょう。
監修者情報


比連崎 実/Webマーケター
大学院卒業後、システムエンジニアを経てマスコミ業界に勤務。約8年間、関東や東海、近畿地方のテレビ局で気象キャスターを経験。現在はWebマーケターとして、住宅会社を中心としたコンサル業務にあたる。Instagramを活用した集客を得意としており、「家を売るためのInstagramマーケティング」などのセミナーにも多数登壇。


太陽光や蓄電池等の専門家。2017年より某外資系パネルメーカーに所属し年間1000件以上の太陽光を販売しトップセールスを記録。これまでの知見を活かしたYouTubeが業界NO,1の再生数を誇り、2021年に開業。現在は一般の方向けに自社で販売〜工事を請け負う。Youtubeチャンネル
※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・東京都環境局
・こどもエコすまい支援事業
・葛飾区公式ホームページ
・経済産業省
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。