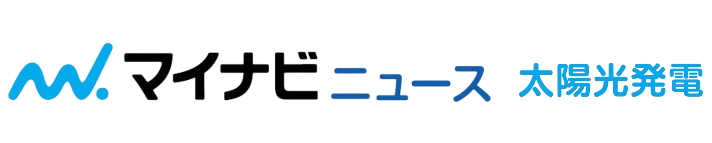土地の有効活用法として、野立て太陽光発電の利用が挙げられます。自宅の屋根などに設置する場合と比べると、発電容量の大きな設備も設置しやすく、土地活用にも役立てられるのがメリットです。
しかし太陽光発電はさまざまな制度を利用するほか、デメリットがあることも事実です。準備不足のまま始めてしまうと、後悔してしまうかもしれません。ここでは、野立て太陽光発電のメリット・デメリット、初期費用やよくある疑問について紹介します。
本記事を読むことで野立て太陽光発電について、より具体的に検討できるようになるでしょう。
マイナビニュース太陽光発電ガイド運営おすすめ!



野立て太陽光発電の導入で失敗しないためには、複数のメーカー・販売施工業者を比較・検討して選ぶことが重要です。メーカーによってかかる費用やサービスなど違いがあるため複数業者をしっかり比較することで失敗を避けることができます。



野立て太陽光発電に関する基礎知識

太陽光発電は設置場所によって、メリット・デメリットや注意したいポイントも変わります。ここでは野立て太陽光発電について、その特徴や概要を解説します。
野立て太陽光発電とは
野立て太陽光発電は自宅や工場の屋根の上ではなく、遊休地や利用していない田畑などの土地へ直に太陽光発電を設置する方法のことです。太陽光発電により利益を上げる仕組みは、発電した電気を電力会社に売ることで成り立ちます。
買取価格は国の固定価格買取制度(FIT)により、事業用の太陽光発電なら20年間、家庭向けの太陽光発電なら10年間、同じ価格で買い取りを継続してくれるため、安定した利益を上げられることがメリットです。
設置方法
野立て太陽光発電の設置方法は、地盤の強度や設置する設備の発電量などによってさまざまです。
たとえば土地の造成を行ったあとにコンクリートで基礎を作り、その上に太陽光発電パネルを設置する台を作る方法や、スクリュー杭と呼ばれる大きなねじを地面に打ち込み設置する方法があります。
以下は、スクリュー杭により設置を行う場合の手順を簡単にまとめたものです。
- 杭を打ち込む場所を測量する
- 位置を決定する
- 地面にスクリュー杭を打ち込む
- 高さを調節する
- ケーブルの埋設配管を行う
- 防草シートと砕石を敷いていく
- 架台を設置し角度を調節する
- 太陽光パネルや機器を設置する
設置完了までにかかる期間は、土地の広さや工事内容にもよりますが6ヶ月が目安です。元の土地の状況によっては、水はけをよくするための工事や草木の伐採が必要なこともあります。
設置容量
野立て太陽光発電は、10kW以上を発電できる産業用太陽光発電が多い傾向にあります。産業用太陽光発電は2020年度まで、10kW以上であれば生み出した電気を全量買い取ってもらえる全量買取が選択できたためです。
また土地の面積が広く太陽光発電に適している場合は、1,000kW以上の発電が行えるメガソーラーを設置できる可能性もあります。
ただし2020年以降は余剰電力のみの買取となり、全量買取を選ぶためには50kW以上の高圧が運用できる設備を用意しなければなりません。敷地面積や立地条件、投資できる予算次第で異なるため、事前のシミュレーションが重要です。
必要な面積と計算方法
産業用太陽光発電と区分される10kW以上のパネルを設置するためには、最低でも約100平方メートル、坪数でいえば30坪の面積が必要です。
ただし、この面積いっぱいに太陽光発電パネルを敷き詰めることはできません。なぜなら、次のような設備用スペースも確保する必要があるためです。
- 機器を設置する面積
- 立ち入り防止のフェンスを設置する面積
- メンテナンス用の通路の面積
最低限必要な面積をある程度把握するために、今所有している土地に設置できる容量と設置したい容量をもとにした計算方法を以下に示したので、参考にしてください。
今の土地に設置できる容量の計算方法
今ある土地から計算する際は2段階に分けて算出します。まずは次の式で、所有する土地の中で利用できる面積を計算しましょう。
利用できる土地の面積=(縦の長さー2)×(横の長さー2)
2を引いているのは、 メンテナンス作業や第三者と設備の間に距離を設けるフェンスや通路に対し、少なくとも1m以上の面積を必要とするためです。ここで分かった面積を、1kWあたりに必要な面積で割ることで計算できます。
たとえば縦25平方メートル、横が16平方メートルの土地があったとします。この場合に利用できる土地の面積は322平方メートルです。例として1kWあたりに必要な面積が10平方メートルと仮定すると、この場合は最大で32.2kWの設備を設置できると分かります。
設置したい容量から計算する方法
設置したい容量をもとにした計算式は以下の通りです。
(導入したい容量×1kWあたりに必要な面積)+外周の面積
50kWの野立て太陽光発電の導入を目指す場合は、1kWあたりに必要な面積を10平方メートルと仮定して計算してみましょう。まず太陽光パネルそのものに必要な面積は50kW×10平方メートルで、500平方メートルとわかります。つまり縦10m、横50mの土地が該当します。
ポイントとなるのが、メンテナンス作業にも活用でき、第三者と設備の間に距離を設けるフェンスや通路を設けることが義務付けられている点です。少なくとも1m以上は必要なので、例でいえば縦12m×横52mの土地が望ましく、面積としては624平方メートル必要だとわかります。
野立て太陽光発電のメリット

野立て太陽光発電は、自宅の屋根などに設置する場合に比べると次の4つのメリットがあり、特に下2つが大きな特徴です。それぞれ具体的になぜメリットといえるのか解説します。
- 長期間安定した収入を得ることができる
- 高利回りが期待できる
- 土地を有効に活用することができる
- 家庭用よりも出力が大きい
長期間安定した収入を得ることができる
野立て太陽光発電は、国の固定価格買取制度(FIT)を利用することで、長期的に安定した収入が得られることがメリットです。具体的には、産業用太陽光発電とされる10kW以上の太陽光発電を設置できれば、20年間は同じ額で電気の買い取りが行われます。
家庭用太陽光発電が10年間であることと比べると、初期投資費用は大きいものの十分に回収できる可能性が高いです。
高利回りが期待できる
不動産投資のように、空室や家賃値下げといったリスクを抱えることなく、高利回りが期待できることも野立て太陽光発電のメリットです。日照時間が長く、日当たりのよい太陽光発電に向いた土地であれば、利回りが10%を超えるケースもあります。
利回りとは、初期投資費用を1年あたりどのくらい回収できるかを割り出した数値です。仮に10%となれば、10年間で初期投資費用を回収し、その後の10年間で得られる利益は手元に残る計算になります。
自分の所有する土地を活用すれば、より利回りが高くなることもあるため、土地活用を目的とした野立て太陽光発電はメリットが大きいといえるでしょう。
土地を有効に活用することができる
未開拓の耕作放棄地や実家が所有していた空き地など、土地の有効活用にも野立て太陽光発電は向いています。たとえば不動産投資の場合は、アパートやマンションの需要が高く人も多く住む地域でなければ難しいでしょう。
しかし太陽光発電の場合は、日照時間の確保や電柱の有無、災害の危険性が少ないなど、向いている土地であれば設置するだけで利益が望めます。
家庭用よりも出力が大きい
産業用太陽光発電は、家庭用太陽光発電に比べてより多くの電気を供給できるため、将来的に自家消費へ切り替えた場合のメリットは大きいといえます。さらに会社などオフィスの電力の一部を、太陽光発電で賄うことも可能です。また災害時にも非常用電源として利用できます。
野立て太陽光発電のデメリット

次に野立て太陽光発電のデメリットをみていきましょう。以下は設置そのもので起きうるデメリットや、家庭用と比較した場合に考えられるデメリットです。
- 近隣住民とトラブルになる場合がある
- 災害で被害を受ける可能性がある
- 周囲に遮蔽物があると影響を受ける
- 家庭用と比べると初期費用が高い
- 農地に設置する場合は手続きが必要
近隣住民とトラブルになる場合がある
対策を十分に行わなかった場合は、近隣住民との間に次のようなトラブルが起きる可能性があります。
- 太陽光パネルに当たった太陽光による光害トラブル
- パワーコンディショナの騒音トラブル
- 電磁波によって体調が悪化したとするトラブル
- 雑草や手入れ不足によるトラブル
- 土壌流出によるトラブル
- 土地境界があいまいだったことによるトラブル
- 子供たちが設備を遊び場にしてしまうトラブル
これらのトラブルは、事前に対策を行うことで回避できる可能性が高いです。オーナーとして、まずは太陽光発電に関する正しい知識を身につけ、近隣住民に対する実質的な影響と心理面への影響の双方を考慮し、客観的な説明ができるようになる必要があります。
たとえばパワーコンディショナの音は、エアコンの室外機くらいが目安です。しかし中にはそれでも気になる方がいる可能性もあるため、事前に野立て太陽光発電を建てたい地域の近隣住民に、あいさつ回りを兼ねて事前調査を行いましょう。遠方に住んでいる場合はトラブルに対応しやすいように、起こりやすいトラブルを把握している業者を探しておくと安心です。
災害で被害を受ける可能性がある
野立て太陽光発電は野外にすべての設備を設置するため、次のような災害による被害を受ける可能性があります。
- 豪雨による土砂崩れで設備が破損
- 台風や暴風による飛来物により設備が破損
- 積雪による設備の破損や発電量の低下
独立行政法人製品評価技術基盤機構が公表した「平成30年度 電気保安統計」によると、台風21号による50kW以上の太陽光発電設備の被害は23件にも上ります。
そのうち被害が出た原因は強風や高潮で、損傷を受けたのはパネルが21件と最も多いです。そのため、次のように事前にできるだけ対策を行うことが大切です。
- 自然災害に有効な保険への加入
- ハザードマップをもとに想定される自然災害の予測
- 想定される自然災害に堪えうる耐久性を持つ設備の設計
- 定期的なメンテナンスによる設備点検
- 業者側のサポート内容の確認
自然災害は、人間の力ではどうにもできないケースも十分考えられます。
しかし、そこで被害を受けた場合にどのようなサポートが得られるのかを、業者によく確認しておきましょう。
メーカー側の保証内容や保証期間も事前に把握しておくことが大切です。また火災保険や地震保険などの損害保険へ必ず加入しておきましょう。
周囲に遮蔽物があると影響を受ける
野立て太陽光発電の場合は、屋根の上に設置するものと比較してパネルの設置位置が低くなるため、周囲の建物や木々など遮蔽物による日陰の影響を受けやすくなることはデメリットといえます。
発電量が減るということは、回収できる費用も少なくなってしまうため、建設前の土地選びや設置時の対策が重要です。
家庭用と比べると初期費用が高い
野立て太陽光発電の初期費用は1,500万円から2,000万円と高額で、屋根に設置するよりも多くの費用が発生します。もし土地を所有していない場合は、土地の購入費用も別途必要です。
さらに面積が広いため、定期的なメンテナンスにかかる費用も毎年50,000円~15万円はかかります。
メンテナンス費用も含めて予算を検討し、初期費用の回収を現実的に計画することが大切です。
農地に設置する場合は手続きが必要
野立て太陽光発電を農地に設置したい場合は、状況次第で農地転用という手続きが必要です。
なぜ農地転用の手続きが必要かというと、日本において農地は農地法によって一定の規制が設けられており、農業以外の目的で使うためには許可を得る必要があるためです。無許可で野立て太陽光発電を建てた場合は、罰金が科されることもあります。
また、農地の面積が4ヘクタールを超える場合は、都道府県知事へ申請を行います。
4ヘクタール以上の農地の場合は、農林水産大臣が指定する市町村の首長へ申請を行い、許可を得ましょう。許可を出せる人が都道府県知事の場合は、次のように手続きを行います。
- 必要書類を取得する
- 許可申請書を農業委員会へ提出
- 許可が下りたら農業委員会より申請者へ許可指令書が送付される
- 宅地造成や太陽光発電設備の設置
- 地目の変更
必要書類については、農地が市街化調整区域内か市街化調整区域外かによっても異なります。また、これらは最低でも1ヶ月以上かかる手続きで、状況次第では農地転用まで半年を超えることもあります。そのため、農地転用を得意分野とする行政書士に依頼することが一般的です。
野立て太陽光発電にかかる設置費用

野立て太陽光発電を始めるためには初期費用としていくら必要になるのか、諸費用やメンテナンス費用、修理費用の目安について解説します。
初期費用
太陽光発電の設置や造成、土地の費用を含めた初期費用は、目安として1,500万~2,000万円です。1kWあたりの価格でいえば、30万円以上~40万円前後が目安です。では、なぜ初期投資が高額になるのでしょうか。価格の内訳をみると次のようになっています。
| 内訳 | 費用目安 |
| 設備費用(モジュール、パワーコンディショナ、操作表示ユニットなど) | 1,200万~1,500万円 |
| 工事費用 | 300万~500万円 |
| 土地購入費用(土地がない場合) | 地域や面積によって変動 |
主に費用としてかかるのが設備面への費用です。土地と設備がセットで販売されている場合もありますが、その場合も1,500万円以上みておくとよいでしょう。土地を所有していない場合は、土地の購入費用や不動産会社へ支払う費用も含めて考える必要があります。
初期費用を節約し、野立て太陽光発電を手元の資金内でスムーズに始めたい方は、以下の記事もご覧ください。

その他の諸費用
諸費用としてかかる可能性があるのは以下の内容です。なお諸費用は、設置する太陽光発電の容量や土地の状況次第で、発生しない場合もあります。太陽光発電の施工を依頼する業者とよく相談しましょう。
| 項目 | 費用目安 |
| 電力会社との接続検討費用 (50kW以上の高圧連携設備の場合) | 21万円 |
| 土地が農地だった場合の地目変更の手続き費用 | 50,000~40万円 |
| 土地の状況次第で整地費用 | 600万円~ |
接続検討とは、電力会社が所有している電力供給設備に対し、自分が所有する太陽光発電を接続するために発生する手続きや工事のことです。50kW以上の高圧連携設備の場合は費用が発生しますが、50kW以下であれば手続きのみ必要になります。
メンテナンスや修理費用
野立て太陽光発電を設置した場合の年間のランニングコストの目安について、以下の表にまとめました。
| 項目 | 発生する理由 | 費用の目安 |
| メンテナンス費用 | 保守点検のため | 1回20,000円 |
| 清掃費用 | 発電障害を防ぐため | 10万円 |
| 損害保険料 | 自然災害のトラブルへのリスク対策 | 初期費用の0.3~3% |
| 固定資産税・所得税 | 太陽光発電の設備と売電収益に対し発生する税金 | 収益と設備に基づく |
| 電気代 | 夜間の待機電力に必要 | 6,000円~(パワーコンディショナの設備にもよる) |
| パワーコンディショナの買い替え費用 | パワーコンディショナの平均寿命が10年といわれるため | 30万円~ |
| 遠隔管理システムの費用 | 長期的な運用においてトラブルをすぐ発見できるため | 40,000円前後 |
メンテナンスは次の頻度で行うことが推奨されています。
- 設置から1年目
- 設置から5年目
- 設置から9年目
- 9年目以降は4年に1回
ただしこれはあくまでも目安です。たとえば風による影響が起こりやすい地域であれば、機器の損傷がないかチェックする頻度を上げ、トラブルを未然に防ぐためのメンテナンス計画を立てる必要があります。

太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!
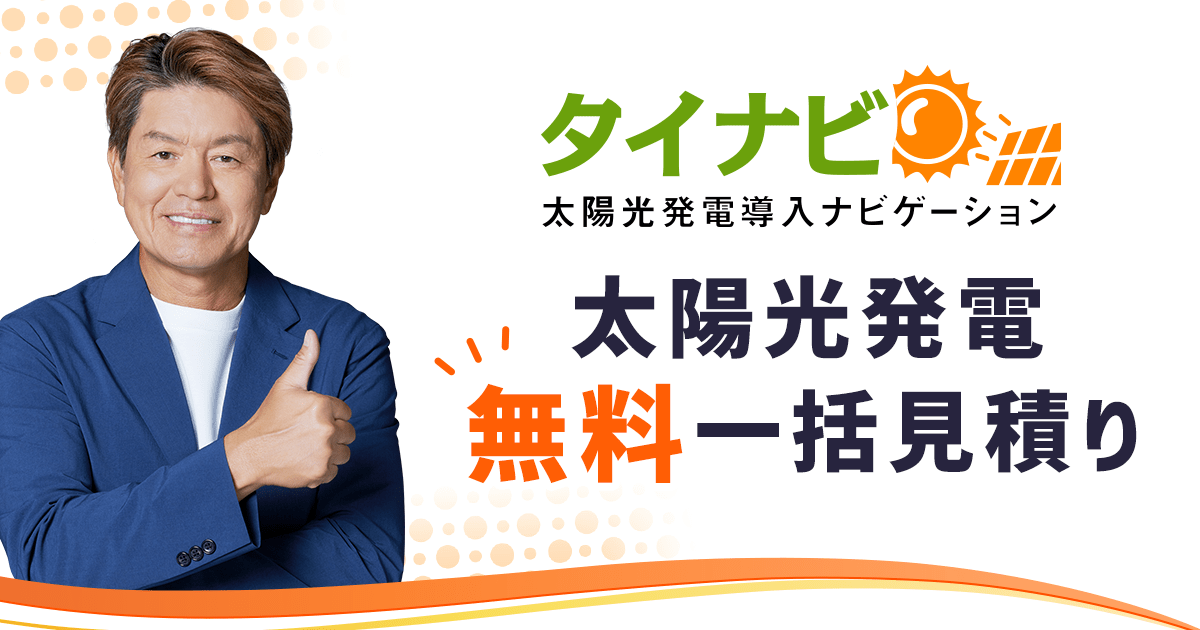
太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース太陽光ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
【Q&A】野立て太陽光発電の設置でよくある疑問
ここでは野立て太陽光発電の設置に関する3つの疑問に、Q&A方式で解説を行います。
- どれくらいの期間で設置費用が回収できる?
- 固定買取期間終了後はどうなる?
- 野立て太陽光発電は今から設置するべき?
太陽光の専門家監修!太陽光発電一括見積もりサイトおすすめランキング

「複数業者を比較して、質の高い業者に依頼したい」「評判が悪い業者に騙されたくない」という方に向けて、実際にサービスを利用したことのある方に行ったアンケート結果をもとに、太陽光発電一括見積もりサイトをランキング形式で紹介!
さらに、専門家に聞いた太陽光発電一括見積もりサイトを利用する際の注意点や、質の高い業者を見極めるポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。
まとめ
野立て太陽光発電は、家庭用太陽光発電に比べると10kW以上の容量を持つ設備を導入しやすく、20年間の全量買取制度を活用することで長期的な収益を得られます。しかし、土地自体に野立て太陽光発電が向いていなかったり、設置できる太陽光発電の容量次第ではデメリットがあったりすることも事実です。
50kWを超えない設備の場合は余剰買取のみが適応されるほか、初期投資も1,200万円以上と高額になります。シミュレーションをよく行い、自分にとって野立て太陽光発電は本当により良い方法なのか、よく検討してみましょう。
※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・東京都環境局
・みらいエコ住宅2026事業
・葛飾区公式ホームページ
・経済産業省
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。