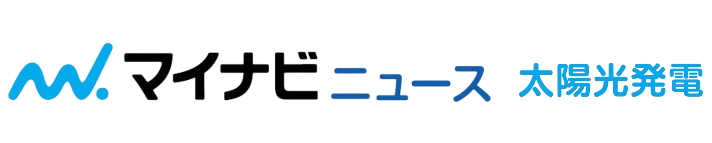停電対策への意識や「創エネ思考」が高まるなかで、マンションに太陽光発電を導入したいと考える方が増えています。「マンションでも太陽光発電ができるの?」という疑問を持つ人もいるかもしれませんが、結論から言うと可能です。
既に2010年の秋頃から、マンションに太陽光発電を導入するオーナーが増えています。また、新築や分譲マンションでも、超小型のソーラーパネルをベランダやバルコニーに設置すれば、小規模ながらも部屋単位での太陽光発電ができる時代になりました。
そこでこの記事では、マンションへの太陽光発電の導入にどのようなメリットや活用方法があるのかを、関わりの深い制度と併せて詳しく解説していきます。この記事を読めば、マンションに太陽光発電を導入することは決して不可能ではないことが分かるでしょう。
マイナビニュース太陽光発電ガイド運営おすすめ!



マンションへの太陽光発電の導入で失敗しないためには、複数のメーカー・販売施工業者を比較・検討して選ぶことが重要です。メーカーによってかかる費用やアフターサービスなど違いがあるため複数業者をしっかり比較することで失敗を避けることができます。
マンションでの太陽光発電の活用方法

太陽光発電によって蓄えた電力をマンションで活用するには、以下の方法があります。この章ではそれぞれの方法について詳しく解説していきます。
- 自家消費にまわす
- 蓄電システムを同時導入し、非常用電源に使用する
- 余った電力は売電する(余剰売電)
まずは自家消費にまわす
自家消費とは、文字どおり太陽光発電によって蓄えた電気を自分のマンション内で使用することです。電気代の節約になるため、オーナーから見ればコスト面、入居者から見れば負担が減るメリットが大きいでしょう。
- 共用部分での使用
- 各部屋での使用
- オーナーの部屋での使用
共用部分で使用
マンションの入居者には、共用部分(エントランスやエレベーターホール、共用廊下や階段など)を維持するための管理費や共益費といった負担金があります。共用部分の照明等は常についているため、毎月支払う電気代はかなりの額になるはずです。オーナーにとってみれば、いくら管理費などの収入があっても、大きなコストに違いありません。
共用部分において太陽光発電による電力を使用できれば、電気代の節約となり、結果的に管理費を減らせる可能性が高まります。実際に管理費が減れば入居者へのメリットはとても大きく、物件の価値も上がるでしょう。
しかし、効率的な運用には蓄電池の併用が必要となってきます。詳しくは次の章でその理由を解説します。
各部屋で使用
次に自家消費率を上げるための手段として有効なのは、太陽光発電による電力を入居者に振り分けて使用してもらう方法です。この方法による入居者のメリットは、振り分けられた電力によって電気代を減らせることだけでなく、もし余った場合は余剰分を売電できるところになります。
設備投資無しではかなわない太陽光発電の電力を、初期費用の負担なしに売電できるかもしれないとなれば、物件の価値が上がりそれに伴って入居率の向上、賃料収入のアップが期待できます。これはオーナーにとって確実なメリットになり、魅力的な付加価値として、他の競合マンションとの差別化が図れるでしょう。
オーナーが使用
最後に投資物件でなく、居住用のマンションに太陽光発電を設置している場合は、その電力をオーナーの室内で使うのもひとつの方法です。オーナー宅の電気代を減らせるだけでなく、要件を満たしていれば、余剰売電で収益を得ることも可能となるため、選択肢としてはこちらも充分に魅力的であると言えるでしょう。
蓄電システムも導入し非常用電源などに
日中の太陽光によって発電された電力を夜間や災害時にも使用できるようにするため、蓄電池を設置し、同時に運用することを蓄電システムと呼びます。蓄電システムは電気代の節約ができるほか、非常用電源としても利用可能です。
- 重要な共用設備への備え
- 自家消費率の維持や向上
- 電気自動車の充電
初期投資額は増えてしまいますが、日中に蓄えた電力を、非常時に最低限動かす必要がある設備のためのエネルギー源にすることができれば、災害に強いマンションとしてアピールできるでしょう。最近では個人での導入に便利な太陽光発電キットでも、バッテリー(蓄電池の役割)・チャージコントローラー・インバーターがセットになっています。
余った電力は売電
自家消費で賄ってもまだ電力が余る場合は、積極的に売電をして、収益を高める方法を取り入れるのも良いでしょう。
注意点としては2020年4月1日、停電時に使用可能な太陽光発電設備を増やすことを目的として、FIT制度内に「地域活用要件」(資源エネルギー庁)が新設されました。この要件は2019年までにFIT認定を受けている発電設備には適用されず、今後新しくFIT認定を受けるためには、この地域活用要件を満たす必要があります。
- あくまで余った電力を売電すること
- 自家消費率30%を維持すること
- 災害時に自立運転機能を利用できるようにすること
- 災害用に給電用コンセントを活用すること
地域活用案件が新設されたことで、低圧の小規模太陽光発電設備の売電は、余剰分のみ買取がされる形式に変更となりました。そして今後も国による検討次第では、制度内容に変更が増える可能性があります。
| 設備規模 | 電力の買取方式 |
| 10kW以上50kW未満の太陽光発電設備(低圧) | 余剰買取方式に変更 |
| 50kW以上250kW未満の太陽光発電設備(高圧) | 全量買取制度を継続 |
“参考:資源エネルギー庁「固定価格買取制度(FIT制度)」”
マンションに太陽光発電を導入するメリット

太陽光発電を導入することで、マンションのオーナーが得られるメリットは以下の通りです。この章ではそれぞれのメリットがどのように働くのか、詳しく解説していきます。
- 投資効果が上がる
- 家賃以外の収入が得られる
- 災害時に電気が使える
- 土地の有効活用ができる
投資効果が上がる
一戸建てと比べ、マンションには特に屋根・屋上などに広いスペースがあるため、容量が多い大型の発電設備を設置しやすい強みがあります。余剰分の電力があれば売電が可能(10kW以上)となり、特に投資用マンションの場合には利回りが増え、金銭的なメリットがアップすると見て良いでしょう。
太陽光発電を整備した「ソーラーマンション」は、まだ多くありません。自家消費分で電気代を節約できるという付加価値によって、他マンションとの差別化を図れるのも、またメリットだと言えます。
この付加価値は、省エネ性能が優れている建造物に対して、国からのお墨付きであるBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)の認定や、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)(資源エネルギー庁)が表示できるようになると、より入居希望者にマンションを強くアピールするポイントにもなります。
毎月収入が得られる
国による再生エネルギーの固定買取制度(FIT制度)の認定を受けることができれば、マンションに設置した太陽光発電によって発電した電力を電力会社に買い取ってもらう、売電収入が得られるようになります。家賃以外の収入源となるため、この売電を目的として導入を検討する方も少なくないでしょう。
FITでは20年間(または10年間)固定価格での売電が可能となっていますが、発電設備の容量によって価格が変わってくることには注意が必要です。2024年以降のFITによる1kWあたりの調達価格については、下記の表をご覧下さい。
| 2024年度 | 2025年度 (4月~9月) | 2025年度 (10月~3月) | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10kW未満 | 16円 | 15円 | 24円(~4年) 8.3円(5~10年) | 24円(~4年) 8.3円(5~10年) |
| 10kW以上~ 50kW未満(屋根設置) | 12円 | 11.5円 | 19円(~5年) 8.3円(6~20年) | 19円(~5年) 8.3円(6~20年) |
| 50kW以上 (屋根設置) | 12円 | 11円 | ー | ー |
| 10kW以上50kW未満 | 10円 | 10円 | 9.9円 | |
| 50kW (地上設置、入札制度対象外) | 9.2円 | 8.9円 | 8.6円 | |
| 入札制度適用区分 | 入札制度により決定 (第20回9.2円/第21回9.13円/ 第22回9.05円/第23回8.98円) | 入札制度により決定 (第24回8.90円/第25回8.83円/ 第26回8.75円/第27回8.68円) | 入札制度により決定 | |
“出典元:資源エネルギー庁「買取価格・期間等」内の表を元に作成(2026年2月現在)”
“参考:経済産業省「令和3年以降の調達価格等に関する意見」”
(注)2021年にFIT制度内に新設された「地域活用案件」により、10kW以上50kW未満の事業用太陽光発電に対し、2020年度以降は自家消費型の余剰電力のみが買取対象になっています。

災害時に電気が使える
2018年に北海道で発生した大規模停電(ブラックアウト)や大型台風など、近年ライフラインが数日に渡り使用不可の状態になるという災害が起きています。過去の教訓をもとに、日本人の災害意識が高まりを見せるなかで、個人が用意できる備え以外にも、マンションに非常用電源があるというのはとても心強いものです。
災害時に太陽光発電による電力を使えるようにするには、ソーラーパネルと蓄電池をセットで運用する必要があります。蓄電池をプラスすることで初期費用は増えてしまいますが、10kW以上で余剰売電を見込むことが可能であれば、長期目線でのメリットがあると考えて良いでしょう。
なお、蓄電池には家庭用や事業用、定置型から持ち運べるタイプのものなど、様々な種類があります。
- 蓄電容量
- 放電震度(太陽光発電による出力の量)
- 電力変換効率(発電した電力を直流から交流にした際の効率)
- 蓄電池として使用可能な電気(kWh)=蓄電容量×放電深度×変換効率
マンションであれば定置型蓄電池を置くことになると思われますが、災害の備えとして蓄電池を導入する場合は特に、上記3点の確認と「蓄電池から使用可能な電気の計算式」を知っておきましょう。さらに詳しい内容については、以下の記事もおすすめです。

土地の有効活用ができる
安全上の理由からマンションの屋根や屋上は使用されておらず、デッドスペースとしてそのままになっていることが多い場所です。戸建てに比べれば日光を遮られるような高い建築物が無いにも関わらず、有効的に活用できないのはもったいないと考えている人も多いでしょう。
そのような屋根や屋上も、ソーラーパネルを設置すれば有効活用ができます。さらにソーラーパネルを屋根に設置することは、発電はもちろん、屋根の劣化を防いだり、最上階の断熱性の向上にもつながる効果も得られます。もちろん季節や窓・部屋の向きにもよりますが、室温が安定することで、住民が住みやすさを実感できるでしょう。

節税につながる
2021年3月31日で終了予定だった中小企業経営強化税制ですが、申請から認定までの期間が、2027年(令和8年)3月31日にまで延長されています。適用条件について詳しくは、下記リンクからご確認ください。
なお制度の名称や対象・期間については変更になる可能性が大きいため、申請の前に確認をお願いします。
| 対象設備 | 適用条件 | 受けられる待遇(どちらかを選択) |
| 「自家消費用」の太陽光発電設備 |
|
|
“参考:中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」”
ソーラーパネルの導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!

太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
マンションに太陽光発電を導入するデメリット

太陽光発電の導入によるメリットについて見てきたところで、この章では避けて通れないデメリットについて解説していきます。リスクとコストを事前に理解することで、不安解消やトラブルの回避に活用してください。
- 全世帯に電気の供給ができない可能性がある
- 入居者の承諾が必要
- 初期費用がかかる
- 避難経路などを考える必要がある
- メンテナンスの費用がかかる
- 追加工事が必要になることがある
全世帯に電気の供給ができない可能性がある
屋根や屋上の面積に対して、設置可能なソーラーパネルの枚数は限られています。
せっかく設置をしたのに、全世帯が必要とする電力量を賄えない可能性は充分に考えられることです。特に太陽光発電は天気に左右されるため、一定の電力を毎日発電できないリスクも想定しておかなければなりません。
全世帯に供給ができたとしても、全室にパワーコンディショナー(パワコン)の導入が必要になることもあります。
電気代の節約どころか、かえって費用がかかってしまったということにしないためにも、マンションの規模に見合う発電能力があるかを、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
入居者の承諾が必要
既に入居者がいるマンションの場合、太陽光発電の設備を導入するには、住民全員の承諾と管理組合の設置許可が必要となります。
「オーナーだから」の独断で導入を決められないところが、一戸建てとの大きな違いのひとつと言えるでしょう。法的な問題や安全性の観点からみて、結果的に許可が下りないケースもあるようです。
逆に言えば上記の問題から、賃貸マンションの入居者が「太陽光発電を導入したい」と訴えても、オーナーからの許可が下りないケースがほとんどです。
つい勘違いしてしまいがちですが、ベランダは居住者の専有部ではなく共有部の一部です。ベランダへの設置であっても、管理組合の許可が必要となります。
初期費用がかかる
何故まだ導入しているマンションが数少ないのかと問われれば、やはり初期投資が高額になりやすいという点が挙げられます。太陽光発電の大きなデメリットとして、誰もが思いつく最大のコストとなるはずです。
まずは大体の費用を把握するために、検討の段階でソーラーパネルの業者に無料見積もりや診断をしてもらいましょう。広く見える屋上や屋根も、思わぬ理由で想像よりも使用できない部分が多くあるかもしれません。ソーラーパネル+蓄電池の蓄電システムの場合、蓄電池の置き場所もあらかじめ確保しておく必要があります。
各メーカーの公式サイトなどで、太陽光発電システムを導入した際の収支や電気代のシミュレーションをすることができます。資金計画を綿密なものとするためにも、積極的に活用してみてください。
“参考サイト:メガ発「太陽光発電投資・売電収入・コスト・減価償却シミュレーション」”

避難経路などを考える必要がある
ベランダやバルコニーのほとんどは、緊急避難経路になっています。もし新築マンションなどで最初から太陽光発電の設置を考えている場合は、避難の妨げにならないよう十分な注意を払う必要があります。
マンションの規約にもしっかりと目を通し、他の居住者の迷惑にならないよう配慮も大切です。また、定期点検を怠ると、火事の原因にもなりうる設備であることをしっかりと認識しておきましょう。
メンテナンスの費用がかかる
屋根や屋上といった屋外に設置する設備である以上、風雨による汚れや破損が起きる可能性は避けられません。
ソーラーパネルの汚れは発電量にも影響が出るので、定期的な点検や清掃といったメンテナンスが必要です。万が一設備に異常が発生したときに、保証期間を過ぎている場合、設備の修理・交換費用がかかります。
ソーラーパネルの寿命は一般的に20年といわれているのに対して、保証は10年間までです。しかし、設置後10年を超えると、パネルやパワコンに不具合が生じ、修理・交換費用がかかるので、あらかじめ修繕計画・資金計画に入れておきましょう。

追加工事が必要になることがある
マンションが特殊な形状であるなど、設置場所によっては追加工事が必要になることがあります。
さらに電気設備である以上、必要な配線にも注意を払わなければなりません。このデメリットについては、見積もりの際に専門家に確認をするとともに、支出予定の費用に余裕をもっておくことが対抗策となります。
マンションに太陽光発電を導入する3つのパターン

太陽光発電の導入は、物件種別によって必要な許可などが異なります。この章では賃貸・分譲・新築、それぞれのパターンについて詳しくみていきましょう。
- 賃貸マンション
- 分譲マンション
- 新築マンション
賃貸マンション
自己所有の賃貸マンションに太陽光発電を設置する場合には、入居者全員の承諾と管理会社からの許可が必要となります。電気代が節約できるようになるメリットと、工事の音などによるデメリットについて説明をおこなったうえで承諾を得るというのは、とても大変な作業になるでしょう。
自分が賃貸マンションの入居者であり、ベランダ等に小型の太陽光発電を設置したい場合には、逆にオーナーからの承諾を得なければなりません。現在ではDIYの延長で個人向けに発電キットなども売られていますが、多少知識のある方や、作業に慣れている方でないとうまく設置ができず、難易度は高めとなっています。
分譲マンション
分譲マンションでの太陽光発電導入には2つのパターンがあります。
- 分譲マンションの屋根に共有で設置するパターン
- 各部屋でベランダに設置するパターン
屋根に共有で設置するパターンでは、居住者がそれぞれ費用を負担することで、発電電力を共有部分に供給することが可能になります。大規模修繕などのタイミング次第では導入も検討しやすいかもしれませんが、各々の負担額やメンテナンスのことを考えると、簡単には話が進まない可能性があります。
各部屋に設置のパターンであっても、ベランダが共有部分であることから、居住者の3/4以上から承諾を得なければなりません。どちらのパターンでも、導入時には所有者の管理組合による話し合いが不可欠です。
新築マンション
一番導入しやすいのは新築マンションの場合です。まだ居住者がいない新築時には、オーナーのみの判断で導入することができるため、設置計画もスムーズに進みやすいでしょう。
現在では国の施策もあって災害に強いマンションが求められており、今後新築されるマンションには太陽光発電の設置がされていることが増えると予想されています。
太陽光発電導入で利用できる補助金や助成金

2026年時点で、太陽光発電システムの単独購入に対する国からの補助金は、残念ながらありません。ただし、各自治体で補助金・助成金制度を設けているところがあります。
制度はあっても申請期間が終わってしまっている場合があるため、補助金や助成金を資金計画に組み込む場合には、あらかじめ期日に関してはしっかりと確認をおこないましょう。なかには予算超過によって早期終了してしまうケースもあるため、注意が必要です。
現在の補助金制度を調べる手がかりとして、以下のリンクをぜひ参考にしてみてください。
“参考サイト:パナソニック「全国の補助金がわかる」”
“参考サイト:新電力NET(一般社団法人エネルギ―情報センター)「電力補助金の公募状況」”
補助金や助成金については、以下の記事もおすすめです。


 マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営
マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営補助金の申請から受け取りまで市区町村は、2か月ほど、国や、都道府県は半年~1年ほどかかかります。補助金について、詳しくまとめた有料サイトもありますので、ぜひチェックしてみてください。
太陽光の専門家監修!太陽光発電一括見積もりサイトおすすめランキング


「複数の業者を比較して、質の高い業者に依頼したい」「評判が悪い業者に騙されたくない」という方に向けて、実際にサービスを利用したことのある方に行ったアンケート結果をもとに、太陽光発電一括見積もりサイトをランキング形式で紹介!
さらに、専門家に聞いた太陽光発電一括見積もりサイトを利用する際の注意点や、質の高い業者を見極めるポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。
「AD-HOME」なら導入費用実質無料で月々の電気代が0円に!
- 専門会社による業界最高水準の安心・安全な施工
- 充実した補償・アフターフォローで導入後も安心
- 申込みから完成までがあっという間!迅速な対応
\ 無料見積もりでAmazonギフト券3,000円分! /
まとめ
FITに「地域活用案件」が追加されたことで、売電に関しては、今後10kW以上の自己消費型の太陽光発電設備によるもの以外は難しくなってしまいました。
しかし、災害に備えるという観点において、太陽光発電にメリットは充分にあります。電気料金の値上がりも続いてしまっているなかで、今後メーカーによる蓄電池の改良がさらに進めば、よりコスパの良い運用がしやすくなることでしょう。
特に新たにマンションを建築・所有する人は、節税や国・自治体の補助金・助成金制度なども上手に活用しながら、太陽光発電の導入を検討してみてください。
※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・東京都環境局
・みらいエコ住宅2026事業
・葛飾区公式ホームページ
・経済産業省
ソーラーパネルの導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!


太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
監修者情報


太陽光や蓄電池等の専門家。2017年より某外資系パネルメーカーに所属し年間1000件以上の太陽光を販売しトップセールスを記録。これまでの知見を活かしたYouTubeが業界NO,1の再生数を誇り、2021年に開業。現在は一般の方向けに自社で販売〜工事を請け負う。Youtubeチャンネル
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。