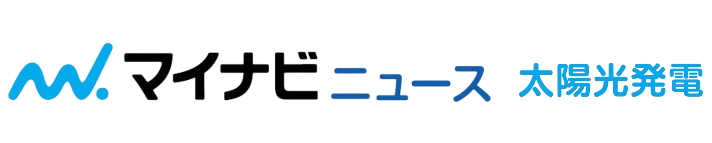土地活用法の1つに太陽光発電設備を設置して、発電した電気を売ったり自家消費したりする方法があります。軌道に乗れば、晴れた日に自動的に電気を作り出してくれるため、遠方の土地を相続した際も利用できるでしょう。
しかし、太陽光発電にはデメリットがあることも事実で、デメリットを把握して計画を練らないと後悔することになるかもしれません。ここでは、太陽光発電で土地活用する10のデメリットと、太陽光発電で得られるメリット、後悔しないためのポイントについて紹介します。
本記事を読むことで、より具体的に土地活用を検討できるようになるでしょう。

ハンファジャパンの「Re.RISE-NBCシリーズ」のおすすめポイント!
- 小さな屋根でも設置できる省スペース設計
- 北面屋根でも眩しさを低減する防眩パネルあり
- 30年の製品・出力保証で安心
\公式サイトはこちら/

太陽光発電で土地活用をする10のデメリット

結論から言えば「環境に良さそう」「自分の土地に向いていそう」といったイメージだけで太陽光発電を始めると、損をする可能性があります。次のようにさまざまなデメリットがあるためです。
- 高額な初期費用
- ランニングコスト(維持費用)の支払い
- 土地の固定資産税は変わらない
- 天候や需要により利益が左右される
- 売電価格は年々下がっている
- 投資資金の回収に時間がかかる
- 土地が農地だと事業の開始までに転用の手間
- 太陽光発電で近隣住民に被害
- 業者の倒産でサポートがなくなる
- 土地によっては太陽光発電を始められない
ここでは、それぞれのデメリットの理由を解説します。
高額な初期費用
土地活用として太陽光発電を行う場合は、数百万円から1,000万円以上の初期費用がかかります。そもそも太陽光発電は、次の2つに分類されます。
- 家の屋根などに取り付けて行う「住宅用太陽光発電」
- 空き地や工場など広い場所を活用する「事業用太陽光発電」
基本的に、土地活用として太陽光発電を行う場合は、事業用太陽光発電を行います。土地活用として安定した運用を目指すのであれば、事業用のほうが向いているためです。太陽光発電による土地活用では、発電した電気を電力会社などに売る売電という方法で利益を得ます。この際に活用されるのが、国が推進するFIT(固定価格買取)制度ですが次の2つに分かれます。
| 出力 | 分け方 | FIT固定期間 |
| 10kW未満 | 住宅用 | 認定から10年 |
| 10kW以上 | 事業用 | 認定から20年 |
売値は、太陽光発電をスタートした時点で決定されることが特徴です。しかし規模が大きい事業用の太陽光発電は、土地の面積に応じた太陽電池パネルを用意し、さらに管理用のシステム導入や設置工事など、さまざまな費用がかかります。
ただしマンションやアパートを、一から建設する場合の初期費用に比べると高額ではありません。また「ソーラーローン」と呼ばれる太陽光発電専用のローンを利用することで、月々の負担を軽くすることも可能です。それでも一戸建てが購入できるほどの初期費用が必要になるため、十分に検討しましょう。

ランニングコストの支払い
太陽光発電を行うにあたり、設備維持のためのランニングコスト(維持費)が年に数十万円かかります。長期間安定した運用を続けるためには、定期点検が必須です。しかし、太陽光パネルやケーブルなどの設備が故障すると、そもそも売るための電気を生み出せなくなります。
その他に設備の交換も必要です。電子機器を数年以上利用していて、電池の持ちが悪くなったり、故障が起きたりした経験がある方も多いでしょう。太陽光発電は20年ほどの長期運用が前提とされるものの、中にはより短期間で交換が必要な設備もあります。
そして、税金面の支払いが増える可能性も考慮しなくてはなりません。
- 所得税がかかる可能性
- 消費税の支払いが発生する可能性
給与所得者の場合は、太陽光発電によって得た利益雑所得が年間20万円を超えた場合には、課税対象となった部分に所得税が発生します。人によっては、税金の支払いが増えてしまう可能性もあるため、ランニングコストは設備への投資とともに、税金の支払いも考慮しておくことが大切です。

土地の固定資産税は変わらない
太陽光パネルは建物としては扱われないため、土地の固定資産税に影響はありません。「小規模宅地等の特例による固定資産税の軽減」という節税効果を得ることができないからです。また、土地が田や畑など農地の場合は、農地転用を行う必要があります。
その場合は固定資産税が高くなる可能性があるため、結果として初期投資の回収が遅れてしまいます。このように税金面において、節税効果は決して高くないと覚えておきましょう。
利益は天候や需要に左右される
太陽光発電は文字通り、太陽光を電気エネルギーへ変えることで発電を行います。つまり太陽光がなければ、発電は行われません。そのため利益を正確に見積もることが難しく、月ごとに利益にばらつきが出ることを考えて、計画を立てる必要があります。また地域柄、天候が悪くなりやすい場所では、太陽光発電を行っても利益が出にくいでしょう。
また、その地域で電気の供給量が多くなりすぎると、せっかく作り出された電気が売れない状態になる「出力制限」が起きるリスクもあります。これは簡単に言えば、電気の消費量に対して生み出される電気の量が多くなりすぎた際に、太陽光発電が行われないように電力会社側が制御を行うことです。
特に土地活用で事業用の太陽光発電を行う場合は、出力制限が起きた結果、想定より利益が少なくなることも考える必要があります。
売電価格は年々下がっている
事業用の太陽光発電の売電が行われるようになった2012年では、10kW以上の売電価格は、1kWhあたり36円(税抜)で取引されていました。しかし2025年度は、1kWhあたり10円(屋根設置の場合、11.5円)に下がっています。
また2020年度以降は、10kW以上の事業用太陽光発電は例外を除き、土地活用目的の太陽光発電が厳しくなっています。なぜなら10kW以上50kW未満の設備は、生み出した電気を全額買い取ってもらえる「全量買取」の認定が選べなくなったためです。2020年度以降は自宅や企業で使った分のうち、余ったものを売る「余剰買取」のみ、以下の条件を満たしたうえで利用できます。
- 生み出した電気のうち30%を自分で消費すること
- 災害時に使える機能を必ず備えること
この2つが前提になるため、遠方の土地に暮らしている人の場合は、そもそも事業用太陽光発電の設置そのものが困難になるかもしれません。よって事業者にも相談して、太陽光発電を行える土地か検討することが大切です。

投資資金の回収に時間がかかる
太陽光発電は、初期投資を全額回収するまでにおよそ10年はかかると言われます。これは1年間あたりの収入を初期投資で割ることで求められる利回りが、約10%程度とされるからです。
投資資金は、土地の状況や設置する設備によっても異なりますが、長期間の運用を考えていない人にとっては、土地活用に太陽光発電を選ぶこと自体が、不向きな可能性があります。
土地が農地だと事業開始までに転用の手間
土地の使用用途は「地目」と呼ばれ、たとえば雑種地や山林、原野などであれば、太陽光発電設備の設置が可能です。しかし、地目が田や畑になっている土地は「農地」と呼ばれ、農業以外の利用を行うためには、広さに応じて都道府県知事か農林水産大臣から許可を得る必要があります。
そこで、土地の使用用途を変えるために「農地転用」という手続きを行い、太陽光発電設備を設置しても問題ない地目へ変更します。ここで注意したいことは、必ず許可が必要という点です。万が一、許可なく農業以外の目的で使用すると、罰則が科せられます。
農地転用の難易度は、農地の広さやその地域の法律、土地のある場所が市街化調整区域に指定されているかなど、さまざまな条件によって異なります。農地転用が認められないケースもあるため、土地活用として太陽光発電を始められない可能性も考えておきましょう。
太陽光発電で近隣住民に被害
太陽光発電の設備の設置方法や設置後の自然災害により、近隣住民と次のようなトラブルが起きる可能性があります。
- 太陽光パネルによる反射でクレームが来る
- 自然災害で破損した太陽光パネルが隣家に直撃
- 台風で設備が吹き飛んで人に直撃
- 隣接する土地を誤って使用してトラブル
- 工事中の騒音や粉塵でトラブル
太陽光の反射については、設置前の段階で入念な確認が必要です。特に周りが住宅街の空き地だと、太陽光発電を始めることでトラブルが起きる懸念もあります。
また災害に備えられるように、土砂災害や近隣河川の氾濫の危険性、地盤なども確認しておきましょう。万が一に備え、火災保険や太陽光発電向けの自然災害補償つきの保険に入る対応も重要です。
業者の倒産でサポートがなくなる
10~20年にわたる運用が必要な太陽光発電では、業者の倒産によって、当初予定していたサポートを受けられなくなるリスクがあります。たとえば、業者側から長期間のメンテナンス補償を提案され、それを念頭に運用していたにもかかわらず、業者が倒産すれば補償は受けられません。さらに悪質な業者の場合は、工事費などの頭金を倒産により持ち逃げされるリスクも懸念されます。
長期的な運用を前提とするからこそ、太陽光発電では自分で情報をきちんと管理しなければなりません。将来的に、太陽光発電を相続したり譲渡したりする可能性も踏まえて、申請時の書類のコピーなどをきちんと保管しておくことが大切です。
土地によっては太陽光発電を始められない
土地によっては太陽光発電を行うこと自体、できない場合があります。たとえば、該当エリアが電力会社の発電のみで間に合っている場合は、供給過多になることを防ぐために許可申請が下りないことがあります。
また、自治体によっては太陽光発電を行うにあたり、近隣住民への説明や許可申請が義務付けられていることもあるため、注意が必要です。実際の条例や制限については、太陽光発電で土地活用を始めたいエリアを管轄する役所や、対応する電力会社に問い合わせてみましょう。
太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!

太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
太陽光発電で土地活用を始める3つのメリット

太陽光発電による土地活用は、デメリットだけではありません。しっかり制度を把握して利用すれば、次のようなメリットを得られます。
- 手間を掛けずに長期の安定収入
- 集客が期待できない土地でも利益
- 自治体からの補助金
手間をかけずに長期の安定収入
太陽光発電は10~20年と長期間運用するため、初期費用を回収したあとも安定して収入を得られる土地活用法です。事業用の太陽光発電を始めた場合は、FIT制度により20年間は開始した当時の値段で、継続して売電できます。買い取ってもらえる費用が一定のため、長期的な収入の予測も立てやすいとされます。
また賃貸経営と比べると、運用に必要な費用も少なく手間もかかりません。なぜなら、状況に応じて大幅なリフォームや修繕工事が必要な賃貸に比べ、普段のメンテナンスにかかるコストは1回20,000円前後と安いからです。業者に管理委託すれば、草刈りなどの手間を少なくできるでしょう。
そして、アパートやマンションのような空室による賃料の減少や、居住者によるトラブルもありません。天候不順により利益が少なくなる場合もありますが、空室を埋めるための広告費などがかからないことも、手間をかけずに安定した収入を目指せる要素といえます。
集客が期待できない土地でも利益
周りに家がなく人が来ないような郊外の土地でも、太陽光発電により利益を生み出せます。賃貸経営や駐車場経営といった土地活用法とは異なり、集客が前提条件に含まれないからです。また、人が来ないような建物が少ない土地のほうが日当たりもよく、太陽光発電による土地活用をしやすいでしょう。
そして、将来的に土地を売ることになったとしても、建物を建てるわけではないため売却も比較的簡単です。賃貸経営の場合は、取り壊す際に住んでいる人に部屋を出てもらう必要がありますが、太陽光発電なら設備を適切に処分すれば問題ありません。
自治体からの補助金
以下は東京都の一例ですが、自治体が独自に行っている補助金制度です。
| 自治体名 | 補助金制度名 | 内容 |
| 東京都 | 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 | 新築:15万円/kW(3kW以下) 10万円/kW(3kW超) 既存:18万円/kW(3kW以下) 12万円/kW(3kW超) |
| 東京都 | 熱と電気の有効利用促進事業「太陽光発電システム」 | 新築:12万円/kW(3.6kW以下) 10万円/kW(3.6kW超) 既存:15万円/kW(3.75kW以下) 12万円/kW(3.75kW超) |
| 東京都 | 東京ゼロエミ住宅関連補助金 | 12〜13万円/kW(3.6kW以下) 10〜11万円/kW(3.6kW超 50kW未満) |
| 荒川区 | 令和7年度新エコ助成事業 | 2万円/kW 区内業者から購入の場合上限は30万円 |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 8万円/kW、上限は40万円 |
| 江東区 | 地球温暖化防止設備導入助成 | 5万円/kWを補助、上限は20万円(単体申請) |
| 新宿区 | 令和7年度新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 | 2万円/kW、上限額は10万円 |
| 杉並区 | 【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成 | 2万円/kW、上限額は8万円 |
| 港区 | 地球温暖化対策助成制度 | 10万円/kW、上限額は40万円 |
その他の自治体の補助金に関する最新情報は下記を参考にしてください。

太陽光発電での土地活用を後悔しないポイント

太陽光発電を成功させるには、未来のプランも考慮しながら運用することが鍵です。主に4つの要素に焦点を当てるべきです。
- 自家消費の可能性
- メンテナンスの徹底
- 土地の適性
- 他の土地活用オプション
それぞれのポイントを詳しく解説します。
自家消費の選択肢を検討する
自家消費が可能な場合、売電よりもコスト効率が良くなる可能性が高いです。これは、電気料金が上昇しているからです。例えば、土地に家を建ててその電力を太陽光発電で賄えれば、電気料金を節約しながら余剰電力を販売できます。
ただし、相続土地などで近隣に住んでいない場合、自家消費は難しいかもしれません。そのような状況では、他の土地活用方法や売却も視野に入れるべきです。
メンテナンスで発電効率を高める
太陽光発電のメンテナンスは、発電効率に直結します。例えば、パネルが汚れていると発電量が減少します。定期的なメンテナンスで、以下のような問題を解消しましょう。
- 太陽光パネルの設置角度や表面の汚れの撤去
- 周辺の木の剪定による日陰
- 落雷による配線のダメージの修復
メンテナンス費用を節約しすぎると、設備の故障や効率の低下が起きる可能性があります。遠隔地に土地がある場合は、遠隔監視システムが有用です。
太陽光発電向きの土地なのかを専門家に相談

太陽光発電を手掛ける業者に相談し、太陽光発電で利益を得られるのか、災害の可能性はないかなど意見をしっかり聞くことが重要です。自治体の制度などによる制限を除き、太陽光発電に向いている土地は次のような土地です。
- 土地の広さが50坪以上ある
- 近くに電柱がある
- 周りに建物がない
- 雪や雨が降りにくい
- 雪が降ったとしても積もらないことが多い
- 日光を遮るものが南・東・西側にない
- 水害の危険がない
- 土地が平坦で必要以上の改良が不要
- 地盤がしっかりしている
- 地価が安い
注目したいことは、電柱の有無と日当たりの良さ、災害の危険性です。電柱は電気を電力会社へ送る際に、送電線をつなぐために必要です。近くにあれば、より効率よく電気を送ることができます。
災害については、水害を受けると機械が故障したり台風で太陽光パネルが飛ばされたりなど、被害が甚大になることがあります。また土地の高低差が激しいと、太陽光パネルを適切に設置できずに傾きが激しくなるかもしれません。地盤調査や地盤補強をしっかり行えるか、業者に依頼する際は確認しておくとよいでしょう。
 マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営
マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営提案された内容には注意が必要です。基本的に業者が提案した提案内容は異なります。
自分にあった商品の提案になっているかどうかを確認する必要があります。
他の土地活用オプションとの比較
太陽光発電以外にも、土地活用の方法は多く存在します。賃貸経営や売却、駐車場経営など、各方法のコストとリターンを比較して検討すると良いでしょう。
「他の土地活用も考えてみよう」と思った方は、以下の2つの記事も参考にしてください。
以上が、太陽光発電で土地を有効活用するためのポイントです。計画的に進めることで、後悔することなく成功を収めることができるでしょう。
太陽光発電で土地活用を始める手順


ここまで読んでみて「やっぱり太陽光発電を始めたい!」と考えた方のために、土地活用で太陽光発電を始める手順を解説します。実際に利益を得られるようになるまでには、業者の選定から太陽光発電の建設まで、半年以上かかる長期的な計画となるため、じっくり検討していきましょう。
見積もりをして業者を厳選
太陽光発電をスタートさせるにあたり、業者の選定は重要です。太陽光発電の業者は、全国展開している大手というものはなく、一般的にその地域に対応した業者を選ぶことになります。メンテナンスを請け負ってもらう場合は、10年~20年という長期的な付き合いになるため、業者を厳選することはその後の運用も左右すると考えましょう。
注意点として、太陽光発電のモニターや工事費が無料など、安さを売りにする業者は避けたほうが賢明です。太陽光発電は、時に1,000万円ほどの初期費用がかかる土地活用法であり、決して安くはありません。複数の太陽光発電の業者から見積もりをもらって、比較したうえで厳選することが大切です。
プラン設計と調査
厳選した業者から、プラン設計と提案を受けます。その後、地盤の硬さなど現地を調査してもらいます。提案を受ける際に注目したいポイントは、以下の9つです。
- 見積もり時に名刺を渡してくれるか
- 太陽光発電に関する質問に答えてくれるか
- 太陽電池など設備は複数のメーカーを扱っているか
- シミュレーションデータ(見積もり、経済効果、環境効果)を提出してくれるか
- 見積もりに項目別費用はあるか
- 施行部門を社内に持っているか
- メンテナンスサービスや保証サービスはあるか
- 十分な資本があるか
- 実績があるか
納得のいくプランができ次第、業者と契約を結びます。
施工をして発電開始
設置工事は、次のような流れで行われます。工事や契約にかかる期間はおよそ6カ月です。
- 電力会社と電力需給契約を結ぶ(業者が代行することも可能)
- 造成や整地を行う
- 太陽光発電パネルを設置する
- フェンスを設置する
- 検査を行う
- 系統連系(電気を電力会社へ送れるようにする)
- 運転開始
契約を結んだあとは、基本的に依頼主自身は工事に深く関わることはありません。ただし電力会社への申請については、業者とよく相談したうえで、自分でできそうになければ業者に代行してもらうことも検討してください。
まとめ
太陽光発電は最大1,000万円ほどの初期投資で、20年もの長期間にわたり利益を得られる可能性がある土地活用法です。しかし、制度やデメリットをきちんと把握しないと、計画不足で後悔する恐れもあります。
デメリットを回避する方法もあるため、今回紹介したポイントを踏まえ、太陽光発電以外の土地活用法を検討することもおすすめです。自分にとってよりよい活用法を見つけていきましょう。
太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!


太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・東京都環境局
・みらいエコ住宅2026事業
・葛飾区公式ホームページ
・経済産業省
監修者情報


太陽光や蓄電池等の専門家。2017年より某外資系パネルメーカーに所属し年間1000件以上の太陽光を販売しトップセールスを記録。これまでの知見を活かしたYouTubeが業界NO,1の再生数を誇り、2021年に開業。現在は一般の方向けに自社で販売〜工事を請け負う。Youtubeチャンネル
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。