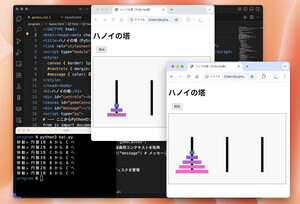日々増加し続けるデータを最大限に活用するには、データ分析基盤の整備・構築が必須となる。IoTデータを活用する場合も、既存で蓄積されているさまざまなデータとの連携が必要になり、データ分析基盤の整備・構築を進めていかなければならない。そこで本記事では、2019年7月31日に開催されたマイナビフォーラム「成功事例から学ぶデータ活用」にて行われた、クリックテック・ジャパンの川畑 英貴氏によるセッションの内容を参考に、次世代のデータ分析基盤といわれる第3世代BIについて解説する。
膨大な量のデータから本当に価値のある課題を見つけ出す
1993年創業のQlikは、全世界に5万社以上の顧客と1,700社以上のパートナーを持つ、ソフトウェア企業だ。主な製品としては、ビジネスインテリジェンスとデータ視覚化のためのソフトウェアであるQlik SenseとQlikViewがある。
「日々生み出されるデータは膨大な量にのぼります。しかし、そのすべてが必要なデータであるとは限りません」(川畑氏)
データは爆発的に増加しており、世界で作成されるデータの量は2020年までに35?45ZB(兆GB)になるといわれている。また、生み出されるデータの種類も、IoT機器からのセンサーデータ、SNSやブログ、Paypalのようなオンライン決済など、多種多様になっている。
だが、たとえば製造ラインを管理する人にとってIoT機器からのセンサーデータは重要である。だが、SNSに流れる情報やオンライン決済の情報は特に必要がないものだ。
「この膨大な量のデータから、自分のビジネスにとって本当に価値のあるデータを、どうやって見つけ出し、そして活用するか。それこそがデータ活用における大きな課題です」(川畑氏)
データ活用における最大のユーザーはビジネスの現場にいる人たち
データを分析して次のアクションへとつなげていく「データドリブン」の重要性が叫ばれている。現在では、データ分析を行い課題解決の手段を探るという手法が、さまざまな場面で行われている。そして、その手法がもっとも必要とされているのは、ビジネスの最前線で活躍するビジネスユーザーである。
「データ活用における最大のユーザーは、エンジニアでもサイエンティストでもなく、ビジネスユーザーです。ビジネスユーザーは専門家ではありません。エンジニアやサイエンティストが利用するような複雑なツールを使用したり理解したりすることはできません。そこで必要なのが、シンプルで簡単にアクセスできるツールの存在です」(川畑氏)
なおセッションでは、「ビジネスユーザー」によるデータ活用の事例がいくつか紹介された。
以下に、その簡単な内容を紹介しよう。
【Case01】意思決定者自身による分析で新商品の開発が加速
全国に430店舗をかまえる回転寿司チェーン店「あきんどスシロー」。同社の寿司皿にはRFIDタグがついており、毎年40億件もの売上データが生成された。かつてはそれらのデータをExcelで管理して分析していたが、生成されるデータの量と速度に対応できていなかった。Qlikを導入後は、商品開発の担当者が自らデータを分析できるようになり、新商品の開発効率が大幅に改善した。
【Case02】大量のデータにリアルタイムでアクセスして素早い意思決定を実現
ヘルスケア製品とサービスを提供するJohnson & Johnson。同社では、製品の問題をできるだけ早い段階で検出できるように、大量のセンサーデータを素早く取り込み、管理者がリアルタイムでアクセスして意思決定を行えるような仕組みを検討していた。そのためのツールとして同社はQlikを選択。製造プロセスの早い段階で問題に対処できるようになり、年間で3,500万~4,000万ドルの節約を実現した。
【Case03】購入する商品の相関関係を見つけ売上高を向上
ヨーロッパの大手石油・ガス会社では、ガソリンスタンドに付属しているコンビニやスナックショップで、顧客が購入していたものについてより多くの洞察を得る方法を検討していた、そこで同社では、Qlikを導入して、顧客が購入した商品の相関関係を見つけ出し、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを作成。同社の収益性と売上高が向上した。
データ分析基盤整備のステップとツール
データ分析には「蓄積」「管理」「可視化/分析」「分析/予測」の4つのステップがある。そして、それぞれに対応したツールとして「データソース」「DWH・データレイク」「BIツール」「統計ツール・AI・機械学習」がある。
「このステップを踏襲するのが一般的ですが、まだ管理のステップが未着手の段階であるのなら、可視化/分析を先に行ったほうがよいでしょう。もともと、分析することが目的なのですから、まずはそこから始めて、徐々に手順に沿った流れに持っていくほうが効率的です」(川畑氏)
なおQlikは、データソースを直接取り込み、可視化/分析と情報の共有までをワンストップで実行できる。つまり「管理」のステップが未着手であっても、すぐに分析が実行可能だ。
データ活用を民主化させる第3世代BIとは
データの量や種類が増加するにつれ、それを活用するBIツールも大きな進化を遂げている。複雑なテクノロジーで一元管理されていた第1世代のBIはレポーティングが主な目的であり、ごく一部の限られたユーザーのみが利用していた。セルフサービスBIと呼ばれ各部署のユーザーが自ら分析を行う第2世代では、多くのユーザーが自由にデータにアクセスして分析ができるようになった。ただ一方で、データに対するガバナンスやセキュリティの面で不安があった。
そして第3世代のBIでは、すべてのユーザーが統制されたデータに、適切なアクセス制御に基づいてアクセスできるようになる。これをQlikでは「民主的アプローチ」と呼んでいる。
ビジネスインテリジェンスにおけるAIの活用
AI・機械学習の時代が到来すれば、当然ながらBIもそれに併せて進化していくことになる。
Qlikには、「連想技術」と呼ばれる特許技術が搭載されている。そこに拡張知能の技術を組み合わせ、分析作業の自動化や省力化などを実現。より高度な分析を可能としている。
「たとえば、これまではデータをグラフ化する際には、そのデータの軸となるものを、自分で見つけ出さなければなりません。しかし拡張知能を使えば、そのデータにとって最適となる軸を自動的に選択してくれるようになります」(川畑氏)
セッション当日は、Qlik「拡張知能」についてのデモが行われた。
デモの内容については、以下のURLにも同様の動画がアップされているので、興味がある方はご覧いただきたい。
「Qlik拡張知能 デモムービー」はこちら
https://www.qlik.com/ja-jp/bi/augmented-intelligence-and-analytics
なお、Qlikでは、2019年2月に機械学習自動化プラットフォームである「DataRobot」との連携を発表した。Qlikが作成したデータを使用し、「DataRobot」が予測モデルを作成、その結果をQlik上で表示できるので現状分析から未来予測までをQlik上にて行うことが可能となっている。
「今後は、分析そのものはAIが行うようになるでしょう。しかし、それをどのように活かすか、判断するのは人です。ですからビジネスユーザーはデータリテラシーの向上に努めなければなりません。私たちQlikでは、データリテラシーを向上させるためのプログラムを提供しています。これはQlikユーザーでなくても参加できます。また、個人で参加できる無償のコースもあります。興味のある方は、ぜひ参加してみてください」(川畑氏)
「Qlik データリテラシープログラム」の詳細はこちら
https://www.qlik.com/ja-jp/services/training/data-literacy-program
[PR]提供:クリックテック・ジャパン