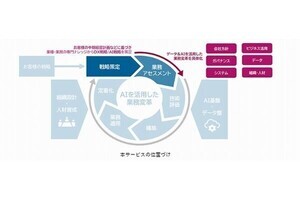1950年に米国の非営利団体であるサイエンス・サービスによって設立されたISEFは、高校生を対象に、毎年1回、5月に米国で開催されている。1997年からは、インテルが教育支援の一環としてメイン・スポンサーとなり活動を継続している。年々、参加国数も増え、世界最大規模の科学コンクールとなり、今年は65カ国から1,500人以上の学生たちが集まった。
日本からは、ISEFの提携コンテストである「日本学生科学賞」と「ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ(JSEC)」の選出により参加権を得た、6プロジェクト11人が参加した。
ISEFでは、生化学や化学に加え、行動科学、動物科学、環境管理など17分野において、高校生サイエンティストたちが研究成果を発表する。審査員には、専門分野で6年以上の研究歴をもつ研究者や博士号取得者などがボランティアとして参加している。ファイナリストたちは、研究をまとめた展示パネルの前で、審査員に対して英語でプレゼンテーションを行い、質問に答えるといった面談形式で審査が行われる。日本の高校生たちにとって、英語での資料作りとプレゼンテーションは、かなり大変な作業となるが、今回の参加者たちは、想定質問も考えて英語で答える練習など、準備を念入りに行ってきていた。
日本のファイナリストのブースでの様子
日本から参加したファイナリストたちの様子を写真と共にお伝えしておこう。
空手は黒帯、その他にもピアノ、習字と多芸多彩な田中里桜さん。今回の受賞については、本人いわく「一生懸命やっていたら、いつの間にかここまできた」。好きな音楽は「クラシックも好きだけど、レディガガも好き」。有孔虫の拡大写真を指して「貝みたいにいろんな形があってきれいでしょ」とまるでファッションや音楽の話をするように楽しげに研究内容を話してくれた。
鹿児島県立錦江湾高等学校の川添信忠さん、前畑大樹さん、叶瑠至亜さん。審査会場に入る直前の様子(写真左)と一般公開日にブースに訪れた人に説明を行っている様子(写真右)。
「今回、専門家の人たちから今後研究を続けるにあたっての具体的なアドバイスを受けたので参考にして研究を続けていく予定」とのこと。彼らの研究は、火山災害の防災対策などに役立つ他、金星の雷の解明にもつながる可能性があるそうだ。
審査当日の会場の様子。休憩時間を挟んで約7時間の間、審査員が入れ替わり立ち変わりブースに立ち寄り、学生たちは質問を受ける。
木村麻里さん(立命館大学1年)は「折り紙を用いた多面体の切断・分割と空間の充填」と題した研究で、一枚の折り紙からさまざまな多面体を作り、これらを組み合わせることで空間を充填できるかどうかを調べた。大会初日には公式メディアからの取材を受け、地震や津波などの災害に数学や科学がどう役立つか? といった質問にも答えていた。
「発表の仕方や練習もがんばってきたけれど、他のプロジェクトを見て元々の勉強が足りてなかったと実感した。ISEFに参加できた事で視野が広がった」と木村さん。一般公開日には、折り紙を使った多面体に興味を持った中学生たちに囲まれていた。
大山暁人さん(八千代松陰高等学校2年)は、液体窒素が金属物質を冷却する過程に見られる再沸騰現象のメカニズムを探る研究を発表した。「不思議だなと思ったことを突き詰めていき、解明できた瞬間の嬉しさが好き」。ISEFを終えて「いろんな人たちとあえて世界の広さを実感した。審査員が多ければ多いほどいろんな目線からアドバイスももらえたので視野を広げることができた」。
福本亮太さん、森川義仁さん(早稲田大学1年)は、心拍・皮膚電気伝導度の測定・解析に基づいて「あがり」状態を示す生体指標を作り、その指標を被験者に色として見せることで「あがり」感を制御するバイオ・フィードバック・システムの構築に成功した。二人とも「あがり」の傾向があるため、なんとか克服できないかとプロジェクトを思いついたそうだ。「英語での説明は緊張したけど、普段日本語で話す時よりも"伝えよう"という気持ちが強まった。『自分も緊張を感じているので興味を持った』と他国の学生がブースを訪ねてくれて嬉しかった(森川さん)」。「とにかくすごく緊張して、話が苦手だけれど、だんだんと話せるようになって積極性が生まれたと思う(福本さん)」。
天野祐嗣さん、江口亮太さん、草野光亮さん(埼玉県立大宮高等学校3年)の3人の研究テーマは「ハエトリグサの捕食反応」。一週間を過ごしての感想は、「人生感が変わったかなと思う。いろいろな国の研究を見て思ったのは、考え方や文化の違いに基づいた研究があって、科学というよりも人文学系に近いという印象も持った」(草野さん)。「他国の学生たちと話をできたことがとても思い出に残っている。科学は世界共通で伝わることだと思った」(天野さん)。「他国の学生たちはすごくポジティブで積極的なので、それに引き込まれて自分たちも積極的に彼らと接するようになっていった。とてもいい経験になった」(江口さん)。