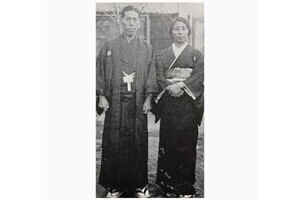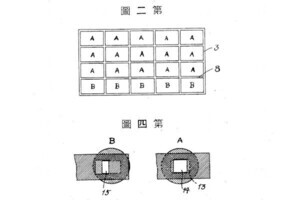フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース開始の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
夢の機械
1932年 (昭和7) 春、上野公園で開催されていた発明博覧会 (本連載 第55回参照) の動力館で、ひとりの男が写真植字機を前に立ちすくんでいた。
「なんという奇想天外な機械だ……!」 男は電撃に打たれたように、しばらく棒立ちになって動けなかった。やがてその機械で植字し、印刷されたパンフレットを受け取ると、呆然としたまま会場を後にした。
男の名は志茂太郎。東京・中野区新井にあった、伊勢元という酒販店の店主だった。発明博覧会には、商談をしに出向いたわけではなかった。もともと〈科学ファン〉だった志茂は、さまざまな発明品が展示されるこの博覧会の開催を楽しみにしており、未知の機械や技術を見に駆けつけたのだった。[注1]
帰宅しても、志茂は熱に浮かされたようになっていた。ひとかかえの装置で数十万の活字に匹敵するような印字をおこなうとは、魔術師のようではないか。
パンフレットには、住所が記されていた。すでに夜だというのに居ても立ってもいられず、志茂は写真植字機研究所に向かった。彼にはこれという目的があるわけではなかった。 〈あれほどにぼくを身ぶるいするほどウツツを抜かさせた写真植字機なるものを作った石井さんという人にひと目会ってみたい――〉[注2] ただそれだけのきわめて単純な動機から、その日のうちに茂吉を訪ねるという突飛な行動に出たのだった。
志茂は〈生まれながらのタイプマニア〉[注3] を自負するほどの活字好きで、のちに小出版社・アオイ書房を創設し、数々の趣向を凝らした書籍や雑誌をつくるのだが、当時は酒販店の店主にすぎず、印刷とはまったくかかわりがなかった。 「お寒うございます!」 われ鐘のような声を響かせて突然たずねてきたこの奇妙な客に、茂吉は面食らっていたが、志茂に邦文写真植字機の話をして聞かせた。[注4]
志茂はすっかり写真植字機と茂吉に夢中になった。その心酔ぶりは、後年振り返ってみずから恋愛にたとえたほどで、〈文字どおり、夜通い日通い〉足しげく通った。この写真植字機との出会いが口火となり、それまでつねに心の底にあった志茂の活字への情熱は、爆発したといってもよかった。[注5] 志茂太郎32歳、石井茂吉45歳の出会いだった。
幼いころ活字に魅せられ
志茂太郎 (1900-1980) は岡山県久米郡稲岡北村 (現・久米南町) 山ノ城で、江戸時代からつづく酒造業・志茂猶太郎の長男として生まれた。生家は、山林のなかの1,300坪におよぶ広大な敷地に建つ豪邸だった。父・猶太郎 (1871-1908?) は酒造業のかたわら、県会議員もつとめたひとだったが、1908年 (明治41) 年、太郎がまだ8歳のときに、37歳で早逝した。[注6]
志茂が活字に目覚めたのは、まだ幼い子どものころだった。 〈ぼくは生まれ持ったタイプマニヤ (ママ) と前記した。左様、学校に上がらぬ子どものころから、活版屋のおじさんにネダッてメツの活字 (筆者注:摩耗したり、傷がついたりした活字) をもらって来ては、朱肉をつけて紙におして楽しんだものである。長ずるにおよび、自分の名まえなど何本かの活字を組み合わせて、上から紙を当てて、プレスを加えて刷り取るに至っては、これはもうりっぱな印刷である。後年造書美術を天職 (あくまで非営利だが) とするに至ったのは、子どものころのこの印書癖がそのまま成長発展したものにほかならない〉[注7]
志茂は山のふもとにある赤坂尋常小学校 (現・久米南町立誕生寺小学校) に通っていた。生家は山林のなかにあったので、近所に活版印刷所があったとは想像しがたい。小学校の付近に活版印刷所があったのだろうか。とにかく彼は、こうした幼少期の体験から、活字と印刷に興味を持ち続けた。
1919年 (大正8) 、岡山県苫田郡津山町 (現・津山市) の旧制津山中学校を卒業すると、志茂は上京し、東洋大学専門学部文化学科に入学した。そして在学中であろう1921年 (大正10) に21歳で田鶴恵 (たづえ) と結婚し、1924年 (大正13) に東京・北区王子の「伊勢元」という酒販会社に入社。やがて1929年 (昭和4)、中野区新井町594番地 (現・新井1-9ほか) に個人商店として「伊勢元」を開店し、その店主となった。[注8]
個人商店とはいえ、伊勢元はJR中野駅北側から徒歩7分ほど、現在のみずほ銀行 中野北口支店から中野区立商工会館あたりの区画に早稲田通りに面して建っていたというから、そうとうな広さの店だったようだ。筆者も実際に現地を訪ねてみたが、想像をはるかに超える大きさにおどろいた。およそ個人商店の規模ではない。
その所在地は、当時、志茂が書いた説明によれば、こうなる。 〈省電 (筆者注:現在のJR) 中野駅 (東中野に非ず) 北口下車、電信隊前の大通り突当り、仁丹の屋根看板のある薬種屋から右へ八軒目で伊勢元 (いせもと) と云う酒屋です〉[注9]
-

アオイ書房は、中野駅北側の酒販店「伊勢元」のなかにあった。青で塗りつぶした部分が伊勢元 (青色塗りつぶしと文字は筆者による)。個人商店としては、かなり大きな店舗だった。地図出典:国土地理院 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html (参照 2025-05-28)
恩地孝四郎との出会い
この伊勢元の早稲田通りをはさんで向かいに、版画家・装本家の恩地孝四郎 (1891-1955) が妻子とともに住んでいた。最初は伊勢元を訪れた客だったのか、その出会いはさだかではないが、恩地と志茂は知り合った。話してみればたがいに竹久夢二に心酔しているということで、ふたりの親交は深まった。
恩地と出会ったこと、そして写真植字機を知ったこと。こうしたことが、志茂を本づくりの情熱に駆りたてたのだろう。やがて1934年 (昭和9) 、志茂は酒販店経営のかたわら、アオイ書房を標榜して本づくりを始める。最初の本は、活動写真弁士・徳川夢声の『くらがり二十年』。3月の刊行だった。本文はセピア色の特色インキをもちいた活版印刷で、装丁にもこだわってつくられた。志茂はこの年の1月に徳川夢声をたずね、もともと雑誌『新青年』で連載されていた文章を単行本化したいと持ちかけた。夢声の文を借りれば、こんな調子だ。
〈この一月になって、葵書房の主人公から「くらがり二十年」の単行本発行の話を持ち出された。これも最初私は、気のりがしなくて、好い加減な返事をしていたんだが、何しろ書房主人の熱心が凄いもんだ。 「是非、やらして戴きます。」 「だって、損に定ってますぜ。」 「いや、損は一向平気です。私は、あれが気に入ったから、出版せずにはいられないのです 元々、本屋は私の本業じゃないのですから、損をするくらいの事は問題じゃありません。」 と云う意気なので、私も遂に動かされたのである。〉[注10]
「損は一向にかまわない」は志茂の一貫した姿勢だった。童画家・武井武雄 (1894-1983) は1936年 (昭和11) ごろだったという志茂との出会いをこんなふうに書いている。
〈恩地孝四郎君の紹介状をもって和服をぞろりと着流した伊勢元の旦那が現れた。はっきりしないが昭和十一年頃である。その紹介状によると「よい本を作る事にはひどく熱心だが、それで金を儲ける事にはさっぱり不熱心な男」とあった。(中略) そこで早速「そういう男が現在の世の中に居る事は知らなかったが、実際に居るとしたらもう少し長生きしたくなった」と返事をしておいた。この男というのが志茂太郎で、これが彼との出合い (ママ) であった〉[注11]
志茂はアオイ書房を創立したあとも、酒販店の店頭にはとくにその看板は出さなかった。店の前には酒樽と味噌樽がずらりと並び、志茂は名入りの前掛けをしめ、妻の田鶴恵は味噌樽の前に座って店番をしていたという。その店の奥に書房があり、活字や機械などを置いて本づくりがおこなわれているとは、道行くひとはだれも想像しなかったろう。[注12]
1935年 (昭和10) 4月、志茂は恩地孝四郎を編集者にむかえ、好事家に向けた愛書誌『書窓』を創刊した。
(つづく)
[注1] 志茂太郎「石井文字の美しさ」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 pp.82-88
[注2] 志茂太郎「石井文字の美しさ」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.84
[注3] 志茂太郎「石井文字の美しさ」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 p.84
[注4] 志茂が訪問したときの様子は、武井武雄「大声将軍今やなし」日本書票協会通信臨時増刊号『追悼 志茂太郎』 (日本書票協会、1980年12月) pp.1-2 の以下の記述による。〈太郎どんには刊叔のほかに大声将軍という仇名を奉ってあった。これは来訪するや夏はお寒い事で、冬はお暑うございますと玄関でわれ鐘のような声を出すからで、うちの子供はみんな大声将軍の方の名で呼んでいた。〉
[注5] 志茂太郎「石井文字の美しさ」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 pp.82-88
この文中に〈こうして当時王子の石井さんのお宅へは、幸い近くに住まっていた便宜さも手伝って、文字どおり、夜通い日通い、(後略) 〉とある (p.85) ため、志茂はこの時点ではまだ北区王子に住んでいたのだろうかと考えたが、倉敷ぶんか倶楽部 編『志茂太郎と蔵書票の世界』岡山文庫、発行 日本文教出版、2018 p.94で〈筆者はこれ以外に信頼出来る志茂の年譜を見たことがない〉といわれている日本書票協会通信臨時増刊号『追悼 志茂太郎』 (日本書票協会、1980年12月) p.4掲載の年譜を見ても、他の文献と同様、志茂は1929年 (昭和4) に中野区新井に「伊勢元」の支店を設け、同地に移ったとあることから、本稿も、当時すでに中野 (中野区新井町594 現・新井1-9ほか)に住んでいた説に依って執筆した。
他に参照した文献は以下のとおり。
片塩二朗「詩、活字になる タイポグラファ・志茂太郎小伝」『ユリイカ』2003年4月号 第36巻第5号、青土社、2003 p.133 / 片塩二朗『活字に憑かれた男たち』朗文堂、1999 p.26 / 荒木瑞子『ふたりの出版人』西田書店、2008 p.10 / 倉敷ぶんか倶楽部 編『志茂太郎と蔵書票の世界』岡山文庫、発行 日本文教出版、2018 p.60など
[注6] 日本書票協会通信臨時増刊号『追悼 志茂太郎』日本書票協会、1980年12月 / 片塩二朗「詩、活字になる タイポグラファ・志茂太郎小伝」『ユリイカ』2003年4月号 第36巻第5号、青土社、2003 / 片塩二朗『活字に憑かれた男たち』朗文堂、1999 / 荒木瑞子『ふたりの出版人』西田書店、2008 /倉敷ぶんか倶楽部 編『志茂太郎と蔵書票の世界』岡山文庫、発行 日本文教出版、2018
父・猶太郎が死去した年については、荒木によれば1908年 (明治41) (pp.7-8)、日本書票協会では1910年 (明治43) (p.4)と食い違っている。
[注7] 志茂太郎「石井文字の美しさ」『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965 pp.86-87
[注8] 日本書票協会通信臨時増刊号『追悼 志茂太郎』 日本書票協会、1980年12月 / 片塩二朗「詩、活字になる タイポグラファ・志茂太郎小伝」『ユリイカ』2003年4月号 第36巻第5号、青土社、2003 / 片塩二朗『活字に憑かれた男たち』朗文堂、1999 / 荒木瑞子『ふたりの出版人』西田書店、2008 / 倉敷ぶんか倶楽部 編『志茂太郎と蔵書票の世界』岡山文庫、発行 日本文教出版、2018
[注9] 志茂太郎「雑用手帖」『書窓』3 (1) 、アオイ書房、1936.5 p.109
[注10] 徳川夢声『くらがり二十年』アオイ書房、1934 序文pp.4-5、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1232693/1/9 (参照 2025-02-24)
[注11] 武井武雄「大声将軍今やなし」日本書票協会通信臨時増刊号『追悼 志茂太郎』日本書票協会、1980年12月 p.1
[注12] 鈴木進「『故園の歌』忘れがたく」『南画鑑賞』9(8)、南画鑑賞会、1940年9月 p.17 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1889971 (参照 2025-02-20)、関野準一郎 著『版画を築いた人々』美術出版社、1973 p.74 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12764597 (参照 2025-02-21)
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969
『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965
「文字に生きる」編集委員会 編『文字に生きる〈写研五〇念の歩み〉』(写研、1975)
倉敷ぶんか倶楽部 編『志茂太郎と蔵書票の世界』岡山文庫、発行 日本文教出版、2018
日本書票協会通信臨時増刊号『追悼 志茂太郎』 日本書票協会、1980年12月
片塩二朗「詩、活字になる タイポグラファ・志茂太郎小伝」『ユリイカ』2003年4月号 第36巻第5号、青土社、2003
片塩二朗『活字に憑かれた男たち』朗文堂、1999
荒木瑞子『ふたりの出版人』西田書店、2008
倉敷ぶんか倶楽部 編『志茂太郎と蔵書票の世界』岡山文庫、発行 日本文教出版、2018
『南画鑑賞』9(8)、南画鑑賞会、1940年9月
関野準一郎 著『版画を築いた人々』美術出版社、1973
【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影