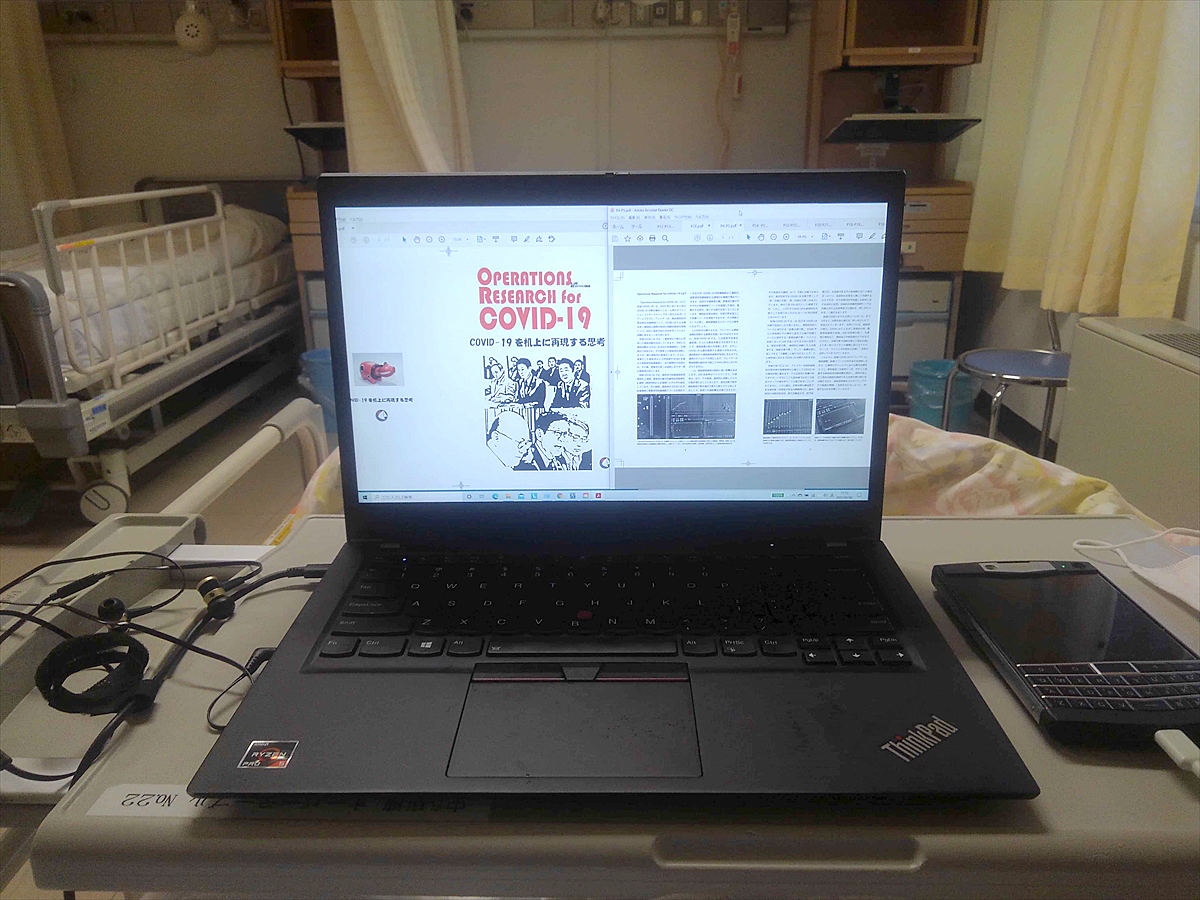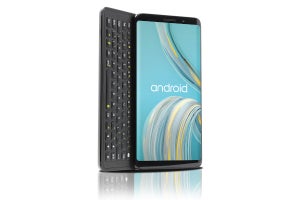物理キーボード搭載スマホが大活躍
脳出血を発症してからしばらく(自分のメモによると16日間)、右手がほとんど動かない状況が続いていましたが、17日目から右手も何とか使えるようになってきました。とはいえ、「持つ」「押す」ぐらいの動作しかできません。
先ほども少し述べましたが、この状態ですと「片手で本体を持って」「もう片手でディスプレイをフリックして」という動作ができません。比較的動かせる左手で画面をフリックしようとしてもうまくいきませんでした。
しかし、私が使っていたUnihertz TitanはハードウェアQWERTYキーボードを搭載していたおかげで「両手でスマートフォンを持つ」「使える親指でキーボードをタイプする」だけで文字を入力できたのです。
これは大変助かりました。“親指打ち”ながらキーボードタイピングができるようになったおかげで、筆者はSNSやメッセージ、メールを通して「外の世界」とつながることができたのです。
親指タイピングができるようになった当初こそ、十数文字の文章を書くのにも40分以上かかるような状況でした。
しかし、当時の主治医やリハビリトレーナー(特に生活動作などの機能回復を担当する作業療法士と思考力、正しくは高次脳機能の回復を担当する言語聴覚士)からの勧めもあって、短いメッセージ(その多くは、Facebookに投稿した発症報告動画に寄せられたコメントへの返事でした)を毎日少しずつ“作文”し続けることによって、タイプできる文字数とスピードはまさに「日を追うごとに」回復していきました。
自分が残していたメモによると、親指タイプができるようになったのが発症して17日後。そのときには、十数文字を作文してタイプするのに40分間以上、300文字程度を作文してタイプするのに4時間程度かかっていました。
しかし、その4日後には40文字程度を作文してタイプするのに約3分間、さらにその7日後には200文字程度を作文してタイプするのに約4分間と日に日に改善されていったのです。
物理キーボードを操作するうちに手の機能が回復
もともとフリック操作が苦手で、たまたまハードウェアQWERTYキーボードを搭載していたスマートフォンを長年にわたって使っていた、という特殊な条件があったとは言えます。
しかしそれでも、個人的には「麻痺がある指でディスプレイの狙った場所をタップするだけでなく、スライドする必要があるフリック操作は難易度が高い」というこの一点において、親指でタイプするだけで文章が作成できるハードウェアQWERTYキーボードを搭載したスマートフォン(というかハンディデバイス)が手元にあったことは幸いであったと思っています。
そうして、親指でUnihertz Titanのキーボードをポチポチとタイプし続けているうちに、右手のマヒが改善してきました。
PCのキーボードがタイプできるかもしれない。そう思った筆者は、主治医と相談したうえで自宅に所有しているノートPCを入院先で使えるか試してみることにしました。次回は入院している状況でノートPCをどのように利用できたのかを説明しましょう。