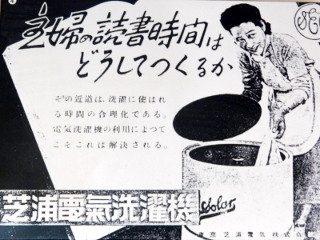金融事業の中心にいながらも、佐藤氏は「誤解を招くかもしれないが、フィンテックという言葉はバズワードの時期を過ぎて古いものになる」と現状を指摘する。例として挙げるのは「ATM」。ATM自体が金融とテクノロジーを融合したフィンテックの一つであり、かねてより存在する。
「フィンテックは金融側から見た表現であって、一般消費者からすれば金融は"意識しないもの"。入り口が別の業態から入り、金融へと繋がることは想像に難くないし、これからの時代はそうしたクロスインダストリーが当たり前になる」(佐藤氏)
AIを活用した業務効率の改善や、IoTにおけるモノのデータ集積・分析といったさまざまなテクノロジーを加味すれば、それは消費者目線ではフィンテックではなく新しいソリューションであり、「フィンテック」というジャンルではなくなる、そういう考えだ。
「交通費精算を、ブロックチェーンなどと組み合わせて即日決済する」「残高照会で単なる家計簿連携だけでなく、医療請求情報などと組み合わせ、精算と医療の安心を担保する」。もちろん、法制度などの壁はあるものの、こうしたコラボレーションの可能性を広く見出したいのがこのコンテストの道筋だ。
「コンテスト自体は数回やるかもしれないが、一つの狙いはAPIを利用してもらうことでどのAPIにニーズがあるのか。ニーズの高いAPIの組み合わせがあれば、それを単一のAPIとしてまとめることで、それが新たな素材になり、イノベーションへと繋がる。『1年後に新たなサービスを』と言うよりも、常にテストできる環境を用意し、アイデアをどんどんブラッシュアップさせて新たなエコシステム構築へと繋げたい」(佐藤氏)
銀行にはAPI公開の努力義務も
5月に可決、成立した改正銀行法によって、銀行にAPI公開の努力義務が課せられた。メガバンクはすでにオープン化に向けた取り組みを進めており、三菱UFJフィナンシャル・グループなどは3月にAPI開放を"宣言"している。地銀についても北國銀行など、ICT化に積極的な姿勢を見せる銀行はあるものの、今年に入ってメガバンクに遅れて再編の波が訪れており、システム統合に加えてのAPI開放は、IT部門に課せられた使命として、あまりにも重い。
ただ、手をこまねくだけでは未来がない。いち早く多業種とのコラボレーションによって商機を見い出せば、生き残りの道筋も見えてくるはずだ。例えば前述の北國銀行はクラウド会計ソフトのfreeeと協業し、中小企業のバックオフィスの自動化支援を行っている。会計業務こそ金融の一つだが、例えば農機具メーカーとコラボレーションして穀物の生産高を自動把握し、時価データと連動させることで会計処理を簡素化できるといったことも可能になるはずだ。
富士通が期待するコラボレーションが出てくるかどうか、9月6日の本選でその答えがわかる。