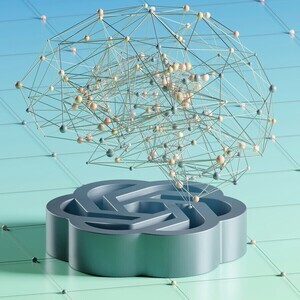多忙な経営者が、茶道や武道といった日本の稽古に打ち込んでいます。なぜ業界で活躍するような人物は稽古に励むのでしょうか? 本連載では『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか』(梅澤さやか著)から、一部を抜粋して紹介します。
第2回は「スマートフォンが『考えさせない道具』として機能する」です。日本文化において、道具と稽古が切っても切り離せない深い関係にあると説く筆者は、なぜスマートフォンを問題視するのでしょうか?
スマートフォンは「考えさせない道具」
人類の歴史において、道具は常に生活と密接に結びついてきました。
現代において、誰もが日常的に使用する道具と言えば、スマートフォンでしょう。さらにはAIがその仲間入りをしつつあります。これらの新しい「道具」は、私たちの生活様式や思考プロセスに大きな変革をもたらしています。
情報検索、コミュニケーション、ナビゲーション、決済など、ほとんどの日常タスクが、考える手間を省いて完結します。この便利さと引き換えに、人はいくつかの能力を失いつつあることは、様々な研究でも指摘されています。
デジタル技術の進歩により、私たちの認知能力に変化が生じています。たとえば、常時情報へアクセスできることで、脳に記憶を蓄える必要性が減り、記憶力の低下につながっています。また、GPSナビゲーションの普及により、地図読解力や空間認識能力が衰えつつあります。
しかし、最も憂慮すべきは、即座に答えが得られることで、自ら考え想像する機会が減少していることです。
デジタル技術の進歩は、人間の思考プロセスや問題解決能力に長期的な影響を及ぼす可能性があります。考える力を失うことで、私たちは単に情報を受け取り、決まりきったパターンで反応するだけの存在になりかねません。つまり、創造的な人間から、プログラムに従う機械のような存在へと変容してしまう危険性があるのです。
この傾向は、すでにソーシャルメディアにおいて顕著に現れています。特に「エコーチェンバー現象」は、1990年代から指摘されている問題です。これは、SNSのアルゴリズムが個々のユーザーの好みや興味に合わせた情報を優先的に表示することで起こります。その結果、ユーザーは自分と類似した意見や考えにばかり触れるようになり、異なる視点や意見に接する機会が減少します。
このプロセスを通じて、特定の意見や思想が繰り返し肯定され、増幅されていきます。言わば、自分の考えが反響して返ってくる「反響室」のような状態がつくり出されるのです。これにより、私たちの思考の多様性や批判的思考能力が徐々に失われていく可能性があります。
ある人が環境問題に関心があるとします。その人がSNSで環境保護の投稿を「いいね」すると、アルゴリズムは似たような内容をどんどん表示するようになります。その結果、その人は環境保護に賛成する意見ばかりを目にするようになり、反対意見や異なる視点にほとんど触れなくなります。これにより、環境問題の複雑さやほかの立場の人々の考えを理解する機会が失われ、一面的な見方だけで「答え」を決めてしまう恐れがあります。エコーチェンバー現象は人の思考の幅を狭め、多様な視点から物事を考える能力を弱めてしまいます。
スマートフォンやAIなど、即座に答えを提供する現代の道具は、たしかに生活を便利にしてくれます。しかし同時に、人間が様々な情報をまとめ上げて深く考える能力を弱めてしまう危険性もあります。いわば「考えさせない道具」として機能する可能性があるのです。ただし、この問題は道具自体が悪いわけではなく、私たち人間の道具との関わり方に原因があることにも注意する必要があります。
対して、伝統的な稽古で使われる道具は、「自分で考える力(感性)を育てるもの」として機能してきました。これからの時代、人々にとって重要なのは、このような道具との建設的な関わり方を意識的につくり出すことではないでしょうか。
では、道具に頼りすぎるのではなく、道具を活用しながら自分の考える力を伸ばしていく姿勢とは、具体的にどのようなものでしょうか。
この答えは、まさに稽古における道具との関わり方から学べるはずです。稽古の過程では、単に道具を使いこなすだけでなく、道具を通じて自身の思考プロセスを磨き、深めていくことが求められるからです。
この学びを現代社会に応用することで、技術の恩恵を受けつつ、人間本来の考える力(感性)を維持・発展させる方法が見えてくるかもしれません。
『エグゼクティブはなぜ稽古をするのか』(梅澤さやか 著/クロスメディア・パブリッシング 刊)
茶道や武道の「稽古」と聞くと、敷居が高く窮屈というイメージがあるかもしれません。しかし、多くの経営者は、多忙にもかかわらず、稽古に打ち込んでいます。どうしてでしょうか。
以下のような効能が稽古にあるからでしょう。
- リフレッシュ効果がある
- 心と体の健康を整えることで、より高いパフォーマンスを発揮するための基盤となる
- 創造力や問題解決力が自然と磨かれ、ビジネスに新たなアプローチが生まれやすくなる
- 肩書きや立場を超え、ひとりの人間として出会うことで、本質的な人脈が育まれ、深いコミュニケーション力も磨かれる
稽古は、仕事と人生を豊かにする「習慣」なのです。
本書では、経営者やビジネスパーソンが実践する「稽古」の事例にふれながら、稽古の魅力と効能を解明します。さらに、そのエッセンスを日々の仕事に応用する方法もご紹介します。
稽古は、AIが持っていない「身体」と「感性」を活かして、高度な知性を発展させる方法です。それこそ現代のエグゼクティブに求められる力です。また、海外からも大きな注目を集めている日本文化の豊かな伝統が凝縮されたものです。稽古によって日本文化を体得することは、これからの時代のブランディングにとって大きな力となるでしょう。
稽古に取り組んでいる方にも、未経験の方にもたくさんの発見がある一冊です。
Amazon購入ページはこちら