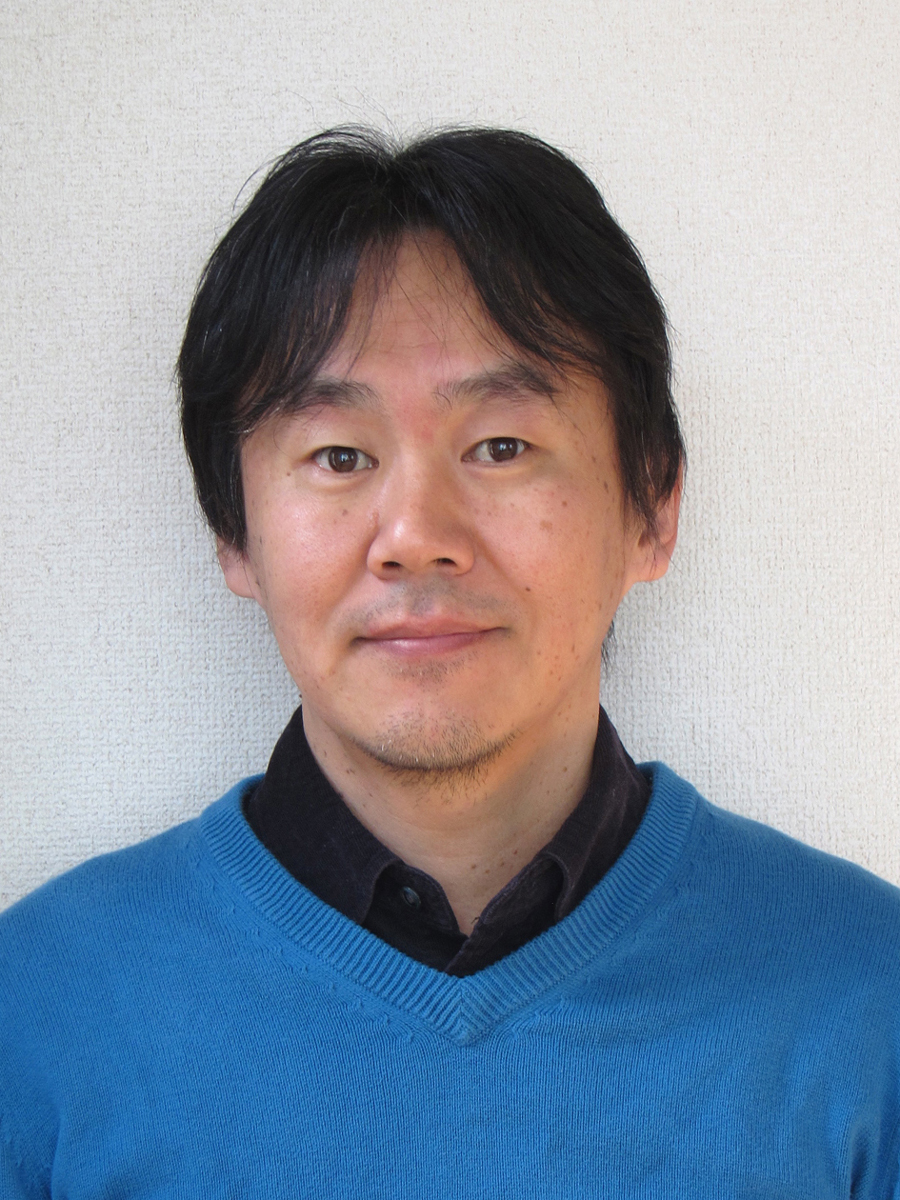自動車業界は電動化が急速に進むかと思いきや急ブレーキがかかる波乱の展開に。混迷の度合いが深まる世界で、「スモールプレイヤー」を自称するマツダはどう戦っていくのだろうか。
スモールプレイヤーならではの革新
マツダというと、日本の自動車会社の中でも、「走る歓び」を前面に押し出したクルマづくりで知られている。しかしながら一方で、グローバルでの年間販売台数は130万台近くに達する。だからこそ、社会課題にも取り組んでいく責任がある。
とりわけこれからは、電動化への対応が重要になる。そこで今回、マツダが掲げたのが「ライトアセット戦略」だ。
直近では、欧州などが仕掛けた「EVシフト」はひと休みという状況だが、代わりにプラグインハイブリッド車(PHEV)は伸びているし、ハイブリッド車(HV)の人気も根強い。理想をいうと、自動車会社としてはこれら全てを手がけることが必要だ。
しかしマツダは、今回の発表会でも自分たちを「スモールプレイヤー」と呼んでいたように、販売台数ではトヨタ自動車の約8分の1にすぎず、電気自動車(EV)専業のテスラよりも少ない。自社だけで全方位での電動化を進めていくには限界がある。
そのためにマツダが導入したのが、「ものづくり革新」だった。具体的には「一括企画」「コモンアーキテクチャー」「フレキシブル生産」などを次々に導入してきた。
2012年に日本で発売された初代「CX-5」以降、このブランドが「スカイアクティブテクノロジー」と「魂動デザイン」を取り入れて、ラインアップを次々に刷新していったことは、クルマ好きなら知っているだろう。
クルマの開発は1車種ごとに行うのが一般的だが、当時のマツダは10年分くらいの商品や技術をまとめて企画した。これが一括企画だ。だから技術もデザインも統一することができた。
「コモンアーキテクチャー」「フレキシブル生産」とは?
加えてマツダでは、開発部門と生産部門が一体となって、共通になる要素と別々になる要素を明確に分けた。エンジンやプラットフォームでは、製造時に基準となる寸法を共通としたうえで、車格や排気量によってサイズを変えていった。これがコモンアーキテクチャーだ。
そしてフレキシブル生産とは、生産現場がこの構造をいかして、さまざまな車種を同じラインで流すことを指す。筆者も工場を見学したことがあり、プラットフォームもパワーユニットも違う「MX-30」と「ロードスター」が同じラインを流れていて驚いた。
もちろん、仕様によって組み立ての時間は違う。そこで例えば、ガソリンよりも補機が多くなるディーゼルエンジンは、途中で別のラインに移動して専用機器を装着し、元のラインに戻すという手法を取っていた。
マツダはこのものづくり革新で、6年間に9モデルを商品化しながら、開発と車両生産のコストは30%、生産設備の投資は20%削減しつつ、過去最高の営業利益を上げることができたという。
今回のライトアセット戦略では、これを発展させた「ものづくり革新2.0」を発表した。
ソフトウェア分野の開発が爆発的に増えることに対応するもので、エンジンやプラットフォームなどで実践してきた効率化をソフトウェアにも展開する。さらに、社内だけでなくサプライチェーンにもこの取り組みを進めていくとのことだ。
例えば、これまでは車種ごとに外注していたソフトウェアは、ベースは共通としつつ社内で行う書き込みを変えることで、効率化を図っていくという。
EV専用工場にはこだわらない
EVについては、当初は全てを自社で開発生産していくとしていたが、中国の長安汽車との共同開発との2本柱で進めていく方針に変えた。後者では昨年、「EZ-6」をデビューさせており、今後は双方から新型車を出していく予定だ。
さらにEV専用プラットフォームについては、バッテリー形状や車両のサイズを問わずに作れるようにし、専用工場は持たないという決断を下した。フレキシブル生産の経験をいかすことで、初期投資を85%、量産準備を80%削減できるとしている。
一方、エンジンについては「スカイアクティブZ」を登場させる。今後さらに厳しくなる環境対策を見据えたもので、2.5リッター直列4気筒をベースとし、スカイアクティブ・テクノロジーのノウハウを投入することで、ハイブリッド前提のユニットを作るということだ。
デビューは2027年で、次期CX-5から搭載していくとのこと。その後、直列6気筒やロータリーエンジンにもこの技術を展開していくそうだ。
でも、今回の発表会でスカイアクティブZは脇役だった。ライトアセット戦略は、あくまでも「ものづくりの」プロセスについてのソリューションだ。
話の中で興味深かったのは、1960年に日本で初めて生産領域にコンピュータを導入し、1996年には商品企画から量産準備までのデータを一元化して開発期間を50%短縮したというエピソードだ。
マツダというと、自分たちの技術を頑なに守っているというイメージが強い。しかし実際は、昔から革新的でやりくり上手なものづくりを行ってきたというわけだ。
だからこそ、スモールプレイヤーでありながら、ロードスターのようなスポーツカーを出しつつ、激動の時代を生き抜いてきたのだろうし、こうした創意工夫はこれからも、マツダらしさを研ぎ澄ませていくうえで大きなアシストになりそうな気がした。