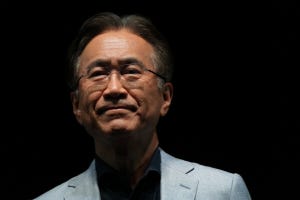三菱電機は、報道関係者およびアナリストを対象にした「IR Day 2024」を開催し、2025年度を最終年度とする中期経営計画の目標を下方修正した。売上高5兆円超の目標は維持したものの、営業利益率は10.0%から8.0%以上に、ROEは10.0%から9.0%にそれぞれ修正。キャッシュ・ジェネレーションは、5年間累計で3兆4000億円を、3兆3000億円へと修正した。
三菱電機の漆間啓社長 CEOは、「FAおよび空調の市場環境は、中期経営計画の策定時から大きく悪化している。たとえば、欧州A2W事業では、補助金制度が延期されるといった影響があり、FAも中国での回復の遅れが見られている。2024年度下期以降の回復を見込んでいるが、短期的には当初想定した水準には届かない。それがわかった段階で迅速に財務目標を見直した。だが、営業利益率は9%を見据えながら、構造改革を進めたい。2024年度からは各事業本部にもROICを導入している。リターンを生むものにしっかりと投資し、実行するのが2024年になる。投資効果の刈り取り、収益力強化を目指す」などと述べた。
また、成長投資は中期経営期間中の2兆8000億円の計画を維持。「2023年度までに、開発費、設備投資、投融資などに1兆4000億円を投資してきた。重点成長事業を中心に成長投資を実行し、持続的な成長を持続する」としている。
FAシステム、パワー半導体、インド、防衛領域への投資姿勢
事業ポートフォリオ戦略については、ビルシステム、空調・家電、半導体・デバイス、FAシステムを「重点投資による事業成長」領域として、三菱電機の成長を牽引する事業に定義。社会システム、電力システム、ビジネス・プラットフォームを「効率化・競争力強化による安定経営への貢献」領域として、経営の安定化に貢献する事業と位置づける一方で、他社との連携やM&Aによる補完を通じて、効率化や競争力強化を進めるという。また、防衛・宇宙システムは「市場拡大への対応と収益性改善」領域とし、拡大する市場に対応するための体制構築を推進。自動車機器は「構造改革、選択と集中」領域と位置づけ、パートナー戦略を迅速に推進することになる。
「重点投資による事業成長」領域のなかでも、FAシステムでは、国内外の生産体制の強化やパートナー戦略により、コアコンポーネントとデジタル領域での競争力強化を進める。「FAシステムのなかには低収益事業もある。パートナー戦略を検討しているものもある」とした。ビルシステムでは、昇降機の新機種投入により、新設ボリュームゾーンの攻略を進めるほか、マルチブランドでの保守およびリニューアル提案を進める。空調・家電では、製品開発の現地化や地産地消の強化により、欧米やインドの成長市場における環境規制ニーズへの対応を強化する。半導体・デバイスではパワー半導体のSiC事業の拡大を推進するという。
また、公共、交通、電力事業といったインフラBA(ビジネスエリア)においては、防衛やソリューション事業に資源を配分。ポートフォリオの転換を進めるという。生産体制の最適化に向け、交通事業関連製品を主力とする長崎製作所と伊丹製作所を統合。電力事業の事業体制の最適化も進めている。「防衛予算の増加を背景に防衛事業への投資を進める。足元では受注が大幅に増加しており、事業拡大に必要な人員や生産ヤードの確保に向けてリソースシフトを進め、開発、生産体制を強化している。ソリューション事業では新たなサービスの事業化に向けて社内実装や組織の整備を進めている。インフラ領域において、新たな成長ステージに向かうべく、ポートフォリオの転換を進めている」と説明した。
自動車機器事業については、2024年4月1日に、三菱電機モビリティが事業活動を開始。電動化事業については、パートナー戦略を推進し、アイシンとの合弁会社設立に関して基本合意したことを発表している。また、カーマルチメディア事業の早期終息や適正な体格での事業の推進。電動パワーステアリングなどの収益力の高い事業にリソースを集中させる姿勢も示した。「自動車産業は構造転換の時代を迎えており、これを成長のチャンスと捉えて、再成長させる。環境変化を見据えた選択と集中を進め、収益力を向上。アイシンとの合弁会社設立により、三菱電機のパワーエレクトロニクス技術、モーター技術、制御最適化技術と、アイシンのインテグレーション技術とのシナジーを最大化し、多様化する電動化ニーズに対応していく」と述べた。
課題事業については、収益性の改善を進めながらも、撤退や売却の見極めを進めている。「課題事業のなかで、売上高合計で1300億円規模の事業が、利益率10%に回復し、課題事業の指定を解除した。だが、3900億円規模の事業に対しては、撤退や売却の意思決定をした。順次、事業の終息を進めている」と報告した。配電用変圧器事業やカーマルチメディア事業、インジェクタ事業、液晶テレビ事業、液晶ディスプレイ事業が、撤退や売却の対象になっている。
さらに、関係会社の再編を推進。2024年度はより抜本的な対策として、機能の強化と運営のスリム化を進めるという。また、政策保有株式は、2023年度に約1693億円を売却し、ルネサスエレクトロニクスの株式も売却。資産効率の向上を図った。「政策保有株は、原則として保有しない方針とした。保有意義が認められないものは積極的に売却する」としている。
デジタル基盤、三菱電機は「Serendie(セレンディ)」を発表
今回の説明会では、デジタル基盤である「Serendie(セレンディ)」を、新たに発表したことが注目された。
三菱電機が打ち出している「循環型デジタル・エンジニアリング企業」を実現するための新たなデジタル基盤と位置づけており、データ活用ソリューション事業、データ収集コンポーネント事業を、「Serendie関連事業」と位置づけ、これら事業で、2030年度には売上高1兆1000億円(2023年度実績で6400億円)、営業利益率23%(同16%)に拡大する計画を打ち出した。
三菱電機の漆間社長 CEOは、「Serendieは、新たな価値の持続的な創出を実現することになる。Serendie関連事業は、三菱電機の収益の柱になる」と意気込みを語った。
三菱電機では、事業本部ごとに、それぞれの業界に最適化したプラットフォームやシステムを構築。電力機器ではBLEnDer、昇降機やビル管理システムではVille-feuille、空調機器や家電、住設機器ではLinovaを展開しており、それぞれにデータ連携が難しい環境にあった。
Serendieでは、WebAPI連携基盤を提供することで、事業領域をまたがったデータの集約、分析が可能になり、データ収集コンポーネントとデジタル基盤を活用し、事業本部を超えてデータ活用ソリューションを開発していくことになる。
具体的には、「データ収集コンポーネント事業」では、顧客に導入したシーケンサやCNC(Computerized Numerical Controller)などのコンポーネントから、データを収集し、通信する機能を提供。さらに、「データ活用ソリューション事業」によって、これらのデータを利用して、統合ソリューションや遠隔監視サービス、保守サービスなどで活用する。すでに、E&F(エナジー&ファシリティ)ソリューション、加工機・数値制御装置リモートサービス、昇降機遠隔監視・保守サービスなどを提供している。さらにSerendieを通じて事業本部の枠を超えたデータ活用ソリューションを提案。ビルと空調、電力の組み合わせにより、快適空間や安全安心、ロボット配送を組み合わせたスマートビルソリューションを実現したり、FAと電力の組み合わせでは、カーボンニュートラルやSCMの最適化による工場向けソリューションの提供を想定したりしている。
なお、Serendieの名称は、「偶然の巡り合いがもたらすひらめき」を意味するSerendipityと、三菱電機がありたい姿として掲げている「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」のDigital Engineeringを掛け合わせた造語であり、異なる領域の機器やシステム、データ同士の新たなめぐり逢い、脈々と培ってきた技術と限りない創造力により、顧客と社会に新しい価値を生み出し、活力とゆとりある社会の実現に貢献するものになるとしている。
また、三菱電機では、現在、6500人のDX人材を、2030年度には2万人に拡大する計画も明らかにした。
漆間社長 CEOは、「Serendie関連事業の目標達成に向けては、DX人材の確保が最も重要である」と前置きし、「組み込みソフトウェア開発に携わってきた人材や、インフラおよび金融システムなどの大規模システム開発に携わってきたIT技術者のリスキリングを進めるほか、積極的な新規採用やM&Aによる拡充も進める」とした。目標とする2万人のうち、約7割がリスキングによる育成を想定している。
品質風土、組織風土、ガバナンス改革の3つの改革
さらに、人材戦略については、「人財こそが事業の基盤であり、競争力の源泉である」(三菱電機の漆間社長 CEO)とし、人材マネジメントの強化、DE&Iの推進を通じた人的資本の価値最大化を推進。年功的要素を廃したジョブ型人材マネジメントへと転換し、若手優秀層の早期抜擢などを加速するという。経営層に占める女性および外国人割合は2030年度には30%(2023年度実績は15%)に拡大。女性管理職比率は12%(同3.6%)に高める。
一方、サステナビリティに対しては、社会および環境を豊かにしながら、事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速。2024年4月に、サステナビリティ・イノベーション本部を設置して、全社横断の活動を推進しながら、ネイチャーポジティブのフロントランナーを目指す方針も打ち出した。
オープンイノベーションの取り組みでは、サステナビリティやデジタル、ディープテックなどの領域でのスタートップ企業との連携強化に向けて、ベンチャーキャピタルが設立するファンドなどへの出資を150億円規模に拡大。中長期では事業拡大や新事業参入などを視野に入れたM&Aも積極的に実行する。また、2030年度までに、産学官連携関連の研究開発に600億円を投資するという。
また、リスクマネジメントについては、サステナビリティ、AIなどの分野で新たに生じるリスクにも迅速に対応する「リスクに強い会社」の実現に向けて、全社横断のリスク管理を推進。生成AIの社内活用を検討するAI戦略プロジェクトグループを社長直下の組織として設置。また、誰でも声をあげやすい「言える化」風土の醸成を進めるという。
三菱電機では、2021年に品質に関する不適切行為が発生して以降、品質風土、組織風土、ガバナンス改革の3つの改革に取り組んでおり、取締役会傘下の「3つの改革モニタリング委員会」による社外専門家の視点も取り入れて、改革の進捗状況のモニタリングを継続していることを説明した。「そもそも現場が品質不正行為を起こす必要がない仕組みと環境の実現に向けて、マネジメント環境の整備、品質基本理念の改訂を行った。また、組織風土改革の指針である『骨太の方針』に基づき、階層や職種、拠点別などの活動を強化している。私自身もこれまでに100以上のタウンホールミーティングを実施し、現場の意見を聞いている。さらに、経営の機動性と透明性の一層の向上を図る。持続的なに企業価値の向上に取り組む」と述べた。