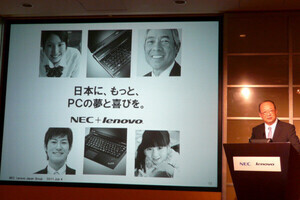日の丸半導体史、NECの華麗なる成功
NECは、1958年に、半導体事業において重要な決定を行った。それは、海外技術の導入ととともに、生産するトランジスタを通信用および工業用に集中。また、民生用半導体で主流だったゲルマニウムを材料にするのではなく、新たにシリコンを採用することもあわせて決定した。とくに、シリコンの採用は、その後のNECの半導体事業拡大を支える重要な決断となった。シリコンは、高い温度まで使用でき、信頼性が高く、通信用や工業用に適しており、集積化の進展にあわせて、その優位性が発揮できたからだ。
さらに、1964年11月にNECの社長に就任した小林宏治氏は、IC事業を、NECの事業発展の中核に置くことを決意した。デバイスからシステムに至るまで広範な専門知識を必要とするIC化の流れは、エレクトロニクスの総合メーカーであるNECには適した事業であると判断。1966年には社内関連部門を集約し、1967年に半導体・集積回路事業グループを発足。NEC社内の英知を集結して、ICの開発、実用化に取り組み、その技術力を背景に、国内トップメーカーとしての地位を築いていった。
このとき、早川電機工業(現シャープ)の要請を受けて、NECは電卓用MOS・ICの開発にも着手した。さらに、LSIの進化にも対応し、電卓用MOS・LSIを開発。電卓の小型化、軽量化、低価格化にも貢献した。
1973年の第一次オイルショックにより、日本経済は低迷。半導体需要も落ち込みをみせたが、NECは半導体の技術動向と市場予測に基づいて、高い水準の投資を継続しつづけ、次々と新製品を市場に投入していった。これが功を奏し、同社の半導体事業はさらに成長を遂げていった。たとえば、1974年の電卓用LSI市場では、NECは40%台という圧倒的なシェアを誇っていたほどだった。
さらにNECでは、シャープからの要請により、POS端末用のLSIを開発。それが、1972年4月に発表された国産初のマイコン「μPD700シリーズ」となって実を結んだ。その後、NECは、国産メーカーとしてはいち早く、4ビット、8ビット、16ビットのマイコンをラインアップ。こうした実績の積み重ねにより、世界有数のマイコンメーカーであるインテル、FCS、ロックウェルと肩を並べる存在へと成長していくのであった。
当時は、日本から米国に半導体を輸出することは、あまり考えられていなかったが、NECは1974年に開発した4キロビットDRAMを輸出。これも、高い品質が評価され、米国で爆発的な売れ行きを見せたのだ。さらにNECは、海外に半導体の生産拠点を相次ぎ建設し、海外事業の拡大を加速していったのである。
NECの半導体事業は、1985年に20億ドル弱の事業規模にまで拡大し、世界1位となる8.2%のシェアを獲得。1990年代の終わりまで、その地位をほぼキープし続けた。
きっかけは日米半導体協定、押し寄せる再編の波
だが、NECをはじめとする日本の半導体メーカーの躍進は、米国にとっては脅威だった。半導体は単純な業界内での競争ではなく、日米の政治問題となり、両国政府間の厳しい交渉を経て、1986年には日米半導体協定が締結された。これ以降、半導体に関する日米貿易は政府によって管理された貿易へと変質。結果として、韓国メーカーが飛躍的にシェアを伸ばす機会をつくることにもつながった。
この協定は、10年にわたって維持され、1993年には米国の半導体生産高が日本を追い抜き、さらに、1990年代半ばになると、日本市場における外国系半導体のシェアは25~30%にまで高まった。さらに、日本の半導体メーカーは、輸出量を減らすために半導体の消費国である欧米やアジア各国に、中小規模の生産工場を建設。これに対して、海外勢は自国内に大規模工場を建設する集中投資を行い、コストを低減。日本のメーカーは、コスト構造において、太刀打ちできない状況へと陥っていったのだ。
さらに、1996年、米マイクロン・テクノロジーが引き起こしたマイクロンショックにより、DRAMの価格が一気に下落。日本の主要DRAMメーカーは、半導体事業で軒並み赤字を計上することになった。それはNECも同様で、1998年度の半導体事業の営業損失は545億円にものぼった。
一方で、超巨大工場でDRAMの生産を集中的に行った韓国サムスン電子は、1990年代後半からシェアを伸ばし、2000年代前半には30%のシェアを超える存在となった。
もはや、日本の半導体業界は、大胆なビジネスモデルの転換を図らなければ、世界を相手に戦っていくことはできなかったが、NECをはじめとする半導体メーカー各社は、痛手が回復しないなかで、この領域に対する大規模な設備投資を継続的に行うという決断は不可能だった。
こうしたなか、進展したのが日本の半導体メーカーによる再編だ。
1999年に富士通、2001年に東芝がDRAM事業からの撤退を決定。NECは、1999年6月に、DRAM分野において、日立製作所との提携を発表し、両社のリソースを結集し、規模の拡大によってコスト競争力の強化を図ることを狙った。
1999年12月に、50対50の出資比率により、NEC日立メモリが発足。2000年9月には、社名をエルピーダメモリに変更した。
エルピーダへの逆風、技術力では覆せなかった
エルピーダメモリへの統合プロセスは、2000年から3段階で進められた。
第1段階は設計および開発、第2段階では販売機能、そして第3段階は生産の統合である。だが、この統合プロセスが進行するなか、半導体だけでなくIT業界全体を大きく揺るがす出来事が発生した。それが、2000年から2001年にかけて起きた、ITバブルの崩壊である。
半導体需要は世界的に落ち込み、とくにDRAMの価格は、エルピーダメモリの採算ラインを大幅に下回る水準にまで下落。親会社であるNECと日立製作所の2社の業績にも影響を及ぼすほどだった。実際、NECの半導体事業は、2001年度に1482億円という営業損失を計上する事態となっていた。
エルピーダメモリでは、外部から経営者を招聘して、経営再建に着手。かつてNECの半導体工場だった広島工場(旧広島日本電気)を基幹拠点として、800億円以上の資金を投入。R&Dから量産までを手掛ける一貫工場の建設によって、2004年春には月産1万8000枚の規模を達成。サーバーやデジタル家電、モバイル機器向けのDRAMに注力する戦略が市場ニーズにマッチし、エルピーダメモリの業績は回復に向かっていった。2003年には三菱電機のDRAM事業も吸収。創業から赤字続きだったエルピーダメモリは、2004年第1四半期には黒字に転換。同年11月には東証一部に上場。2006年度にはNECと日立製作所の関連会社から外れることになった。
しかし、そこに再び逆風が吹いた。
2008年9月のリーマンショックにより、DRAM市場が急変。需要の縮小に伴いDRAM価格は前年の約3分の1にまで下落。エルピーダメモリは、2008年度に1788億円の当期純損失を計上することになったのだ。
経営危機に陥った同社であったが、世界トップクラスのDRAMの開発設計技術を有していることが認定され、2009年に改正産業活力再生特別措置法の第1号認定を受けて、日本政策投資銀行から300億円の優先株出資を受け、再建に取り組み始めた。だが、DRAM価格の下落と、1ドル80円前後という極端な円高により、業績を回復させることができなかった。
2011年時点で、先行する韓国サムスンのシェアは45%。日本唯一のDRAMメーカーであったエルピーダメモリのシェアは第3位の15%。ウォン安を背景に世界市場での価格競争力を持つサムスンに対して、エルピーダメモリは長期化する円高で厳しい戦いを余儀なくされており、同社の経営トップは、「リーマンショック前と比べると、韓国のウォンとの差は70%になる。70%の差を埋めるには、テクノロジーで2世代先に行かないとペイしない。為替が完全に競争力を失わせている。この為替変動の大きさは一企業の努力ではカバーしきれない」と悔しさをにじませた。
2012年2月には会社更生法の適用を申請。同年7月には、マイクロン・テクノロジーとのスポンサー契約に合意し、2013年7月にはマイクロン・テクノロジーが、エルピーダメモリの全株式を取得した。
その後、皮肉なことに、DRAMの価格が急速に回復。DRAM事業を行う企業の集約が進み、スマホをはじめとするモバイル機器の世界的な普及がDRAMの需要を牽引。日本の半導体関係者の間では「あと1年持ちこたえていれば…」と、エルピーダメモリの退場を惜しむ声があがっていた。
NECエレクトロニクスからルネサスエレクトロニクスへ
NECの半導体事業において、DRAMと並ぶ柱となっていたのが、マイコンやシステムLSIである。
だが、2000年前後から、世界中の総合電機メーカーにおいて、設備投資の大規模化や、他事業との特性の違いなどを理由に、マイコン事業やシステムLSI事業を切り離す動きが加速しており、NECエレクトロニクスの誕生も、こうした世界的な潮流のなかで起きたものだった。
NECは、2002年11月に、DRAMを除く半導体事業を分社化し、NECエレクトロニクスが誕生。2003年7月には東証一部に上場した。2003年3月期の連結売上高は7250億円。社員数は2万4000人で、生産および販売拠点は世界12カ所に展開し、順調なスタートを切った。
NECエレクトロニクスが扱う製品は多岐にわたり、幅広い業界に顧客を持ち、なかでも主力製品となっていたのが携帯電話端末向けLSIだ。液晶ドライバや、ベースバンドLSI、NOR型フラッシュメモリと疑似SRAMを組み合わせたシステムメモリを製品化。さらに、DVDレコーダー用の信号処理LSIや駆動LSI、自動車向けのマイコンが、同社の主力製品となっていた。
NECエレクトロニクスは、さらなる事業の拡大へ向けて山形工場に約600億円を投資し、300mmサイズの半導体用シリコンウエハーを用いた最新鋭設備を稼働。さらにコスト競争力を高めるために規模を追求し、同工場に対する最終的な投資額は2000億円に達した。
だが、この固定費が、その後に訪れる市況悪化によって、経営を直撃することになった。
また、NECエレクトロニクスでは、顧客志向を徹底し、顧客との緊密な関係を築き、顧客からのニーズに真摯に応えることを目指したが、これよって多品種少量生産への要望が強まり、設計や生産の効率が低下。価格競争力が下がるという悪循環に陥っていったのである。
さらに、顧客志向の徹底が、自分たちが対峙している少数の重要顧客の意向のみを重視する誤ったメッセージとして浸透。社内の思考を内向きにしてしまい、市場全体の変化や、最終的な製品を利用するエンドユーザーのニーズを掴みにくくする状況を生んでしまったことも見逃せない。
NECエレクトロニクスでは、プラットフォーム戦略を打ち出し、あらゆるメーカーが採用できるモノづくりを開始したものの、顧客に1対1で向き合うという手法から抜け出すことができず、2005年度には赤字に転落。2008年度にはリーマンショックの影響もあり、684億円の営業赤字を計上してしまった。
NECは、事業の抜本的な立て直しのため、NECエレクトロニクスを同業他社と経営統合する道を模索。三菱電機および日立製作所の半導体部門を分社、統合して設立したルネサステクノロジとの合併を決定した。
だが、補完関係となる相手ではなく、競合する相手との合併に、社内からの反発は強かった。そして、リスク回避のために複数購買をしていた取引先からも批判の声が出ていた。
そうしたなかで、2010年4月に、ルネサスエレクトロニクスが誕生。当初は、NEC、三菱電機、日立製作所の持分法適用対象会社だったが、2013年には産業革新機構が筆頭株主となり、経営を主導。2014年度には黒字化し、インターシル、IDTなどを買収。現在でも、マイコンでは世界一の座を維持している。
「良いものを作れば売れる」の美学と呪い
NECの半導体事業を振り返ってみると、1980年代半ばから1990年代にかけては、世界一のポジションを獲得する存在であったものの、様々な変化のなかで、自らの力で事業を継続する道を選択することができなかった。
2000年前後に、借入金が2兆3000億円を超えていたNECに、大規模な投資が必要である半導体事業を継続する体力はなく、しかも、総合電気メーカーから、インターネットソリューションプロバイダへの転換を目指す方針のなかで、半導体事業は切り離すという選択しかなかったともいえる。
NECの120年史には、こんなエピソードが紹介されている。
「高性能テレビ向けLSIを、海外のテレビメーカーに提案した際、試作品の画面を見比べても、台湾メーカーのLSIを使った製品とほとんど見分けがつかなかった。だが、映像をスローモーションで見比べると、NECのLSIの良さがわかる。NECは、この違いが競争力になると考えてLSIを開発していたが、テレビにそこまでの性能を求める人が世界にどれだけいるのか。テレビメーカーは、技術を褒めてくれたが、買ってはくれなかった。同様のことはあらゆる分野で起きていた」
日本企業には、「良いものを作れば売れる」という成功体験がある。だが、その考え方が通用しなくなり、必要な機能だけに集中し、安価に提供することが価値となる時代へと世界は変わっていった。その流れに乗り遅れたのが、NECの半導体事業だったともいえる。