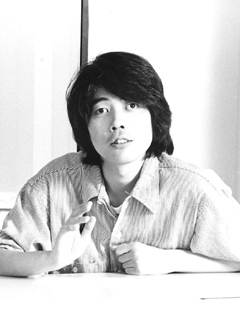iPhone 15シリーズが発表された。さっそく予約した方もいれば、今年(2023年)は見送るつもりだという人もいるだろう。iPhoneも、成熟製品に近い存在になって、数年使い続けるのは当たり前になってきている。
今年のiPhone 15シリーズでは、充電/データ伝送用に用意されているLightningポートが廃止され、USB-Cに変更された。規格としては、無印iPhone 15とiPhone 15 PlusがUSB 2.0相当で480Mbps、iPhone 15 ProやPro MaxはUSB 3.2 Gen2相当で10Gbpsでのデータ伝送ができる。
この値は仕様上の理論値なので、話半分くらいに考えておけばいい。そして、大事なことだが、高速伝送にはそのための対応ケーブルを別途用意する必要がある。
iPhoneがUSB-Cになって便利になること
USB-Cになって何が便利かというと、iPhone用と他の機器用に2種類のケーブルを使い分ける必要がなくなることだ。
たとえば、モバイルバッテリを考えてみよう。多くのモバイルバッテリは、USB-Cのポートを装備する。製品によっては2つめのポートとして板状のUSB-Aポートを持つものもあるが、充電にはUSB-Cポートを使う。両端USB-Cのケーブルを使って、USB PD対応のACアダプタからバッテリへ電力を送り、それを蓄えるわけだ。
一方、満充電状態のバッテリを持ち歩き、iPhoneのバッテリが不安になったら、そのバッテリからiPhoneへ電力を移動して充電する。だが、去年までのiPhoneでは、バッテリを充電するときに使った両端USB-Cのケーブルは使えない。iPhone用の片側USB-C、片側Lightningのケーブルを用意しておき、それを使って充電しなければならない。
つまり、万全を期して持ち歩きガジェットを揃えるには、USB PD対応ACアダプタ(USB-C)、片側がUSB-Cで片側がLingtningケーブル、両端USB-Cケーブルの3点が必要だ。
だが、iPhoneがLightningを撤廃したことで、2本のケーブルの使い分けの必要がなくなるというわけだ。つまり、持ち歩くケーブルが1本減る。
USB-A - Lightningのケーブルは少しずつ引退させていこう
Lightningのプラグは表裏がなく、どちら向きにも装着できる便利さが画期的だった。登場は2012年で、製品としてはiPhone 5からだ。2年後の2014年に最終仕様が決まったUSB-Cのプラグも表裏はない。
だが、Lightningケーブルは、もう片側がUSB-CやUSB-Aである必要があった点で、決してユーザーフレンドリーではなかった。両端Lightningというケーブルが一般的になって、iPhone専用の周辺機器はそのコネクタを装備するようになっていたら、世界は変わっていたかもしれない。だが、そうはならなかった。
これからは、手持ちのすべてのケーブルを両端USB-Cに統一することができる。ケーブルの抜き差しの際に、デバイスごとに電気の流れる向き、データの流れる向きなどを考える必要がなくなるのだ。iPhoneのユーザーにとっては、Lightningがプラグの表裏を意識しなくてもよくなったのと同じくらいに画期的な出来事ではないだろうか。
今年はiPhoneの買い替えを見送るつもりの層も、数年以内には買い替えのタイミングがくる。そのときに備えて、片側USB-Aでもう片側がLightningという両端のプラグが異なるケーブルは少しずつ引退させていこう。
古いiPhoneがLightningを装備している以上、そこはどうしようもないが、もう片側はUSB-Cを前提に考え、モバイルバッテリ、ACアダプタを購入する場合は、USB-Cポートを装備したUSB PD対応のものを選ぶようにしたい。
あらゆる機器がUSB-Cケーブルでつながる時代
USB PDのPDは、Power Delivaryの頭文字をとったもので、各種デバイスを安全に、そして高速に充電するための標準規格だ。両端がUSB-Cプラグのケーブルでアダプタと充電する機器を接続するか、ACアダプタから直出しのケーブルの先端についたUSB-Cプラグを充電する機器に接続して充電する。規格としては両端USB-Cプラグのケーブルを使うのが前提だが、特例として、Lighningも規格に準拠していた。
USB PD対応のアダプタと充電される機器は、インテリジェントに相談し、どのくらいの電力をやりとりするかを相談して決める。そして、過度な発熱などが起こらないように、電力を微調整しながらより短かい時間で満充電に達するように電力をやりとりする。
USB PDの充電の仕組みは、これまでの片側Lightning、もう片側USB-Cケーブルでも同様の振る舞いだった。でも、これからは、両端USB-Cケーブルを使うことになる。
特例が撤廃されるかたちとなる今年以降のiPhoneはもちろん、すでにUSB-Cが一般的になっているAndroidスマホ、そして、WindowsノートPCや各種のMacBookなど、あらゆる電子デバイスがUSB-CによるUSB PD充電で電力をまかなう。それどころか、スマートウォッチ、イヤフォン、シェーバーや電動歯ブラシなど、充電が必要なあらゆる機器がUSB-Cを使うようになる。
プラグの表裏、信号や電気の流れる方向、充電する機器側、アダプタ側など、何も考えなくても、一本のケーブルでつなげばそれでいい時代がすぐそこにやってきている。
とはいえ、その先には、個々のPD対応ACアダプタの対応電力、ケーブルの対応電力といった細かい仕様の違いを理解するという、ちょっとしたハードルが待ち受けている。カフェやパブリックスペース、バスや電車、飛行機といった乗り物の座席などで提供される充電用のUSBポートが板状のUSB-Aだといった世の中のインフラがUSB-Cに置き換わるにも時間がかかるだろう。もう少しの辛抱だと思いたい。