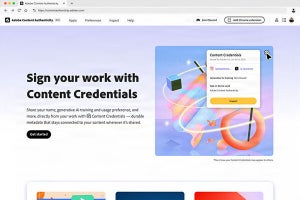AIがクリエイティブに急速に浸透する中で、アーティストはどのように創作物を保護すればよいのだろうか? AdobeはAIの利活用を進める一方で、クリエイターが自身の作品の出どころや正当性を証明し、AI時代における創造性の保護を支えるツールの提供にも積極的に取り組んでいる。
イラストレーターのマイケル・フゴソ氏(Adobeシニア・デザインエヴァンジェリスト)が、ある寿司レストランに行った際、過去に自分がデザインしたロゴが使われていることに気づいた。そのレストランの経営者によれば、ロゴは「別のデザイナーから購入したものだ」という。「ふざけるな」という気持ちになったが、自分のデザインであることを主張してみたものの、証明する材料は自分のファイルと作成日しかなく、それだけで相手を納得させることはできなかった。
-

Adobe MAX 2024 初日のキーノートで、Illustratorの新機能とProject Neoをデモしたマイケル・フゴソ氏。The Vergeの記者に「『Bill and Ted』がステージにいるようだった」と評されたほどハイパーエネルギッシュなプレゼンテーションだった
「私の作品はよく盗まれるんです。いつもです。Etsy(ハンドメイド商品を扱うオンラインマーケット)を探すと、イラストレーターなら、自分の作品を勝手に壁紙にして販売している業者に出くわすでしょう」。
フゴソ氏はデザインの盗用だけでなく、なりすましのInstagramアカウントを作られたこともあり、現在はブランドを守るためにMeta認証(月額14.99ドル)を契約している。「だから、こういうものがあれば、全てが記録されているので助かります」。
フゴソ氏の言う「こういうもの」とは、Adobeの「コンテンツクレデンシャル」である。
-

コンテンツクレデンシャルを適用したフゴソ氏の作品。CRアイコンがメディアにコンテンツクレデンシャルが付与されていることを知らせる。コンテンツクレデンシャルに対応していないWebサイトでも、Chromeの「Content Credentials」拡張機能を導入することでコンテンツ認証情報を確認できる
コンテンツクレデンシャルは、デジタルコンテンツの作成者が自分の作品の出どころや加工履歴などを証明できる技術である。例えば、撮影した写真にコンテンツクレデンシャルを付与すると、作成者情報、加工・編集履歴、使用したツールなどの情報が記録される。この情報は、他者がその写真の信頼性を確認する手がかりとなり、自分の作品の正当性を証明し、インターネット上での不正利用から守ることが可能となる。クリエイターが自身の権利を守り、きちんと評価を受けられるようにするためのツールであり、SNSで画像や動画が簡単に拡散される現代において、フェイク情報の拡散を防ぐためにも重要な役割を果たす。
コンテンツクレデンシャルは今、開花を待つ時期にある。
Adobeはここまで長い道のりを歩いてきた。こうした業界全体で取り組むソリューションの実現は、ニワトリとタマゴの悪循環に陥ることが多い。Adobeは、業界全体で使えるオープンな標準技術として実現するため、まず5年前のMAX 2019で、Twitter(現X)やThe New York Timesとともに「コンテンツ認証イニシアチブ」(CAI:Content Authenticity Initiative)を立ち上げた。CAIは、デジタルコンテンツの出所と信頼性を確保することを目指し、他の企業やメディア団体との協力を通じて、デジタルコンテンツに信頼性を持たせる技術を推進する活動を行っている。そして、2021年にオープンな標準を策定することを目的とした団体「C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)」に設立メンバーとして加わり、同年にC2PA規格に基づいた技術としてコンテンツクレデンシャルを発表した。
CAIのメンバーは3,700を超え、主要なテック企業、ソーシャルメディアプラットフォーム、報道機関、カメラメーカーが参画している。C2PA規格対応は順調に拡大しており、コンテンツクレデンシャルはこの1年だけでもGoogle/TikTok/OpenAI/Meta/LinkedIn/Amazonが対応を進め、米国防総省(DoD)がDVIDSでホストされている画像に採用するなど、公的機関から民間企業まで幅広い分野で普及が進んでいる。
-

10月15日にYouTubeがC2PA標準に対応、説明欄に「このコンテンツの作成手段」(How this content was made)というセクションを設け、映像と音声がカメラで撮影され、編集・加工されていないことを示せるようにした
-

10月15日にニコンがC2PA規格に対応したコンテンツクレデンシャル機能を追加するファームウェアの開発を進めていることを発表し、MAX 2024で開発中のファームウェアを実装した「ニコン Z6III」を展示していた。2025年半ばを目標に、一部報道機関などに向けて提供する予定
そして来年、コンテンツクレデンシャルはアーティストやクリエイターの利活用という点で大きな進展を遂げる。
現在、コンテンツクレデンシャルは、 Photoshop/Lightroom/FireflyなどのAdobe製品に組み込まれて提供されているが、MAX 2024開催直前にAdobeは「Content Authenticity」を発表した。これはクリエイターが自身の作品にコンテンツクレデンシャルを手軽に付与できるWebアプリで、これにより作品制作にAdobeのツールを使ったかどうかにかかわらず、コンテンツクレデンシャルを適用できるようになる。2025年第1四半期のパブリックベータ開始を予定している。
MAX 2024では、AdobeのブースでContent Authenticityのプレビューデモが行われていた。そこで強調されていたのが、「耐久性のあるコンテンツクレデンシャル」を付与できるという点である。これまでコンテンツクレデンシャルに対して、「作品のスクリーンショットを撮ったり、カメラで撮影したらどうなるのか?」という疑問が投げられてきたが、その課題への対策になる。これは、電子透かし、フィンガープリンティング、暗号署名付きメタデータを組み合わせたもので、来歴情報が削除されたり、コンテンツのスクリーンショットが撮影された場合でもクレデンシャルが復元される。
-

「耐久性のあるコンテンツクレデンシャル」(durable Content Credentials)は、セキュアメタデータ、電子透かし、フィンガープリンティングの3つを組み合わせることで、単独では効果を発揮できない耐久性を実現している
もう1つ強調されていたのは、クリエイターが自身のコンテンツを「生成AIモデルのトレーニングに使用しないこと」を選択できるシグナルの導入である。 この新しい保護レイヤーは、AIが生成するコンテンツがますます普及し、洗練されつつあるデジタル環境において不可欠なものである。
-

「Generative AI Training」にチェックを入れることで、クリエイターはコンテンツクレデンシャルを通じて、生成AIモデルのトレーニングへの使用を拒否する意思を示せる。生成AIのオプトアウトアグリゲーターであるSpawningがこの設定への対応を約束しており、Adobeはこの機能の採用を業界全体に広げるよう取り組みを進めていくとのこと
Adobeのコンテンツクレデンシャルのアプローチは、悪質な行為者と戦うのではなく、善良な行為者が自分の作品の信憑性を証明できるようにし、クリエイターに力を与えることにある。それに対し、「AI生成を明確に識別できるようにするべき」など、より厳格な対策を求める意見も存在する。
フゴソ氏は、「全ての作品の背景にはクリエイターのストーリーがあります。私の作品の場合、その多くは航空宇宙エンジニアだった父の影響を受けています」と述べる。AIは芸術的なスタイルを模倣し、人間のクリエイターに酷似した作品を生み出すことができるが、同時にAIは人間の創造性をさらに高めるツールにもなる。Adobeは後者の可能性を追求している。コンテンツクレデンシャルの考え方は「人間性の証明(proof of humanity)」である。何時間もかけてテクスチャを施した作品であれ、AIを利用した作品であれ、クリエイターが制作するコンテンツの背後には人間の創造性がある。それを示せるようにするというアプローチだ。
それを採用するかどうかはクリエイターの判断に委ねられるが、近い将来、クリエイターやアーティストは創作だけでなく、作品を保護するためにもテクノロジーとより深く関わる必要が出てくるだろう。 その兆候はすでに明確にあらわれている。AI倫理、透明性への対応は、ブラシやデザインソフトと同様に、クリエイターのツールキットに不可欠なものとなりそうだ。
最後に「Project Know How」にも触れておこう。これは製品化の段階ではない実験的な機能やツールを披露するMAXイベント「Sneaks」で公開された技術である。
コンテンツクレデンシャル技術を基盤に、デジタルタグを利用してクレデンシャルの耐久性をさらに高めている。デモでは、わずか8秒に切り取られたクリップからオリジナル動画(1分50秒)を導き出し、しかも加工された部分を特定してみせた。この技術はデジタル以外のコンテンツにも有効で、ポスターなど作品が印刷されたものからでも追跡できる。デモでは、素材的に識別が困難なトートバックに印刷されたものからでも、コンテンツクレデンシャルのデータに導くことができた。
-

左の8秒のクリップから元の動画を見つけ、1人の子供が削除されていたことを明らかにした
-

トートバッグに印刷された粗いプリントをカメラに向けると(左)、イメージにコンテンツクレデンシャルが付与されていることを識別、元の作品の詳細な履歴を表示(右)
Sneaksは、いわば「実験的なアイデアのショーケース」のようなもので、Sneaksで披露される技術が全て製品化されるわけではない。しかし、「Project Know How」は非常に印象的なデモであった。今後のコンテンツクレデンシャル強化に何らかの形で取り入れられることを期待したい。