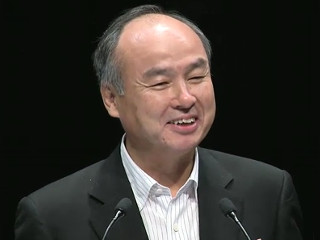ワイモバイルは都心でこそ、それなりの知名度があるものの「地方ではまだまだ認知が少ない」(島田氏)。ソフトバンクユーザーの解約受付や、料金を確認して契約を渋るユーザーに対して、いわゆるLCC(Low Cost Career)としてのワイモバイルショップへと案内することで、結果として最低限の契約を勝ち取る設計にしている。
「ワイモバイルがあるのがソフトバンクグループ最大の強み。基本軸は当然単価の高いソフトバンクですが、軽自動車的にワイモバイルもありますよ、とおすすめできるところが良い。かねてからソフトバンクショップ、ワイモバイルショップとしてのノウハウを蓄積しているため、お客さまへの提案、熱意などは他代理店よりも高いと思います」(島田氏)
格安スマホにはない強みを守るために
細かい仕掛けでは、2階に店を構えるカフェも同社の直営。フランチャイジーではなく直営にすることで、営業収入はもちろん、カフェのメニューにショップへ送客するためのチラシを挟むといった"相乗効果"も狙っているという。
「もともと、カフェやレストランのフランチャイズ事業のノウハウがありますから、自社でカフェを運営する力を持っています。何より、一度カフェがあると認識してもらって常連になれば、それだけショップの露出機会は増えますし、商店街やショッピングモールと違って離脱の可能性も少ない。年配の方なんかは、もし下のショップでスマートフォンを買って使い方がわからなければ、カフェついでにショップで質問もできる。利用満足度を上げて"地域密着"を追求できればと考えています」(島田氏)
システム化や無駄を削ぎ落としたコスト設計でMVNOが台頭している。ただ、2017年4月に国民生活センターが公開した"格安スマホ"に関する相談件数は、2011年度が20件であったのに対し、2016年度には1045件(2015年度は380件)と急増している。安易なMVNOへの移行によって「繋がらない」「使い方がわからない」「料金が高い」といった問題が浮き彫りになった格好だ。
もちろん、総コストが下がりつつも通信サービスを利用できるメリットは大きい。ただ、これまで主要3キャリアのサービスに慣れたユーザーが安易に乗り換えることで、思いもよらぬトラブルに遭う可能性があることも忘れてはならない。生き残りをかける携帯ショップの多角化戦略は、サポートを担う"インフラ"を守る戦いでもあるのだ。