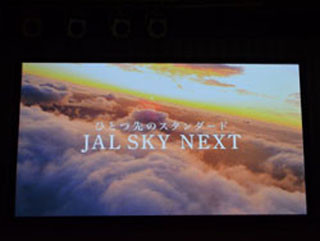既報の通り、日本航空(JAL)が今年7月、国内線初となる機内インターネット接続サービスを開始する。同社は2012年7月から長距離国際線の機内で衛星通信とWi-Fiを利用したインターネット接続サービスを提供していたが、開始から2年を経て、ついに国内線にもそれが拡大される格好となる。
サービス名称は国際線・国内線とも「JAL SKY Wi-Fi」で、機外との通信に衛星回線を用いる点は共通だが、国際線と国内線では飛行時間が大きく異なるため、料金体系やサービス内容はそれぞれの利用シーンに合わせたものが用意されている。
今回、同社で機内エンターテインメントなどの開発を担当する顧客マーケティング本部 商品サービス開発部の江幡考彦氏に話を聞く機会を得た。前編となる本稿では、主に国際線におけるサービスのねらいや技術的な仕組み、今後の展開などについて詳しく紹介したい。
導入のきっかけは「経営破綻」と「東日本大震災」
前述の通り、JAL SKY Wi-Fiの名称でサービスが始まったのは2012年だが、実はそれ以前にも2004年末から約2年間、成田からロンドン・ニューヨークなど一部の長距離路線でインターネット接続が提供されていた。これは、米ボーイングが開発した「Connexion by Boeing」と呼ばれるサービスを利用したもので、今回のJAL SKY Wi-Fiと同様に、衛星回線を経由してノートPCなどのWi-Fi対応機器からインターネットに接続できた。
しかし2006年8月、ボーイングは当初の期待ほどビジネスが拡大しなかったとして、インターネット接続事業からの撤退を発表。Connexion by Boeingを利用していたすべての航空会社のインターネット接続サービスが同年末をもって終了してしまう。
利用が伸びなかった理由としては、当時は現在ほどWi-Fi対応機器が普及していなかった、いつでもネットにつなぎたいという需要が大きくなかった、機内ではむしろ「ネットや仕事からは開放されたい」と考える顧客のほうが多かった……などの点が指摘されているが、一言で言えば、時期尚早だったということになるのだろう。とはいえ、インターネット需要の高まりに備え、日本航空では他のシステムの検討を引き続き行っていた。
江幡氏によると、機内インターネットの導入が再び具体化する直接的なきっかけはふたつある。
ひとつは、日本航空グループの経営破綻である。2010年1月に会社更生法を申請して倒産した同社は、社会から厳しい視線が注がれる中で再建を図ることになった。だが、大きくブランド価値を毀損した中で再びユーザーから選ばれるエアラインとなるには、名実ともに「日本航空は生まれ変わった」ことを市場に示さなければならず、サービス面においても利用者本位の新鮮な体験を提供していく必要があった。
もうひとつのきっかけが、2011年3月の東日本大震災だった。震災当初、航空路線でも全国的な混乱が生じたが、特に地震発生時に飛行中だった航空機の一部では、東日本の広い範囲で空港が同時に閉鎖されたために、行き先を変更し着陸するまでかなりの時間を要した。
「大地震が発生した」以外の情報が入ってこない中、一種の閉鎖空間である飛行中の機内でただ待つしかなかった乗客の不安は大きく、機内から地上との連絡や最新ニュースの確認などを可能にする手段の必要性は明らかだった。
機内は5カ所のアクセスポイント、機外は12~18GHzの「Kuバンド」で通信
日本航空では、座席を刷新した「SKY SUITE 777/767」機を2013年1月から順次国際線に投入し好評を得ているが、JAL SKY Wi-Fiはこれに約半年先行する形でニューヨーク線から提供が始まった。
国際線では、米Panasonic Avionicsの「eXConnect」というシステムを利用。機内には5カ所程度のWi-Fiアクセスポイントを設置し、機外とは「Kuバンド」と呼ばれる周波数帯(12~18GHz)の衛星回線を使用することで、機内インターネット接続サービスを実現している。
航空機には、運航情報を地上とやりとりするためのACARSと呼ばれるデータ通信システムが搭載されている。ACARSは、地上からの電波が直接届かない洋上では衛星回線を使用してデータの送受信を行うが、機内インターネット接続サービスに用いられる衛星回線はまったく別物で、アンテナなどの通信設備が別途新たに搭載される。
ACARSではLバンド(1~2GHz)と呼ばれる電波が使われているが、これは波長が長い分天候の影響を受けにくいという長所はあるものの、帯域が狭く通信速度は遅い。テキストメッセージの送受信程度であれば問題ないが、画像などを含めるとWebページ1枚が1MBを超えることも珍しくない現代においては、昔のアナログモデムでネットにつなぐようなもので、利用者にストレスを強いることになる。
対して、KuバンドはBS・CS放送などにも利用されている周波数帯で、大容量の映像の伝送も可能な帯域を確保できるため、上空においてもADSL回線並みの通信速度を確保できるのが特徴だ。
なお、長距離路線ではひとつの通信衛星のサービスエリア内に飛行区間が収まらないため、位置に応じてPanasonic Avionicsが契約している複数社の衛星を切り替えながら飛行していく。通信衛星は赤道上空にあるため、北極に近い高緯度を飛行する(航空機は定期路線でも気流の状態などに応じて異なるルート・高度を飛ぶ)場合一部つながりにくくなる場合もあるが、高高度での水平飛行中はおおむね常時インターネット接続が可能となっている。
このような事情のため、サービスの具体的な通信速度は案内されていないが、ほとんどのWebサイトの閲覧には問題ない水準のようだ。
衛星との通信を行うためのアンテナは、機体上部の外側に取り付けられており、目視でもアンテナ部分のふくらみが確認できる。ただし外部から見えるドーム状のパーツはアンテナに風雨が当たらないようにするためのカバーで、アンテナ本体はドームの中に搭載されている。気流が直接触れる場所に新たな機器を設置し、さらに機体に穴を開けて配線を行うため、アンテナの取り付けにはあたっては米連邦航空局(FAA)、国土交通省航空局の承認を得る必要がある。
アンテナの取り付けにかかる工期は約2週間。機体の整備スケジュールに合わせて取り付けを行うこともあるが、アンテナ設置のためだけに機体を格納庫入りさせたこともある。
通信機器の購入・設置などにかかる費用は日本航空が負担しているが、サービス自体の運営は料金の収受も含めてPanasonic Avionicsが行っている。街中の飲食店などに通信事業者の公衆Wi-Fiサービスが導入されているのと同じ仕組みと考えるとわかりやすい。
日本航空では、JAL SKY Wi-Fiはあくまで機内サービス向上の一手段として考えており、この料金を直接の収益源として期待するものではないという。ただし、容量に限りのある衛星回線を乗客間で共有するため、本当に使いたい利用者に対しての品質が落ちることがないよう、少なくとも機外との通信に関しては有料での提供を前提になるとしている。
なお、日本航空でも今後新造機が導入される場合はボーイング787型機が中心となる見込みだが、機体の大部分が炭素繊維で構成される787では世界的にもまだアンテナの取り付け例がなく、現在米国で当局の承認を得るための手続き中という。ただ遠くない将来787でも対応は可能となる見込みで、いずれは同型機へもサービスが広がる可能性はある。
日本は「LINEの需要が特に高い」
国際線の長距離路線ではもともと座席の個人用モニタで映画などを楽しむことができるため、YouTubeなどのコンテンツへのアクセスは割合的には小さく、またビジネスクラスなど上位クラスの乗客の利用が多いという。このため、現在はノートPCで仕事をするビジネス客の利用が中心と考えられるが、スマートフォンの利用が幅広い世代に広がっているので、客層の拡大も予想される。
国際線のJAL SKY Wi-Fiでは、料金を支払うとID・パスワードが発行される形式なので、例えばノートPCで利用開始後、有効時間が残っていればいったんログアウトしてスマートフォンやタブレットなど別の機器から再ログインすることも可能だ。
ネットワークはPanasonic Avionicsが管理しているので具体的なプロトコルやポートは明らかにされていないが、VoIP通話機能を持つアプリケーションからは通信が行えないようになっている。ただし、日本の利用者から特に需要が大きいため、LINEのトーク(テキストチャット)機能は遮断されないよう日本航空から要望を出し、ネットワークの設定をカスタマイズしてあるという。
また通常、通信用の電波を発信する機器は常時使用が禁止されているが、機内のアクセスポイントとの通信を目的とするWi-Fiの使用は離着陸時を除き許可されている。Connexion by Boeingによる2004年のサービス提供前に、使用が制限される電子機器を具体的に規定した国土交通省の告示(航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示)の改正が済んでいたため、今回については新たな規制緩和を待つ必要はなかったという。
ただし、Wi-Fi以外の通信機能(3G/LTEなど)は引き続き利用禁止なので、利用者側のモバイル機器の正しい使い方は、
- 地上で飛行機のドアが閉まる前に、機器を機内モードに設定して電源を切る
- 離陸後、Wi-Fi利用可能がアナウンスされてから機器の電源を入れ、機内モードのままWi-Fiのみをオンにする
- サービスを利用する
- 着陸態勢に入り電子機器の電源オフがアナウンスされたら電源を切る
という手順になる。なお、前出の告示では「無線LANシステムを装備する航空機内において当該システムに接続して使用するもの」に限り使用可能となっているので、Wi-Fi対応の飛行機に乗っている間も、PCとスマートフォンを直接結ぶアドホック通信や、携帯型ゲーム機での対戦プレイなどを行ってはいけないということになる。
後編では、今年後半に導入される国内線版のJAL SKY Wi-Fiを中心に、その概要やサービスの意図について、JAL SKY Wi-Fiサービス全体への私見も交えて紹介していく。
■後編はこちら
「ネットにつながる『安心感』が、JALを使う理由になる」 - JAL SKY Wi-Fi担当者に聞く・後編