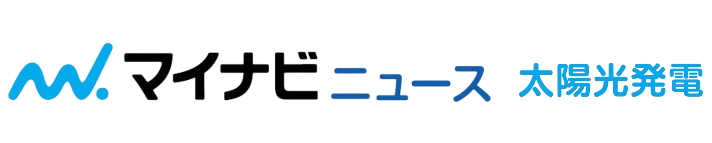太陽光発電による売電は、固定価格買取制度(FIT)によっていくらで買取ってもらえるのかが決まっています。買取の条件や価格は毎年変わるため、新規でこの制度を利用するなら最新の情報が必要です。
そこでこの記事では、2026年度の固定価格買取制度の基本的なことから太陽光発電で利益を出すコツまで、徹底的に解説していきます。設備の導入には少なくとも数百万円かかり運用は数十年続くので、後悔しないためにも制度の詳細をおさえておきましょう。
マイナビニュース太陽光発電ガイド運営おすすめ!



紹介するランキングは、太陽光発電メーカーの利用者に向けておこなったアンケート結果を集計し、マイナビニュース太陽光ガイド運営が独自のロジックで作成したものです。(クラウドワークス調べ 2021/11/18〜2021/12/1 回答者45人)
その他のサイトは以下の記事で紹介しています。

2026年度の太陽光発電の固定価格買取制度

2026年度の固定価格買取制度では、電気をいくらで買取ってもらえるのでしょうか。売電による利益を考慮して設備を導入しようとしている場合は、想定より安いといつまでも初期投資を回収できず、赤字になってしまうかもしれません。そこで発電容量ごとの買取価格や、実際に太陽光発電を導入する流れなどを解説していきます。
2026年度の発電容量別の買取価格
2026年度の買取価格は、発電容量別で次のようになっています。
| 発電容量 | 買取価格(1kWhあたり) | 期間 |
| 10kW未満 | 15円+税 | 10年 |
| 10kW以上50kW未満 | 11.5円+税 | 20年 |
| 50kW以上250kW未満 | 8.9円+税 | 20年 |
| 250kW以上 | FIPのみ選択可能※1 | – |
※1 電力市場の価格によって電気の買取価格が変動する制度
10kW未満は住宅用という分類で、4.5kWあれば節電した4人家族の使用電力をまかなえるでしょう。10kW以上は事業用という分類で、売電を前提とした大規模な太陽光発電を想定しています。
一度契約を結ぶと、それぞれ定められた期間は契約時の買取価格で売電が可能です。再契約を結ぶ場合は、そのときの買取価格で一定期間売電を続けることになります。
大規模な太陽光発電の入札
250kW以上の大規模な太陽光発電の売電では、業者による入札が導入されています。入札は業者間の競争によるコストダウンが目的で、実際の電気利用者の負担が軽くなります。
また入札は、その都度募集される発電容量が変わるので、募集された容量に対して入札の希望者が多いと、売電契約を結べない可能性があります。利益を優先して上限価格にしていると、他者との価格競争に負けるかもしれません。
電気料金に含まれる賦課金の仕組み
電力会社が個人や企業から電気を買取りして販売する場合は、買取りにかかった費用をどこかで回収しなければ事業として成り立ちません。そのため太陽光発電のような再生可能エネルギーの販売には、賦課金というものが設定されています。
利用者が支払う電気代は次のように計算できます。
- 利用者の支払い=電気料金+賦課金
賦課金は電力会社への交付金や電力の供給量などで決まり、2026年度では1kWhで3.49円です。太陽光発電で消費電力を全てまかなっている場合は支払う必要はありませんが、このような仕組みになっていることは把握しておきましょう。
住宅用で太陽光発電を始める流れ
戸建て住宅に太陽光発電を設置し、固定価格買取制度を使って売電する場合は次の流れで発電を開始します。
- 業者に太陽光発電での売電を相談
- 太陽光発電の設備の見積り
- 見積り内容で正式な契約
- 売電の申込み
- 太陽光発電設備の設置
- 業者から引き渡しの説明
- 試運転してから売電を開始
売電の申込みは、電力会社と経済産業省へ必要な書類を提出します。事業計画書の作成を求められるため、初めて売電を始める人は業者に相談するか代行業者を利用したほうが、スムーズに手続きが進むでしょう。
なお、遅くても3ヶ月程度で認定の許可が下ります。
事業用で太陽光発電を始める流れ
事業用の場合も、太陽光発電を導入する流れの基本は住宅用と大きく変わらず、次のようになっています。
- 投資の目的や規模をある程度決めて業者へ相談
- 事業用の太陽光発電の見積り
- 理想に合ったプランで業者と契約
- 事業用の売電の申込み
- 作成したプランに合わせて工事
- 完成したら引き渡しの説明
- 試運転してから売電を開始
住宅用との大きな違いは、250kW以上だと入札の申込みをすることと、50kW以上で電気主任技術者の選任が必要になることです。住宅用と同様に売電の申込みは複雑なため、業者の助けを借りながら進めましょう。
2026年度以降の固定価格買取制度

今から太陽光発電による売電の計画を立てたとしても、2026年度中に申込みを開始できるとは限りません。また契約期間が過ぎると再更新の必要もあるため、固定価格買取制度が将来どのようになるのか知っておかないと、想定していた利益が得られない可能性があります。そこで、2026年度以降の動向について解説していきます。
買取価格は2021年度より値下がり
固定価格買取制度が開始された2009年当初は、住宅用で1kWhあたり48円でした。しかし買取価格は値下がりを続け、2026年の住宅用で15円です。
再生可能エネルギーの利用者側にとっては、電気代が現状より安くなることはうれしい事態ですが、売電する側にとっては厳しい状況です。
制度の開始当時よりは、太陽光発電設備の価格は下がり発電効率も上がっていますが、利益を出したい人は早く始めたほうがよいでしょう。特に事業用で始めた方は契約期間が20年のため、1円の違いでもトータルの利益に出る影響は大きいです。
250kW以上の太陽光発電はFIPがメイン
電気の買取制度は2022年4月から、FIPという新しい仕組みが導入されました。これまでの固定価格買取制度では、市場価格にかかわらず一定の価格で買取ってもらえていましたが、FIP制度では市場価格に一定の価値を上乗せした額が売電収入になる仕組みで、市場価格が高い状況であれば短期的に収入は増えてくれます。
従来通りの固定価格買取制度も残りますが、250kW以上の太陽光発電ではFIP制度しか選択できません。
2026年度以降に売電で利益を最大化したい場合には、市場価格の変動も予測して利用する制度を選択しなければならず、精度の高い収益をシミュレーションすることは難しくなります。
固定価格買取制度の終了者が増加
2009年に始まった固定価格買取制度では住宅用の契約期間が10年のため、2019年から終了者が出てきましたが、このことを「卒FIT」といいます。
売電を続ける場合は電力会社と再度契約を結びますが、当時より買取価格が半額以下になり今後どうしたらよいのか問題になりました。この問題は、これから固定価格買取制度で売電を始める人も抱える悩みです。10年後は2025年より買取価格の低下が予想されているため、再契約を結ぶと利益は減ってしまいます。
事業用で始めた場合は、現状で実質利回りが6~7%といわれています。期間が20年のため、初期投資が回収できた頃に契約の更新です。将来どうしたいのかを考えておかないと、電気の扱いに困ってしまうでしょう。
2024年度以降の太陽光発電で利益を出すコツ

多額の出費をして太陽光発電を始めるのであれば、できるだけ固定価格買取制度を利用して利益を出したいものです。そこで、太陽光発電の導入が初めての人におすすめのコツを5つ紹介していきます。
- 設置業者を厳選
- 蓄電池を導入
- 補助金を申請
- 事前にシミュレーション
- 買取してもらう電力会社を厳選
それぞれどのようなことをしていくのか、詳しくみていきましょう。
設置費用を節約するため業者を厳選

住宅用に太陽光発電を導入する場合には、1kWあたりの初期費用は20万~30万円が相場です。しかし実際に支払う代金は、全く同じ設備であっても業者によって違います。業者がよく取り扱っているメーカーの設備であれば、割引がきいたり工事の単価が安かったりして、100万円以上の差が出ることも珍しくありません。
少しでも初期費用を抑えるためにも、業者は必ず複数社で比較してから厳選してください。見積りまでならどの業者でも基本的に無料です。太陽光発電に関する一括見積りサイトを利用すると、設備を設置する地域で対応してくれる業者を自動的にリストアップしてくれます。一度の情報入力で見積りの依頼もできるため、手間を大幅に削減できます。
太陽光発電の初期費用について、内訳まで詳しく知りたい方は以下の記事もおすすめです。

 マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営
マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営業者から提案された内容には注意が必要です。また、単価が適正かどうかを確認する場合は、同じ商品を相見積すると確認しやすいです。
太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!


太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース太陽光ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
太陽光の専門家監修!太陽光発電一括見積もりサイトおすすめランキング


タイナビ以外にも複数の業者を比較して、質の高い業者に依頼したいという方に向けて、実際にサービスを利用したことのある方に行ったアンケート結果をもとに、太陽光発電一括見積もりサイトをランキング形式で紹介!
さらに、専門家に聞いた太陽光発電一括見積もりサイトを利用する際の注意点や、質の高い業者を見極めるポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。
自家消費を増やすため蓄電池を導入
太陽光発電を導入するだけでは発電できない早朝や夜は、電気代を支払わなければならず、時間指定で電気代を安くしていても毎月電気代はかかり続けます。そこで利益を出すためにおすすめのコツが、自家消費を増やすための蓄電池の導入です。蓄電池は昼間の太陽光発電の余剰分を貯めておけて、早朝や夜に使用して電気代をゼロにすることができます。
また今後は電気代が値上がりする可能性があるため、売電するより自家消費したほうがトータルで得をします。特に固定価格買取制度が切れたあとは、蓄電池を使い自家消費したほうがよいです。蓄電池の設置スペースを確保する必要がありますが、導入することで災害に強い家にもなってくれます。


自治体や国に補助金の申請
太陽光発電の普及は自治体(都道府県・市区町村)や国が推進していて、次のような補助金があります。
【東京都の自治体が独自に行っている補助金の例】
| 補助金がある自治体 | 補助金名 | 制度の概要 |
| 東京都 | 住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 | 太陽光発電:10〜18万円/kW 蓄電池:12万円/kWh |
| 東京ゼロエミ住宅関連補助金 | 太陽光発電:10〜13万円/kW (上限36〜39万円) 蓄電池:12万円/kWh | |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 太陽光発電:10〜20万円/kW 蓄電池:8〜12万円/kWh | |
| 東京都港区 | 地球温暖化対策助成制度 | 太陽光発電:10万円/kW(上限40万円) 蓄電池:機器費の2分の1(上限40万円) |
| 東京都葛飾区 | 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 | 太陽光発電:8万円/kW(上限40万円) 蓄電池:機器費の4分の1(上限20万円) |
| 東京都荒川区 | 令和7年度新エコ助成事業 | 太陽光発電:2万円/kW(上限25〜30万円) 蓄電池:5千円/kW(上限10〜15万円) ※条件あり |
| 東京都新宿区 | 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 | 太陽光発電:2万円/kW 蓄電池:機器費用の10分の1 |
| 東京都江東区 | 地球温暖化防止設備導入助成 | 太陽光発電:5〜6万円/kW 蓄電池:1〜2万5千円/kWh |
| 東京都杉並区 | 【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成 | 太陽光発電:2万円/kW 蓄電池:機器費用の1/4 |
【太陽光発電に関する国の補助金】
| 補助金制度 | 制度の概要 |
| みらいエコ住宅2026事業 | 2026年度に行われる予定 「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、「GX志向型住宅」の新築及び省エネ改修等への支援 最大で125万円 |
自治体や国の補助金は年度内で予算が決まっており、当初の募集期間中でも予算切れで早期に終了します。また年度が変わると、制度の条件が変わったり制度そのものがなくなったりもするため、早期に申し込みするようにしましょう。
東京都以外のお住まいの地域に関する補助金情報は下記を参考にしてください。


事前に実利回りでシミュレーション
太陽光発電の発電量を維持するためには、定期的なメンテナンスやパワーコンディショナと呼ばれる機器の交換が必要です。固定価格買取制度による売電価格だけで利回りを計算していると、手元に残るお金の少なさで後悔してしまうかもしれません。
利益をシミュレーションするときは、最低限メンテナンスなどのコストを勘定に入れ、実利回りで考えておきましょう。さらに発電量は天候に左右されるため、地域の日照量などを考慮しておくと、精度を上げて利益をシミュレーションできます。
特に融資を受けて事業用として売電を行う場合は、返済に余裕を持っておかないとすぐに事業が破綻してしまいます。事業計画書を業者に作成してもらうときに、どこまでのことを想定した利益なのかを確認しておきましょう。
太陽光発電が儲かるかどうかについては、以下の記事でも紹介しています。


高額な買取り先と契約
2016年以降の電力自由化でさまざまな新電力会社が生まれており、一部の電力会社では固定価格買取制度よりも高額な「プレミアム買取制度」というものを導入しています。事業形態の工夫などで利益を確保していて、買取価格の上限はありません。
地域によって契約できる電力会社の数は変わります。買取価格の高さや手続きのしやすさ、手数料の有無などで比較してください。最寄りの地域でどのような売電先があるのかは、経済産業省資源エネルギー庁の「登録小売電気事業者一覧」などから調べられます。
太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!
太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。 特に編集部がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!

太陽光発電を始める前の基礎知識


導入する太陽光発電の設備についてまったく知識がない状態では、業者の提案内容で問題がないのかを判断することは難しいでしょう。価格は見積もりで比較できても、十分な発電ができるかどうかまではわかりません。そこで太陽光発電の基礎知識として、パネルの種類ごとの特徴や必要な性能などを解説していきます。
太陽光発電パネルの種類と特徴
太陽光発電パネルの種類は、使われる素材によって大まかに次の5つがあります。
| 種類 | 特徴 |
| 単結晶シリコン | 初めて実用化された太陽光パネルの素材 発電効率がよい 高純度の結晶を必要として割高 |
| 多結晶シリコン | 単結晶シリコンの製造過程の余りで作成 単結晶シリコンより発電効率は落ちる コストが安い |
| アモルファスシリコン | 結晶になっていないシリコンを使用 加工が容易で軽量 結晶の太陽光パネルより発電効率は落ちる |
| ハイブリッドシリコン | 単結晶とアモルファスのハイブリッド 高温でも高い発電量を維持 製造に手間がかかり割高 |
| CIS | 銅、インジウム、セレンの3種で作られた太陽光パネル シリコン系より発電量が1割高い 経年劣化に強い |
メーカーによっては、特定の種類の太陽光発電パネルしか扱っていない場合があります。それぞれの特徴を把握しておくと、厳選が容易になるでしょう。
太陽光発電パネルに求められる性能
最適な太陽光発電パネルは、価格以外に次の性能にも注目して選ぶようにしましょう。
- 変換効率
- 出力
- 耐久性
変換効率は、高ければ高いほど発電量が増えてくれます。同じ発電量でも変換効率が高い太陽光発電パネルを採用するほど、設置する面積は小さくなります。出力も変換効率と同様に、高いほど少ない数で目的の発電量の達成が可能です。
耐久性は、ただ耐用年数が長いだけでなく環境による悪影響を受けにくいかも重要です。海が近い地域では塩害に強く、雪がよく積もる地域では雪の重みに耐えられる頑丈さが求められます。
太陽光発電パネルが耐震性や雨漏りに影響
太陽光発電パネルを既存の屋根の上に設置すると、耐震性や雨漏りに影響が出てきます。太陽光発電パネルの1枚当たりの重さは15kg程度ですが、電気代をゼロ円にしようとするとトータルで数百kgになります。重さは分散されていても、住宅の重心は上がり揺れやすくなるでしょう。
また屋根に穴をあけて架台を取り付けるため、経年劣化や施工不良などで雨漏りが起こってしまいます。リスクを下げたい人は、太陽光発電パネルの設置実績が豊富な業者に依頼するとよいでしょう。
【Q&A】固定価格買取制度の気になる疑問
ここまで固定価格買取制度について、基本的なことから利益を出すコツまで紹介してきました。しかし実際に売電を始めてから不安になることもいくつかあるでしょう。そこで売電の初心者が抱きやすい疑問について解説していきます。
まとめ
太陽光発電の売電は、基本的に固定価格買取制度に従います。2026年では住宅用は1kWhあたり15円で買い取ってもらえて、契約は10年続きます。しかし制度は毎年細かな変更が加えられ、買取価格だけ見ても2026年頃には11円になろうとしています。売電できる量も2020年度よりは制限がかけられ、50kW以上でないと全量を買い取ってもらえません。
これから太陽光発電を導入する人は、最新の固定価格買取制度を参考に利益が出るかどうかを検討してみてください。複数業者の見積もりを比較してアドバイスも聞きながら導入を進めると、後悔するリスクは下がるでしょう。
太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!
太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。 特に編集部がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!

※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・東京都環境局
・みらいエコ住宅2026事業
・葛飾区公式ホームページ
・経済産業省
監修者情報


太陽光や蓄電池等の専門家。2017年より某外資系パネルメーカーに所属し年間1000件以上の太陽光を販売しトップセールスを記録。これまでの知見を活かしたYouTubeが業界NO,1の再生数を誇り、2021年に開業。現在は一般の方向けに自社で販売〜工事を請け負う。Youtubeチャンネル
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。