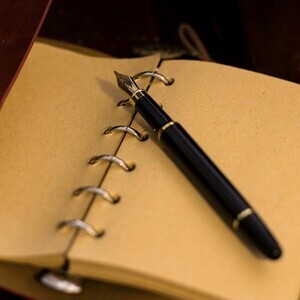この連載では、日本で初めてコーチングで上場したビジネスコーチの橋場剛 取締役副社長が、経営者・経営幹部に対するエグゼクティブコーチングについて語ります。第1回のテーマは「エグゼクティブコーチングが刺さる2つのタイプ」
エグゼクティブコーチングの対象に選ばれる人とは
企業の社長、取締役、執行役員、部長といったエグゼクティブ層の方々に対して行われるエグゼクティブコーチングは、そもそもどのような人が対象に選ばれ、どのような人に刺さるものなのでしょうか。
20年以上にわたって、こうしたエグゼクティブ層500名以上に対して1対1でエグゼクティブコーチングを行ってきましたが、対象に選ばれるのは一言で言えば「会社から期待されている人」です。そして、エグゼクティブコーチングが「刺さる人」、つまり「成果につなげることができる人」には大きく2つのタイプがあります。
一つは「悪癖を持った優秀な人」、もう一つは「悪癖は持っておらず、さらによりよく成長したいと考える優秀な人」です。つまり「デキる人」ということになるのですが、なぜこうしたタイプにエグゼクティブコーチングが刺さるのか、について今回はお伝えしたいと思います。
そもそもエグゼクティブコーチングの場合、パーソナルコーチングとは異なり本人みずから「私が受けたい!」というケースは極めてまれであり、多くの場合、企業の経営幹部や人事部門から推薦または選抜されることが一般的です。
エグゼクティブコーチングを1名に対して実施するお金があれば、若手もしくは中堅社員を1名採用できてしまうため、依頼する企業側としては、成果が出るか出ないかよく分からない人には投資するはずありません。
どうせ投資するなら「成果が出る人(または成果が出る可能性が高い人)」を選ぶことになり、「成果が出る可能性が高い人」=「デキる人」となります。
「デキる人」は社員を1名採用できるくらいのお金を会社が自分に投資してくれていることの意味を十分に理解しており、コーチングを通じて「成果を出すこと」が、自身の次のキャリアアップにつながることも理解しています。
エグゼクティブコーチングの目的は端的に言えば、「リーダー自身が行動変容することで周囲に肯定的な影響力を与えること」です。
エグゼクティブコーチングは通常のコーチングとは異なり、コーチングの開始前と開始後に360度評価を行うことが一般的であるため、「成果を出す=開始前より開始後の360度評価のスコアが上がる」ことが求められます。
いわゆる「デキる人」とは、これまで仕事を通じて「一定の結果」を出してきた人たちであり、エグゼクティブコーチングのような人材育成投資に対しても「仕事の一環」として結果を出すことにコミットする確率が高くなります(もちろん例外もありますが)。
2つのタイプ別、コーチングで生み出される成果
一つ目のタイプ「悪癖を持った、デキる人」は、期待されている成果が非常に分かりやすいです。例えば、「コーチング前の状態が、パワハラ傾向の言動あり」だったものの、「コーチング後の状態が、パワハラ傾向の言動がなくなる(または大きく改善される)」となれば、コーチングによる一定の成果として認められやすいからです。
つまり、「マイナスの状態」から「ゼロの状態」「プラスの状態」に転換できれば成果となります。
一方で二つ目のタイプ「悪癖は持っておらず、さらによりよく成長したいと考えるデキる人」が対象となる場合は、一見コーチングによる成果が見えにくくなりがちです。
それはこのタイプの場合、往々にしてテーマとなるのが「経営者・経営幹部としての視座を高め、視野を広げたい」とか「優れたリーダーとしての引き出しを増やしたい」とか、短時間では実現しにくく、かつ、数値化しづらい定性的な成果がコーチングに期待されがちだからです。
しかしながら、例えばエグゼクティブコーチングを受けたある優秀な経営幹部が、「自分の言葉で、社員に対して分かりやすく経営ストーリーを語れるようになった」場合、社員一人ひとりに与える影響(インパクト)は計り知れず、絶大です。
経営幹部自らが紡ぎ出した熱のこもった言葉によって、わかりやすいストーリーが説得力を持って語られる――そうすることで、社員のモチベーションが上がり、生産性向上につながるからです。
次回は、コーチングが刺さる「悪癖を持ったデキる人」「悪癖は持っておらず、さらによりよく成長したいと考えるデキる人」がそれぞれ実際にどのようなテーマでコーチングを受け、どのような壁にぶつかり、解決につなげていくのか、具体的にお伝えしたいと思います。