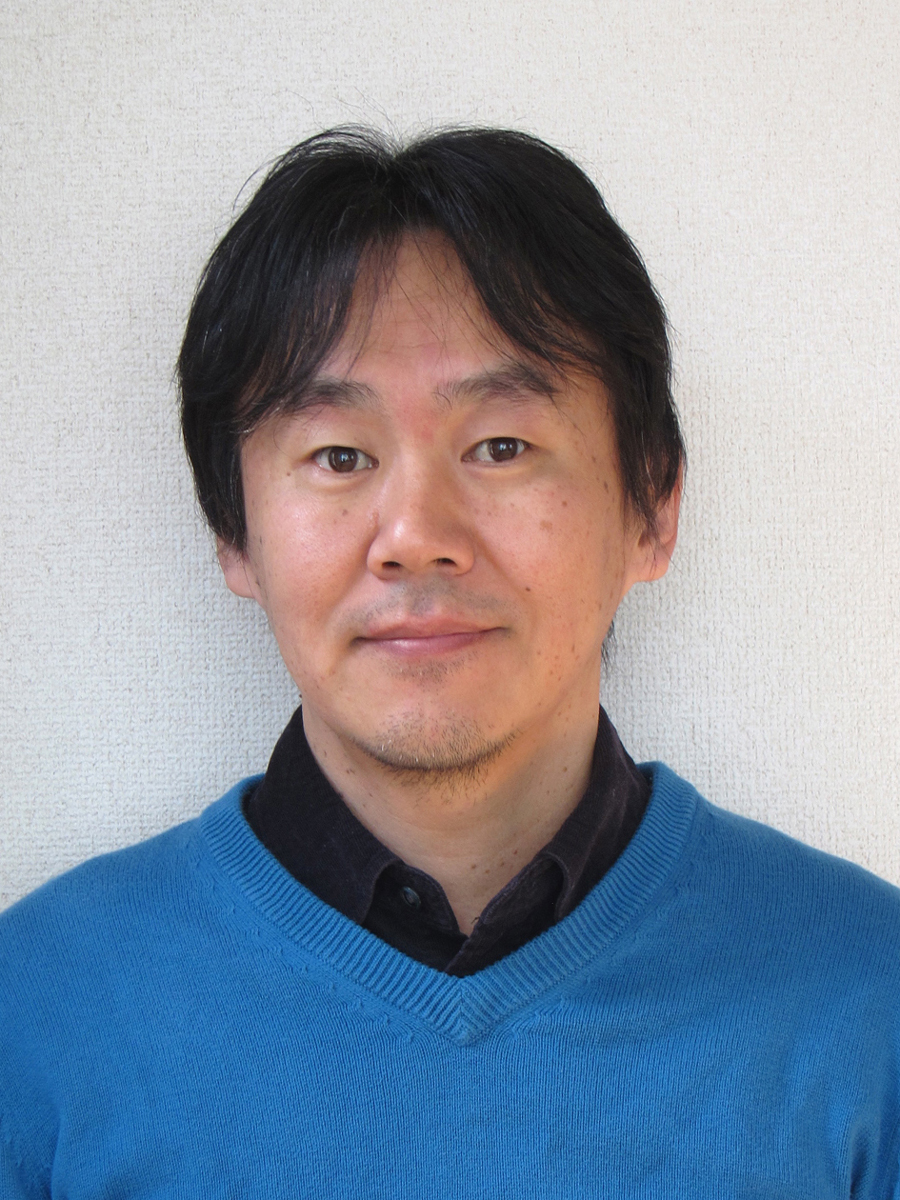プレミアムコンパクトの代表格として根強い人気を保ち続けている「ミニ」(MINI)。ラインアップの中には「ミニ」とは言えないようなボディサイズの車種もあるが、それでも多くの人がミニとして認めているのはどうしてだろうか。現行3ドアのデザインを見ながら考えた。
なぜ「ミニクーパー」と呼ばれるのか
地球環境に優しく、それでいて付加価値の高いクルマとして注目されているのが「プレミアムコンパクト」というカテゴリーだ。さまざまなブランドから多彩な提案がなされているが、輸入車でこのカテゴリーの代表格と言えば「ミニ」ではないだろうか。
現在は「クラシックミニ」と呼ばれるオリジナルモデルは、スエズ動乱がきっかけで石油価格が急騰し、経済的な小型車が求められたことを受けて1959年に生まれた。
それまではノーズに縦置きして後輪を駆動していた直列4気筒エンジンを横向きに積んで前輪駆動とし、キャビンとトランクを一体化した2ボックススタイルを採用。その後のコンパクトカーの基本形を生み出したことは多くの人が知っているとおりだ。
しかもミニは、小型軽量であるうえにエンジンに余裕があり、タイヤを四隅に配していたので走りも良かった。そこに目をつけたのが、当時最強のF1コンストラクターだったジョン・クーパーだ。彼はメーカーに掛け合って高性能版を生み出した。これが「ミニクーパー」で、レースやラリーで輝かしい成績をマークすることになった。
一方で、コンパクトでありながら広いキャビンを備えていたうえに、愛らしい見た目のおかげもあって、2000年まで40年以上作り続けられるロングセラーにもなった。
人気が確立したミニを傘下に収めたのがドイツのBMWだ。1994年に製造元のローバーを買収すると、2001年にはBMW製ミニの新型を送り出した。日本には買収翌年の1995年3月2日(ミニの日)に上陸している。
BMWプロデュースのミニは、時代に合わせてボディサイズを拡大していった。低い位置にあった金属製バンパーは、ボディと一体化した樹脂製に置き換えた。ボディタイプはコンパクトカーでは一般的になっていたハッチバックになった。
それ以外に、デザイン面で2つの変化があった。ひとつは垂直だったフロントマスクに丸みをつけ、ヘッドランプのレンズ面を斜めにしたこと。もうひとつはボディとルーフをつなぐピラーをブラックアウトして、窓まわりが連続しているように見せたことだ。
ハッチバック系とSUV系の差別化が目立つ
フロントマスクの一新は、ミニらしさをキープしたままモダンに見せ、ピラーのブラックアウト化はルーフの塗り分けをアピールすることに成功している。どちらも絶妙な演出だと今でも思う。
ボディバリエーションが増えたことも特徴だ。クラシックミニにあったのはワゴンやバン、ピックアップなど、荷物を運ぶためのバリエーションだったが、BMWのもとではコンバーチブルやSUVといった遊び心をアピールするスタイルが登場。ハッチバックには実用性を高めた「5ドア」が追加された。
このうち「クロスオーバー」と名付けられたSUVは、ハッチバックやコンバーチブルよりひとまわり大柄で、BMWのコンパクトな車種とプラットフォームを共有した。「1シリーズ」が後輪駆動から前輪駆動に切り替わり、「2シリーズ・アクティブツアラー」を用意できたのもまた、ミニのおかげと言うことができる。
そのミニも、当初から設定のある「3ドア」は昨年、4代目に進化。続いて「5ドア」「コンバーチブル」も新型に切り替わっている。3つのボディとも、これまではスポーティーモデルのグレード名だった「クーパー」が全車に使われるようになったことも特徴だ。
前で書いたように、クーパーとはもともと高性能版につけられた名前だが、今はミニ全体のことを「ミニクーパー」と呼ぶ人が多い。伝統にこだわらず、そんなトレンドに柔軟に対応する姿勢もまた、根強い人気の秘訣ではないだろうか。
ちなみにSUVは3ドアよりも前にモデルチェンジしており、同時に名前をクロスオーバーから海外と同じ「カントリーマン」に変えた。
電気自動車(EV)専用の「エースマン」が登場したこともニュースになる。クーパー5ドアに近いサイズのSUVで、先代まで存在したクラブマンに近い車格だ。ミニのEVはこれ以外にクーパー3ドアとカントリーマンにも設定される。
今回はクーパー3ドアに、日本自動車輸入組合(JAIA)主催の試乗会で乗ることができた。
エクステリアはグリルの中央にボディ同色のバーが入ったことが目立つ。先代のマイナーチェンジで採用したデザインを引き継いだもので、個人的には違和感があるが、ダークなボディカラーを選べば気にならないかもしれない。
ヘッドランプはクーパーでは丸型のままだが、カントリーマンとエースマンは角形だ。前者で伝統を受け継ぎつつ、後者はSUVらしい力強さを表現するという住み分けだと理解した。
伝統と先進を融合したメーターに感心
サイドパネルはプレスラインがなく、シンプルに徹している。このあたりもクラシックミニから変わらない部分だ。
興味深いのは、クーパー3ドアは試乗したエンジン車とEVでディテールが違うこと。EVではドアハンドルがグリップタイプからフラップタイプになり、フェンダーアーチが省かれる。ここも伝統と革新の住み分けを上手に実現していると感じた。
リアは縦長のコンビランプに中央のナンバープレートというクラシックミニからの配置を受け継ぎながら、コンビランプが三角形になり、ナンバープレートホルダーが左右いっぱいにまで伸びた。
SUVの2ボディは、ナンバープレートがバンパーに移動したことに気づく。クロスオーバーが登場した頃はこの位置にあったので、戻ったとも言える。ヘッドランプもそうだが、クーパー系とSUV系で、それぞれの個性を明確にしてきているようだ。
インテリアはエクステリア以上に見どころだ。先代では、クラシックミニ由来の大きなセンターメーターをマルチファンクションディスプレイとして活用し、速度計などは運転席の前に置いていたが、現行型はついにセンターにすべてを収めた。テスラのような眺めだ。
その下にはスターター、シフトセレクター、ドライブモード切り替えのスイッチを伝統のトグルタイプでコンパクトに並べた。おかげでシート間は収納スペースとしてフルに活用できるようになった。
センターメーターは全面がタッチ式有機ELディスプレイで、スイッチ操作で多彩な表示を可能としているうえに、インパネやドアトリムの仕立てもクラシカルな要素が消え、素材や色使いを含めてカジュアルになった。
クラシックミニの初期型と同じセンターメーターのみとしつつ、電動化や電脳化の流れにもしっかり対応し、時流にも合わせた技に感心した。
そしてもうひとつ、販売台数があまり見込めない3ドアを残していることにも注目したい。これこそがデザインと走りにおけるミニのアイコンであり、3ドアがあるからこそカントリーマンやエースマンを「ミニである」と説得できると考えているのだろう。
ポルシェも「911」をずっと作り続けているから、「カイエン」や「タイカン」をポルシェとして認めてもらえる。欧州の人たちはやっぱり、ブランドのなんたるかをよくわかっていると感じた。