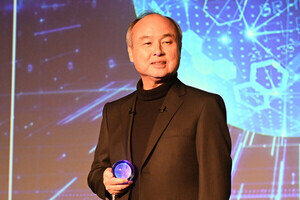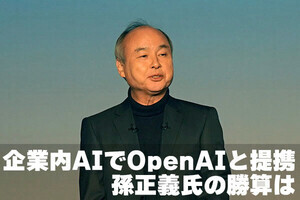米Perplexityは2月14日(現地時間)、「Perplexity Deep Research Agent」を発表し、Deep Researchモードの提供を開始した。同モードでは、AIが自律的にリサーチを行い、総合的なレポートを生成する。従来の一般向けAIチャットボットとは異なり、金融、マーケティング、製品調査といった専門的な用途に対応し、高度なタスクの遂行を想定している。同日よりWeb版で利用可能になり、無料版では1日に5回、サブスクリプションのPerplexity Proでは最大500回までリサーチを実行できる。モバイルアプリ(iOS、Android)、Mac用アプリにも近日中に展開される予定である。
Web版で利用するには、検索ボックスのモードセレクタから「Deep Research」を選択する。Deep Researchは検索機能とコーディング機能を備えており、ユーザーが入力したクエリに対して、多数の情報ソースを調査し、検索と推論を繰り返しながらリサーチ内容を洗練させていく。「人間の専門家が何時間もかけて行う作業を2〜4分で完了できる」としている。生成されたレポートは、PDFやMarkdown形式で書き出すことが可能であり、Perplexity Pageに変換して共有することもできる。
同様のリサーチ機能はGoogleやOpenAIも提供しているが、いずれも有料のサブスクリプションサービスに組み込まれている。一方、Perplexity Deep Researchは1日の利用回数に制限があるものの、無料ユーザーでも利用可能である。さらに、3つのサービスの中でレポート生成に要する時間が最も短い。
Perplexityによると、Perplexity Deep Researchは、AIの性能を評価する「Humanity’s Last Exam」(幅広い学問分野にわたる専門的な質問を含むベンチマークテスト)において21.1%の精度スコアを達成した。これはGemini Thinking、Grok-2、OpenAIのGPT-4oなどを大きく上回る。OpenAIのDeep Researchは26.6%とPerplexityよりも高いスコアを記録しているが、現在この機能を利用するには月額200ドルのChatGPT Proへの加入が必要である。
総合すると、現時点でレスポンスが速く無料でも利用できるPerplexityはアクセシビリティに優れ、Googleは既存の生産性エコシステムとの統合に強みを持ち、OpenAIは分析の深度において優位性を持つ。