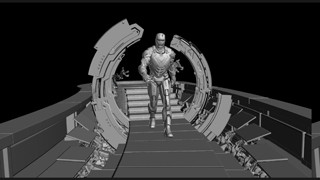立体映画の100年に及ぶ歴史をまとめ、仕組み、歴史、作品を完全解説した書籍「3D世紀/驚異!立体映画の100年と映像新世紀」(ボーンデジタル刊)の著者であり、日本及びアジア圏初の3D映画などを手掛けたアスミック・エースのプロデューサーである谷島正之氏と、第25回東京国際映画祭コンペティション部門に於いて、3D映画として初めて受賞(「観客賞」)を受けた最新作『フラッシュバックメモリーズ 3D』が現在公開中の映画監督 松江哲明氏をゲストに迎え、和やかなムード中で盛り上がりを見せる"3D映画"対談。前編に続き、後編では、「3D映画の製作現場や視聴環境」などの話題を中心に話を聞いた。
――日本国内での3D映画の現場事情についてもう少しお聞かせください。
谷島氏:海外と比較して日本国内で3D映画の普及が進まないことについては、制作環境や予算はもちろん、興行界、クリエイターの特性など様々な要因があると思います。ハリウッドに代表されるアメリカ映画では、今や全体の約4分の1の作品が3D映画となってきました。今後、アッという間に半分程度まで普及していくでしょう。そういった意味では、海外からの3D映画コンテンツの流入量は必然的に増してきますので、国内の映画にも少なからず、その影響は出てきます。日本では、2011年秋から冬にかけて、若手クリエイターたちが、それぞれの方法論での3D映画を立て続けに発表しました。今後、クリエイター、特に新鋭監督と映像産業がより呼応し、3D対応作品が増えていき、欧米から遅れること数年といったスパンで3D製作映画が普及していくでしょう。日本の映画界では、最新テクノロジーの採用が極端に早いモノと遅いモノがあるのですが、3D映画は、産業とクリエイティブ(もしくはセンス)の両方が伴わなければならない。片方では駄目。そういう意味で、普及が特に遅い部類のテクノロジーといえます。
松江氏:映画制作自体が、ハリウッド映画とそれ以外(邦画を含む)といった区分けができるほど、予算や興行の規模などに違いが生じているのは、皆さんもご存知の通りです。少し前に、京橋にあるフィルムセンターで、改めて『ターミネーター2』を見る機会があったのですが、20年近く前の映画なのにめちゃくちゃ面白い!!これは、特に3D映画に限ったことではないのですが、娯楽系の大作映画では、『ターミネーター2』を超えるような日本映画は残念ながらいまだに登場していないと思うんです。それは、ハリウッドのスタイルを踏襲して同じような映画を作る限り超えることのできない壁だとも感じています。そう考えると、3D映画についてもハリウッド的な手法で制作された国内3D映画が爆発的なヒットを生むというのはかなり難しい状況にあるはずです。
ちなみに、ハリウッドに真っ向から対抗できるとすれば、それは映画としての様式美やシステムがまったく異なるボリウッド(インド)ではないかと、個人的には思うですよ。また、あえて日本の作品で勝負するのであれば宮崎駿監督のアニメーション作品を、そのまま3D映画として出すしかないでしょうね。
――最近の3D映画に関する制作や視聴の環境についてはいかがでしょうか?
松江氏:実際に、自分で3D映画『フラッシュバックメモリーズ 3D』を撮ってみて感じたことですが、撮影時のハードルはかなり下がってきています。3D撮影に必要な二眼式のカメラも非常にコンパクトになり、導入コストも下がってきています。逆にまだまだ苦労が多いのは、編集環境の部分です。3Dで撮影するとフルHDの素材をふたつ同時に扱うことになるので、どうしても編集機としてPCを用いると苦しい部分がでてきてしまうんです。おかげで、この作品でも、3D担当スタッフにはかなり泣いてもらった部分もありました。また、デジタルでの撮影や編集は、3D映画と非常に相性が良いです。フィルムは傷つきやすいため、特に左右どちらかの映像が少しでも途切れてしまえば破綻してしまう3D撮影には不向きなんです。実際にデジタルで3D映画を撮影してみて、「こんなに3Dとデジタル技術ってリンクするんだ!」といった場面を非常に多く体験することになりました。
谷島氏:かつてのフィルム時代に3D映画を撮ろうと思うと、通常の2D映画の約3倍の予算がかかっていたんですよ。しかし、私が2009年に手がけた『戦慄迷宮3D』では、通常の約1.3倍程度の予算で制作を行いましたし、現在ではさらにコスト面での製作者への負担は確実に少なくなってきていますね。
一方、視聴者側の環境としては、3Dテレビなども一般向けに発売され、3D映画を手軽に家庭で見ることも不可能ではない環境が整いつつあります。十分な3Dコンテンツがラインナップされていない現状では、残念ながらメーカー側が思うように普及が進んでいない状況ではありますが。しかし、対談の冒頭で松江監督もおっしゃっていましたが、映画館で見る3D映画と家庭のテレビで見る3D映画は、別のものであり、同じ映画でも楽しみ方が自ずと違ってくるはずです。
松江氏:また、そのようなコンテンツが出揃っていない現状ならではの3D映画の製作者側のメリットとして、コンペティターの少なさも挙げられると思います。3D映画に対応する劇場はあっても公開する作品が少ない状態なんです。だからこそ、本来ミニシアター系での上映となるであろう僕の作品が、新宿バルト9などのシネマコンプレックスでも公開できる(笑)。このように、自分の作品をより多くの人に大してアピールを行えるのも、クリエイターにとっては大きなチャンスといえるのではないでしょうか。 ちなみに、僕にとっては、そもそも映画製作のワークフローがデジタル化されたこと自体のメリットの方がとても大きいわけです。映像の高画質・高音質化などはもちろんのこと、何よりも撮影や編集の簡易性や利便性の向上といった多大なる恩恵を享受できる。僕のようなクリエイターが、今の手法で映画を作ることができるのはデジタル技術のおかげですからね。
――今後の3D映画や映画制作に対して、おふたりが期待することをお聞かせください。
松江氏:ハリウッドと同じスタイルで3D映画を作るのでなく、低予算でもいいから日本独自のアイディアやオリジナリティを盛り込んだ3D映画が多く登場してきてほしいですよね。画一的なものばかりでなく、フィルム映画と同様に、大小様々なバリエーションに富んだ3D映画が個人的にもぜひ見てみたいです。面白い作品だけでなく、つまらない作品をもっともっと楽しんでみたいというか、映画の持っている幅のようなものはなくらないで欲しいなと思います。フィルム、デジタル、2D、3Dといった枠に囚われることなく、クリエイターが自由な発想で、ある種わがままに作品を生み出せる環境が大切ですよね。
谷島氏:まずは、クリエイターの方々に3D映画や3D技術の面白さを感じていただき、結果として多種多様な3Dコンテンツが登場することを何よりも期待したいです。ファンタジー・ホラー映画『ラビット・ホラー3D』(清水崇監督)、子供向けの『映画 怪物くん 3D』(中村義洋監督)、時代劇初の3D映画『一命』(三池崇史監督)、昭和へよりタイムスリップする為に3Dを活用した『Always 三丁目の夕日‘64』(山崎貴監督)など、徐々にですが邦画にも良質な3Dコンテンツは増えてきています。しかしながら、ハリウッド映画のバリエーションには、まだまだ到底追いつけていませんからね。なお、技術的なことでいえば、裸眼での3D映画鑑賞の実現が、今後のさらなる重要なターニングポイントとなるのではないでしょうか。
最近では、とかく3D映画のデメリットなどが脚光を浴びがちですが、これも"サイレントからトーキーへ" 、" モノクロからカラーへ" 、"ビスタから大型スクリーン(シネスコ)へ"などの例を出すまでもなく、新しい技術や規格が導入される際の過渡期には、常に批判が絶えなかったように、賛否両論入り混じった論争が付きものですからね。細かいことはさておき、デジタル技術の恩恵により、フィルム時代の質の悪い3Dから脱却し、映像美の獲得と共に、映像産業全体へも波及し、久方振りの「第三の映像革命」としてデジタル3Dは、映像史を変えました。クリエイターの皆さんには、3D映画の色々なメリット/デメリットを引っ括めて、ぜひ楽しみながら、乱暴でも良いから新しい映像空間に想いを馳せ、作品を撮っていただければなと考えています。CGの歴史がそうだったように、若いクリエイターの未知なるセンスが、3Dの可能性をより押し拡げると信じているので。