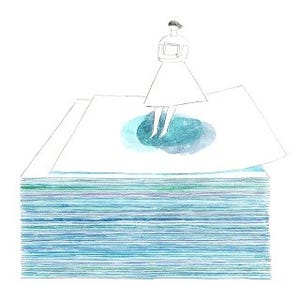男が途切れたことがない。あまり品のない言い方をすれば、時子はそういう女だった。
別にそうしようと思ってそうしているわけではなかった。時子のことを、誰かを狙っては落とし、飽きたら別の男に乗り換えるあくどい女のように言う女もいなくはなかったが、時子としては、そんなつもりはまったくなかった。
ただ、誰かを好きになってしまうのだ。魅力的な男に興味を持ち、深く知りたいと思って接近してゆく過程で、好意を持つようになる。そして不思議なことに、相手も同じように、時子に好意を持つようになるのだった。
相手を知りたい、と思うと時子は当然のように相手の好きなことにも興味を持った。映画が好きな相手なら、いつの時代のどんな監督が好きかを知り、すぐに観たし、テニスが趣味だと言われたら、ユニフォームを揃えてやってみたりもした。そうして相手がどういう精神性を持っているのか知ってゆくと、自然にどういう服を着たどういう女が好きなのかも想像でき、時子は相手の好む服を自然に選び取り、部屋も相手が好むように模様替えをしたりする。
そういう「好かれるために当然のこと」をしない他の女たちが、時子に嫉妬したり、陰口を叩いたりすることが、時子には理解できなかった。こんなに簡単なことを、なぜみんなしないのだろうか。それすらしないで、相手が勝手に自分のことを好きになってくれるとでも思っているんだろうか、と、冷めた気持ちで見ていた。
それは、時子が29歳の誕生日に突然起こった。時子はそのときにつきあっていた男と、やたら洗練された雰囲気の店にいた。いつもは気軽に飲める店に行くことが多いのに、誕生日だからいい店を探してくれたのかな、と時子は思っていた。味も品が良く、時子は新しい場所を冒険するような気持ちで、料理を楽しんでいた。
デザートのろうそくを吹き消したときだった。時子は、そういういかにもイベントらしい演出があまり好きではなかったのだが、喜んであげないと、と少しぎこちない笑顔を浮かべていた。しかし、向かい合って座っている男は、もっとぎこちない顔をしていた。
「時子、俺と結婚してほしい」
その瞬間、時子は周りの音が遠のいていくような気がした。反射的に、嫌だ、と思った。その男とつきあうのが楽しくないわけじゃない。ただ、時子には、つきあっていて先が見えてしまう相手だった。今は楽しいけれど、そのうち興味を失ってしまう相手。尊敬できるし、面白い人だと思うけれど、一緒に暮らしたり、人生をともにしたいとは思えない相手。そもそも、相手が時子を「気の合う理想的な女性」だと思っているとしても、それは自分が相手に「合わせている」からだ、という思いが強くあった。
時子は曖昧に微笑み、いかにも涙をこらえているような演技をして、パウダールームに駆け込んだ。こんなときでも、そんな器用なことができる自分が嫌いだと初めて思った。嫌だ、とはっきり口にできない自分は、何をしているんだろう。
恋愛をしている、はずだった。けれど、どの相手ともずっと一緒にいることは考えられなかった。つきあい始めるまでは面白い。なのにつきあい始めると、この先どのように馴れ合い、どのように自分の気持ちが終わっていくのか、想像できてしまう。そんなことを繰り返して、いったい何になるのだろう。時子は初めて、自分のしていることがわからなくなった。
家に帰ると、時子は着けていた腕時計とピアス、ネックレスを外した。国産のピンクゴールドの時計。華奢な金色のネックレス。小さな花が揺れる形の、同じ金色のピアス。こういう控えめな感じが、相手の好みなのだと知っていた。
じゃあ、私は? 私はこういうのが好きなんだろうか? と考えてみると、時子は全然、それらの何ひとつ、好きではなかった。
クローゼットを開けてみる。好きな服を探そうとしたが、見つからない。今の相手に気に入られるために買った服、その前の相手に気に入られるために買った服。どれも嫌いなものではなかったし、自分に似合うものを選んでいたけれど、好きか、と考えると、自信を持って好きだと言えるものはなかった。
時子は、自分の部屋が急に大きな空洞のように感じた。大きな空洞の中に、自分だけが取り残されている。この部屋の中に、私だけのためのものが何かあるんだろうか、と思うと、怖くなった。
食器棚にも、下着の入った引き出しにも、ドレッサーにもそういうものは何ひとつなかった。最後に、画鋲やドライバーなど、つまらない実用品だけを入れている引き出しを開くと、赤い缶が目に飛び込んできた。
もともとはお菓子が入っていた、赤い缶。時子はそれを、中学生の頃に裁縫道具入れにした。それ以来ずっと、それを使っていた。誰に見せるものでもなかったし、他のもっと洒落た容れ物に変えたいとも思わなかった。針仕事を頻繁にするわけではなかったが、たまにボタンをつけたり、ほんの少しのほつれを繕ったりするとき、時子はその缶を開けた。
それは、つまらないものだったけれど、まぎれもない自分だけのためのものだった。時子はやっと、すがりつけるものを見つけた、と思った。そして、自分のことが初めて、少しだけわかったような気がしたのだった。
<著者プロフィール>
雨宮まみ
ライター。いわゆる男性向けエロ本の編集を経て、フリーのライターに。著書に「ちょっと普通じゃない曲がりくねった女道」を書いた自伝エッセイ『女子をこじらせて』、対談集『だって、女子だもん!!』(ともにポット出版)がある。恋愛や女であることと素直に向き合えない「女子の自意識」をテーマに『音楽と人』『SPRiNG』『宝島』などで連載中。マイナビニュースでの連載を書籍化した『ずっと独身でいるつもり?』(KKベストセラーズ)を昨年上梓。最新刊は『女の子よ銃を取れ』(平凡社)。
イラスト: 安福望