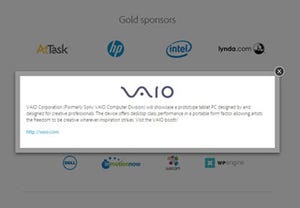VAIO株式会社は、7月1日に新会社としてスタートして以降、取引先との契約を結びなおしている。
これらの契約のなかでも、VAIOのビジネスに大きな影響を及ぼすのが、CPUの調達先となるインテル、OSの調達先となるマイクロソフトとの取引契約だ。
というのも、CPUやOSの調達価格は、調達するボリュームによって大きく変動する。ソニー時代には、ピークとなった2010年度には870万台を出荷。2013年度でも560万台の出荷実績を誇っていたソニーのPC事業だが、VAIO株式会社となってからの規模は大きく減少。2015年度目標で35万台としている。会社がスタートしたばかりの2014年度はさらにこの数字を下回る可能性がある。
| VAIOシリーズの年間出荷台数(単位は万台) | |||
| ■99年度 | 140 | ■07年度 | 520 |
|---|---|---|---|
| ■00年度 | 250 | ■08年度 | 580 |
| ■01年度 | 350 | ■09年度 | 680 |
| ■02年度 | 310 | ■10年度 | 870 |
| ■03年度 | 320 | ■11年度 | 840 |
| ■04年度 | 330 | ■12年度 | 760 |
| ■05年度 | 370 | ■13年度 | 580 |
| ■06年度 | 400 | ||
しかも、事業範囲を国内に限定する形でスタート。それは、これまでのグローバルPCカンパニーの位置づけからも大きく異なる。こうした事業規模の大幅な縮小は、当然のことながら調達価格にも影響するのは明らかだ。
ある業界関係者は、「インテルとマイクロソフトの調達価格が跳ね上がることで、同じ製品を開発したとしても、最終価格で1~2万円上昇することになるだろう」と試算する。
これは、VAIOのモノづくりにどの程度、影響するのだろうか。
VAIOの赤羽良介副社長はそれについて、「VAIOは、パートナー各社と一緒になって新たな技術を開発し、それによって、革新的なPCを出してきた実績がある。この点は、インテルにも、マイクロソフトにも評価してもらっている。関係はこれまでとは変わらない」と語りながらも、「調達コストはボリューム依存のところがあるため、確かに課題だといえる」と続ける。具体的な影響額については明言しないが、コスト上昇の要因となっているのだろう。
その対策として赤羽副社長は、ひとつの姿勢を示す。
「仕事に活用してもらうお客様に対して、深く突き刺さる商品を開発する必要がある。そのために必要な機能や性能にはコストをかけ、一方で不要なところには標準部品を使用していくといったようにメリハリをつける」。
そして、標準部品に関しても、「ODMを活用することで、ODMの調達力を生かした調達コストのコントロールを行いたい」とする。
VAIOが目指しているPCは、付加価値型製品。その付加価値がコスト上昇を吸収するといったことも視野に入れているだろう。
「全体のコスト上昇を抑えていく取り組みは当然行うが、お金をかけたところを、付加価値としてしっかりと感じていただけるものを作らなくてはならない。コスト以上の付加価値を提案できれば、認めていただけると考えている」と赤羽副社長は語る。
だが、VAIO株式会社と、インテル、マイクロソフトとの関係が、ソニー時代と異なるのは調達面だけではない。
グローバルPCカンパニーであったソニー時代には、インテル、マイクロソフトともに、グローバルを担当するチームで対応していたが、日本国内だけでビジネスを行うVAIO株式会社の場合、ローカルを担当するチームで対応することになり、共同販促活動についても、その範囲で推進されることになる。
たとえば、2013年11月、日本マイクロソフトは、WDLC(ウィンドウズ デジタル ライフ コンソーシアム)と共同でWindows XPからの乗り換え促進キャンペーン「最新パソコン、買うなら今でしょ!」を展開した。
その際、キャンペーンのパンフレットに記載したPCは、NEC、富士通、東芝、ソニーの4社の製品だけだった。NECもグローバルで展開するレノボグループということを考えれば、いずれも世界展開をしているPCメーカーであることが共通点だ。つまり、一定数量の取引をベースにして、選択されたメーカーだということもできる。
しかし、現在のVAIOのポジションを考えると、2013年同様、ほかの3社と横並びで取り扱われることが難しいかもしれない。こうした共同販促では、今後、「その他メーカー」に分類される可能性もある。規模が重視されるPC産業において、これはある種仕方のないことだろう。
だが、そうしたなか、ソニーの平井一夫社長は、VAIOの認知度向上に向けて、「少しでも支援を行いたい」という姿勢をみせる。
平井社長は、「ソニーグループには約14万人の社員がいるが、用途に適したモデルがあるということを前提に、会社のPCは、なるべくVAIOを持ってもらいたいと考えている」と語る。
そして、こんなことにも言及する。「ソニーピクチャーズの映画のなかで、PCが使う場面があれば、まずはVAIOを使ってもらうという提案をするなど、マーケティング上のコラボレーションも考えたい」。
海外で販売されていないVAIOを、海外の映画で使用するということには違和感があるが、こうした細かい部分の支援についても平井社長は考えているようだ。
VAIOの商標は依然としてソニーが持っているが、VAIO株式会社の社名は、平井社長が許諾したことで実現したもの。平井社長も「製品ブランドだけでなく、社名にまで、VAIOの名前を使っていいといったのは私」と語る。
「社名に使っているブランドだけに、VAIO株式会社には、柔軟に運用してもらいたいと考えている。よほどのバッティングがない限りは、VAIO株式会社の商品群のなかで、VAIOのブランドをつけることをサポートしたい。VAIOは昔の仲間。オペレーション、マーケティング上ではサポートしたい」と平井社長。
ソニーが強力な援軍になることを期待したい。