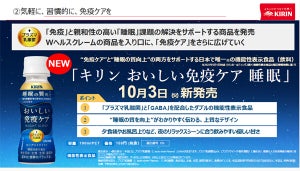キリンホールディングスと小岩井乳業は、埼玉県狭山市にあるプラズマ乳酸菌の菌体製造工場と小岩井乳業東京工場のメディア向け見学会を12月4日に実施。菌体製造ラインへメディアを一斉に案内するのは初の試みとのことで、おいしさと健康価値を両立した製品づくりについて説明された。
■プラズマ乳酸菌で「免疫ケア」を訴求
今回の実施された見学イベントはプレゼンテーションパートと見学パートの2部構成。第1部のプレゼンパートでは、キリンホールディングスの鈴木侑磨氏より同社がヘルスサイエンス領域に取り組む理由について紹介した。
「キリンは『キリングループ・ビジョン2027』で、ヘルスサイエンス領域を主力事業として注力していくことを掲げています。その中で免疫は健康の土台と位置付けていますが、健康課題の自覚の有無を調べると、アレルギーやダイエットなどと比べて一般の方々の意識はまだまだ低いのが現状です」
続けて、免疫のメカニズムとプラズマ乳酸菌のはたらきについて説明した。
「免疫には会社組織のように上下関係があり、司令塔となる細胞が存在します。プラズマサイトイド樹状細胞(pDC)という細胞で、プラズマ乳酸菌は世界で初めてpDCを直接活性化ができる乳酸菌です。これまでの一般的な乳酸菌は一部の免疫細胞のみを活性化するだけでした。それに対して弊社が2012年に論文として報告したプラズマ乳酸菌は、pDCの司令塔を直接活性化するため、免疫細胞全体の活性化を促すことができます」
同社では免疫ケアの必要性についての啓発や、習慣的な免疫ケアの浸透を推進。行政との取り組みなども含めて、幅広い接点で発信を行なっている。
「プラズマ乳酸菌との接点を増やし、気軽に習慣的な免疫ケアを行ってもらうため、多くのパートナー企業さんと現在57商品を展開しています。10月末時点でのプラズマ乳酸菌関連商品の売上は、対前年比4割増という状況です。また、国外でのプラズマ乳酸菌のビジネス展開も加速しているところで、プラズマ乳酸菌の菌体の製造能力は2022年比で約2倍に増強しています」
小岩井乳業の東京工場長・佐藤武氏は、同社の経営理念や歴史について説明した。岩手山の麓にある岩手県雫石町で1891年に創業した小岩井農場は、約3000ヘクタールの広さを誇る日本最大級の民間総合農場だ。
「小岩井という名前のルーツは、地名と思っている方がけっこういるんですが、共同創始者である3名の頭文字をとって命名されています。1976年には小岩井農牧の乳業部門を分社化。キリンビールさんと小岩井農牧さんの折半出資で小岩井乳業株式会社が設立されました」
東京工場が操業したのは1966年。現在は発酵乳と乾燥乳酸菌粉末を製造している。
「『小岩井 生乳100%ヨーグルト』など、当社のヨーグルト作りには「前発酵製法」を採用しています。原材料となる生乳と乳酸菌を大きなタンクに入れ、乳酸菌を増やすのに最適な温度を保ち、じっくり半日以上発酵させる方法です。じっくりと乳酸発酵させることで発酵臭や酸味が抑えられた、なめらかなヨーグルトになります。また、タンクの中で発酵させた後は撹拌し、フィルターを通して容器に充填することで、さらになめらかな食感を実現しています」
■安全・安心と、おいしさにもこだわった製造工場
小岩井乳業東京工場には事務所棟と2棟の製造棟から成り、今回はプラズマ乳酸菌の菌体製造ラインと、ヨーグルトの製造ラインをそれぞれ見学した。
発酵乳の製造棟は4階と2階に当たる部分で製造ラインが稼働している。こちらの製造棟には見学コースが設けられており、5階と3階からそれぞれのフロアをガラス越しに見下ろすことができた。ちなみにこちらは一般用の見学コースとして整備されたようだが、コロナ禍の影響などもあって現状では広く一般公開をできずにいるという。
この東京工場では週6日、一日40〜60トンの生乳を受け入れており、東京工場へ届けられた原乳はタンクに送られる前に品質や状態をチェックされる。小岩井の生乳100%ヨーグルトなどの原材料になる原乳の約半分は岩手県産とのことだ。
この検査に合格した原乳はパイプで4階のタンクへと送られて均質化・殺菌が行われる。均質化は乳脂肪という脂肪の粒の大きさがバラバラの原乳を細い管の中に通して乳脂肪の粒の大きさを揃える工程で、加熱による殺菌の処理をした後に乳酸菌を加えて発酵させる。
出来上がったヨーグルトは次に配管を通って2階へと送られる。このフロアは充填と包装の2つの工程が厳重に分けられており、充填エリアに入る場合は外から埃やゴミ、ウイルスを持ち込まないように厳重な衛生管理が行われている。大型容器のための充填機と小型容器のための充填機があり、2台を合わせて年間約4000万個の商品を充填しているそうだ。
充填後の容器は隣のエリアへ運ばれ、金属探知機による検査や規定の分量が入っているかを確認する重量検査を経てダンボールに梱包。冷蔵倉庫から出荷される前にも味・成分・なめらかさなどに関する厳しいサンプリング検査を行っているという。
最後に見学したのはプラズマ乳酸菌の菌体製造ラインがある製造棟。撮影禁止のエリアも多かったが、工程としては大きく「増やす」「集める」「乾かす」「詰める」の4工程があるという。
まず「増やす」工程では、培地と呼ばれる乳酸菌の食べ物が入っているタンクの中で培養され、温度や酸素濃度、phなども常時モニターして管理。乳酸菌を効率的に増やしている。糖やタンパク質、ミネラルなどを含んだ培地は透明な麦茶のような色をしているそうだが、乳酸菌が増えていくと白く濁り、ミルクティーのような色に変わっていくという。
次に乳酸菌を「集める」工程では、遠心分離機で比重の重い乳酸菌を集め、培地など乳酸菌以外の部分を取り除き、洗浄。そうしてできた液体を200℃ほどの熱風の中へスプレーし、一瞬で乾燥させて粉末にしているそうだ。
最後の乳酸菌の粉を袋に詰める包装工程では、すり鉢のような網の目の器具がついたふるいの機械や、鉄製の異物を捕捉するマグネットフィルターを通って袋詰めしていた。各袋の重さを測った後はX線検査機で異物がないかチェックしているという。
こうした生産現場のこだわりを知ると、いつものヨーグルトの味わいもよりおいしく感じられそうだ。