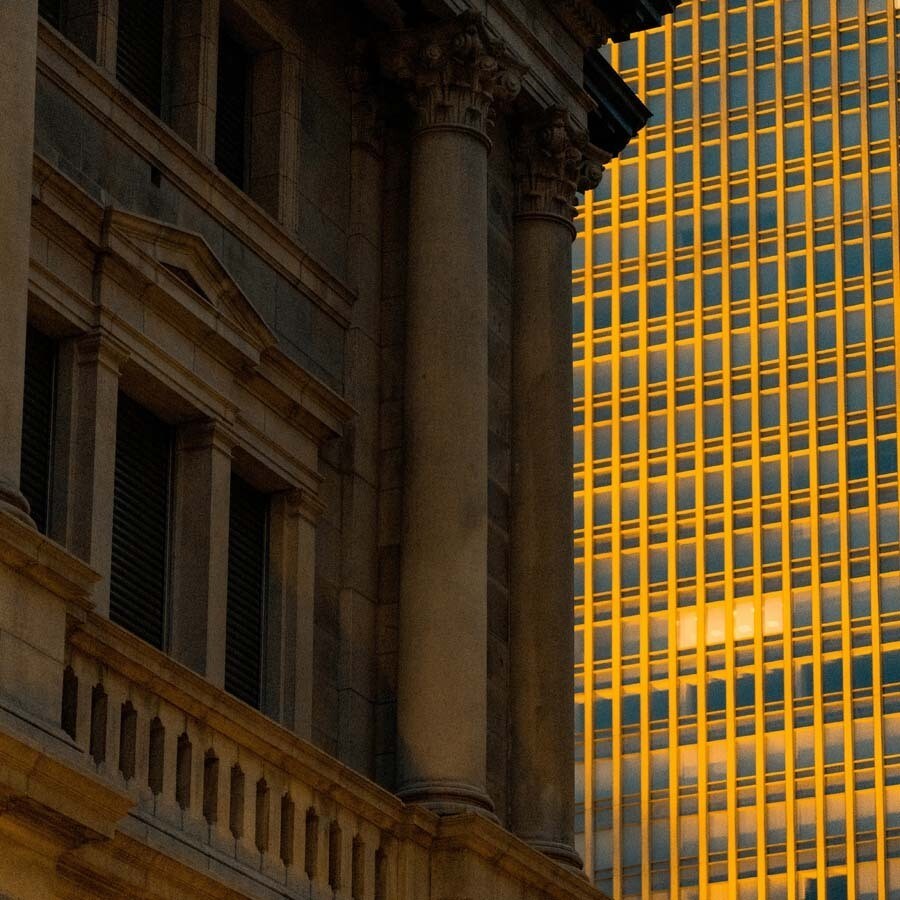日本銀行は2024年3月にマイナス金利を解除し、同年7月と今年1月に追加の利上げを決めています。今後も利上げが継続すれば、住宅ローンの借入金利が上昇し、変動金利で住宅ローンを組んでいた場合は、金利負担が増えることになります。
現在、変動金利で借りている人の中には将来の金利上昇に不安を覚えている人も多いと思います。そこで、変動金利から固定金利に借り換えた方がいいのか、そのまま変動金利で借り続けた方がいいのか、将来の金利上昇を見込んだシミュレーションをしてみました。また、借り換えを判断する基準や注意点なども紹介しているので参考にしてください。
住宅ローンの金利の仕組み
まずは、住宅ローンの金利の仕組みについておさらいしておきましょう。
住宅ローンの金利タイプには、半年に1回金利を見直す「変動金利型」と金利が完済まで変わらない「全期間固定金利型」、あらかじめ決められた固定期間の後は変動金利などを選択できる「固定期間選択型」の3つのタイプがあります。
一般的に変動金利型の住宅ローンは固定金利型の住宅ローンより金利が低い傾向があります。2025年3月現在、主要銀行の変動金利は0.3%~0.5%程度、固定金利(フラット35最頻金利)は1.94%となっています。
そのため、住宅ローンを利用している人の5割が変動金利型、4割が固定期間選択型、残りの1割が全期間固定型を選んでいます(※)。
※住宅金融支援機構「2022年度 住宅ローン借換えの実態調査結果」
このまま低金利が続けば、変動金利のままで問題ありませんが、金利上昇が予測されると、固定金利への切り替えを検討したくなると思います。問題はそのタイミングです。金利が低いうちは変動金利で借り続けて、金利が上昇してきたら固定金利に借り換えればよいと考えがちですが、それでは遅い場合があるのです。
「金利が上昇してから固定金利に借り換え」では遅い
固定金利は、10年国債の利回りに連動する長期金利の影響を受け、変動金利は、日銀が金融政策として定める基準となる短期金利(政策金利)の影響を受けます。そして、金利の上昇には順序があります。
まずは、10年国債の利回りに連動する長期金利が上昇し始め、そのあとで、政策金利が追従する形で上昇するのが一般的です。長期金利は市場の金利動向を先取りして動く傾向があり、政策金利は経済への影響を考慮して慎重に調整する必要があるため長期金利に遅れて変動します。そのため、変動金利が上昇したタイミングでは、すでに固定金利は上がっている可能性が高く、その時点で借り換えをすると、高い金利で契約することになってしまいます。
そうした事態を避けるためには、金利が本格的に上昇する前に動くことが重要となります。しかし、将来の金利動向を知ることができない以上、借り換えのタイミングをはかるのは難しいと言えるでしょう。
金利が上がっても毎月の返済額は急には上がらない
元利均等返済の変動金利型住宅ローンは、年2回の金利の見直しで金利が上昇しても、毎月の返済額は5年間変わらない「5年ルール」があります。また、毎月の返済額が増えたとしても以前の125%までという「125%ルール」があるため、急激な返済額の増加はありません。
そのため、金利の上昇によって、月々の返済が困難になることはそれほどありませんが、返済額を抑えたことで、返済額に占める利息の割合が増え、元本部分の返済が繰り越されることで総返済額は増えてしまいます。返済額に急な変化がないため、仮に借り換えをした方がいい局面であってもタイミングを逃してしまう可能性もあります。
金利上昇時の変動から固定への借り換えシミュレーション
実際に、金額にどのくらいの影響があるのか、変動金利から固定金利に借り換えをした場合としなかった場合の比較をしてみましょう。
<条件>
・ローン残高3000万円
・残りの返済期間30年
・元利均等返済
変動から固定に借り換えをした場合
- 変動金利0.4%から固定金利1.94%に借り換え
- 諸費用90万円
変動金利のまま借り続けた場合
- 5年ごとに0.5%ずつ金利上昇
現時点でのフラット35の最頻金利である1.94%で固定金利に借り換えた場合、総支払額は4,050万円となりました。このうち利息が960万円、諸費用を含めると合計で1,050万円です。
一方、借り換えを行わず、変動金利のままで返済を続け、5年ごとに0.5%ずつ金利が上昇した場合の総支払額は3,566万円、利息は566万円となりました。
今回の試算では、借り換えは行わずに、変動金利のままで返済を続けた方が総支払額は少なくなりました。
ただし、金利の上昇幅が0.5%以上だった場合や、ローン残高が多い、返済期間が長い場合には変動金利の方が総支払額が多くなる可能性があります。
借り換えすべきか判断する際の3つの基準
借り換えをした方がいいのか判断するときに、一般的に、次の3つの基準を満たしていると借り換えのメリットがあるといわれています。
- ローン残高が1,000万円以上
- 残りの返済期間が10年以上
- 金利差が1%以上
前出の試算をみてみると、残りの返済期間が10年の時に、ローン残高は1,000万円以上残っていますが、その時の金利差は0.46%なので基準を満たしていません。25年後には金利差が1%程度になりますが、返済期間とローン残高が少なくなっているので、これも基準を満たさず、借り換えのメリットはないと判断できます。
ただし、住宅ローン選びには、金利以外にもさまざまな要因があるため、総合的に判断する必要があります。次項では、借り換えを検討するときに知っておきたい3つの注意点を解説します。
住宅ローン借り換えの注意点
1.諸費用を考える
借り換えは金利だけでなく、諸費用も含めて考える必要があります。借り換え時には新規契約時と同様に手数料や諸費用がかかります。諸費用の例として、事務手数料、保証料、団体信用生命保険料、印紙税、登記関連費用などがあります。
借入額や返済期間、その他の条件で諸費用は変わってくるので、諸費用が表示される金融機関のローンシミュレーションで目安を知っておくといいでしょう。
2.団信の保障を考える
民間の金融機関の住宅ローンでは、団体信用生命保険(団信)の加入が必須になっているところがほとんどです。借り換えによって、団信の保障を見直すことができます。
最近は、がん保障や3大疾病保障など、保障が充実している団信が増えてきており、団信目的で借り換えを検討する人もいます。保障範囲が広い団信は金利の上乗せが必要になる場合があるので、保障内容と支払い額を吟味して住宅ローンを選びましょう。
3.健康状態など審査が通るか
いざ借り換えが決まっても、健康状態や収入減、クレジットカードの支払い遅延などによって借り換えの審査に通らないこともあります。新規で購入したときよりも月日が経っているので、その間に大きな病気をしたり、健康状態に問題が生じたりすると、団信に加入できないことで借り換えができなくなることがあります。
ほかにも、購入した物件の価値が下がると、担保評価がローン残高よりも下がってしまい、審査が厳しくなります。
このように、借り換えたくても借り換えられないという状況もあることを知っておきましょう。なお、審査の基準は金融機関それぞれなので、1つの金融機関の審査に落ちても、別の金融機関の審査では通る場合があるので、複数の金融機関に審査の申し込みをするといいでしょう。
まとめ
借り換えを検討する際は、金利動向だけでなく、ローン残高や返済期間、諸費用、団信の保障など、総合的にみて判断することが大切です。多くの場合、住宅ローンの返済期間はその人の人生の長い期間を占めます。今後のライフプランや家計状況を踏まえて、無理のない返済プランをご検討ください。