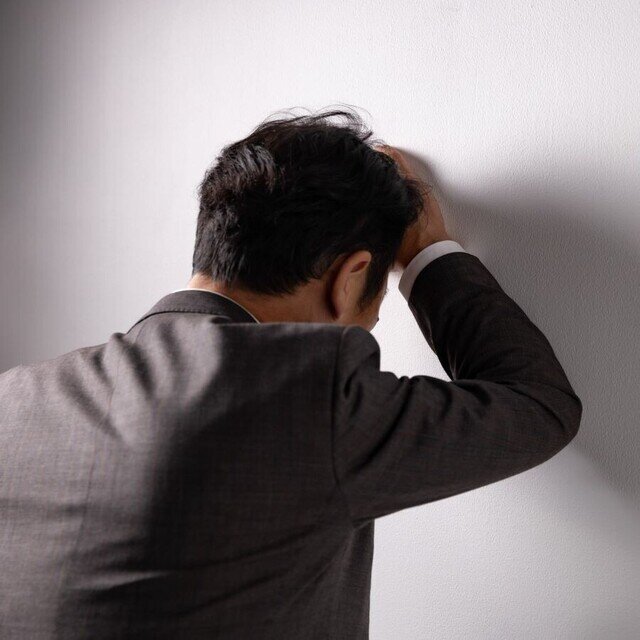日本初のボトラーズ事業から樽のリペアまで、独自の取り組みを加速
こういった潮流のなかで、三郎丸蒸留所もまた新たな取り組みを加速させている。
その代表とも言えるのが、2021年にモルトヤマの下野孔明氏とともに始めた「T&T TOYAMA」だ。日本の蒸留所によって造られた原酒を購入し、自社で調達した特別な樽を用いて熟成しボトリングする、世界初の本格的なジャパニーズウイスキーボトラーズ事業である
また「T&T TOYAMA」では、ジャパニーズウイスキーの魅力を伝えるために各蒸留所のマンガづくりも行っている。第一弾・第二弾は、シノアリスのコミカライズなどを担当したヒミコ氏が漫画を担当。日本語版のみならず英語版も用意されている。マンガというジャパニーズカルチャーの魅力を活用した、日本らしさあふれる事例と言えそうだ。
もともとIT業界で働いていたこともあり、IT導入も積極的に行っている稲垣氏。その一例がウイスキーの原酒が入った樽を管理する「樽クラウド」だ。
「ウイスキー造りに使う樽って、一回使ったら終わりではないんです。前の酒を払い出して次の原酒を入れていくので、履歴が重要です。スコットランドだといまだに紙ベースだったりするところもあります。多くはExcelなどで管理するんですが、番号をひとつ間違うだけで大変なことになる。しかし、樽クラウドなら樽に印刷したQRコードを読み込むだけで、確実な情報にアクセスできます」(稲垣氏)
一方で、クラフトウイスキーの盛り上がりとともに供給不足が深刻化している樽のリペア、リメイクなどを専門とする事業「Re:COOPERAGE (リクーパレッジ)」を2024年末に稼働した。「樽職人は全国でも希少な存在であり、ウイスキーの守り神」と稲垣氏は表現する。樽は「魂 (スピリッツ)の器」であり、原酒を一滴たりとも無駄にしないための、ウイスキー事業を支える取り組みだ。
そして現在、新たにブレンダー室が作られている。これまで稲垣氏を初めとした三郎丸蒸留所のブレンダーは分析室の片隅で作業を行っていたが、これからは専用の部屋で作業を行えるわけだ。そしてこのブレンダー室は、組子の仕切りを通じてブレンド体験ができるワークショップルームにつながっている。
地域に根付きながら世界に存在感を
「三郎丸蒸留所のウイスキーは、富山でしか作れないウイスキー」と稲垣氏は言う。ウイスキー造りにも使われる若鶴の仕込み水は、地下深くより汲み上げられたもので、適度なミネラルを含み、一年を通して冷たく清らかな軟水だ。
そして「ZEMON (ゼモン)」は高岡市の「高岡銅器」の技術によって造られたものであり、富山県産ミズナラを用いたウイスキー樽「三四郎樽」も井波の木工技術が使用されている。新しいブレンダー室では組子が取り入れられている。
「三郎丸蒸留所の使命は『地域に拠って、世界に立つ』です。地域に根付きながら世界に存在感を示していきたいと思っています」(稲垣氏)
なお、前編でお伝えした三郎丸蒸留所の歴史、後編でお伝えしたジャパニーズウイスキーの変遷については、稲垣氏の著書「ジャパニーズウイスキー入門」でより詳細に解説されている。ウイスキーに興味をお持ちの方は、ぜひご一読いただきたい。
富山に立脚した若きリーダーは、これからグローバルに向けてどのように飛躍していくのだろうか。三郎丸蒸留所の躍進を今後も見守っていきたい。