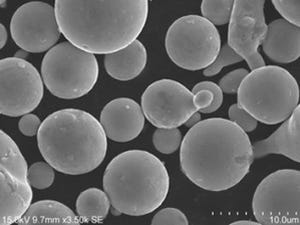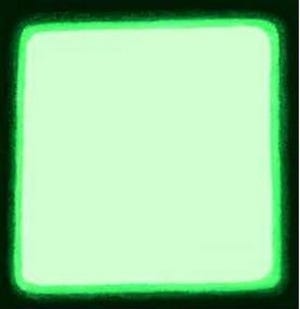東北大学は、太陽電池用結晶の育成法を考案し、擬似単結晶と呼ばれるシリコン結晶の育成に成功したと発表した。
同成果は、同大 金属材料研究所の米永一郎 教授、大野裕 准教授、徳本有紀 助教、沓掛健太朗 助教、宇佐美徳隆 准教授らによるもの。詳細は応用物理学会発刊の学術雑誌「Applied Physics Express」にオンライン公開された。
太陽光発電は結晶シリコンを基板とする太陽電池を主力材料に普及・生産の拡大が世界的規模で進んでいる。2011年の太陽電池用基板の生産統計によると、約50%が多結晶シリコン、40%が単結晶シリコン、10%がその他となっている。この比率は今後10年で大きく変化し、多結晶シリコンは、変換効率の向上が期待される擬似単結晶シリコンに置き換えられると予測されている。擬似単結晶シリコンは、種結晶を利用して育成されるが、多結晶シリコンと同じ製造装置と太陽電池製造工程を使用でき、また多結晶シリコンに比較して太陽電池の変換効率が絶対値で1%弱向上するという利点がある。1%の変換効率向上は、すでに成熟しつつある結晶シリコン太陽電池では画期的なことであり、2012年の世界の多結晶シリコン太陽電池生産量からの換算では、エネルギー発電量として大型火力発電所一基分に相当するという。このため、ここ数年で擬似単結晶の研究開発が急速に進む見通しだ。
しかし、シリコン融液から種結晶を使って擬似単結晶を育成する過程で、ルツボに接する部分から擬似単結晶とは別の方位の多結晶粒が多数発生してその占有部分が拡大する多結晶化という大きな問題が存在しており、これにより1つのインゴットから得られる擬似単結晶ウェハの比率が低下してしまうという課題があった。例えば、一般的な80cm角状のインゴットで多結晶化すると、擬似単結晶ウェハの歩留りは36%まで低下する。すなわち1%の変換効率向上の恩恵が、インゴット内の36%の部分でしか受けられないことになる。
このため、多結晶化を防止する研究が多数進められている。例えば、結晶の成長条件を調節することで、固液界面の形状を制御して多結晶粒の面積拡大を抑制することが提案されている。しかし、結晶の成長条件はインゴットの品質、生産効率、コストに直結するパラメータのため、それらとの両立を図ることは難しいため、成長条件と独立した多結晶化を抑制・克服する方法が求められていた。
今回、研究グループは、種結晶を複合化して特異な結晶粒界を形成し、この人工粒界の特性を利用して多結晶化を抑制する擬似単結晶インゴットの成長方法を考案した。まず、多結晶化の原因となるルツボ壁から発生する結晶粒によって形成される粒界の多数が、Σ3と呼ばれる粒界であることを見出した。このΣ3粒界は、インゴットの成長方向に対して傾いて発生するため、成長とともにインゴットの中央部分まで進展し、多結晶部分の面積が拡大する。これが多結晶化の原因となる。
今回、提案された方法では、複合させた種結晶によってΣ5と呼ばれる粒界をルツボ壁に沿って形成。Σ5粒界はインゴットの育成段階で成長方向に真直に伸びるほか、ルツボ壁から進んでくるΣ3粒界と反応してΣ15粒界を形成する。Σ15粒界も成長方向に伸びるため、多結晶粒の拡大はこの時点で止まることとなる。つまり、インゴットの中央部分は1個の結晶粒として擬似単結晶のままとなる。これが、結晶粒界の特性を機能的に利用することによって多結晶化を抑制する機構となる。この成果は、結晶粒界の基礎的研究によって初めて得られたものだという。
|
|
|
図1 (a)擬似単結晶シリコンの成長模式図。従来技術(左)と新技術(右)。(b)多結晶化を抑制する機構。ルツボ近傍の拡大図。Σ3粒界がΣ5粒界と反応しΣ15粒界に変わることで、多結晶粒のルツボ中央への伝搬が止められる |
さらに、この機構に基づき10cm角のインゴットにおいて、多結晶化を抑制したインゴットの育成にも成功している。一般に、ルツボ壁から数cmの部分は太陽電池用ウェハには利用されないため、今回の方法によって多結晶化の範囲をルツボ壁近傍のみに留めることで、100%の擬似単結晶ウェハの歩留りが期待されるようになる。すなわちインゴット内のすべてのウェハで1%の変換効率向上の恩恵を享受できるようになるのだ。将来の擬似単結晶シリコンのシェア予測は2020年で全太陽電池の40%と言われており、この予測から考えると、この歩留りの向上が太陽光発電の分野に与える影響は大きいものと考えられる。
|
|
|
図2 従来技術および新技術で育成した擬似単結晶シリコンインゴットから切り出したウェハの断面写真。人工粒界の形成以外はすべて同一の工程・条件にてインゴットを作製した。多結晶化した部分は黄色で示されている。右図中の白破線は、人工的に形成したΣ5粒界の位置を表わしており、Σ5粒界によって、多結晶化が太陽電池として使用されないインゴット外周部に限定されることがわかる |
また、今回の方法は、既存の太陽電池産業への導入障壁が極めて低いという特徴を持っている。同方法の鍵となる複合種結晶による粒界の形成や粒界反応は、結晶サイズや結晶成長条件にはほとんど依存しないため、結晶サイズや結晶成長条件によらず適用することができ、多結晶化の抑制と結晶品質や生産性とを両立させることができる。さらに、このような機能性粒界を人工的に形成するための複合種結晶は、従来の擬似単結晶の成長で用いられてきた種結晶を切断して並べ直すだけで形成できるため、現状の擬似単結晶の生産設備がそのまま適用でき、また製造工程の調整なども必要としない。すなわち、明日からでも迅速かつ簡易に生産現場に導入できるということとなる。このように、今回の開発は、産業界の要請に即応する成果であり、太陽光発電分野の発展に確実に寄与するものと研究グループはコメントしている。
ただし、太陽電池用の擬似単結晶シリコンには「転位密度の低減」という問題がまだ残されており、この問題が解決されれば、単結晶シリコンに匹敵する、さらに高い変換効率が得られる結晶が期待されるようになる。
なお、研究グループでは、転位欠陥の多くは結晶粒界から発生するため、今後も結晶粒界の研究を進め、転位発生を有効に抑制する結晶粒界を明らかにし、これらの成果を融合した「結晶粒界エンジニアリング」の確立を目指していくとするほか、太陽電池用の超高品質、かつ経済的に優れた擬似単結晶シリコンの実現に向けた研究を継続していくことで、5年、10年先の太陽光発電産業への貢献を目指すとしている。