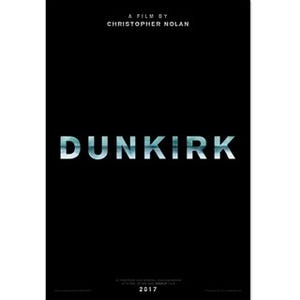戦争映画というシンプルなカテゴリーでは到底語り尽くせないクリストファー・ノーラン監督作『ダンケルク』(9月9日公開)。『インセプション』(10)や『インターステラー』(14)に続く革新的な映像体験はもとより、多層的に描かれた人間ドラマにもうならされる。来日したノーラン監督に単独インタビューし、その舞台裏に迫った。
今回ノーラン監督は初めて実話の映画化に臨んだが、イギリス人である監督にとって「ダンケルク」という題材には、特別な思い入れがあった。本作で描かれるのは、第二次世界大戦中にフランスの港町ダンケルクで起きた史上最大の救出劇だ。
ドイツ軍に追い詰められたイギリスとフランスの連合軍兵士40万人を救出しようと、イギリスから軍艦だけではなく約900隻の民間船が自らの意思でダンケルクに向かった。この不屈の精神と決意は、イギリス人の誇り“ダンケルク・スピリット”として、後世に語り継がれている。ノーラン監督に言わせると「体に染み込んでいる」そうだ。
陸の防波堤での1週間、海峡を渡る船での1日、空中戦での1時間と、それぞれの異なる時間軸を編み込んだ緊迫感溢れる106分間。映像への没入感はハンパなく、怖くて思わず目を背け、弾を避けようとしてピクリと体が動く瞬間もあった。まさに「一切緩急をつけず、お客さんを休ませないという容赦ない映画にしたかった」と言うノーラン監督の狙い通りだ。
戦場の対局を見せる上で監督がこだわったのは、ダンケルクから外へとカットバックしないことだった。「軍の上層部や政治家たちが何かをしゃべっているといったありがちなシーンに飛ばすことを一切禁じた。ひたすら戦場を映すことで、そこでのドラマが深くなり、サスペンスで引っ張っていくことができると考えたんだ」。
空から援護射撃をするイギリス軍パイロット・ファリア役のトム・ハーディとは、『インセプション』、『ダークナイト ライジング』(12)に続いて3度目のタッグとなった。奇遇にもトムの祖父が当時ダンケルクの戦地にいて、彼が少年の頃、退役軍人の祖父からその話を聞いていたそうだ。
「トムのおじいさんの件はオファーの際には全く知らなかった。まあ、第二次大戦で祖父母を亡くしたイギリス人は大勢いるからね。僕の祖父も第二次世界大戦に趣き、ダンケルクにはいなかったけど、空軍でパイロットをしていて亡くなっている」。
トム・ハーディのキャスティングの決め手は前2作で認めた演技力にあった。「パイロットは操縦席に乗り込んだ後、マスクを付けっぱなしになるので、目で感情とストーリーを語れる俳優が欲しかった。彼は『ダークナイト ライジング』の時も、マスクをつけた役柄(ベイン)を演じていたが、目だけでも見事な演技を見せていたから」。
ノーラン監督の名を日本で最初に知らしめたのは監督2作目の『メメント』(00)だろう。映画デビュー作『フォロウィング』(99)と同様に、時系列をシャッフルするという脚本の新たな方程式を見せ、映画ファンを驚嘆させた。脚本家としても超一流のノーラン監督だが、今回は史実をリスペクトし、一切キャラクターの背景を盛らず、敢えて台詞を極力抑えた。
「兵士たちの口から、自分はどこから来たのか、どういう人なのか、といったことを説明させないようにした。あくまでもその兵士がその場で立たされた現状に、お客さんが引き込まれていく映画にしたかった。途中でテンションを緩ませたくなかったんだ」
お手本にしたのは、アルフレッド・ヒッチコックやアンリ・ジョルジュ・クルーゾなどサスペンスの巨匠の作品だ。「彼らは台詞ではなくビジュアルでテンションを挙げ、ストーリーを語っている。そういったアプローチは脚本段階からこだわり、脚本自体も76ページという非常に簡潔なものとなった」。
登場するのは架空の人物だが、彼らはノーラン監督がリサーチした当時の資料や、実際にダンケルクで生き延びた退役軍人たちから聞いた体験談を反映させたリアルなキャクラターたちだ。
ダンケルクで多くの兵士たちが次から次へと命を落としていく中、ある民間人の少年の死も描かれていく。そこにはノーラン監督の戦争における死生観が投影されていた。「このエピソードも、戦時中のいろんな実体験をベースにしたものだが、実は彼のキャラクターには非常に重要な役割がある。僕があの少年の死を通して訴えたかったことは、戦場の死というのは非常にランダムなもので、生きるか死ぬかの境目が決まるのは“たまたま偶然”に過ぎないという点だ」。
ノーラン監督は「戦地においての栄光の死というもの描きたくなかった」と語気を強める。確かに兵士ではない少年を死に至らしめたのは、不運な出来事だったというしかない。
「死んだ兵士に対して生き残った者が、『君は英雄だ』とか『立派な自己犠牲を払った』とかいろんな後付けの解釈を加えることがよくある。でも、僕はそう思わない。実際、彼らが死んだのはたまたまだったんだ」。
その少年は戦地の状況について何も理解していないまま救出作戦に参加し、悲劇に見舞われる。「彼は非常にナイーブで良い少年で、兵士たちを助けようとする。そんな彼が死んでしまうことはとても不条理なことだ。でも、実際に戦場の男たちの運命というのはそういうものなんだと僕は思う。つまり戦地では勧善懲悪の原理なんて一切働かない。モラルがある人だからといって、生きながらえるわけではないんだ」。
身内を戦争で亡くしているノーラン監督の口から出た言葉だからこそ、より一層重みが感じられる。
折しも不安定な世界情勢となり、日本もきな臭い状況にある今、『ダンケルク』が公開されることはとても意義深い。多くの戦争映画の場合、ベクトルは“死”へ向かうのだが、本作では救出劇という“生”に向けられている気がするからだ。
まあ、いろんな講釈はさておき、一番声を大にして言いたいことは「この映画史上に残るエポックメイキングな映画は、絶対にでかいスクリーンで体感すべきだ!」ということ。これに尽きる!
(C)2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.