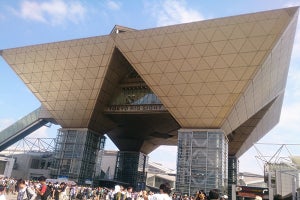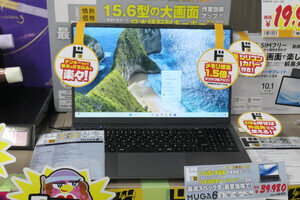新型コロナウイルス感染の深刻な状況が続いている。働き方も、そして生き方さえも変えなくてはならない事態だ。その状況にITがどんな貢献ができるのかを考えたとき、仕事の支援から、心のケアまで、あらゆる面での可能性が浮かび上がっている。
外出の自粛が求められれば、外との接点はインターネット頼みとなる。遠い未来のことだと思っていた遠隔医療なども今回の状況で急務となっている。新型コロナがなければ年単位での未来ストーリーだったはずだ。技術的にはすぐに可能でも、解決しなければならない問題がたくさんあるからだ。
自宅作業に備えてギガに余裕を
インターネットに多くを依存する暮らしでは、月末で残りギガを気にしていては暮らしに支障が出てきてしまうことさえ考えなければならない。4月に入り年度が代わり、本来なら新生活をスタートするであろうタイミングだが、新入社にしても入学にしても自宅待機が当面続くような状況の中で、研修や授業、オリエンテーションなどもオンラインで行うことを表明する企業や教育機関も多い。
自宅に容量を気にしないで使える光などのインターネット回線があればいいが、あるのはモバイルネットワークのみという世帯も少なくないだろう。ここはひとつ、この状況が収束するまでの間だけでも、契約内容を見直し、ギガの残りを気にしないでもいいようにプランを変更しておくことをおすすめしたい。
本当は、携帯電話事業者各社が災害時のような特例で速度制限なしの対処をしてくれるとありがたいのだが、キャリアばかりに犠牲や奉仕を強いるわけにもいかない。冷静に計算をしてみると、郊外から都心に移動しないということは、往復で数百円を使わないということでもある。そのコストをインターネットのために使うというのも現実的だ。
以前、この状況下、インターネットトラフィックが増大していることについてこのコラムで言及したが、局所的な災害ではなく、日本全体が非常の際に、インターネットがどのような動きを見せるかは、今後のインフラ整備のための貴重なデータにもなるだろう。そのデータを少しでも確からしいものにしてほしい。
ネットだけでは無理なこと、いつかは普通に
IT依存には悪いこともたくさんある。AIの判断やロボットなどによる自動化が進むことによる人間不在の枠組みの懸念、さらに社会の監視の重要性が高まることによる不安。こうして新型コロナ後の世界観は、人が何十年もかけて育むはずのことを、ものの半年で加速化してもたらすこととなるにちがいない。
個人的にはインターネットと普通に向き合うようになってすでに30年近くが過ぎた。最初につないだときから、今、ごく普通に享受しているオンラインの世界が必ずくると思っていたが、本当にそうなるには時間がかかった。当時は、電車の中のほとんどの人が紙の新聞や本ではなく、なんらかの端末を眺めるようになると書いたりもしていたが、やっぱり実現までは長かった。でも、実際にそうなった。いずれにしても、これから、オンライン依存の傾向はますます高まるだろうし、今回の状況によって、そのトレンドはますます加速する。
今、われわれにできることは、とにかくインターネットを浴びるように使い、それが人類の暮らしにどんな貢献をするのか、するはずなのかを身をもって体験し、インフラ側に、その爆発的な需要に応えられるだけの準備をしておいてもらうことだ。だが、トラフィック増大とはいえ、すでに冗長性を確保したインフラ事業者側としてはビクともしないくらいの増加にすぎないという分析もある。
その背景には、インターネットでは無理なことが世の中にはまだまだたくさんあるという現実がある。その「無理」も、将来には無理ではなくなる。その将来をできるだけ近いものにすることに貢献するには、とにもかくにも使うしかない。こういう時期だからこそ、ちょっと未来のことを考えてインターネットを活用してほしい。