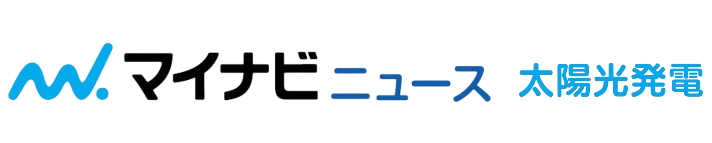自家消費型の太陽光発電を導入すべきなのか、迷っていませんか?ソーラーパネルを設置して作られた電力を自分の家で消費する自家消費型の太陽光発電は、電気料金を節約できるなどのメリットがあります。
一方で、導入するためのコストが高額になるなどの、デメリットもいくつかあります。こうしたメリット・デメリットについて把握してから、自家消費型の太陽光発電を導入するのかどうか検討しましょう。
この記事では、自家消費型の太陽光発電に関する基礎知識やメリット・デメリットだけではなく、自家消費率をアップさせる方法なども取り上げます。本記事を読むことで、自家消費型の太陽光発電が本当にお得なのか把握でき、正しく導入できるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
マイナビニュース太陽光発電ガイド運営おすすめ!



自家消費型の太陽光発電の導入で失敗しないためには、複数のメーカー・販売施工業者を比較・検討して選ぶことが重要です。メーカーによって必要な費用やアフターサービスなど違いがあるため複数業者をしっかり比較することで失敗を避けることができます。


自家消費型の太陽光発電に関する基礎知識

まずは、自家消費型の太陽光発電の種類や注目されている理由など、基本情報を見ていきましょう。
自家消費型の太陽光発電とは
自家消費型の太陽光発電とは、ソーラーパネルを屋根に設置し、作られた電力を自分の家で消費する方法のことです。
発電した電気を電力会社に売って、収入を得る投資型の太陽光発電もありますが、自家消費型の場合、この名称の通り自分の家で消費するため、売電することはありません。
かつては投資型の太陽光発電に人気がありましたが、今現在、自家消費型の太陽光発電が注目を集めています。自家消費型が注目されている理由は、次の項目で詳しく紹介します。
注目されている理由
自家消費型の太陽光発電が注目を集めている理由は、年々売電価格が低下しているからです。電力の売電単価はFIT(固定価格買取制度)により経済産業大臣が決定していますが、設置費用の低下などを理由に、毎年売電価格が低下しています。一昔前は売電単価が高く、投資型の太陽光発電をやっていても、着実な利益を確保できていました。
しかし現在では自家消費で電気代を浮かせた方がお得になっている状況です。
また、産業用太陽光発電の全量売電制度が2020年度で廃止となったこともあり、自家消費で電気を使用した方が利益が高くなるため、今、自家消費型の太陽光発電の注目度は加速しています。
自家消費型の太陽光発電の種類
自家消費型の太陽光発電には、全量自家消費型と余剰売電型の2種類があります。ここでは、それぞれの詳細を紹介します。
全量自家消費型とは
全量自家消費型は、太陽光発電による電力をすべて自家消費にするシステムです。
通常売電するためには、固定価格買取制度の事業計画認定の申請を行う必要がありますが、すべて自家消費にするため、手続きがなくなり電力会社と連携するための費用も不要です。電気の消費量が多い場合は、全量自家消費型が向いているでしょう。
余剰売電型とは
余剰売電型は、太陽光発電で自家消費しきれなかった電力を売電に回すことができるシステムです。
余剰売電は、10㎾未満の家庭用太陽光発電システムだけではなく、10kW以上の産業用太陽光発電でも可能です。「電気をすべて使いきれそうにない」「電気を無駄にしたくない」というケースでは、余剰売電型がマッチするでしょう。
自家消費型の太陽光発電を導入するメリット

自家消費型の太陽光発電を導入するメリットは、以下のようにたくさんあります。
- 電気料金を節約できる
- 停電のときも電力が使用できる
- 補助金が貰える
各メリットを知り、自家消費型の太陽光発電を導入するのかどうか検討しましょう。
電気料金を節約できる
自家消費型の太陽光発電を導入するメリットは、電気代を抑えられることです。
ソーラーパネルで発電した電力を使用できるため、電力会社から電力を購入する機会が減るからこそ、電気料金の節約につながります。また、電気料金に含まれている、基本料金も削減できます。
基本料金の節約にも繋がる
電気料金の基本料金は、「最大デマンド」と呼ばれる電気使用量の大きかった時間帯の電力量を基準に計算されています。
自家消費型の太陽光発電を導入すれば、たくさん電気を使用する時間に消費する量を抑えられて最大デマンドが下がるため、電気料金の基本料金も下げられます。
電気代のコストダウンを目指している方は、自家消費型の太陽光発電を導入しましょう。
停電のときも電力が使用できる
災害や停電などにより電気の供給が止まってしまった場合でも電力を使用できることは、自家消費型の太陽光発電を導入するメリットです。
非常用電源として、ガソリン式発電機や小型バッテリーなどがありますが、大量の燃料やバッテリーが必要になるケースもあり、使い続けることは難しいでしょう。
しかし自家消費型の太陽光発電ならば、晴れていれば電力を使い続けられるため、停電時でも安心です。
補助金が貰える

自家消費型の太陽光発電は、国から補助金が貰えるメリットもあります。2025年度はすでに募集が終了していますが、過去には以下の補助制度が行われました。
| 補助金 | 対象 |
| ZEH補助金 | ZEH住宅の新築、購入など |
| ZEH+実証事業 | ZEH住宅の新築、購入など |
| 先進的再エネ熱等導入支援事業 | ZEH住宅の新築、購入など |
概算要求とは、財務省に提出される見積書のことであり、財務省で閣議決定することで制度として利用できます。自身が補助の対象になっているのか確認してから、申請の手続きを行いましょう。
 マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営
マイナビニュース 太陽光発電ガイド運営補助金が受け取れるまでにはかなり時間がかかります。 HPにまとめサイトがあるのでそれを活用しましょう。
自家消費型の太陽光発電を導入するデメリット


自家消費型の太陽光発電を導入する際、メリットばかりではなく、次のようなデメリットもあります。
- 高額な初期費用がかかる
- 設置スペースを確保しなければならない
- メンテナンス費用の負担がかかる
- 夜間や天候が悪い日は発電できない
ここでは、各デメリットについて詳しく見ていきましょう。
高額な初期費用がかかる
自家消費型の太陽光発電を導入するデメリットは、初期費用が高くなってしまうことです。太陽光発電には、以下のような設備が必要になっています。
- ソーラーパネル
- パワーコンディショナー
- 分電盤
- 接続箱
- 配線
さらに自家消費型の場合、発電や消費などを管理するための自動制御システムも必要です。融資を受けて始めることも可能ですが、高額な初期費用がかかってしまうと認識しておきましょう。
設置スペースを確保しなければならない
産業用の太陽光発電を設置する場合、工場のような広い面積の設置スペースが必要となることもデメリットです。産業用太陽光発電を設置できるスペースは、以下のような場所です。
- 建物の屋根
- 使っていない土地
- 駐車場
産業用の太陽光発電は、サイズが大きくなるからこそ、広い面積を必要とします。また、古い建物の屋根の場合、法律によって設置できない可能性があるため注意が必要です。
メンテナンス費用の負担がかかる
太陽光発電には、メンテナンス費用もかかります。パワーコンデショナーが寿命を迎えた場合の交換費用やパネルの清掃費用、定期点検費用などのランニングコストがかかるため、「太陽光発電にメンテナンスが必要ない」というイメージは誤りです。
また、パネルを掃除しなければ、発電効率が悪く発電量が下がる傾向にあります。自家消費型の太陽光発電を導入した後は、しっかりとメンテナンスするようにしましょう。
夜間や天候が悪い日は発電できない
天気が良くない日や夜には発電できないことも、デメリットです。雨や雪の日も同様に、発電できません。発電できない日が続いた場合は、電力会社から電力を購入しなければならず、当然費用がかかってしまいます。
しかしながら、蓄電池を導入し余剰電力を貯めておくことで、発電が行えないときでも電力を使用可能です。次の章では、蓄電池の導入など太陽光発電の自家消費率をアップさせる方法について詳しく紹介します。
太陽光発電の自家消費率をアップさせる方法


太陽光発電の自家消費率を上げるためには、以下の方法がおすすめです。
- 蓄電池を併用する
- オール電化やエコキュートと組み合わせる
- 電気自動車を導入する
- 家に住む人を増やす
前々章で紹介したメリットの恩恵を受けるためにも、こうした太陽光発電の自家消費率をアップさせる方法について理解を深めておきましょう。
蓄電池を併用する
電機を貯められる蓄電池と太陽光発電を併用することによって、効率よく運用できるようになります。蓄電池を併用するメリットは以下の通りです。
- 停電したときに貯めておいた電力を使える
- 蓄電池に蓄えておけば、夜間も太陽光発電を活用可能
電力を貯められるようになるため、万が一のときでも安心です。一方で蓄電池は、設置場所を確保しなければならなかったり、劣化による買換えが必要になったりするデメリットがあることも理解しておきましょう。
太陽光発電と蓄電池の併用についてより詳しく知りたい方は、以下の2つの記事もおすすめです。




太陽光発電の導入を検討しているなら、「タイナビ」の一括見積もりがおすすめ!


太陽光発電や蓄電池の設置で、希望に合う施工業者を効率よく探すなら、太陽光発電・蓄電池の一括見積もりサービスが便利です。中立的な立場から、あなたの状況に合うおすすめの施工業者を紹介し、契約までサポートしてくれます。
特にマイナビニュース 太陽光発電ガイド運営がおすすめしたいサービスが「タイナビ」です。タイナビがおすすめな理由は大きく4点!
- ご利用者数100万人を突破した信頼できるサービス!
- 一人ひとりに合った「最新の補助金情報・太陽光発電に関するメリット・デメリット」を丁寧に説明
- たった30秒で最大5社から簡単一括無料見積もり
- 比較により最大100万円安くなった事例も!
オール電化やエコキュートと組み合わせる
オール電化にすることで、ガス代として使用していたものが電気代になるため、電気の自家消費を増やせます。またオール電化は、ガスを使わないからこそ火災の危険性が少なく、楽に掃除をできて衛生的というメリットもあります。
電気を使った給湯器であるエコキュートは、ヒートポンプによって空気の熱でお湯を沸かす設備であり、それほど電気を使う必要がありません。エコキュートと似た電気温水器は、電気ヒーターを使って電気のみでお湯を沸かすため、エコキュートよりも電気代が高い傾向にあります。
ただし、オール電化はライフラインを電気だけに頼ることになり、停電などがあると生活機能が破綻してしまう可能性があります。エコキュートは、エアコンの室外機程度の大きさになっているヒートポンプユニットと貯湯ユニットを設置しなければならず、ある程度のスペースが必要です。
さらにエコキュートの設置費用も、50~80万円程度と安いわけではありません。オール電化やエコキュートについては、以下の記事でも詳しく解説しています。


電気自動車を導入する
電気自動車を導入することで、太陽光発電の自家消費を増やせます。また太陽光発電の電気で充電すれば、ガソリン代や軽油代の節約にもつながるメリットがあります。
さらに、V2H(Vehicle to Home)という機器を導入することで、電気自動車のバッテリーとして搭載されている電池が家の中でも使えるようになり、補助金も申請可能です。
ガソリン自動車から電気自動車に移行する世の中の流れになっています。太陽光発電の導入とともに、電気自動車の購入も検討するのも一つの選択肢です。
家に住む人を増やす
二世帯住宅にしたり、1人暮らしだった大学生の子どもを家から通わせたりすることでも、電気使用量を増やせます。また、日中家で過ごしている人が多いほど自己消費率が上がります。民泊なども、電気使用量を増やせるおすすめの方法です。
ただし、家に住む人を増やすことは自分だけの問題ではないため、家族としっかり話し合うようにしましょう。
自家消費型の太陽光発電に関するQ&A
自家消費型の太陽光発電に関するよくある質問も見ていきましょう。
- 初期費用はどれぐらい?
- 初期費用をゼロにする方法は?
各質問に対して答えを紹介するので、より自家消費型の太陽光発電について知りたい方は、参考にしてください。
初期費用はどれくらい?


資源エネルギー庁が2023年に公開した資料によると、太陽光発電の導入費用の平均値は、以下の通りです。
- 10kW以上50kW以上:25.5万円/kW
- 50kW以上200kW未満:20.7万円/kW
相場は、1kW当たり20万~30万円程度です。ただし、設置するための費用を安くする方法は以下のようにたくさんあります。
- 設置業者を吟味する
- 費用が安い商品を設置する
- トータルの支払いが安くなるローンを選ぶ
同じ商品を取り扱っていても、設置業者によって費用は変わってくるため、業者を吟味することは非常に大切です。業者を選ぶ際は、複数社の見積もりを比較し、お得になるのかしっかりと検討しましょう。
また、ソーラーローンを使用する場合、トータルで支払いが安くなるのか、ローンシミュレーションをしっかりと行ってから金融機関を決めることをおすすめします。
太陽光発電の設置方法と節約方法についてより理解を深めたい方は、以下の記事がおすすめです。





設置費用を抑えるなら新築時の導入がベストです。一方で、既存の家に設置する際に、設置費用を抑えるコツはありませんが、補助金を活用することが挙げられます。
太陽光の専門家監修!太陽光発電一括見積もりサイトおすすめランキング


「複数の業者を比較して、質の高い業者に依頼したい」「悪徳業者に騙されたくない」という方に向けて、実際にサービスを利用したことのある方に行ったアンケート結果をもとに、太陽光発電一括見積もりサイトをランキング形式で紹介!
さらに、専門家に聞いた太陽光発電一括見積もりサイトを利用する際の注意点や、質の高い業者を見極めるポイントも紹介しているのでぜひご覧ください。
初期費用をゼロにする方法は?
PPA事業者に屋根を提供し、屋根の設置費用を負担してもらうことも可能です。
PPAとは、電力販売契約のことです。家の所有者に設備の所有権はありませんが、PPA事業者に屋根を貸すことで事業に相乗りするような形となり、電力会社より電力を格安で買えるメリットもあります。
PPAでの太陽光発電以外にも、以下のような初期費用をゼロにする方法があります。
- 設置する設備をリースする
- 事業者に屋根を貸す
リースは、事業者に毎月リース料を支払うことになりますが、太陽光発電の所有権を持てます。だからこそ余剰分を売却して利益を得ることも可能です。
屋根貸しは、事業者に屋根を貸すことで賃料を得るやり方です。ただし、事業者から支払われる屋根の賃料は一般的に年1万円ほどであり、利益率が高いとは言い切れません。
また、戸建て向けのサービスはあまりないため、注意が必要です。こうした太陽光発電の投資方法の詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


まとめ
自家消費型の太陽光発電は、ソーラーパネルを屋根に設置し、電力を自分の家で消費する方法のことです。年々売電価格が低下しているため、ひと昔前まで主流であった投資型以上に今、注目を集めています。そんな自家消費型の太陽光発電を導入するメリットは、電気料金を節約できるだけではなく、停電のときも電力が使用できることです。
しかしながら、初期費用が高かったり、メンテナンス費用がかかったりするデメリットもあるため、その点も留意しておきましょう。太陽光発電の自家消費率をアップさせるためには、蓄電池の併用やオール電化・エコキュートとの組み合わせ、さらに電気自動車の導入などがおすすめです。
また、もっとも手軽な方法は、家に住む人を増やすことです。さまざまな角度から自家消費型太陽光発電についてしっかりと理解し、導入を検討しましょう。
※「マイナビニュース太陽光発電」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・東京都環境局
・みらいエコ住宅2026事業
・葛飾区公式ホームページ
・経済産業省
監修者情報


太陽光や蓄電池等の専門家。2017年より某外資系パネルメーカーに所属し年間1000件以上の太陽光を販売しトップセールスを記録。これまでの知見を活かしたYouTubeが業界NO,1の再生数を誇り、2021年に開業。現在は一般の方向けに自社で販売〜工事を請け負う。Youtubeチャンネル
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。