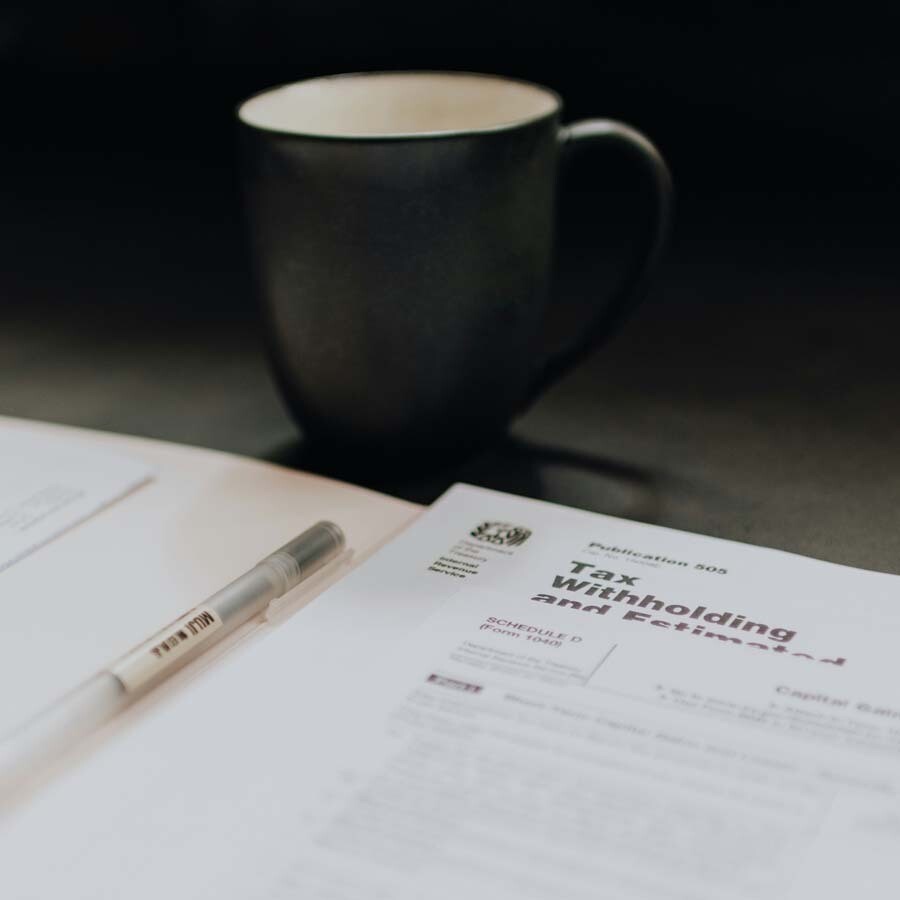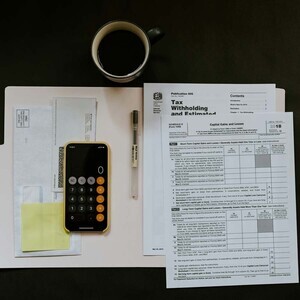いよいよ今年も確定申告の季節がやってきました。
株式、債券、コモディティなど、資産の守りを固めるために分散投資をされている方も増えましたが、その中で今注目されているのが不動産投資です。
不動産投資は、安定した収益を見込める魅力的な投資手段ですが、利益に対して課せられる税金が一つの大きな壁となることもあります。 特に、税負担が大きくなると、せっかくの投資効果が薄れてしまうことにもなりかねません。
そこで、本連載では全5回にわたり、不動産投資における節税術をテーマに、税金を最適化し、より効率的に資産を増やしていくための方法を解説します。
税金の仕組みを理解し、実践的な節税策を取り入れることで、投資の収益性を最大限に引き出すことが可能です。
このコラムを通じて、税負担を減らしながら不動産投資の魅力をさらに深めていきましょう。
不動産投資で節税効果を得られるのはどんな人?
第1回の本連載では、不動産投資でどういった税金が節税できるのか、そのカラクリもご説明しました。
第2回の今回は、不動産投資において節税効果を得られるのはどんな人か、解説していきます。
まず、不動産投資を行う上での大前提として、不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンに位置付けられることを理解していただく必要があります。不動産投資による節税は短期的な利益というよりも、長期的な資産形成を目指しながら得られる副次的な効果です。資金計画や収支管理、将来のリスクを見越した戦略的な計画を立て、安定した資産運用を視野に入れている人が適しています。
では、本題に入りましょう。
第1回の連載でも記しましたが、節税を目的とした不動産投資は、不動産所得を帳簿上赤字にし、給与所得・事業所得などと損益通算することによって課税所得を圧縮するスキームを活用します。
したがって、所得が高いほど税率が上がる累進課税制度の仕組みにより、給与所得や事業所得が多い高所得者ほど、このスキームに取り組む価値が高いと言えるでしょう。
では実際の年収を挙げて、さらに詳しく解説します。
年収が1,500万円以上の人
まず、不動産投資で節税が有効になるのは、課税所得が1,100万円〜1,200万円を超える人です。なぜなら、このラインを超える部分の税率は以下のように非常に高くなるからです。
- 所得税:33%
- 住民税:10%
- 復興特別所得税:0.693%
合計で43.693%もの税率が課されます。
一方、収益物件を売却したときの譲渡所得税(長期譲渡所得の場合)は20.315%の税率です。この差(43.693% - 20.315%)が、節税の大きなポイントとなります。
このように所得税率・住民税率と譲渡税率の差異を利用することで、節税効果を実感することができます。さらに税率差が大きければ大きいほど節税効果は高まりますので、課税所得が高ければ高いほど不動産投資による節税に向いていることになります。
高所得者にとって最も効果的な節税方法は、築古の木造または軽量鉄骨造といった物件への投資です。減価償却費を短期間で多く計上することで、不動産所得に赤字を発生させ、それを給与所得や事業所得と相殺して総所得を圧縮することで、納める所得税を減らし、節税ができます。
減価償却を活用した節税スキームについては次回以降の連載で詳しく解説します。
年収1,500万円を超えない人
反対に課税所得が1,100万円以下の人は、不動産投資を節税目的で行っても、その節税効果は小さく、不動産投資において享受できる節税メリットが少ない場合があります。
まず、節税を目的とした不動産投資は短期的に減価償却をとることが主な目的となるため、築年数の古い物件を取得するケースが多くなります。しかし、築古物件は修繕費などの突発的な支出が発生しやすい傾向にあり、金利や融資期間の面でも厳しい条件となる場合もあります。一方、新築や築浅物件の場合は修繕費などの支出リスクを抑えられ、融資、収益性の観点でも安定した賃貸経営が実現できます。
補足ですが、手段として新築・築浅物件も購入時の諸費用を経費計上し、会計上のマイナスをつくることもできます。しかし、2年目以降は節税効果が薄くなります。
結論、課税所得が1,100万円以下の方は、短期的な節税を目的とするのではなく、新築・築浅物件を選び、長期的にキャッシュフローを積み上げる不動産投資に取り組むことをおすすめします。
また、不動産投資を行う場合には毎年の確定申告が必要になりますが、この際には青色申告を活用することをおすすめします。青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる可能性があるからです。この65万円の青色申告特別控除は非常に魅力的な制度ですが、適用するためいくつかの条件を満たす必要があり、事業所得が赤字の場合には使用できませんので注意しましょう。
次の連載では、実際に不動産投資でどれくらいの節税効果があるのか、節税スキームも併せて詳しく解説していきます。お楽しみに。