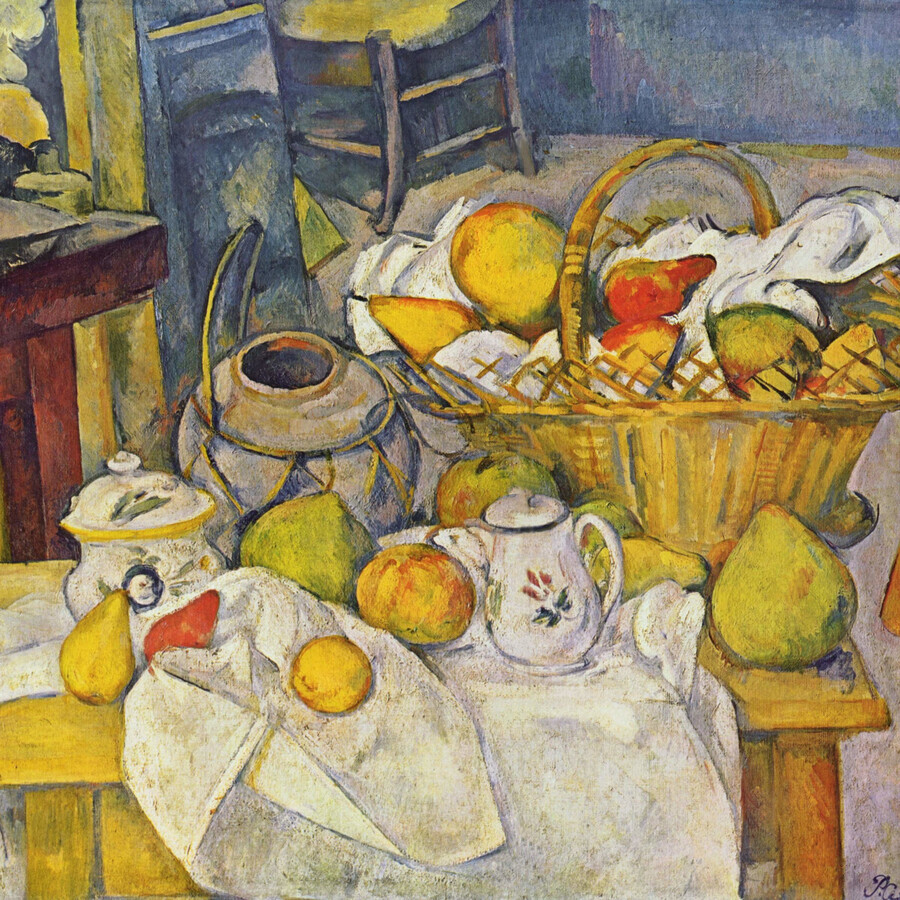この連載では、新潟大学 日本酒学センター編著の『愉しい日本酒学入門』(河出書房新社)から一部を抜粋し、日本酒の基本を学んでいきます。
今回は「日本酒の成分と味の基本構造」です。以下、『愉しい日本酒学入門』から抜粋します。
日本酒度ってどんな指標?
ラベルに「アルコール分」のほかに、「日本酒度」、「酸度」、「アミノ酸度」などの成分値が記載されている日本酒があります。
「日本酒度」は、日本酒の比重を表すのに便利なように工夫された独特の尺度で、計量法では、
日本酒度=(1/比重)-1)×1443
と定義されています。日本酒度は15℃で測定し、4℃の純粋な水と同じ重さであれば0、それより軽いものは正の値、重いものは負の値になりますので、日本酒の比重はアルコール分が同じであれば、不揮発成分(主として糖分)によるため、おおむねマイナスになるほど糖分が多いことになります。
「酸度」は、日本酒中の酸の量を、0.1規定の水酸化ナトリウム溶液により滴定した値であり、「アミノ酸度」は、遊離アミノ酸量をホルモール滴定法により測定した値です。
国税庁では、毎年、市販酒類に関する調査をおこなっており、国税庁HPには日本酒の成分値が公開されています。
2022(令和4)年度の一般酒の成分値を20年前の2002(平成14)年度と比較すると、日本酒度は1.4高くなり、酸度は変わらず、アミノ酸度は0.14減少しています。糖分、アミノ酸度が少なくなっていることから、日本酒の味はライト化しているといえるでしょう。ただし、ここ数年については成分変化が小さくなっています。
日本酒の味の構造は、甘口・辛口、濃い(コク、はば)・淡い、きれい(調和、まるい)・雑味の3次元構造とされています。
日本酒の成分には5つの基本味のうち、塩味はなく、ビールのイソフムロンやワインのポリフェノールといった特徴的な苦味、渋味成分は含まれませんので、甘味は糖分、酸味は有機酸、苦味や渋味には窒素成分が大きく影響しています。
また、アルコール分は、ビールで約5%、ワインで12%前後(7~14%)、日本酒は15%前後(13~18%)で、日本酒はアルコールの有する「甘味、苦味、刺激感」で香味のバランスを保っています。
日本酒中のおもな有機酸は、乳酸、コハク酸およびリンゴ酸です。これらは、おもに酵母が発酵中に生成します。乳酸には渋味、コハク酸にはうま味があり、酸味だけではなく日本酒の味に関係しています。最近では、乳酸菌、リンゴ酸を多く生成する酵母、クエン酸をつくる白麹菌を使用して、従来と酸の量や構成を変えた日本酒が販売されています。
甘口と辛口、どうやって決まる?
日本酒の甘口か辛口は、糖分と酸のバランスで約8割が決まります。糖分が多いと甘くなりますが、酸が多ければ甘味と相殺されます。
「日本酒度」は、比重を示しているだけですのでアルコール分の影響を受け、酸も考慮していないので、甘口辛口の指標としては参考程度にしかなりません。日本酒中のグルコース濃度から酸度を引いた「甘辛度」のほうが人の感覚とよく合います。
AV=G-A
※AV:甘辛度 G:グルコース(g/dL) A:酸度(mL)
※AVが「0.2以下を辛口」「0.3から1.0をやや辛口」「1.1から1.8をやや甘口」「1.9以上を甘口」
たとえば、グルコースが2.1、酸度が1.2の日本酒は、甘辛度0.9でやや辛口に該当します。
純米酒は、酸度が高くグルコースが少ないものが多いため「辛口」および「やや辛口」が多く、一般酒は「やや甘口」・「甘口」、吟醸酒および本醸造酒はその中間となります。 糖分や酸以外で甘辛に関係するのはエステル等の甘い香りとアルコールによる刺激感です。吟醸酒は、グルコースが比較的多くフルーティな吟醸香)エステル)を多く含むため甘く感じられるものが多いです。