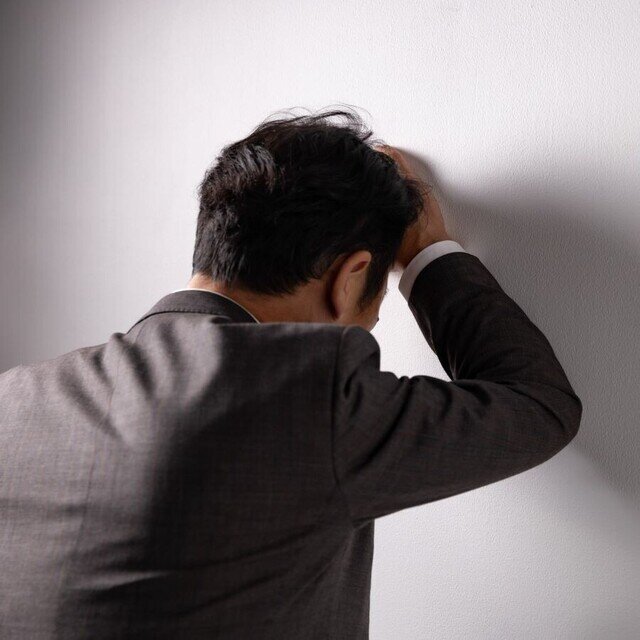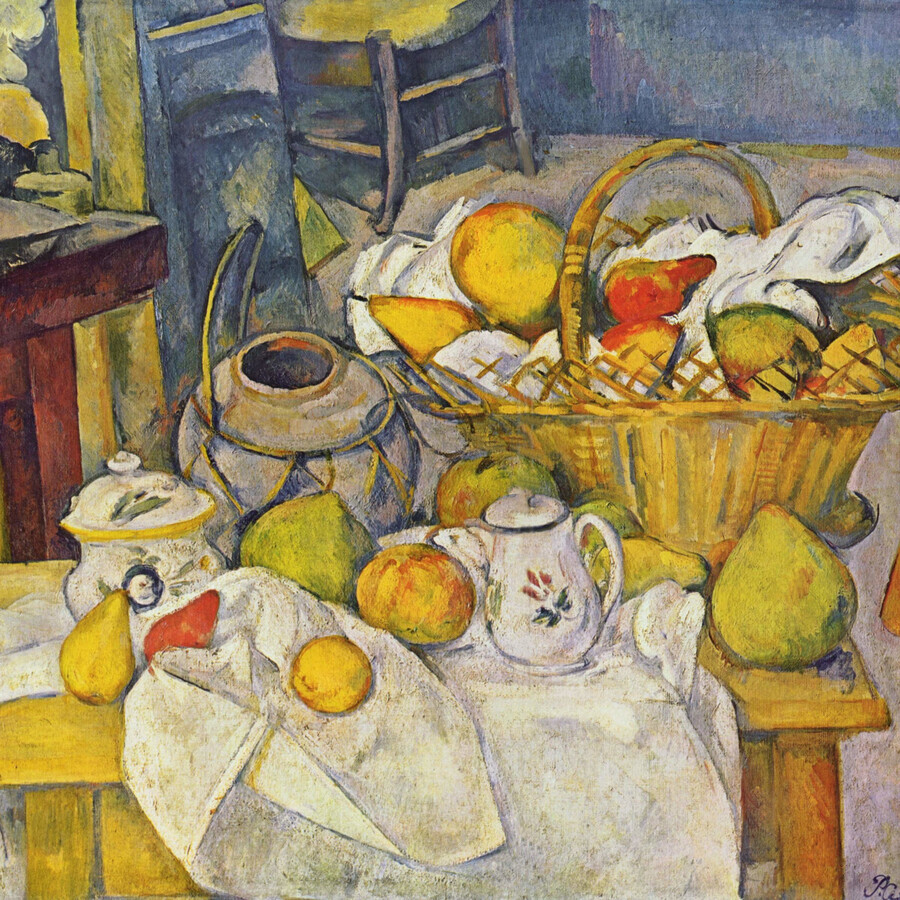この連載では、『美術館が面白くなる大人の教養 「なんかよかった」で終わらない 絵画の観方』(KADOKAWA)から一部を抜粋し、有名な絵画に秘められた物語や歴史を読み解いていきます。絵画に描かれた物語や歴史を知れば美術館に行くのが楽しくなるだけでなく、あなたの教養のレベルが1段階上がるかもしれません。
今回取り上げるのは、フィンセント・ファン・ゴッホの『夜のカフェ』という作品です。
以下、『美術館が面白くなる大人の教養 「なんかよかった」で終わらない 絵画の観方』から抜粋します。
ゴッホにとって色彩とは
―前略―
この絵は『夜のカフェ』という作品です。まずはここまでと同じように、じっくりと観てみてください。
酔っ払った客達がいる室内。中央にはビリヤードの台があり、それを囲むようにテーブルと椅子が並べられています。5人の客達と、白い服を着たこの居酒屋(カフェ)の店長がいます。壁は赤く、天井は緑色で塗られています。吊るされた灯りは怪しい光を放っています。人物や家具、空間はどこか歪んでおり、人間のプロポーションはどこかおかしく、そして色彩のどぎつさは目を引きます。
さて、この絵画の作者ゴッホは下記のような言葉を残しています。
「ぼくたちはぼくたちの絵に語らせる以外に何もできない」
〔引用:『ファン・ゴッホ 日本の夢に懸けた画家』(角川ソフィア文庫) 圀府寺司(著) KADOKAWA P207〕
彼はこの絵で何を語りたかったのでしょうか。
実は、彼はこの絵についてこのような言葉を残しています。
「赤と緑によって人間の恐ろしい情念を表現しようと努めた」
「僕は『夜のカフェ』という絵で、カフェ(居酒屋)とは人が身を持ち崩し、気が変になり、罪を犯すところだということを表現しようと努めた。つまり、柔らかいピンク、鮮紅色、ブドウの搾りかすの赤のコントラストによって、また硬い黄緑と青緑とコントラストをなすルイ15世風、ヴェロネーゼ風の柔らかな緑、これら全てを地獄のるつぼと白っぽい硫黄色の雰囲気の中に放り込むことによって、居酒屋の闇の力のようなものを表現しようとした」
〔引用:『西洋美術の歴史7 19世紀:近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』 尾関幸、陳岡めぐみ、三浦篤(著) 中央公論新社 P448 ※かっこ内は筆者補足〕
つまり彼は、色彩を通じて、「人間の恐ろしい情念」や「居酒屋の闇の力」を表現しようとしていたのです。ここに新しい革命があります。
彼は人間の内面、感覚の表現のためなら、空間の歪みや色彩が現実から乖離していても問題ないと考えました。つまり、色というものは内面を表現するためにあって、外部の世界の模倣のためにあるのではないと考えていたのです。
リアルな絵画を破壊してそれまでとは違う絵画の方向性を探ったマネもモネも、結局は人間の肌のための白色、水を表現するための青色のように、何か現実世界を表現するために色彩というものを使っていました。けれどゴッホは違うのです。現実世界のものを絵画で表現するためではなく、内面を表現するために、そしてその結果、現実世界のものと色が乖離したとしても問題ないと考えていたのです。
『美術館が面白くなる大人の教養 「なんかよかった」で終わらない 絵画の観方』(井上 響 著/秋山 聰 監修/KADOKAWA 刊/定価2,200円)
美術館に行って楽しめる人、楽しめない人の違いは、ちょっとした観方の差だった!? 美術館に行くのが好きなのに、絵画に興味はあるのに、なんとなく楽しみきれない。そんな悩みを抱えている人は少なくないと思います。その効果的な解決方法は、自分なりの絵画の観方を身につけることです。そうすることで、まるでピントの合ったメガネをかけるように、色鮮やかに、そして今までと違ったように作品を鑑賞することができます。でも残念なことに、絵画の観方は基本的に誰も教えてくれません。そこで、東大の美術史で学んだ筆者が今回、こっそりと絵画の観方、そのコツをまとめました。有名絵画を含む130点以上の作品を使って、絵画の観方を解説をしています。具体的に本書で解説している観方の秘密は「物語」と「歴史」の知識。この2つの知識を身につけることで、自然と絵画の観方が身についていきます。