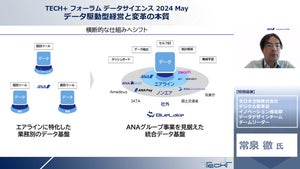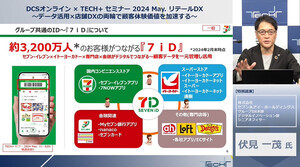2022年11月22日、京都大学(京大)らの研究グループは、ビスマス系高温超伝導ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ光源の製作に成功。それと同時に、その放射原理を偏波解析により明らかにしたというプレスリリースを発表した。では、この高温超伝導ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ光源とはどのようなものなのか。そして、この研究成果によりどのような展望があるのだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。
高温超伝導ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ光源とは?
京大大学院の掛谷一弘准教授、物質材料研究機構(NIMS)の齋藤嘉人NIMSジュニア研究員、高野義彦MANA主任研究者の研究グループは、ビスマス系高温超伝導ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ光源の製作に成功し、その放射原理を偏波解析により明らかにした。
ちなみにウィスカーとは針状を意味する。では、このビスマス系高温超伝導ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ光源とはどのようなものだろうか。
Beyond 5G・化学分析・生体イメージングなどの分野での応用が期待されるのが、テラヘルツの周波数帯だ。そして、テラヘルツ帯の電磁波を発信する小型のものとして、超伝導テラヘルツ光源が注目されている。しかし、このような光源素子の実現には、高品質平板状単結晶の育成技術と微細加工技術が必要なため、製造までに時間を要するなどの課題があるのだ。そこで彼らは、ウィスカー結晶に注目。ウィスカー結晶は、「品質の高い結晶が得られる」「簡単な装置で結晶を育成できる」「高い発振強度が得られる」そして「製造までに短時間で済む」というメリットがあるのだ。
すでにウィスカー結晶を用いたテラヘルツ発振を発見している研究グループにとって、ウィスカー結晶の固有な屈折率を特定することが、素子の発振モードを特定することを意味するのだが、そこで、彼らはウィスカー結晶の屈折率を特定した。さらにその結果、これまでの平板状単結晶とはウィスカー結晶の屈折率が異なることを明らかにしたのだ。
-
本研究の高温超伝導ウィスカーデバイスからテラヘルツ波が放射されることを示した偏波解析計算結果のスナップショット。矢印は電界の大きさと方向を示し、発振周波数0.73テラヘルツの半周期、-0.68ピコ(10-12)秒ごとに反転する(出典:京都大学)
この成果は、ウィスカー結晶を用いたテラヘルツ発振素子の設計が可能になったことを意味するという。加えて、素子の空洞共振周波数から少しずれた周波数でも比較的強い電磁波の放射が起きることも、三次元電磁場シミュレーションによって確認しているとのこと。つまり、超伝導テラヘルツ発振素子が持つ特徴である、単一の素子が単色かつコヒーレントなテラヘルツ波を広い周波数範囲で発振するという点の説明において、重要な発見に至ったのだ。
なおこの研究成果は、2022年11月21日に米国の国際学術誌『Applied Physics Letters』にEditorsʼ pickとしてオンライン公開されている。
いかがだっただろうか。今回、化学組成の違いによっても結晶の屈折率が異なることが示されたことにより、適切な材料を選ぶことによってテラヘルツ発振の周波数を大幅に拡大することも可能だと示される。偏波制御、高密度アレイ化による高強度放射が可能な超伝導テラヘルツ光源が社会実装されることで、特にBeyond 5G、化学分析、生体イメージングなど分野の未来は大きく変わっていくことだろう。