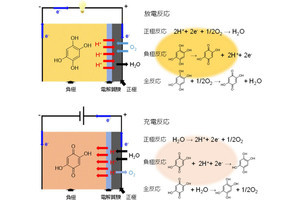山梨大学と理化学研究所(理研)の両者は10月30日、マウスの凍結「2細胞期胚」を国際宇宙ステーション(ISS)で解凍し、微小重力環境下でもほ乳類の胚が正常に発生し分化できるのかを調べた結果、胚盤胞期まで発生でき、胎児側の「内部細胞塊」(ICM)と、胎盤側の「栄養外胚葉」(TE)へと正しく分化できることが確認され、また一部の胚はICMが2か所に分かれており、一卵性双生児が生まれる可能性が示されたことを共同で発表した。
同成果は、山梨大 発生工学研究センターの若山清香助教を中心に、宇宙航空研究開発機構、日本宇宙フォーラム、理研 バイオリソース研究センター(BRC)、明治大学 農学部らの共同研究チームによるもの。詳細は、物理・生命科学・地球科学などの幅広い分野を扱うオープンアクセスジャーナル「iScience」に掲載された。
ほ乳類の受精卵(初期胚)は、受精後34日後に将来胎児へ発育する「胚盤胞」になり、その中ではICMとTEに分化する。この最初の分化がどのようにして決定されるのか、ICMとTEがきれいに2つに分かれる仕組みやICMが1か所に集まる仕組みなど、わかっていないことは多い。もし最初の分化や胚盤胞の形成に地球の1G環境が関与している場合、微小重力環境では初期胚が正しく発生できない可能性がある。
-
ヒトを含むほ乳類の初期胚の最初の分化。受精卵は8個に分裂するまで(8細胞期)は全細胞が同じ状態(未分化)だが、胚盤胞へ発生する過程で最初の分化が行われ、ICMとTEに分かれる(出所:山梨大プレスリリースPDF)
そうした中、研究チームは以前からほ乳類の宇宙生殖に関する研究を行ってきており、地上で疑似的な微小重力環境を用いて実験を行ったところ、初期胚が正しく発生できない可能性が示されたことから今回、実際に宇宙で確かめることにしたという。
しかし、マウスなどを宇宙で交配させることは難しく、ほ乳類の宇宙生殖実験はほとんど行われたことがない。また、マウスの卵子や初期胚は0.08mmと非常に小さく、高度な操作技術を習得しなければ扱えないため、初期胚を用いた宇宙実験も実施できていなかった。
そこで今回は、誰でも説明書を読むだけで簡単に、凍結受精卵の解凍や、その後の培養が可能な「宇宙胚解凍培養デバイス」(ETC)を開発。なおISSでは、受精卵の凍結保存用の液体窒素(-196℃)を扱えないことから、ETCには理研 BRCで開発された-80℃で凍結保存できる「HOV法」が採用された。
2021年8月28日、1つのETCにマウスの凍結2細胞期胚が90個入れられ、合計8個がISSへと届けられた。同年9月6日に、星出彰彦宇宙飛行士によって初期胚が解凍され、世界初となる、微小重力環境でのほ乳類初期胚の培養実験が開始された。
-
(A)凍結前のマウス2細胞期胚。(B・C)今回開発されたETC。(D)ISS内で星出宇宙飛行士が、ETCを使って胚の解凍と培養を行っている様子。(E)地上で発生した胚盤胞。(F)ISS内の人工1G環境で発生した胚盤胞。(G)ISS内の微小重力環境で発生した胚盤胞。これらの胚盤胞は化学固定されているため平たくなっている。画像提供:A~C、E~G:山梨大、D:JAXA/NASA(出所:山梨大プレスリリースPDF)
4つのETCは微小重力環境で(宇宙0G区)、残りの4つは「きぼう」内の人工重力発生装置による擬似1G環境で培養された(宇宙1G区)。さらに、筑波宇宙センターでも4つのETCにより培養が行われた(地上1G区)。培養開始から4日後、ETCへ化学固定液(低濃度ホルマリン)を注入して胚が固定され、冷蔵庫で約3週間保存後に帰還船に載せて地球に戻された。地上1G区では回収できた胚のうちの82個(61.2%)が、宇宙1G区では19個(29.5%)が、宇宙0G区では17個(23.6%)が胚盤胞となっていた。
次に、宇宙0G区の12個の胚盤胞を使って、ICMとTEへの分化やDNA損傷率が調べられた。すると、両1G区の結果とほぼ一致し、胚盤胞の品質に差はなかったとした。宇宙0G区の残り5個の胚盤胞は網羅的遺伝子発現解析が行われ、両1G区と有意に変化した遺伝子発現は見られなかったという。
しかし詳細な観察から、宇宙0G区の胚盤胞の12個中3個(25%)でICMが2か所に分離していたとする。一方、両1G区ではそのような胚は6~7%と少数だった。通常、ICMは胚盤胞の1か所に集まっており、もしICMが2か所に分離してしまうと、一卵性双生児として産まれてくる可能性があるとした。
また、ICMがなぜ胚盤胞の中で1か所に集まるのかが不明なことから、地上で胚盤胞を培養液の上層にそっと置き、底に沈んだ時のICMの位置が調べられた。すると、90%の確率でICMは胚盤胞の下部に位置することが判明。もしICMが重力によって胚盤胞の底に集まっているのであれば、微小重力環境ではICMが胚盤胞の中で1か所に集まるのが難しくなるかもしれないという。
今回の研究で、微小重力環境においてほ乳類の初期胚が胚盤胞期まで発生できることが確認された。しかし、本当に正常であることを調べるためには、胚盤胞から産仔を産ませる必要があるとする。将来的には、ISSで発生した胚盤胞をISS内で再凍結し、地上に持ち帰り、レシピエント雌の子宮へ移植して子供を産ませる研究を行う必要もあるだろうとしている。
-
ISS内で発生した胚盤胞の品質。(A~D)胚盤胞のICMとTEが染色されたもの。(A)地上1G。(B)宇宙1G。(C・D)宇宙0G。(E~H)γH2A.x蛍光免疫染色によりDNAダメージが検出されたもの(ICMも同時に観察)。(E)地上1G。(F)宇宙1G。(G・H)宇宙0G。(D・H)ICMが分離しているのがわかる。(I)胚盤胞のICM、TE、総細胞数のグラフ。X軸の1gは地上1G、a1gは宇宙1G、μgは宇宙0G。(J)ICMが分離していた胚盤胞の割合。Dishとは、通常の培養方法で発生させたもの。地上1GおよびDishは追加実験が行われ、合計300個以上の胚盤胞が調べられた。(K)網羅的遺伝子発現解析の主成分分析。宇宙0G(μg:青色のだ円)で発生した5個の胚盤胞はいずれも、地上1G(Ground control:茶色の円)および宇宙1G(Artificial-1g:赤い円)の内側にあり、差が無いことが示されている。画像提供:山梨大(出所:山梨大プレスリリースPDF)
また今回は、一卵性双生児の出現頻度が高まる可能性が示されたが、ETCから回収できた胚盤胞の数が少なすぎて、この結果が本当に正しいかどうかは不明とした。もっと多くの胚をISSで胚盤胞へと発生させ、その品質を調べる必要があるとしている。
それに加え、ETCはまだ完成されたものではないため、すべての胚を回収でき、胚盤胞へ発生させられるデバイスを開発できれば、今後の宇宙実験でより多くの胚盤胞を得られ、確固たる証拠を出すことが可能になるはずとしている。