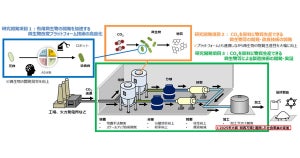島津製作所は、ヒトの腸内環境を再現した細胞培養装置である「腸内細菌共培養デバイス」のテスト販売を開始したと発表。有酸素、無酸素空間を1つの培養容器内に実現し、「酸素が必要な腸管上皮細胞」と「酸素のない環境を好む腸内細菌」の共培養が可能になったとした。
同製品の基礎技術は、京都大学生命科学研究科 片山高嶺教授との共同研究によるもの。また同製品を試用した森永乳業の研究成果は4月13日に科学雑誌「Frontiers in microbiology」に掲載された。
また、6月27日〜28日開催の「第27回腸内細菌学会学術集会」にて京都大学の片山教授、慶応義塾大学薬学部の長谷耕二教授、金倫基教授らとの共同研究の成果および同製品の発表を行う予定だという。
腸内細菌は、糖分やアミノ酸、食物繊維を摂取し、代謝物として乳酸や酢酸、ビタミンなどさまざまな物質を生産。そして、代謝された物質を腸の表面部分(腸管上皮細胞) が吸収することで全身に作用することが近年、知られるようになってきた。。
この相互作用を確認するためには「血流から細胞へ酸素が供給される有酸素(好気)環境」と「腸内細菌の生息に適した無酸素(嫌気)環境」の再現が必要とされるが、従来、腸管上皮細胞を培養しつつ環境をコントロールすることは困難だったという。
そうした中で同製品は、独自開発の培養容器によって実際の腸管に近い環境を作り出し、腸管上皮細胞と腸内細菌の相互作用の評価を可能にしたとのこと。
シート状に培養した腸管上皮細胞を培養容器にセットし、腸管腔側には腸内細菌と細菌用培地、腸組織側には細胞用培地を使用。仕組みとしては、空間を無酸素状態に保つ容器である嫌気チャンバー内に設置することで腸管腔側は無酸素状態を維持し、酸素を含んだ細胞用培地を封入することで腸組織側に酸素を供給するとしている。
通常、細菌が過剰に増殖すると腸管細胞が死滅してしまうが、新鮮な細菌用培地を継続的に供給する機能が過剰な腸内細菌を押し流すことで、3日間以上の長期間実験を実現。腸管上皮細胞のTEER計測機能も搭載しており、培養中に細胞が死滅していないかなどの状態確認もできるという。
なお、同社は同製品が使用される細胞培養実験後に得た、腸内細菌から産出された代謝物や菌数の変化の情報、腸管上皮細胞を介し体内に取り込まれる物質などの情報を、高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS)やガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で分析していくことで、今後の人体に対して影響を与える代謝物の解析をはじめとする研究につなげたいとしている。