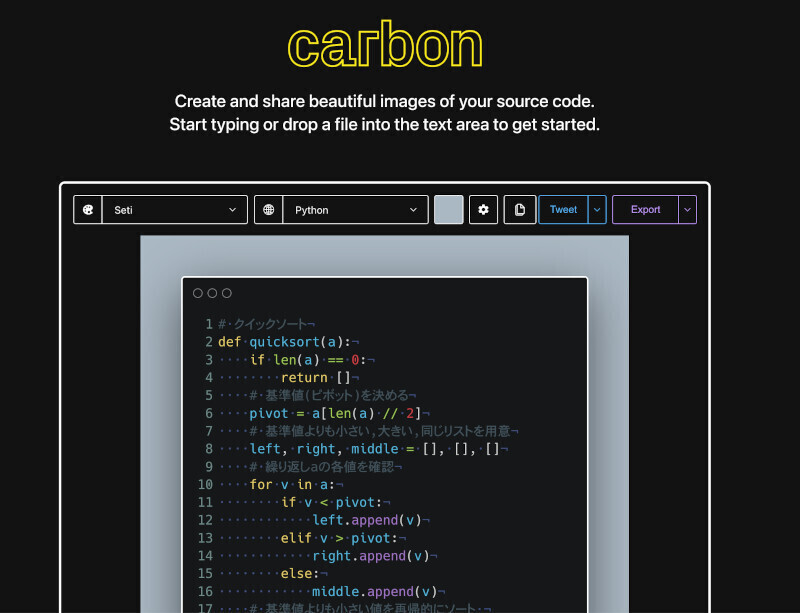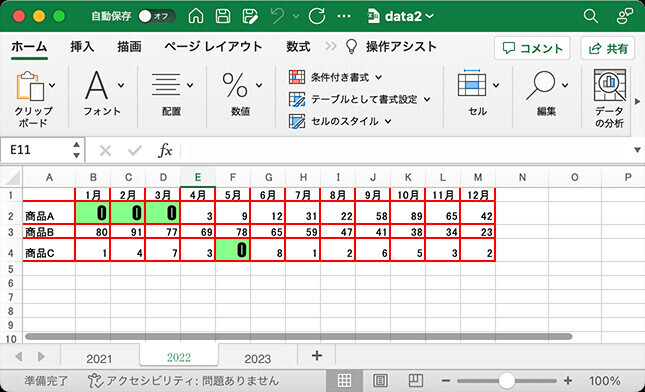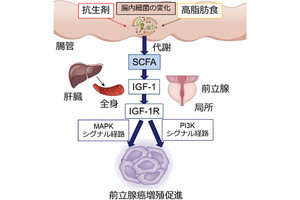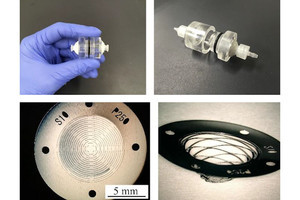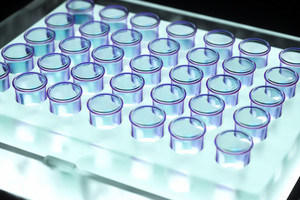京都大学(京大)ならびに東京大学(東大)を中心とする研究グループは、腎盂や尿管の尿路上皮に発生する予後不良ながんである「上部尿路上皮がん」の腫瘍検体および術前に採取した尿を用いて大規模なゲノム解析を行った結果、遺伝子変異に基づき、異なる生存率を示す5つの分子病型に分類できること、ならびに術前の尿中にはがん組織と同一の遺伝子異常が認められ、上部尿路上皮がんの精度の高い診断が可能となることを証明したと発表した。
同成果は、京都大学大学院医学研究科・腫瘍生物学講座の小川誠司 教授(兼:京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)主任研究者)、同 藤井陽一 研究員(兼:同所属研究者)、東京大学大学院医学系研究科・泌尿器外科学分野の久米春喜 教授、および東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センターの宮野悟 教授(研究当時、現:東京医科歯科大学 M&D データ科学 センター長)らを中心とする研究チームによるもの。詳細は米国の国際学術誌「Cancer Cell」にオンライン掲載された。
腎盂がんや尿管がんの総称である上部尿路上皮がんは、10万人あたり0.5~2人程度と希少であり、遺伝学的な背景は十分に解明されていないながらも、非浸潤がんであっても浸潤がんであっても腎尿管の全摘出が必要とされ、腎不全や透析のリスクなども生じることが知られている。
また、診断方法としては、非侵襲的なものとしては尿細胞診や超音波検査があるが、その診断精度は膀胱がんと比べて低いとされているほか、侵襲的な手法としては腎盂尿管造影尿管鏡を用いるが、診断時のステージIIIやステージIVである割合は高く、臨床における大きな問題となっているという。
そこで今回、研究チームでは、がん組織のDNAならびにRNAをマルチオミックス解析ならびに東大医科学研究所のスーパーコンピュータ「SHIROKANE」を活用することで調査を実施。その結果、199例の上部尿路上皮がんに対し、全体の5%程度に著しく遺伝子変異が多い状態であることが判明したほか、遺伝子変異数は膀胱がんよりも少ないことが判明。高頻度変異症例では生殖細胞系列のミスマッチ修復遺伝子変異が多く認められ、こうした状態はリンチ症候群の関連疾患であることが示されたという。
遺伝子異常の多さに着目し、さらに調査を進めた結果、上部尿路上皮がんにおける重要なドライバー遺伝子26個の同定に成功。これらは膀胱がんにおけるドライバー遺伝子とほぼ同一なものであったという(26個中23個が同一遺伝子であったという)。また、各がんごとに遺伝子異常の頻度が異なっていることも判明。解剖学的部位により、同じ上部尿路上皮がんといっても、高頻度に変異しているドライバー遺伝子が異なることも判明したという。
遺伝子変異による病型分類としては、遺伝学的特徴により、高頻度変異型、TP53/MDM2変異型、RAS変異型、FGFR3変異型、トリプルネガティブ(これらのいずれの遺伝学的特徴も持たない病型)の5つの分子病型に分類できることが示され、それぞれが特徴と有しているという。また、興味深いのは高頻度変異型とFGFR3変異型の5年生存率は90%以上あるが、それ以外の型では低くなることも判明。生存率低下に影響を与える因子を調べたところ、高頻度変異型とFGFR3変異型はコピー数の異常が少ないこと、RAS変異型はCpGアイランドと呼ばれる遺伝子発現の制御領域のメチル化が亢進している傾向にあることなどが判明したという(ただしトリプルネガティブは症例数が少なく有意差がみられなかったが、恐らくは有意差が生じるはずとの見方を研究チームでは示している)。
さらに研究チームは、上部尿路上皮がんは、遺伝子を調べれば手術前に分かる可能性を探索するために、尿にがん細胞が混じってくるのではないかと考え、尿の中の細胞を集めて、遺伝子変異を調査。その結果、尿中から82.2%の症例でがん部と同じ遺伝子変異を検出することに成功。尿細胞診による感度が32.9%程度であるとしており、有意に高い値が示されたとする。また、これらの遺伝子異常は上部尿路上皮がん患者の術後に採取した尿や上部尿路上皮がん以外の疾患の患者さんから採取した尿からはまったく認められなかったとのことで、従来、信州型で調べていたものが非侵襲型で、かつ高い精度で調べることができる可能性が示されたとしている。
ただし、研究チームによると今回の成果について、コンセプトとして、従来の尿細胞診よりも高い確率で上部尿路上皮がんの診断が非侵襲的に調べることができたものであるとしており、ただちに臨床応用することはまだ難しいとしているが、一方でどういうタイプのがんなのかまで分かることは、治療方針の策定などにもつなげることができるほか、手術後のフォローなどにも使えることが期待されるとしている。