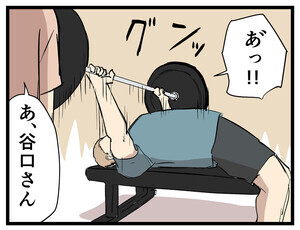|
---------------------------------------------------------------------------
初恋、初体験、結婚、就職、出産、閉経、死別……。
人生のなかで重要な「節目」ほど、意外とさらりとやってきます。
そこに芽生える、悩み、葛藤、自信、その他の感情について
気鋭の文筆家、岡田育さんがみずからの体験をもとに綴ります。
「女の節目」は、みな同じ。「女の人生」は、人それぞれ。
誕生から死に至るまでの暮らしの中での「わたくしごと」、
女性にとっての「節目」を、時系列で追う連載です。
---------------------------------------------------------------------------
名前をつけてやる
入江紀子の漫画『のら』の主人公には、名前がない。天涯孤独で戸籍や住民票を持たず、住所不定かつ年齢もよくわからない、野良猫のような女の子が、さまざまな人の日常生活に「居候のプロ」として一時的にもぐりこみ、そしてまたふと居なくなる、短編連作集である。
私が初めて読んだのは創刊間もない『コミックガンマ』誌上で、時系列を辿るとおそらく12、13歳の頃だったと思う。中学生になりたての時期、作中にもたくさん登場する普通の少年少女と同様、漠然と家出したくてたまらない時期だ。生まれた家庭と育ての両親に縛られた生活を捨てて人生をリセットし、自由気ままに生きられたらどんなにいいだろう、と思っていた。そして作中の人々と同様、「のら」が語る不思議な言葉に耳を傾けてその考えを改め、結局は自分の人生に戻っていく。
「名前、ないの。すきに呼んで」――コミュニケーションの第一歩として名前を問われると、「のら」は大抵、こう答える。作中の登場人物たちは、訳アリで本名を隠したがっている家出娘だろうと勝手に慮り、適当な名前をつけて呼びはじめる。連作を読みつぐ読者だけが知っている。彼女には、本当に、故郷も家族も名前も、何もないのだ。それはつまり、自分自身の人生を持たないということでもある。フーテンのフー子と呼ばれれば出たきり戻らず、男と対になる名前がつけば彼に恋をする。小説に書かれて広く読まれるようになると、また本人の姿が消える。まるで最初からノンフィクションの現実世界には存在していなかったかのように。
誰かの生活にほんのちょっと割り込んで好意に甘え、どこにも根を下ろさずに、宿のない日は一晩中、街を歩き続ける。車寅次郎のような男が惚れる男の放浪者と同じようにはいかず、「のら」は野宿中の公園でレイプされたり、引きこもりの家に軟禁されたりもする。彼女のように生きていけたらいいなぁと憧れる一方で考える、もし本当に私が彼女なら、きっと早々にくだらない理由で野垂れ死にするだろう。
なぜなら、私には私の名前があるから。それはすなわち、私は私自身の、一続きの人生を持っているということである。始まりも終わりもなく、たくましくて儚く、おそろしく強運な「のら」のブツ切れになった人生とは違い、私には、ずっと呼ばれる続ける名前がある。たとえ親から授かったものであろうとも、それは死ぬまで「私のもの」だ。私には私の名前と人生があり、その背負い込んだ荷物を必死で守ろうとする限り、どこを彷徨ったって野良にはなれずに、手前で死ぬだろう。あたたかい灯りの点る屋根のついた家と自動的に出てくる晩ごはんを噛み締めながら、中学生の私はそんなふうに考えていた。
誰が殺した黒歴史
私の人生には、名前がついている。名前がその人間を規定する。『のら』を読んでいた12歳は、そう気づいた年頃だった。名前とは自己と他者とを区別するだけでなく、私が生きる道筋の「連続性」を示すものでもある。12年分引きずってきた荷物の重みは、今すでに結構しんどい。みんなとお揃いのランドセルを下ろして、通学カバン自由の中高一貫校へ上がり、伸びた背丈のぶんだけ目方も増えて、干支が一巡りすれば、「たった12年で、こんなに人生が重くなるの?」とそろそろ気づく年頃だった。
進学した私は、小説が書きたくて文芸部に入部した。部員が執筆した詩や小説を手作りの文芸誌にまとめて、文化祭で来場者に頒布するのが主な活動だ。作品を発表する際、本名を使用する部員は一人もいなかった。みんな原稿の中身以上に凝ったペンネームをつけて、時には複数のペンネームを持つことで複数の人格を使い分けたりもした。部活だけではない。雑誌やラジオ番組へのハガキ投稿、同人誌即売会への出展や、バンドのおっかけ。学校で禁止されていたさまざまな課外活動をするとき、私たちはいつも、専用の架空の名前を作ってそれを名乗った。
辞書で引いた難訓漢字、好きなキャラクターから一文字、尊敬する文豪と同じイニシャル、画数占い、相性占い、欧文の綴りまで気にして、中二病全開でいろいろな名前を考案した。思いついた名前の数が思いついたお話の数を上回ったら、物語の登場人物にどんどんつけてみたり、書き進めるうちに気に入ってやっぱりまた自分で名乗ったり。自分ではない自分の名前を、人格を、人生を、物語を作り出すことに熱中した。
10代の頃に考案したこれら複数のペンネームを、私は未来永劫、明かすことはないだろう。当時の私がGoogleの検索範囲に及んで現在の私と紐付き、永久に消せなくなることなど、あってはならない……。まぁ「黒歴史」とまでは言わないけれど、「あのキラキラした名前の軽やかな彼女たちは、かつては私の一部だったが今はもういない、銀の銃弾に心臓を撃ち抜かれ、塵となって消えました」と言っておきたい。
だから、いい大人になってから突如として珍妙なハンドルネームを名乗り、インターネット上で面白おかしく反社会的かつ非現実的な振る舞いを謳歌して、もう戻ってこられないところまで行き着いた時点でいきなり「ネット人格と実人生とが乖離しすぎてしまった」「素性を明かして本業の宣伝活動もすべきか悩む」「やっぱり改名したので過去のことは忘れてほしい」「母親にバレそうなので来月アカウントを消す」などと往生際の悪いことを口にする人たちを見ると、少しは同情するけれども、あまりにも無防備すぎるだろ、と腹立たしくもなる。
そうした自意識の統合作業というものは、せいぜいが中学生くらいまでの間に手痛い経験を済ませておくべき、いわば義務教育の範疇ではなかろうか。オフ会で自己紹介するとき、職場の上司にバレたとき、呼ばれて恥ずかしくなるようなハンドルネームはつけないに限るし、実名顔出しでマスコミ記者会見を開いたって胸を張って堂々と同じことを口にできる、そんな発言しか書かないのが、何よりの護身術である。閑話休題。
なんだかそれは特別な響き
高校へ上がって部長を務めていた頃だろうか。新入部員の後輩に、「部内誌の原稿って、本名で書いちゃいけない決まりでもあるんですか……?」と怪訝な顔をされたことがある。心のきれいな少年に「王様は裸だ」と言われたような気分だった。どうせ部員数も頒布数も少ないし、筆跡や文体ですぐバレるし、内輪しか読まないのだから、最初から本名で書いても同じではないか。そうツッコミを入れられる12歳を眩しく感じた。数ヶ月後、その子もまた、初めて作った意欲的なキラッキラのペンネームを冠した処女作を提出して「こちら側」へ渡ってきたのだが、少し申し訳ない気持ちになったのを覚えている。
「だって、本名だと気恥ずかしくて書けないような物語も、ペンネームなら自由に書ける気がするじゃない?」「親が勝手につけたダサい本名なんか知られたら、せっかく作った夢物語が壊れるじゃない?」「漱石も、鷗外も、吉本ばななもペンネームだよ、そのほうがプロの作家っぽくてカッコイイでしょ?」……どう答えてみても、露見するのは裏返しになった「本名で生きる自分」の冴えない現実。ペンネームをかぶせることによって覆い隠したい、恥ずかしさ、不自由さ、ダサさ、夢のなさ、素人臭さ、子供っぽさ、カッコ悪さ、なのである。
一方で、こんなこともあった。大好きなバンドのラジオ番組にファックスを送ったら、一人がその投稿を読み上げ、「ラジオネーム、◯◯◯ちゃん。へー、かわいい名前ですねー」と言ったのだ。妹と聴いていた私は、文字通り、子供部屋で飛び上がって狂喜した(かわいい中学生ですねー)。自分が送った質問に対する回答などろくすっぽ聴いていなかった。今、褒められたのは、私が自分で考えた、私の名前だ。
学校の成績や素行や身だしなみといった「正解」を知っている設問で花マルをもらっても、褒められているようには感じなかった。洋服や髪型はまだ親の厳格なコントロール下にあったから、容姿外見にお世辞を言われても自分の手柄とは思えなかった。小遣いで買った文房具などを友達から羨ましがられるのは、それに比べればかなり気分がよかったが、所詮は既製品の消費に過ぎない。同じ店で同じ金額を払えば、友達も明日から同じものが手に入る。ああ、だけど今、この人が褒めてくれた名前は、何もないところから自力で作った、紛うことなき「私のもの」だ。ありがとう、谷中敦!
この世界のどこかにいる、まだ見ぬ誰かに、私のことを見つけてほしい。気づいて、認めて、評価して、褒めてほしい。だけど「本当の自分」のことは知られたくない。私の最も魅力的なところ、一番いいカッコ、学校や保護者の手を離れて私自身が自由にコントロールしている私の姿だけを、見てほしい。「コーデリアが無理なら、せめて最後にeのつくAnneと呼んで」。10代はつくづく、毎日が自己顕示欲との戦いだったなぁ、と思う。
そして誰でもない私に
名前のない女の子に憧れて、たくさんのペンネームを命名していた頃。それは「人生をリセットしたい」と思っていた頃だ。心機一転の中学進学といっても、小学校までと何も変わらない。きっと高校もこの調子だろう。激しい受験を勝ち抜いてきた外部生にも、燃え尽きたような表情の子が少なくなかった。
そして中二病に集団感染した。ギャルからオタクまで、教室内のどのグループにおいても、絶望と頽廃と死を匂わせるものがやたらと流行していた。主人公が無残に殺されて終わる漫画、30以上を信用せずに20代で命を絶ったロックシンガー、銀の皿に載せた愛する男の首を所望する姫君の話、愛する姫君のため自分の両眼を潰した男の話、盗んだバイクで走り出して死んだとってもいい奴の話。デカダンに殉ずればよいのだ、どうせ私が19歳の夏にはノストラダムスの予言が的中して、みんなみんな終わるのだから(かわいい中学生ですねー)。
たくさんの使うあてのない「名前」を作る行為は、そんな死を想う毎日の中で唯一、なんだかとても生産的で創造的な営みである気が、していた。私の人生には、名前がついている。私一人にたくさんの名前がつけば、私は一度にたくさんの人生を生きることになる、気がする。与えられた運命を超えた存在になれる、気がする。なぜなら、名前がその人間を規定するから。
死のう、死のう、死ね、殺せ、殺せ、殺してくれ、と考えながら一方で、生きよう、生きよう、生きよう、といくつも名前を作っていた。自分の名前を大切にすることは、自分を大切にすることだ。自分が作った、まるで自分でないようなキラッキラの名前を大切にすることは、そのキラッキラの誰かに生命を与え、人生を与え、そしてそれを我がことのように大切にすることだ。「私が私として、手段を問わず、この生を全うする」ことに幾許かの愛着を抱き、ちょっとうんざりして投げやりな態度を見せながらも、改めてこだわりはじめたのが、ちょうど12歳だった。
昔の子供が「元服」して「世に出る」ために「名を改める」のがこの年頃からというのは、なんとなく頷ける気がするし、昔の子供もこの年頃に、自分の引きずる荷物の重みに、初めてびっくりしたのかもしれない。そしてやっぱり、人にはとても読ませられない恥ずかしい日記とか、綴っていたのだろう。今も昔も、名もなき野良猫になれない人間は、そうやって人生に折り合いをつけていく。
<今回の住まい>
この頃、実家の改築が終わるまでの期間、5人家族で父方の祖父母の家に間借りしていたことがある。元は叔母のものだった部屋や祖父の書斎、応接間をあてがわれ、入浴や食事のタイミングをずらし、実家とは違う慣れない生活臭が漂う家に、縮こまるようにして暮らした。本当はビートルズが聴きたかったのに荷物にはジョン・レノンのCDしかなく、仕方なく「Mother」ばかり聴いて発狂しかけたのを懐かしく思い出す。以来、ポール派である。
岡田育
1980年東京生まれ。編集者、文筆家。老舗出版社で婦人雑誌や文芸書の編集に携わり、退社後はWEB媒体を中心にエッセイの執筆を始める。著作に『ハジの多い人生』『嫁へ行くつもりじゃなかった』、連載に「天国飯と地獄耳」ほか。紙媒体とインターネットをこよなく愛する文化系WEB女子。CX系の情報番組『とくダネ!』コメンテーターも務める。
イラスト: 安海