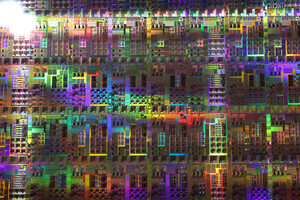私がこの最終章でメインに話したいのは正確には法廷闘争ではない。何故なら、この件についてはインテル側が法廷闘争にもつれ込むのを嫌って事前に和解したからである。2009年のことである。当時の円換算で1250億円の大金を和解金としてキャッシュでAMDに支払った。これはAMD側の一方的勝利であった。言い方を変えれば、インテルはAMDが訴えた通りのことをしたので、法廷審理が始まると不利になると判断し事前に和解したということである。この辺のいきさつについて、できるだけ正確に記録しておこうというのが、この最終章の目的である。
この和解した事件は、内容的には独占禁止法についてであり、半導体業界によくありがちな特許、著作権など知的所有権に関する法廷闘争ではない。しかし、かつてAMDとインテルは半導体業界に典型的な知的所有権がらみの闘争に明け暮れた時期があった。最終章第2話では、その歴史を簡単に解説しておきたい。一般に、半導体業界で繰り広げられる法廷闘争の数々には次のような共通点が多い。
- 法廷闘争中は両社の弁護士同士で法律用語が行き交うので、普通のエンジニア、マーケッターには内容はちんぷんかんぷん。
- 半導体の技術革新、業界の変化のスピードにはお構いなしに法廷ではマイペースに手続きが進められるので、ほとんどの場合、法廷闘争の結果が実際のビジネスに影響するにはタイミング的に大きなズレが生じる。
- 訴訟が発生する理由は、競合が明らかに知財を侵害していると思われる場合、あるいは、現在は圧倒的な市場シェアを持っている大手が、このまま放っておくと後でビジネスに大きく影響してしまうと思われる新興勢力の出現に懸念を持った場合が多い。
- 訴訟には多大な金がかかり、結局弁護士事務所が儲かるだけである。訴訟をやり続けるメーカーの製品を買うカスタマー側には不安要素が増し大変な迷惑な話となる。
簡単にAMDとインテルの法廷闘争の前史をまとめると次のようになる。
1985年 インテルが80386を出荷
1990年 AMDが80386互換品Am386を出荷開始(このいきさつについてはこちらを参照)
1991年 インテルがAm386を著作権侵害で提訴、インテルはAm386の出荷停止を要求
1992年 米カリフォルニア州連邦裁判所の仲裁人がAMDのAm386の製造・販売権を認める裁定
1992年 同じ裁判所の陪審員がAMDのマイクロコード権利を認めず、AMDはAm486出荷延期
1992年 上記の裁判においてAMDが逆転勝訴、AMDに著作権が認められ、Am486出荷開始
これだけ見ても何のことかよくわからない読者が多いと思うので、以下に解説する。
- インテルが80386を出荷開始したのは1985年で、AMDはインテルのセカンドソース契約に基づいて互換品を開発出荷できていたら、その翌年くらいには出荷を開始できたはずである。
- しかし、インテルがセカンドソース・ライセンス契約を一方的に破棄したため、AMDは独自でAm386を開発しなければならず、その発表が1990年までずれ込んだ。
- インテルはAMDが独自開発品Am386を発表して、インテルのシェアを奪うと見るや否や、著作権侵害でAMDを提訴。出荷停止を要求。その間、カスタマーは非常に不安になった。特に日本のカスタマーは慎重に対応したので日本市場におけるAMDのCPUビジネスは大きく遅れることとなった。
- 裁判手続きでは調停人の作業と陪審員の裁判が平行して進み、調停人がAMDに権利を認めたにもかかわらず陪審員は認めず、AMDは次期製品のAm486の出荷を延期せざるを得なくなった。陪審員裁判というのはハイテクの裁判には向かないことが多い。
- 最終的にはAMDの逆転勝訴で(この裏にはインテル側の決定的証拠の故意の未提出があった)最終的に決着。それ以降のAMDとインテルは著作権問題についてこれ以上争わないことを合意。その後、この問題は2社間においては消滅した。
とまあ、こんなわけであるが、さらに単純化して説明するならば、AMDは互換品のビジネスをAm386からAm486に至るまで知的所有権の領域においてインテルから徹底的に邪魔されたわけで、その解決まで足掛け7年もかかったことになる。日進月歩の技術競争に明け暮れる半導体業界において7年というのはとてつもなく長い期間であり、今から思えばAMDはよく廃業に追い込まれなかったなと感じる。その間のAMDが被った機会損失には多大なものがあり、何よりも、その間独占市場に頼らなければならなかったカスタマーはいかに高い値段でインテルから製品を買わされていたかが容易に想像できる。私は、この時からインテルの市場独占と錬金術のような利益率が確立されたのだと思っている。
インテルにビジネスを邪魔されたのはAMDだけではなかった
実際にこのインテルの著作権法攻勢によってCPUのビジネスから撤退を余儀なくされた企業もある。その代表格はNECである。ここで著作権といっているのは、マイクロコードと呼ばれるCPU回路に命令を出すソフトウェアのことをさす。CPUの黎明期には今のようにハードウェアとソフトウェアのはっきりとした業界レベルの垣根がなく、ハードウェアを実際に動かすために必要なソフトウェア(ファームウェア)などは元々ただでついてくるという認識しかなかった。
NECの場合、優れたx86互換CPU製品V20/V30を持っていたが、インテルの著作権侵害の裁判攻勢にあってインテル互換品のビジネスから撤退することになった。最終的にはかなり後になってNECが勝訴したが、長引く裁判の最中はNEC側が積極的に販売を控えたこともあって、こういうことになった。これが象徴しているのは、NECは裁判には勝利したがビジネスでは敗退したということである。もしNECがこの著作権侵害の法廷闘争を跳ね返し、全社を挙げてインテルと真っ向勝負していたら、当時の両社の規模を考えたらインテルは存在していなかっただろうなどと楽しいことを考えてしまう。勿論タラレバの話であるが…
著者プロフィール
吉川明日論(よしかわあすろん)
1956年生まれ。いくつかの仕事を経た後、1986年AMD(Advanced Micro Devices)日本支社入社。マーケティング、営業の仕事を経験。AMDでの経験は24年。その後も半導体業界で勤務したが、今年(2016年)還暦を迎え引退。現在はある大学に学士入学、人文科学の勉強にいそしむ。
・連載「巨人Intelに挑め!」記事一覧へ