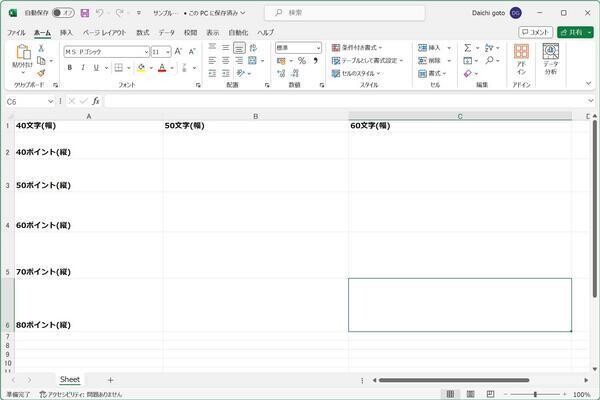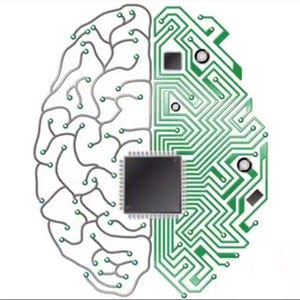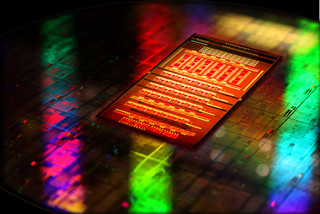筑波大学は、誘電率の変化を伴う絶縁体・半導体の熱によるスイッチと反磁性・量子磁石の光スイッチを共に示す「1次元鎖型金属錯体(分子ワイヤー)」の開発に成功したと発表した。このように1分子で磁性・電気伝導性を自由に切り替えられる物質は、1次元鎖型化合物としてははじめてだという。
成果は、筑波大数理物質系の大塩寛紀教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間9月17日付けで英国科学雑誌「Nature Chemistry」オンライン速報版に掲載された。
省エネルギーかつ大容量の情報処理技術を開発するためには、集積型電子回路の微細化が最重要課題だ。半導体の処理性能は「ムーアの法則」にしたがい向上してきたが、近年プロセス微細化の限界や物理的な諸問題によって、近い将来に限界に達することが懸念されるようになってきた。こうした状況の中で、究極の集積型電子回路として期待されるのが、「分子回路」だ。分子回路を構成する最も重要な要素の1つが、分子素子をつなぎ合わせる配線の役割を果たす「分子ワイヤー」だ。
分子ワイヤーの候補としては、1次元鎖型構造を持つ電気伝導性分子が、これまで数多く開発されてきた。しかし、分子ワイヤーそのものがスイッチング機能を持つ「素子」として機能する「機能性分子ワイヤー」の開発は、これまで例がなかった。
そうした中で大塩教授らは今回、外部刺激で電気伝導性と磁性が同時に切り替わる、新しい分子ワイヤーの開発に成功したのである。これは、異なる酸化鉄を持つ2種類の金属イオンを有機分子でつないだ1次元鎖型分子を合成することで達成されたものだ。
適切な有機分子でつながれた2種類の金属イオンが異なる酸化鉄(例えば、M2+とM3+)を持つ場合、金属イオンの種類が同じであれば、2つの金属イオンの間を電子は自由に動くことができる。一方、金属イオンの種類が異なる場合(今回はコバルトと鉄)は、通常ならば電子は動けない。
これまで大塩教授らは、金属イオンを取り囲む有機分子の性質と電子の動き方の関係を詳細に調べてきた。その結果、最適な有機分子を使用すれば、外部刺激を加えることで電子の場所をコバルトから鉄、もしくは鉄からコバルトへと自由に動かせることを発見したのである。
今回の手法を1次元型錯体に適応することにより、分子中の電子の場所を熱や光で自由に動かすことが可能となるというわけだ。
さらに今回の研究では、電子がコバルトにある場合(高温相)と鉄にある場合(低温相)とでは、1次元鎖型分子の性質が大きく異なることも判明した。電子が鉄にある低温相では、1次元鎖型分子は反磁性を示し、電気をまったく流さない絶縁体だったのである。
ところが、コバルトに電子が移動した高温相は室温付近で常磁性を示すだけでなく、電気を比較的よく流す半導体になることがわかったのだ。
この高温相における半導体挙動は、交流電場を用いた測定から検討した結果、コバルトイオンと鉄イオンの間の電子の移動が、1次元鎖構造中を伝播するメカニズムで説明できることも判明した。また、高温相と低温相は、温度を変えることで自由にスイッチの切り替えが可能だ。つまり、この1次元鎖型分子は、温度を変えることで磁性・電気伝導性・誘電性のスイッチを切り替えられるのである。
さらに、極低温でこの分子に光を照射すると、鉄からコバルトに向かって選択的に電子が動くことも今回の研究で発見された。その結果、光で生成する高温相では、分子中のスピンがすべて同じ方向にそろった状態となり、スピンの反転が凍結された磁石のような状態になることが明らかとなったのである。
通常の磁石は、すべてのスピンがそろった状態を極めて安定に保っており、スピンが反転することはない。しかし、この1次元鎖型錯体の構造は、1本の鎖状の形状をしているため、外部刺激に応答して量子磁石になるというわけだ。
なお、今回開発した1次元鎖型錯体の電気伝導性はまだ低く、分子ワイヤーとして応用するにはより高い電気伝導性を得る必要があるという。
ただし、この1次元鎖型錯体の最大の特長の1つは、金属イオンと有機分子の組み合わせを自在に変えることで、電子の動きやすさを調節できる点にある。今後、より適切な有機分子を用いることで高電気伝導度を達成することにより、温度・光・磁場・電場による高いスイッチング機能を持つ革新的分子ワイヤーの開発が期待できると、大塩教授らは述べている。