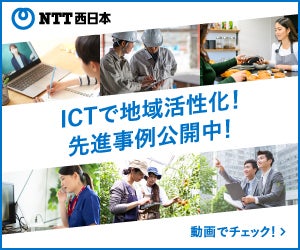広大な森林をDX(デジタルトランスフォーメーション)で“見える化”し、森林から吸収されたCO2をJ-クレジットとして活用することで、森林保護と地域経済の活性化を両立させる新たな取り組みが注目を集めている。その舞台となるのが、全国有数の杉生産地である宮崎県諸塚村である。
この地でスタートした森林・林業DX事業は、ICTを活用して森林資源情報の“見える化”を行い、さらに「J-クレジット制度」を用いてその森林が吸収するCO2量を付加価値として販売する、まさに“森林に新たな付加価値をつけて、売買を行う”もの。2024年10月には、「森林由来のJ-クレジットを活用したカーボン・オフセット付リース」として商品化がされ、第一号の契約にも結び付いた。
本記事では森林・林業DXという先進的な手法を通じ、地元の山々に新たな息吹を吹き込むプロジェクトに迫るべく、キーとなる5社にインタビューを実施。取り組みの概要や、過去の実証実験、そして将来の展望について伺った。
-

お話を伺ったのは、右から農林中央金庫 食農法人営業本部 福岡支店 九州営業第三部長の志野 英樹氏、JA三井リース九州株式会社 代表取締役社長の関 正人氏、諸塚ARCプロジェクト協議会 会長の佐藤 喜代光氏、耳川広域森林組合 諸塚支所 支所長の藤本 司氏、NTT西日本 宮崎支店 ビジネス営業部 ソリューション担当 主査の湯地 裕史氏。
・全国有数の森林所有者を抱える宮崎県の課題解決に森林・林業DXで挑むNTT西日本グループ
・J-クレジットとカーボン・オフセットで実現する森林保全活動の新モデル
・大きな進展を見せるプロジェクトのスタート地点
・地域の連携で進める森林・林業DXの現場の声
・“オール九州”へと広がる未来像と各社のビジョン
森林のライフサイクルを維持するために、必要不可欠であるDX推進
森林のライフサイクルをどのように維持していくかを考えたとき、重要な存在となるのは森林所有者だ。宮崎県では約14.5万人が森林を所有しており、宮崎県の世帯数が約47万世帯という数字を踏まえると、およそ3割が森林に関わる世帯となっている。しかし、小規模・零細なものが大半となる所有形態ゆえに、必ずしもすべての森林所有者が管理を適切に行えているわけではない。
仮に放置され森林が荒廃してしまうと、利活用の最終段階を担うステークホルダーにたどり着くこともなく、森林が起点となる木材などの物流もなくなってしまう。
そのような背景から、近年、森林のライフサイクル維持の出発点として、森林所有者の管理に対するモチベーションを高める必要があることが課題となっている。そこで欠かせないのが、DXだ。
NTT西日本グループは、森林・林業分野においてDXを推進し、森林の“見える化”を図ることで森林のライフサイクルの維持に貢献している。
「森林の健全なライフサイクルを維持するためには、デジタルの活用は欠かせません」と、NTT西日本 宮崎支店の湯地 裕史氏は語る。
NTT西日本 宮崎支店は2021年4月、耳川広域森林組合や諸塚村、宮崎大学などと連携し、宮崎県諸塚村を舞台に「森林・林業DX推進協議会」を設立した。
代表的な取り組みは、ドローンを活用した森林情報のデジタル化や森林デジタル情報を活用した森林管理、民有林の集約化による J-クレジット創出だ。
森林管理は、従来は人が山の中に入って1本ずつ樹木の計測を行い、森林資源情報を調べていたため、計測に何日もかかったり、事故に合うリスクが発生したりしていた。ドローンを活用することでこの計測をデジタル化し、森林所有者の負担を低減した。
J-クレジットの創出は、森林所有者に対して金銭的な還元を実現する仕組みを構築したのがポイントである。また、JA三井リース九州が商品化した「森林由来のJ-クレジットを活用したカーボン・オフセット付リース」により、リース契約を締結した企業が間接的に森林保全活動に貢献できる新たな取り組みにもつながることとなった。
「デジタル化を通じて、山林の所有者と利活用の最終段階を担うステークホルダーをつなぎ、お互いにWin-Winの関係を築くことが重要です」と湯地氏は強調する。
全国有数の森林所有者を抱える宮崎県の課題解決に
森林・林業DXで挑むNTT西日本グループ
この協議会において、NTT西日本グループは、J-クレジットの創出に向けた「森林・林業DXソリューション」を提供している。
具体的には、地域の森林状況に応じた森林ビジョンや森林経営計画の策定を行う森林ビジョン策定支援サービス、ドローンなどを活用し森林資源情報の計測・解析を行う森林資源解析サービス、J-クレジット制度に基づいて施策の企画立案からクレジットの創出・流通まで、一気通貫で支援するカーボンクレジット創出・流通支援サービスがある。
J-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用、そして適切な森林管理によるCO2吸収量などを、売却・移転が可能な「クレジット」として国が認証する制度である。これにより、CO2の削減・吸収量を確かな情報に基づいて取引可能となる。クレジット購入は環境活動への貢献だけでなく、企業のPRやブランド強化にもつながるとあり、購入を検討している企業も多い。
NTT西日本グループはこのサービスを通じて、適切な森林管理で創出されたクレジットによる地域の脱炭素化・企業のカーボン・オフセットを促進している。
カーボン・オフセットとは、企業などがどうしても削減しきれないCO2排出量をクレジット購入で埋め合わせる仕組みを指す。これにより、実質的な排出量ゼロをめざす活動が可能となる。
これらの取り組みは、森林保全と経済的利益を両立させる新しいモデルとして注目されている。
J-クレジットとカーボン・オフセットで実現する森林保全活動の新モデル
森林・林業DX推進協議会では、森林情報のデジタル化によって創出されたJ-クレジットを新たに商品化した。それが「森林由来のJ-クレジットを活用したカーボン・オフセット付リース」だ。
同商品は、2024年10月17日にJA三井リース九州によって取り扱いをスタートした。対象となるリース物件の使用によるCO2排出量を、適切な森林管理で得られるCO2吸収量のクレジットで相殺するもので、環境対策と地域貢献を同時に実現する仕組みとなっている。同年10月23日には、地元企業との間で第一号のリース契約が締結された。
このサービスの鍵を握るのが、農林中央金庫によるJ-クレジット取引の媒介だ。同金庫は、持続可能な森林経営や地域活性化をめざし、林業従事者の所得向上と地球温暖化対策を両立させる取り組みを推進している。
「農林水産業の発展と脱炭素社会への貢献のために、今回のプロジェクトを積極的にサポートしています」と農林中央金庫の志野 英樹氏は述べる。
一方、リースを活用して新たな商品を開発したのがJA三井リース九州だ。同社は、国内初の森林系再造林によるJ-クレジットの価値を高く評価し、リース物件との組み合わせによる地域貢献の可能性を見出した。
「この仕組みを活用すれば、リース物件の使用に伴い発生するCO2排出量を相殺できることに加えて、J-クレジットの地産地消を促すことができると判断しました。すでに契約会社様のリース社有車2台に本サービスを適用しており、PCや他のリース物件への展開も視野に入れているところです」とJA三井リース九州の関 正人氏は説明する。
また湯地氏は、これらの取り組みについて次のような見解を示す。「森林組合等を会員とする金融機関である農林中央金庫さんと連携し、地域全体を巻き込む形でこのサービスを実現できました。このような仕組みが林業の未来を大きく変える可能性を秘めていると期待しています」
本サービスのもう一つの強みは、広範囲の森林エリアをまとめて一つのプロジェクトとして扱うことで、申請コストを大幅に削減できる点だ。今回の諸塚村における取り組みでは、約150件ものクレジットを束ねて申請することで、効率的な運用を可能にしている。
申請業務を担う耳川広域森林組合の藤本 司氏は話す。「諸塚村でのJ-クレジットは、森林由来の再造林方法論として国内初の認証事例となりました。広大なエリアをまとめて一つのプロジェクトとして申請することで、申請コストを大幅に削減した、画期的な仕組みを実現しています」
森林組合のJ-クレジット創出・販売を全般的にサポートしている志野氏も「技術的にハードルが高い中で実現した意義は大きいですね」と続ける。
「こうした手法は、JA三井リースグループ内でも注目されており、全国的な展開にも期待が寄せられています」と関氏もその反響を補足した。
大きな進展を見せるプロジェクトのスタート地点
こうした一連のプロジェクトの発端は、前述した2021年にスタートした実証事業の取り組みへとさかのぼる。
実証事業では、①ドローンや人工衛星による森林情報のデジタル化、②取得した森林情報をAIによって解析・資産評価などを行いクラウド上に見える化、③地域の林業に関わるプレイヤーが取引やコミュニケーションを図るクラウドサービスの構築という大きな3本柱で森林・林業DXの社会実装に向けた実験が行われた。
発起人となった湯地氏は、「全国一の杉生産量を誇る宮崎県の地域特性に着目し、林業分野で地域DXを進め、新たな価値を創出したい」という想いで声を上げました。地域のステークホルダーと協力しながら、膝を突き合わせて課題に取り組むことで、広がりのある取り組みへと発展することができました」と振り返る。
しかし、プロジェクトのスタート当初には、多くの課題が立ちはだかっていた。
藤本氏は話す。「当時、私たちの業務の多くは紙ベースで行われており、デジタル化が進んでいませんでした。また、森林所有者の高齢化や村外在住者の増加により、現地管理の負担も大きくなっていました。これらの課題に対して、プロジェクトでは所有者がモニターとして参加し、システムの実用性を検証することで、遠隔管理の実現をめざしました」
また、諸塚ARCプロジェクト協議会の佐藤 喜代光氏も、デジタル技術の可能性を強調する。「自宅のPCから森林の状況を確認できるというのは画期的でした。また、地域の横のつながりが強い諸塚村では、多くの所有者がプロジェクトに賛同し、96名もの協力を得ることができました。この取り組みがさらに一歩進むことで、再造林のJ-クレジット創出につながったと言えます」
さらに、湯地氏は、所有者に直接金銭的な還元があるJ-クレジットの意義に着目する。「森林が育つまで40~50年以上もの期間、経費がかかるだけだった再造林が、J-クレジットを通じて所有者や後継者のモチベーションを高める仕組みを提供できるのではないかと期待しています」
このように、デジタル化を核に据えた取り組みは、地域の林業が抱える課題を解決しながら、持続可能な森林経営の未来を切り開く重要なステップとなっている。
地域の連携で進める森林・林業DXの現場の声
耳川広域森林組合と諸塚ARCプロジェクト協議会は、NTT西日本グループと共に森林・林業DXの取り組みを進めてきた。その中で、プロジェクトを並走した感想を語った。
まず、藤本氏は次のように振り返る。「NTT西日本グループの方々は非常に熱意があり、私たち現場にもやる気を引き出してくれました。また、行政データの調整やデータ収集には苦労もありましたが、そこは諸塚村の協力が非常に大きかったですね」
続いて佐藤氏は、森林・林業DXの効果について次のように述べる。「ドローンの活用により、上空から木々の本数を確認する技術を確立できました。また、所有者が世代交代を迎える中で、デジタル技術を活用した可視化が後継者の理解促進にも役立っています」
“オール九州”へと広がる未来像と各社のビジョン
森林・林業DXを軸とした取り組みは、現在も進化を続けている。各社が抱く今後のビジョンは、さらに広がりを見せているようだ。
志野氏は、2050年ネットゼロ目標についてこう語る。「森林クレジットの創出サポートを通じた森林組合の支援に加え、当金庫は金融機関として2050年の目標達成に向け、投融資先の脱炭素に向けた取組ステージに応じたソリューション提供を進めております。2028年からの炭素賦課金導入を見据え、企業によるJ-クレジットの活用も活発化すると見込まれる中、カーボンクレジットを活用したソリューションはお客様の脱炭素の取組みをサポートする重要なツールとして取組みを拡大したいと考えています」
一方、関氏は、創出されたクレジットをリースに活用するだけでなく、創出側としての役割を担い地域活性化にも取り組む意思を示す。「今回の取り組みを通じて、鹿児島や熊本の企業からも関心を寄せていただいております。いずれは“オール九州”で連携を進め、創出されたクレジットをより多くの企業に活用してもらうことで、今まで以上に地元に還元できる仕組みを構築したいですね」
佐藤氏は、資金活用の可能性について言及する。「森林所有者の中には、J-クレジットによって資金が流れてくるという仕組みに対して、まだピンと来ていない方もいらっしゃいます。今後は、資金をどう活用していくのがよいかが最も問われていくと思います。今回の取り組みを起点に、地域の理解を得ながら、地域全体で新たな価値を創出していきたいと考えています」
また、藤本氏も「もともと九州の人々は地元愛が強いですから、九州全体に広がる取り組みをめざし、クレジット創出量を増やして期待に応えていきたいですね」と語る。
そして湯地氏は、大きく2つの視点を提示する。「1つ目は森林所有者問題です。森林の情報を共有し、価値を広く理解してもらう仕組みづくりを進めていきたいです。2つ目は九州産クレジットを広げ、今回の実証事業をモデルケースとしてスケールアップすることです」
さらに湯地氏は、「林業という特殊な業界で企業間の連携が進んだのは大きな一歩です。この事業を通じて地域の可能性を広げていきます」と意気込みを語る。
これらの地域や組織の壁を超えた取り組みは、九州全体にわたる連携と持続可能な地域発展をめざす、大きな一歩となるだろう。
[PR]提供:NTT西日本