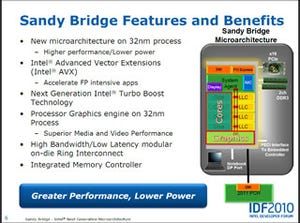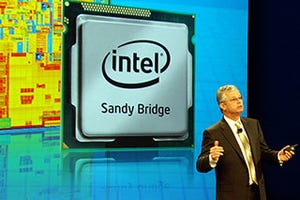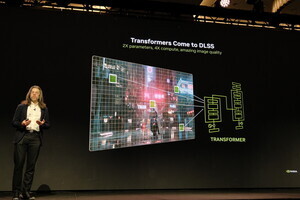既報の通り、IDF Fall 2010の基調講演ではSandy Bridgeが大々的に取り上げられた。実際基調講演の後にはIntelのサイトでウェハ(Photo01)やダイ(Photo02)、パッケージ写真(Photo03)が掲載されたし、Technical Sessionではかなり細かな内部アーキテクチャのレベルまで語られた。ということで、まずはSandy Bridgeの内容解説を行ないたいと思う。

|
Photo01: ダイサイズだが、以前同様に写真から計算してみたところ、21.4mm×10.4mmで、222.6平方mmという計算になった。もっともダイシングの切り代を考えると、20.4mm×9.4mmの191.8平方mm程度という試算も可能で、概ねこの間(多分200平方mmよりちょっと大きいくらい)が実際のダイサイズではないかと思われる。ちなみに有効そうなダイの数を数えると279個となった。 |

|

|
Photo02: ダイの拡大図。この写真からダイの縦横比を計算すると1:2.086というあたりで、21.4mm×10.3mmとかそんな感じだと辻褄が合う計算になる。 |
Photo03: 実に横長である。Yieldを考えれば、もう少し正方形に近いほうが有利な気もする。 |
In-Order部
ということでまずレポート1本目ではコアのPipeline構造について御紹介したい。既に塩田氏により、ある程度の解説があるので、これを下敷きに説明を薦めることにする。
Sandy Bridgeは、Fetch→Decode→Alloc/Rename/Retirementを行なうIn-Order部と、Scheduler/Executeを行なうOut-of-Order部に分かれているので、まずはIn-orderのFetch~Decode部(Photo04,05)である。このレベルでは、従来のNehalemとは殆ど変わらない構造となっている。ただこれに加えて、最大1.5K命令分のDecoded μOp Cacheが搭載された(Photo06)。これに伴い、どうも従来のLSD(Loop Stream Detector)は廃された(というか、このDecoded μOps Cacheに統合された)形になるようだ。もともとCore 2/NehalemのLSDは、あくまでも小ループの検出のみを行なう仕組みであり、他の分岐予測機構とは一種独立した形で実装されていたが、Sandy Bridgeではこのループ検出も分岐予測機構の中に組み込まれると同時に、より大きなバッファを持つ事で長大なループあるいは複雑なループに対応できるようになった、という事である。

|
Photo05: もっとも、MicroFusionやMacroFusionの組み合わせとか制約に関しては、多少なりともNehalem世代から改善されているのではないかとも想像されるが、このあたりは公式なドキュメントが出てみないと何とも言えない。 |
その分岐予測機構は今回「ゼロから作り直した」(Photo07)としている。ターゲット数が2倍とかより長大なHistoryに対応といった話は、実はNehalemもSandy BridgeもBTBのサイズとか構造が公開されていないので何とも言えないのだが(非公式な情報としては、L1 BTBが512Entry、L2 BTBが2K Entryという説がある)、まぁこれらは単純に倍になっていると考えてよさそうだ。また、Decode μOp CacheがHitしている間はFetch~Decodeが寝ている(Photo08)というのは、Clock Gatingをもう少し強力に掛けられる、というあたりではないかと想像される。

|
Photo07: Nehalemの場合はこんな感じ。まぁCore 2のものを多少改善したというレベルである。 |
続いてはAllocate/Rename/Retirementである。このスライドでは、In-Order側のAllocate/Rename/RetirementとOut-of-Order側のSchedulerが一緒になってしまっているが、とりあえずIn-Order側を考えるとZeroing Idiomsという新機能がある。このZeroing Idioms、春のIDF Beijingでは説明が一切なかったので謎だったが、これがXORなどを使ったレジスタクリアを指す、という話は塩田氏のレポートにあるので繰り返さない。ちなみにこれは、Intelの提供するCode Analyzerをつかって、命令単位で「それがどう実行され、どういうHardware Resourceを消費するか」を分析するためのものである。プレゼンテーションそのものはAVX命令の説明であり、なので例も普通のXORではなくAVXレジスタに対するXORとなるVXORPSとなっている。左端を見れば判るとおりμOpそのものは発行される(だからNum of μOpsが1)にも関わらず、ポート(これは後で説明する)を一つも占有しないあたり、これは実際には命令を発行せず、Retirement Unitだけで処理されると判断できる。