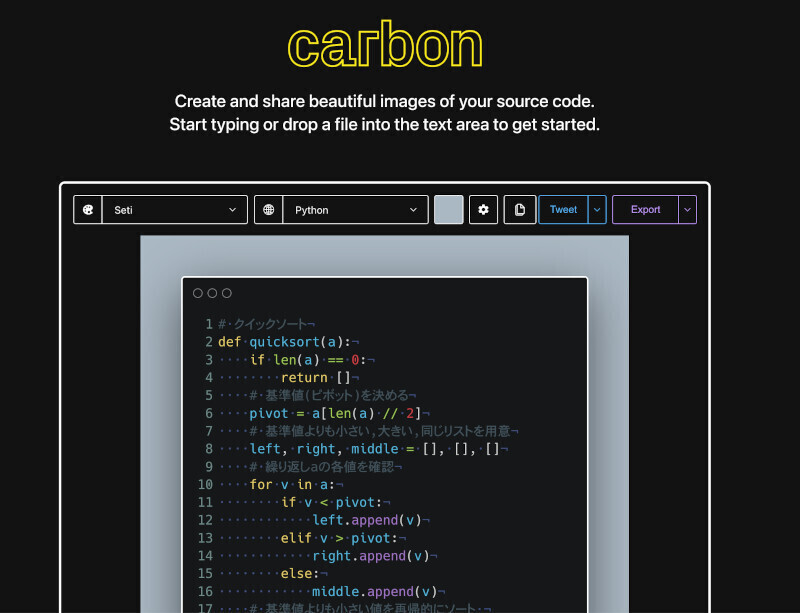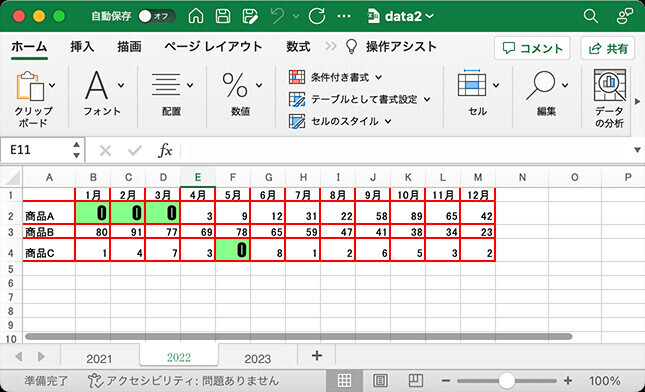前回は、「システム艦」における「センサーと武器の連接、データや指令の自動受け渡し」という話について書いた。ところが、この話が成り立つには、センサーが探知した目標の中からどれか優先度の高い目標を選び出すとともに、どの武器を使って交戦するかを決定するというプロセスが必要になる。
交戦に至るまでの四段階
センサーから武器にデータや指令を渡す作業を迅速化しても、その前段階でモタモタしていたのでは意味がなくなってしまう。そこで出てくるキーワードが「状況認識」「脅威評価」「武器割当」「意志決定」といったところだろうか。
まず「状況認識」だ。意味は読んで字のごとくで、どんな敵がどこにどれぐらいいるのか、対する味方は誰がどこにいるのか、損傷の有無や残弾の状態はどうなのか、などなど、交戦に関わるさまざまな情報を取り込んで、置かれている状況を正しく把握することである。
基本となるのは彼我の位置関係を把握することだが、そこでは、自艦が持つセンサーに加えて、データリンクで結ばれた他の艦や航空機などから流れ込んでくるデータも加味する必要がある。
ただし、データの供給元がバラバラだからといって、それぞれ別個の画面に情報を表示したのでは、状況認識の役に立つどころか、却って足を引っ張ってしまう。複数の画面を見て回りながら、頭の中で状況を組み立てなければならないからだ。だから、複数の情報源から得られたデータを単一の戦況図にまとめる、いわゆるデータ融合の機能は不可欠なものになる。
それができて初めて「脅威評価」が成立する。つまり、脅威度が高く、真っ先に交戦しなければならない探知目標がどれなのか、を判断する作業である。
自らの身に降りかかってくる脅威に高い優先度を設定するというだけならまだ分かりやすいが、イージス艦みたいに自艦のみならず艦隊全体の防空を担当する艦になると、脅威評価の際の優先度は違ってくる。ときには防護すべき対象(たとえば空母)への脅威を優先しなければならないこともあり得るからだ。
脅威評価ができたら、それに対して何で立ち向かうかを決める、いわゆる「武器割当」の作業が必要になる。使用する武器が決まって、初めてデータを射撃管制システムに送り込むことができる。艦砲を撃つのに艦対空ミサイルの射撃管制システムにデータを送ったところで、何の役にも立たない。
そして最終的に交戦の「意志決定」を行うことで、「撃ち方始め」と命令を発することができる。
コンピュータ化による迅速な処理
これらのプロセスを人手に頼らず、コンピュータに自動処理させる方が効率的なのはいうまでもない。ただし、コンピュータに勝手に戦争を始めさせるわけにはいかないので、最後の「意志決定」は人間の仕事である。いったん「意志決定」ができれば、その後はコンピュータ任せの自動交戦にしてもよいが。
最初の「状況認識」についていえば、自艦が持つセンサー群や他の艦・航空機といった複数の情報源から流れ込んできたデータを重畳して、単一の戦況図(picture)を作成する必要がある。前述したデータ融合である。
それは口でいうほど簡単な仕事ではない。レーダーやソナーの探知データは相対的な方位・距離のデータだから、それを基にして絶対座標を割り出して、地図上にプロットする必要がある。すると座標系の統一という話まで関わってくる。
また、探知した目標ごとに「目標ファイル」を作成して、時々刻々と変化していく追跡データに混乱が生じないようにする必要がある。
脅威評価の基本として分かりやすい例を出すと、明後日の方に向かって飛翔する対艦ミサイルよりも、自艦に向かって飛翔する対艦ミサイルの方が優先度が高い、という話になる。しかし、先にも触れたように、常に自艦の身を護ることだけ考えていればよいとは限らない。艦隊全体、あるいは自艦とその近所にいる僚艦にも護りの傘を差し伸べなければならない場面だって存在する。すると当然ながら脅威評価のロジックは違ってくる。
こういった諸々の作業を受け持つのが、指揮管制装置という名のコンピュータである。イージス艦を例に取ると、イージス武器システムの一員として、指揮決定システム(C&D : Command and Decision)と呼ばれる機材がある。イージス巡洋艦なら指揮決定システムMk.1、イージス駆逐艦なら指揮決定システムMk.2を使う。
指揮管制装置のキモはソフトウェア
もちろん、コンピュータの処理速度が遅くて脅威に対応しきれないのは問題外だし、扱うことができるデータの量が少なすぎて、脅威が多くなったときにオーバーフローしてしまっても困る。だから処理能力や記憶容量などといった話が「どうでもいい」というわけではないのだが、それらは必要条件であって十分条件ではない。
人間が行っていた作業を、より迅速かつ確実にコンピュータにやらせようというのだから、指揮管制装置は、人間の思考や作業を代行できるコンピュータでなければならない。すると、ソフトウェア、なかんずく状況認識・脅威評価・武器割当を行う部分のロジックをどこまで熟成させられるかが問題になる。
そういったところの機能について、運用実績を積み上げるとともにバグをいぶりだして熟成するプロセスを繰り返すことで、ようやく「使える」ソフトウェアができる。それができていないうちに、やれ「同時多目標交戦能力がすごい」とか、やれ「ミサイルの射程が長い」とか、やれ「ミサイルの搭載数が多い」とかいうところを自慢しても空虚である。
ただ、ソフトウェアをバージョンアップしていく過程でハードウェアの更新が発生することもあるし、ソフトウェアが重たくなればハードウェアの能力向上が必要だ。だから、ソフトウェアの「ロジック」の部分を作り込むだけでは済まない。ハードウェアの更新に対応できるように、高い移植性を備えたソフトウェアにしておかなければならない。
近年、艦載コンピュータは指揮管制措置も含めてCOTS(Commercial Off-The-Shelf)化が進んでおり、安上がりに高性能な機器を導入できるようになった。ところが、その一方では、製品のライフサイクルが短くなるという課題にも直面している。
すると、最初に導入したものをそのまま使い続けるのではなく、定期的にハードウェアを入れ替えたりソフトウェアを更新したり、といったイベントが発生することを前提にして、ハード/ソフトのライフサイクルを組み立てる必要がある。
実際、米海軍ではそういう方向に舵を切っており、ハードウェアとソフトウェアを定期的に更新する方式を取り入れる事例が出てきている。イージス戦闘システムがそうだし、対艦ミサイル対策を専門に担当する指揮管制装置・SSDS(Ship Self Defense System)Mk.2もそうだ。
たとえば、ハードとソフトをそれぞれ隔年で更新することにして、「ある年はハードの更新、その翌年はソフトの更新、そのまた翌年はハードの更新」という具合になるわけだ。ソフトの更新をACB(Advanced Capability Build。念のために書くとAKBではない)、ハードウェアの更新をTI(Technical Insertion)と呼んでいる。
執筆者紹介
井上孝司
![]()
IT分野から鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野に進出して著述活動を展開中のテクニカルライター。マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。「戦うコンピュータ2011」(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて「軍事研究」「丸」「Jwings」「エアワールド」「新幹線EX」などに寄稿しているほか、最新刊「現代ミリタリー・ロジスティクス入門」(潮書房光人社)がある。